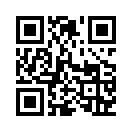ヘビメタパパの書斎 › 国産
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2021年07月19日
名刺がわりの挑戦状
2020年1月10日。新木場スタジオコースト。
コロナ禍になり、私のGALNERYUSライブ参戦はこの日で止まってしまっています。
映像化され、現地での感動はまだ強く刻まれています。
その映像の中で最も印象的だったのは、[DESTINY]での小野さんとFUMIYAが笑顔で見つめ合うシーンでした。
まさかそのライブのあと、FUMIYAが脱退ということになるとは。
その後任としてLEAが加入。
ミニアルバムとはいえ、加入後初リリースということで注目が集まりました。
GALNERYUS [UNION GIVES STRENGTH]

2021年リリース。
ミニアルバムとはいえ、6曲+リレコーディング2曲ということでそこそこのボリュームになります。
直訳すると「団結は、力を与える」といった感じでしょうか。
タイトルからして、この時期だからこそのメッセージを感じさせます。
なんといっても注目はLEAのプレイ。
そして、このコロナ禍を経ての方向性がどうなるのか。
アルバム発売前にリリースされたMV[WHATEVER IT TAKES (Raise Our Hands!)]は、勇気や希望を強く抱かせつつポジティブに飛翔する感動的なナンバーでした。
これを聞いて、「もしかして[VETELGYUS]の路線なのか!」とワクワクした人も多いことでしょう(私です)
そしてリリースされた今作。
LEAのお披露目ということもあり、もともと強いリズム隊の主張がさらに強くなっている印象がありますね。
SYU「LEAくん初だし、ちょっと前面に出しとくから」
TAKA「じゃ俺も」
YUHKI「じゃ俺も」
SYU「どうぞどうぞ(俺も)」
小野さん「俺は別に‥」
SYU「わかりました!(いつも以上のハイトーンメロディとヘドバン必至リフを用意)」
といったやりとりが見えてきそうな。(←イメージです)
1分近い静けさからヘヴィかつドゥーミーとすらいえるイントロダクションで「!?」と意表を突かれる[THE HOWLING DARKNESS]で幕を開けます。
続いて刻まれていくリフも重く、ダークな印象で蹂躙していくかのよう。
ときにブラストビートのような刻み方も織りまぜる。
その世界観を小野さんのVo.が中和していく。
サビでようやく扉が開いて光が射すかのようなメロディを顔を出しますが、基本的にはその重厚さをベースにしています。
実にSYUらしい。実に挑戦的。
事前に公開されたMVのチョイスすら、この曲からスタートさせるための策略かと思ってしまいます。
そういえば、ガルネリウスが得意なポジティブ飛翔系のMVって意外と少なかったりするんですよね。
続く[FLAMES OF RAGE]は配信ライブで初披露された曲ですね。
ややスラッシーとも言えるスピード感は、配信ライブ見ながら「小野さんの首がもげちゃうんやん‥」と思うほど。
そのときは今までにない印象のヘヴィーさを感じましたが、この位置に配置されると印象が全く違う。
静かに語るかのようなAメロから、センチメタリズム溢れるBメロ。ガッツに満ちたサビ。
目眩く展開が耳を捉えて離しません。
J-POP的‥いや、歌謡曲的とも言える[HOLD ON]。
こういう「小野さんだからこそ」の曲を聞くと、SYUの器用さ、小野さんへの経緯、そして小野さんの魅力を感じることができます。
ここ数作のコンセプトアルバム(?)では聞けなかった曲ですね。
イントロのメロディライン、加速具合、リフ。
そしてサビの展開。
まさにガルネリ王道チューンである[SEE THE LIGHT OF FREEDOM]。
全てが「これ、FLAGシリーズでもよかったんじゃないの?」と思わせてくれる曲。
本編ラストを飾るのはMVとなった[WHATEVER IT TAKES (Raise Our Hands!)]。
♪これがただのまぼろしで、夢からさめてかつてのように
手を取り合い笑いあえたら、もうなにもいらない。
♪これがただのまやかしで、夢からさめてかつてのように
抱きしめあい笑いあえたら、もうなにもいらない。
♪未来へ向かって、祈りはいま輝きはじめている
決して奪わせない、僕らの生きる時代への自由を
GALNERYUSの最大の魅力であり武器である、光が燦然と輝く天空へと翔けぬけていくようなメロディを小野さんのハイトーンが彩る。
そしてコロナ禍の今だからこそ胸を打つ歌詞。
強いメッセージ性は新たなアンセムとなることでしょう。
そして今回、もう一つの大きなサプライズとなったのが[DEEP AFFECTION][EVERLASTING]のリレコーディング。
ブックレットに[Lyrics:YAMA-B]の文字を見たとき、オールドファンは感慨深くなったことでしょう。
過去の曲は歌詞を変えてリレコーディング。
インタビューなどでは「前任ボーカルは‥」と話すよそよそしさ。
YAMA-B脱退後、そんな経緯を経て、今回のリレコーディングは実に原曲に忠実。その忠実さにも驚きました。
これはなにかの雪解けが始まっているのかもしれませんね。
:
:
ということで、聞きどころ満載ではありますが、「そうきたか‥」と意表をつかれたというのがファーストインプレッション。
聞けば聞くほど深いという点はいつもの「らしさ」ではありますが、さきほど書いたように「挑戦的なアルバムだな」という印象が強い。
次作への展開も全く読めません。
王道の曲、魅力爆発の曲、新機軸の曲。
こういった様々な品揃えも含めて、まさにLEAくんの「お披露目」であり、生まれ変わったバンドの名刺がわりのようなものでしょう。
次のフルアルバム、どういった方向性へと導くのか。
読めないからこそウキウキします。
きっとこれもSYUの策略。
GALNERYUS WHATEVER IT TAKES (Raise Our Hands!)
コロナ禍になり、私のGALNERYUSライブ参戦はこの日で止まってしまっています。
映像化され、現地での感動はまだ強く刻まれています。
その映像の中で最も印象的だったのは、[DESTINY]での小野さんとFUMIYAが笑顔で見つめ合うシーンでした。
まさかそのライブのあと、FUMIYAが脱退ということになるとは。
その後任としてLEAが加入。
ミニアルバムとはいえ、加入後初リリースということで注目が集まりました。
GALNERYUS [UNION GIVES STRENGTH]
2021年リリース。
ミニアルバムとはいえ、6曲+リレコーディング2曲ということでそこそこのボリュームになります。
直訳すると「団結は、力を与える」といった感じでしょうか。
タイトルからして、この時期だからこそのメッセージを感じさせます。
なんといっても注目はLEAのプレイ。
そして、このコロナ禍を経ての方向性がどうなるのか。
アルバム発売前にリリースされたMV[WHATEVER IT TAKES (Raise Our Hands!)]は、勇気や希望を強く抱かせつつポジティブに飛翔する感動的なナンバーでした。
これを聞いて、「もしかして[VETELGYUS]の路線なのか!」とワクワクした人も多いことでしょう(私です)
そしてリリースされた今作。
LEAのお披露目ということもあり、もともと強いリズム隊の主張がさらに強くなっている印象がありますね。
SYU「LEAくん初だし、ちょっと前面に出しとくから」
TAKA「じゃ俺も」
YUHKI「じゃ俺も」
SYU「どうぞどうぞ(俺も)」
小野さん「俺は別に‥」
SYU「わかりました!(いつも以上のハイトーンメロディとヘドバン必至リフを用意)」
といったやりとりが見えてきそうな。(←イメージです)
1分近い静けさからヘヴィかつドゥーミーとすらいえるイントロダクションで「!?」と意表を突かれる[THE HOWLING DARKNESS]で幕を開けます。
続いて刻まれていくリフも重く、ダークな印象で蹂躙していくかのよう。
ときにブラストビートのような刻み方も織りまぜる。
その世界観を小野さんのVo.が中和していく。
サビでようやく扉が開いて光が射すかのようなメロディを顔を出しますが、基本的にはその重厚さをベースにしています。
実にSYUらしい。実に挑戦的。
事前に公開されたMVのチョイスすら、この曲からスタートさせるための策略かと思ってしまいます。
そういえば、ガルネリウスが得意なポジティブ飛翔系のMVって意外と少なかったりするんですよね。
続く[FLAMES OF RAGE]は配信ライブで初披露された曲ですね。
ややスラッシーとも言えるスピード感は、配信ライブ見ながら「小野さんの首がもげちゃうんやん‥」と思うほど。
そのときは今までにない印象のヘヴィーさを感じましたが、この位置に配置されると印象が全く違う。
静かに語るかのようなAメロから、センチメタリズム溢れるBメロ。ガッツに満ちたサビ。
目眩く展開が耳を捉えて離しません。
J-POP的‥いや、歌謡曲的とも言える[HOLD ON]。
こういう「小野さんだからこそ」の曲を聞くと、SYUの器用さ、小野さんへの経緯、そして小野さんの魅力を感じることができます。
ここ数作のコンセプトアルバム(?)では聞けなかった曲ですね。
イントロのメロディライン、加速具合、リフ。
そしてサビの展開。
まさにガルネリ王道チューンである[SEE THE LIGHT OF FREEDOM]。
全てが「これ、FLAGシリーズでもよかったんじゃないの?」と思わせてくれる曲。
本編ラストを飾るのはMVとなった[WHATEVER IT TAKES (Raise Our Hands!)]。
♪これがただのまぼろしで、夢からさめてかつてのように
手を取り合い笑いあえたら、もうなにもいらない。
♪これがただのまやかしで、夢からさめてかつてのように
抱きしめあい笑いあえたら、もうなにもいらない。
♪未来へ向かって、祈りはいま輝きはじめている
決して奪わせない、僕らの生きる時代への自由を
GALNERYUSの最大の魅力であり武器である、光が燦然と輝く天空へと翔けぬけていくようなメロディを小野さんのハイトーンが彩る。
そしてコロナ禍の今だからこそ胸を打つ歌詞。
強いメッセージ性は新たなアンセムとなることでしょう。
そして今回、もう一つの大きなサプライズとなったのが[DEEP AFFECTION][EVERLASTING]のリレコーディング。
ブックレットに[Lyrics:YAMA-B]の文字を見たとき、オールドファンは感慨深くなったことでしょう。
過去の曲は歌詞を変えてリレコーディング。
インタビューなどでは「前任ボーカルは‥」と話すよそよそしさ。
YAMA-B脱退後、そんな経緯を経て、今回のリレコーディングは実に原曲に忠実。その忠実さにも驚きました。
これはなにかの雪解けが始まっているのかもしれませんね。
:
:
ということで、聞きどころ満載ではありますが、「そうきたか‥」と意表をつかれたというのがファーストインプレッション。
聞けば聞くほど深いという点はいつもの「らしさ」ではありますが、さきほど書いたように「挑戦的なアルバムだな」という印象が強い。
次作への展開も全く読めません。
王道の曲、魅力爆発の曲、新機軸の曲。
こういった様々な品揃えも含めて、まさにLEAくんの「お披露目」であり、生まれ変わったバンドの名刺がわりのようなものでしょう。
次のフルアルバム、どういった方向性へと導くのか。
読めないからこそウキウキします。
きっとこれもSYUの策略。
GALNERYUS WHATEVER IT TAKES (Raise Our Hands!)
2021年03月26日
♪長い間待たせたね
4年ぶりのリリースになるそうだ。
コロナ禍という混乱の中リリースされたこのアルバム、オープニングの「♪長い間、待たせたね」の歌詞が胸を刺します。
TEARS OF TRAGEDY [ TRINITY ]

2020年リリース。
ジャパニーズメロディアスハードロックの旗手と言っていいでしょう。
これが4thとなります。
実はこのバンドに知り合ったのは前作リリース後だったので、純粋な「新作」として向き合うことができたのは今作が初めてなのです。
慟哭メロディックデスメタルバンド THOUSAND EYES で活躍する TORUが中心となり、歌姫HARUKAのヴォーカルが彩りを添える。
なんといっても彼らの魅力はそのメロディに尽きる。
美しく、儚く、瑞々しく、柔らかく、優しい。
今作でも、そんな前作までの魅力を継承し、さらにステップアップした印象です。
そのステップアップの根幹を支えるのはHARUKAのヴォーカルの表現力によるものも大きいのではないでしょうか。
前作まではところどころで声の平坦さを感じたりする場面もありましたが、今作では「こんな歌い方もできるのか!!」という驚きを感じさせてくれます。
TEARS OF TRAGEDYのジャケットは徐々に少女の成長を物語っていくものになっているのですが、今作ではついに少女が「女性」になった姿に。
前作は、そのジャケットイメージ通り、「つぼみが徐々に開花して咲き誇っていく」ような印象のアルバムでした。
そして今作は「美しい花がしっかりと根を張り、強く咲き誇る姿」を思わせます。
オープニングを飾るイントロダクション[TRINITY]はアルバムタイトルにも冠されています。
「三位一体」を意味するキーワード。
メンバーの脱退を経て、3人の新体制で新たな扉を開く。
その扉の先に美しい光が射し込んでいるかのような情景が目に浮かぶ魅力的なイントロになっています。
その華やかなイントロダクションを切り裂くかのようにTORUのギターが切り込んでくるオープニングトラック[NONSITE]。
力強くポジティブに躍動するメロディに導かれ、「♪長い間、待たせたね」という冒頭の歌詞。この歌詞は「この言葉で始めたい」と決めていたと聞きます。
軽やかに水面を踊るかのような疾走感は彼らの真骨頂。
ややシンフォニックなアレンジで幕を開ける「幽玄」。
この曲が「こんなに表現力が豊かになったのか!!」というHARUKAの魅力を最も感じられる曲なのではないでしょうか。
Aメロ~Bメロでの力強く説得力のある歌、スポットライトのあたる舞台で軽やかに舞うかのようなサビの歌唱。
歌詞の美しさという相乗効果もあり、ひとつの象徴的な曲になっています。
前作の瑞々しさを感じさせる[INNOCENT GRAM]。
「あぁ、これだよなぁ」という安心感と暖かさを感じさせてくれます。
[OUTSIDER]はヘヴィメタリックなダークな色合いから徐々にメロディを帯びていく展開。
そう、こういった「ダークカラー」の世界観も彼らのアルバムには欠かせない。
影があるからこそ光が輝く。そのコントラストも魅力なのだ。
[NO.5]はいわゆるメロディックスピードメタル的な疾走感。
あえて淡々と語っていくかのような歌唱がシリアスさを演出しつつ、サビではドラマティックな高揚感を与えてくれます。
最終盤に配置される「時に鏡は嘘をつく」。
この曲は今まででいうところの[Curse Bride][Prison Of Abyss]といった劇的長尺曲のポジショニングになるのでしょうか。
それらと比べるとやや短めですが。
とはいえ、荘厳さ&ドラマ性はそれらの曲と肩を並べる出来栄え。
このポジションの曲が大好きだった私にとっては「今作もやってくれたか・・!!」という昂りが押さえられません。
そしてこれも恒例ですが、そういった劇的な曲のあとに再び清涼感のある曲でエンディグへと導いていく[クロノメトリー]。
ラストに向かって「あぁ、ティアーズのアルバムが終わるんだな」という心地よいエピローグでありエンドロール。
ということで、ファンのら期待を裏切らない素晴らしいアルバムに仕上がりました。
そして今回はデスヴォイスも封印。
この点については賛否あるかもしれませんが、個人的にはより一般層にアピールできる可能性が出てきたという意味でアリなのではないでしょうか。
もちろんピュアなメロディックメタルとしても一面もありつつ、HARUKAの柔和なヴォーカル+J-POP的ともいえるキャッチーかつポジティブなメロディはさらに新しいファンを獲得してくれることでしょう。
メタルというカテゴリに縛られることのない、大きな空へ羽ばたいていくような期待感に満ちたアルバムになりました。
TEARS OF TRAGEDY - Nonsite (OFFICIAL VIDEO)
コロナ禍という混乱の中リリースされたこのアルバム、オープニングの「♪長い間、待たせたね」の歌詞が胸を刺します。
TEARS OF TRAGEDY [ TRINITY ]

2020年リリース。
ジャパニーズメロディアスハードロックの旗手と言っていいでしょう。
これが4thとなります。
実はこのバンドに知り合ったのは前作リリース後だったので、純粋な「新作」として向き合うことができたのは今作が初めてなのです。
慟哭メロディックデスメタルバンド THOUSAND EYES で活躍する TORUが中心となり、歌姫HARUKAのヴォーカルが彩りを添える。
なんといっても彼らの魅力はそのメロディに尽きる。
美しく、儚く、瑞々しく、柔らかく、優しい。
今作でも、そんな前作までの魅力を継承し、さらにステップアップした印象です。
そのステップアップの根幹を支えるのはHARUKAのヴォーカルの表現力によるものも大きいのではないでしょうか。
前作まではところどころで声の平坦さを感じたりする場面もありましたが、今作では「こんな歌い方もできるのか!!」という驚きを感じさせてくれます。
TEARS OF TRAGEDYのジャケットは徐々に少女の成長を物語っていくものになっているのですが、今作ではついに少女が「女性」になった姿に。
前作は、そのジャケットイメージ通り、「つぼみが徐々に開花して咲き誇っていく」ような印象のアルバムでした。
そして今作は「美しい花がしっかりと根を張り、強く咲き誇る姿」を思わせます。
オープニングを飾るイントロダクション[TRINITY]はアルバムタイトルにも冠されています。
「三位一体」を意味するキーワード。
メンバーの脱退を経て、3人の新体制で新たな扉を開く。
その扉の先に美しい光が射し込んでいるかのような情景が目に浮かぶ魅力的なイントロになっています。
その華やかなイントロダクションを切り裂くかのようにTORUのギターが切り込んでくるオープニングトラック[NONSITE]。
力強くポジティブに躍動するメロディに導かれ、「♪長い間、待たせたね」という冒頭の歌詞。この歌詞は「この言葉で始めたい」と決めていたと聞きます。
軽やかに水面を踊るかのような疾走感は彼らの真骨頂。
ややシンフォニックなアレンジで幕を開ける「幽玄」。
この曲が「こんなに表現力が豊かになったのか!!」というHARUKAの魅力を最も感じられる曲なのではないでしょうか。
Aメロ~Bメロでの力強く説得力のある歌、スポットライトのあたる舞台で軽やかに舞うかのようなサビの歌唱。
歌詞の美しさという相乗効果もあり、ひとつの象徴的な曲になっています。
前作の瑞々しさを感じさせる[INNOCENT GRAM]。
「あぁ、これだよなぁ」という安心感と暖かさを感じさせてくれます。
[OUTSIDER]はヘヴィメタリックなダークな色合いから徐々にメロディを帯びていく展開。
そう、こういった「ダークカラー」の世界観も彼らのアルバムには欠かせない。
影があるからこそ光が輝く。そのコントラストも魅力なのだ。
[NO.5]はいわゆるメロディックスピードメタル的な疾走感。
あえて淡々と語っていくかのような歌唱がシリアスさを演出しつつ、サビではドラマティックな高揚感を与えてくれます。
最終盤に配置される「時に鏡は嘘をつく」。
この曲は今まででいうところの[Curse Bride][Prison Of Abyss]といった劇的長尺曲のポジショニングになるのでしょうか。
それらと比べるとやや短めですが。
とはいえ、荘厳さ&ドラマ性はそれらの曲と肩を並べる出来栄え。
このポジションの曲が大好きだった私にとっては「今作もやってくれたか・・!!」という昂りが押さえられません。
そしてこれも恒例ですが、そういった劇的な曲のあとに再び清涼感のある曲でエンディグへと導いていく[クロノメトリー]。
ラストに向かって「あぁ、ティアーズのアルバムが終わるんだな」という心地よいエピローグでありエンドロール。
ということで、ファンのら期待を裏切らない素晴らしいアルバムに仕上がりました。
そして今回はデスヴォイスも封印。
この点については賛否あるかもしれませんが、個人的にはより一般層にアピールできる可能性が出てきたという意味でアリなのではないでしょうか。
もちろんピュアなメロディックメタルとしても一面もありつつ、HARUKAの柔和なヴォーカル+J-POP的ともいえるキャッチーかつポジティブなメロディはさらに新しいファンを獲得してくれることでしょう。
メタルというカテゴリに縛られることのない、大きな空へ羽ばたいていくような期待感に満ちたアルバムになりました。
TEARS OF TRAGEDY - Nonsite (OFFICIAL VIDEO)
2020年08月11日
令和の最先端
「大風呂敷」と言えるタイトル。
そこからみなぎる自信。
彼の最新作は、その大風呂敷に負けない濃密なものになりました。
THE 冠 [日本のヘビーメタル]

日本ならではのヘビメタ(あえてHeavyMetalとは言わずに)を追求し、このアルバムが10枚目になるようです。
リリースは2020年。
さて、私は彼らのことはここ数年で聞き始めた後追いです。
アルバムも数枚しか持っていないので、いままでのアルバム遍歴や音楽性の遷移といった点についてはまだまだ知らないことが多い。
コアなファンの方々には、そんなある意味「ニワカ」に属する私の戯れ言としてサラリと流して頂きたいのですが‥
これは最高傑作でしょう。
密度、勢い、気合い、魂。
圧倒されるレベルでどんどん叩きつけてきます。
彼らの音楽は、コミカルさや可視化した「ヘビメタ」感。
SEX MACHINEGUNSあたりに通じるものがあるかと思います。
ある意味で「自虐的」とすら言えるものがありました。
ですが、今回は違う。
世界観は変わっていないにも関わらず、
「それがどうした」
「これが生きざま」
「これがヘビーメタル」
という自信に満ち満ちています。
冠徹弥のヴォーカルも、いつも通りハイテンションでありながら、金切り声で叫ぶ場面よりも誇らしげに堂々とした歌い方が目立つ。
そしてそれがより一層このアルバムに貫祿を与えています。
オープニングからフルスロットルの「日本のヘビーメタル」。
彼ら恒例の「ヘビーメタル」シリーズですね。
「最低で最高なミュージック」「無駄なものほど美しい」
世の中で虐げられている「ヘビメタ」への強い反骨心を見せつける力強い曲になっています。
そうそう、この曲もですし、アルバム全体に言えることなのですが、サウンドが生々しい。
作られたものではなく、そのままの姿を叩きつけているような。
その生々しさがこのアルバムの魅力を押し上げている感があります。
とくにドラムがその印象が強い。
冠さんらしいコミカルな歌詞やセリフが楽しい「やけに長い夏の日」。
フェスでオーディエンスが地蔵化してしまう切なさを歌っていますね。
なんだか目に浮かぶんですよ‥冠さんがフェスのステージに立って、アリーナが冷たい視線でそれを見てる姿が‥切ない歌詞が身に沁みます。
ライブでの盛り上がり必至のシンガロングでスタートする「キザミ」。
荒々しくスラッシーに刻まれていくリフからの、突然空が開けていくかのようなキャッチーかつ耳障りのいいサビへ。
この展開、彼らの得意技であり、私が最初に「ビキニライン」で惚れた彼らの強力な魅力の一つだ。
その名の通り、1分で爆裂疾走、「蹂躙していく」感が爽快な「1分で」。
この1分に詰め込まれて爆発させる怒り。
OUTRAGEの[YOU SUCK]を思い出しますが、あの曲は2分程度だったでしょうか。
それよりも濃密だ。
歌詞が珠玉なヘヴィバラード「大人の子守歌」。
囁くように始まり、哀愁と郷愁をプンプンと薫らせながら、サビでは昭和歌謡を思わせるメロディ。
歌詞との相乗効果が悲壮感を演出します。
高揚感とメロスピ的な明朗さが印象的な「だからどうした」。
これはライブで盛り上がるヤツです。
そして最終盤の「メタリックロマンス」。
ヘヴィメタルという沼に陥った人であれば、誰もが「すげぇ分かる!」と首がもげるほど頷きたくなる歌詞。
典型的な冠さんのメロディ。
得意のヒステリックヴォイスでのサビ。
「あなたに出会わなければ、普通の暮らしをしていたのに」
「あなたに染まるほど、まわりは引くけれど」
バンギャ目線で綴られていく歌詞の一つ一つがヘヴィメタルファンに突き刺さるのです。
ということで、捨て曲なしの隙のないアルバムになっています。
今までのアルバムは、まっとうなヘヴィメタルファンに自信を持ってオススメできるかというと、「イロモノ」扱いされそうで少し躊躇しました。
が、今作は違う。
同じ路線でありながらもヘヴィメタルと向き合うスピリットが強靱だから、こういったコミカルなバンドが苦手でもメタルファンに響くのでは‥という期待がある。
自らが「日本のヘビーメタル」を名乗り、「令和の最先端」と歌う。
それが言葉遊びで終わることなく説得力を持っている。
このアルバムを引っさげてのツアー、行きたかった‥。
そして、このアルバムの曲をしたいところですが、このご時世だからかMV作られていないんですよね‥
あとは是非ご自身で手にとり、この魅力を感じてほしいものです。
そこからみなぎる自信。
彼の最新作は、その大風呂敷に負けない濃密なものになりました。
THE 冠 [日本のヘビーメタル]

日本ならではのヘビメタ(あえてHeavyMetalとは言わずに)を追求し、このアルバムが10枚目になるようです。
リリースは2020年。
さて、私は彼らのことはここ数年で聞き始めた後追いです。
アルバムも数枚しか持っていないので、いままでのアルバム遍歴や音楽性の遷移といった点についてはまだまだ知らないことが多い。
コアなファンの方々には、そんなある意味「ニワカ」に属する私の戯れ言としてサラリと流して頂きたいのですが‥
これは最高傑作でしょう。
密度、勢い、気合い、魂。
圧倒されるレベルでどんどん叩きつけてきます。
彼らの音楽は、コミカルさや可視化した「ヘビメタ」感。
SEX MACHINEGUNSあたりに通じるものがあるかと思います。
ある意味で「自虐的」とすら言えるものがありました。
ですが、今回は違う。
世界観は変わっていないにも関わらず、
「それがどうした」
「これが生きざま」
「これがヘビーメタル」
という自信に満ち満ちています。
冠徹弥のヴォーカルも、いつも通りハイテンションでありながら、金切り声で叫ぶ場面よりも誇らしげに堂々とした歌い方が目立つ。
そしてそれがより一層このアルバムに貫祿を与えています。
オープニングからフルスロットルの「日本のヘビーメタル」。
彼ら恒例の「ヘビーメタル」シリーズですね。
「最低で最高なミュージック」「無駄なものほど美しい」
世の中で虐げられている「ヘビメタ」への強い反骨心を見せつける力強い曲になっています。
そうそう、この曲もですし、アルバム全体に言えることなのですが、サウンドが生々しい。
作られたものではなく、そのままの姿を叩きつけているような。
その生々しさがこのアルバムの魅力を押し上げている感があります。
とくにドラムがその印象が強い。
冠さんらしいコミカルな歌詞やセリフが楽しい「やけに長い夏の日」。
フェスでオーディエンスが地蔵化してしまう切なさを歌っていますね。
なんだか目に浮かぶんですよ‥冠さんがフェスのステージに立って、アリーナが冷たい視線でそれを見てる姿が‥切ない歌詞が身に沁みます。
ライブでの盛り上がり必至のシンガロングでスタートする「キザミ」。
荒々しくスラッシーに刻まれていくリフからの、突然空が開けていくかのようなキャッチーかつ耳障りのいいサビへ。
この展開、彼らの得意技であり、私が最初に「ビキニライン」で惚れた彼らの強力な魅力の一つだ。
その名の通り、1分で爆裂疾走、「蹂躙していく」感が爽快な「1分で」。
この1分に詰め込まれて爆発させる怒り。
OUTRAGEの[YOU SUCK]を思い出しますが、あの曲は2分程度だったでしょうか。
それよりも濃密だ。
歌詞が珠玉なヘヴィバラード「大人の子守歌」。
囁くように始まり、哀愁と郷愁をプンプンと薫らせながら、サビでは昭和歌謡を思わせるメロディ。
歌詞との相乗効果が悲壮感を演出します。
高揚感とメロスピ的な明朗さが印象的な「だからどうした」。
これはライブで盛り上がるヤツです。
そして最終盤の「メタリックロマンス」。
ヘヴィメタルという沼に陥った人であれば、誰もが「すげぇ分かる!」と首がもげるほど頷きたくなる歌詞。
典型的な冠さんのメロディ。
得意のヒステリックヴォイスでのサビ。
「あなたに出会わなければ、普通の暮らしをしていたのに」
「あなたに染まるほど、まわりは引くけれど」
バンギャ目線で綴られていく歌詞の一つ一つがヘヴィメタルファンに突き刺さるのです。
ということで、捨て曲なしの隙のないアルバムになっています。
今までのアルバムは、まっとうなヘヴィメタルファンに自信を持ってオススメできるかというと、「イロモノ」扱いされそうで少し躊躇しました。
が、今作は違う。
同じ路線でありながらもヘヴィメタルと向き合うスピリットが強靱だから、こういったコミカルなバンドが苦手でもメタルファンに響くのでは‥という期待がある。
自らが「日本のヘビーメタル」を名乗り、「令和の最先端」と歌う。
それが言葉遊びで終わることなく説得力を持っている。
このアルバムを引っさげてのツアー、行きたかった‥。
そして、このアルバムの曲をしたいところですが、このご時世だからかMV作られていないんですよね‥
あとは是非ご自身で手にとり、この魅力を感じてほしいものです。
2020年07月06日
類は友を呼ぶ
類は友を呼ぶ、ということか。
敬愛するアーティストのソロアルバムは、私が愛するミュージシャンで脇を固めた、強力布陣となりました。
SYU [ VORVADOS ]

日本を代表するメロディックヘヴィメタルバンドであるGALNERYUSのキーパーソンであるSYUのソロアルバム。
2019年リリース。
「VORVADOS」とは聞き慣れない単語でありますが、意味としては「クトゥルフ神話に登場する架空の神」とのことで、そこはあまり深く堀下げずにおきましょう(←よくわかっていない)。
コンスタントにクオリティの高い作品を提示し続けているGALNERYUSですが、さらにソロアルバムをリリースとは‥SYUの創作意欲は底無しですね。
ゲストヴォーカルのラインナップは‥
Fuki (Fuki Commune / ex.LightBringer)
苑 (摩天楼オペラ)
HARUKA (TEARS OF TRAGEDY)
団長 (NoGoD)
小野正利 (GALNERYUS)
DOUGEN (THOUSAND EYES)
AKANE LIV (LIV MOON)
どうですかこれ!私の好きなバンドばかり、まさに夢の競演といってもいい。
ギタリストのソロアルバムというと、インストアルバムだったり、自らのルーツを遡って意外性を見せるアルバムだったり、というイメージが強い。
そんな中、ゲストミュージシャンの個性を生かしつつ、SYUのメロディを堪能できるという、実に贅沢なアルバムになっています。
ソロアルバムというよりは、彼が好きなヴォーカリストを集めて、そのヴォーカリストたちに歌ってほしい曲を楽しんでいるかのようです。
オープニングのインストナンバー&タイトルトラックの[VORVADOS]。
その緊張感と昂りに導かれ、アルバムの幕が落ちる。
そして劇的に幕を開けるのはFUKIちゃんによる[REASON]。
GALNERYUSでも聞くことができる正統派ヘヴィメタルチューンのメロディと疾走感に、強靱なFUKIちゃんの声が重なる。
個性のせめぎ合い。
そしてそのせめぎ合いが生み出す相乗効果。
鮮烈なインパクトです。
続いては摩天楼オペラ苑さんによる[ここで区切れと天使は歌う]。
もうね、このタイトルからして摩天楼オペラを意識して作ってくれてるなぁと思いますよね。
曲としては、やや変拍子を交えてのメロディとなっており、私が期待する「摩天楼オペラ的、シンフォメロスピ」とは一線を画す。
とはいえ、やはり苑さんの個性的なヴォーカルが生きる曲になっています。
TEARS OF TRAGEDYのHARUKAさんによる「暁」。
ややミディアム&ヘヴィなメロディとHARUKAさんの澄んだ声のコンビネーション。
HARUKAさんはもう一曲参加していますが、その「もう一曲」の方が「らしい」かなと思いますが。
NoGoDの団長による[EUPHORIA]。
団長の囁き的な声からのハイトーンシャウトで始まり、メロディアスなスピード感で駆け抜けてゆく。
歌詞も含め、なんともNoGoD的なのが嬉しい。
団長がメロディを歌うときは団長の魅力が際立ち、ギターパートではSYUの圧倒的存在感が姿を現す。
DOUGENの慟哭の咆哮とAKANE LIVのオペラティックな美声のコントラストが際立つ[Chaotic Reality]。
それに続く[CACOTOPIA]。
ややマイルドでありながらも芯の通った魅力的な声、ときおり聞こえる歌いまわしはGACKT風だな‥誰だこれ‥と思っていたら、なんとSYU本人。
個人的には大好きな声質で驚きました。
今回のような豪華ゲストのアルバムもいいけど、自分で歌ったアルバムでもイケるじゃないか!という期待が沸いてきます。
FUKIちゃんによるもう一曲は、ややメランコリックに舞うような[AndroiDedication]。
実にキャッチー。
[REASON]のように強靱なヴォーカルもいいけど、こういったアニソン的&J-POP的な曲を歌うFUKIちゃんも魅力的なのだ。
小野さんの、小野さんによる、小野さんのために書かれたようなバラード「哀傷」。
何も言うことはありません。
GALNERYUSで小野さんの魅力を知り尽くしたSYUだからこそのバラード。
自然体の小野さんのヴォーカルが堪能できます。
実質ラストを飾る[未完成の翼]。
大好きなHARUKAさんの魅力全開です。
解放感を伴い、天空を舞うかのようなメロディ。自らの翼を広げ、そのメロディの中を優しく滑空するかのように舞い上がるHARUKAさんの歌声。
TEARS OF TRAGEDYの魅力でもある勇気と希望に満ちた歌詞。
この二人の組み合わせならこんな曲だろうな‥という期待通り、いや、期待以上の魅力的なコンビネーションとなっています。
‥と、立て続けに書いてしまいましたが、一言で言うと「どの組み合わせも魅力的すぎる」のです。
よくもまぁ、これだけヴォーカリストを引き立てる曲を書けたものだな‥と。
「マイホーム」であるGALNERYUSの充実に加えて、このソロでの充実っぷりは尋常じゃない。
基本的にはGALNERYUSのアルバムが素晴らしいだけで大満足なのですが、これだけのクオリティを見せてくれると次も期待してしまいますね。
そして次があるなら、SYUのヴォーカルで‥いや‥今回のメンバーも捨てがたいし‥悩ましいところですね。
SYU from GALNERYUS(GUEST VOCAL:Fuki)「REASON」
敬愛するアーティストのソロアルバムは、私が愛するミュージシャンで脇を固めた、強力布陣となりました。
SYU [ VORVADOS ]

日本を代表するメロディックヘヴィメタルバンドであるGALNERYUSのキーパーソンであるSYUのソロアルバム。
2019年リリース。
「VORVADOS」とは聞き慣れない単語でありますが、意味としては「クトゥルフ神話に登場する架空の神」とのことで、そこはあまり深く堀下げずにおきましょう(←よくわかっていない)。
コンスタントにクオリティの高い作品を提示し続けているGALNERYUSですが、さらにソロアルバムをリリースとは‥SYUの創作意欲は底無しですね。
ゲストヴォーカルのラインナップは‥
Fuki (Fuki Commune / ex.LightBringer)
苑 (摩天楼オペラ)
HARUKA (TEARS OF TRAGEDY)
団長 (NoGoD)
小野正利 (GALNERYUS)
DOUGEN (THOUSAND EYES)
AKANE LIV (LIV MOON)
どうですかこれ!私の好きなバンドばかり、まさに夢の競演といってもいい。
ギタリストのソロアルバムというと、インストアルバムだったり、自らのルーツを遡って意外性を見せるアルバムだったり、というイメージが強い。
そんな中、ゲストミュージシャンの個性を生かしつつ、SYUのメロディを堪能できるという、実に贅沢なアルバムになっています。
ソロアルバムというよりは、彼が好きなヴォーカリストを集めて、そのヴォーカリストたちに歌ってほしい曲を楽しんでいるかのようです。
オープニングのインストナンバー&タイトルトラックの[VORVADOS]。
その緊張感と昂りに導かれ、アルバムの幕が落ちる。
そして劇的に幕を開けるのはFUKIちゃんによる[REASON]。
GALNERYUSでも聞くことができる正統派ヘヴィメタルチューンのメロディと疾走感に、強靱なFUKIちゃんの声が重なる。
個性のせめぎ合い。
そしてそのせめぎ合いが生み出す相乗効果。
鮮烈なインパクトです。
続いては摩天楼オペラ苑さんによる[ここで区切れと天使は歌う]。
もうね、このタイトルからして摩天楼オペラを意識して作ってくれてるなぁと思いますよね。
曲としては、やや変拍子を交えてのメロディとなっており、私が期待する「摩天楼オペラ的、シンフォメロスピ」とは一線を画す。
とはいえ、やはり苑さんの個性的なヴォーカルが生きる曲になっています。
TEARS OF TRAGEDYのHARUKAさんによる「暁」。
ややミディアム&ヘヴィなメロディとHARUKAさんの澄んだ声のコンビネーション。
HARUKAさんはもう一曲参加していますが、その「もう一曲」の方が「らしい」かなと思いますが。
NoGoDの団長による[EUPHORIA]。
団長の囁き的な声からのハイトーンシャウトで始まり、メロディアスなスピード感で駆け抜けてゆく。
歌詞も含め、なんともNoGoD的なのが嬉しい。
団長がメロディを歌うときは団長の魅力が際立ち、ギターパートではSYUの圧倒的存在感が姿を現す。
DOUGENの慟哭の咆哮とAKANE LIVのオペラティックな美声のコントラストが際立つ[Chaotic Reality]。
それに続く[CACOTOPIA]。
ややマイルドでありながらも芯の通った魅力的な声、ときおり聞こえる歌いまわしはGACKT風だな‥誰だこれ‥と思っていたら、なんとSYU本人。
個人的には大好きな声質で驚きました。
今回のような豪華ゲストのアルバムもいいけど、自分で歌ったアルバムでもイケるじゃないか!という期待が沸いてきます。
FUKIちゃんによるもう一曲は、ややメランコリックに舞うような[AndroiDedication]。
実にキャッチー。
[REASON]のように強靱なヴォーカルもいいけど、こういったアニソン的&J-POP的な曲を歌うFUKIちゃんも魅力的なのだ。
小野さんの、小野さんによる、小野さんのために書かれたようなバラード「哀傷」。
何も言うことはありません。
GALNERYUSで小野さんの魅力を知り尽くしたSYUだからこそのバラード。
自然体の小野さんのヴォーカルが堪能できます。
実質ラストを飾る[未完成の翼]。
大好きなHARUKAさんの魅力全開です。
解放感を伴い、天空を舞うかのようなメロディ。自らの翼を広げ、そのメロディの中を優しく滑空するかのように舞い上がるHARUKAさんの歌声。
TEARS OF TRAGEDYの魅力でもある勇気と希望に満ちた歌詞。
この二人の組み合わせならこんな曲だろうな‥という期待通り、いや、期待以上の魅力的なコンビネーションとなっています。
‥と、立て続けに書いてしまいましたが、一言で言うと「どの組み合わせも魅力的すぎる」のです。
よくもまぁ、これだけヴォーカリストを引き立てる曲を書けたものだな‥と。
「マイホーム」であるGALNERYUSの充実に加えて、このソロでの充実っぷりは尋常じゃない。
基本的にはGALNERYUSのアルバムが素晴らしいだけで大満足なのですが、これだけのクオリティを見せてくれると次も期待してしまいますね。
そして次があるなら、SYUのヴォーカルで‥いや‥今回のメンバーも捨てがたいし‥悩ましいところですね。
SYU from GALNERYUS(GUEST VOCAL:Fuki)「REASON」
2020年05月11日
新たなストーリー、開幕。
なんだかんだで10年以上続いているこのブログですが、たまに覗いて頂ける方々には私の趣味嗜好はなんとなく伝わっている(というかバレている)と思います。
そう。
そんな私のハートを射抜く、大好きなタイプのバンドが日本から生まれました。
Chaos O Sanctuary [KINGDOM OF THE GLORIFIED]

日本発。
2019年リリース、これがデビュー作となります。
そもそも私は全く知りませんでした。
が、たまたまtwitterで流れてきて、たまたま聞いて、もうカラダが勝手にamazonをクリックしていた‥という、ここまで数分の出来事。
そのくらい私のココロを瞬殺してくれました。
メロディ。
スピード。
シンフォ。
流麗。
荘厳。
華麗。
メロディックスピードメタル大好き。
シンフォニックメタル大好き。
ネオクラシカル大好き。
そんな人(私です)なら、その「好き」が全て詰まっています。パンパンに詰まっています。
そんな衝撃のデビューを飾った彼ら。なんといってもデビューと思えぬクオリティが驚きです。
そして国産バンドとはいえヴォーカルは違和感ない英語詩。
バンド結成の経緯はこのあたりのHPが分かりやすいと思いますが、要約するとですね‥。
「「ロールプレイングミュージック」をテーマとし、メロディックスピードメタルを基盤としつつ、クワイヤ等の導入により、シンフォニックかつオーケストラチックなサウンド要素が強く打ち出されている。」
もうココだけで「ありがとう‥ありがとう‥」と言いたくなりませんか。なりますよね。
・ヴォーカルのAndyはフランス人。
・紅一点のHikaruはプロのフロート奏者。美しい美貌だけでなく、フルートにシンセにクワイアの女性ヴォーカルも担当。
・アートワークはDragonForceの作品を手がけた人。
・プロダクションはNOCTURNAL BLOODLUSTやTHOUSAND EYES、CRYSTAL LAKE、Unlucky Morpheus、TEARS OF TRAGEDY、Serenity In Murderなどを手掛けた国内メタルシーンで数多くのアーティストのサウンドプロデュースを行ってきたSTUDIO PRISONERのHiro氏が制作を指揮
・アルファベットOの円の中を一つの空間、聖域とした
ワクワクする要素がテンコモリすぎますね。
そりゃ、これだけクオリティが高い作品になるのも頷けます。
音楽性は言わずもがな‥というか、目指していたものが一点の曇りもなく具現化された音像になっています。
ANGRAを思わせる「聖」なイメージを纏う崇高かつ荘厳なイントロダクション[Heaven's Gate]。
この手のジャンルではこういった音色のイントロダクションが用いられることが定番ではありますが、その盛り上げからのいわゆる「出オチ」になってしまうこともある。
が。
続くオープニングチューン、しかもタイトルトラックである[Kingkdom of the Glorified]でその懸念はいとも簡単に砕かれます。
シリアスなメロディをベースとしたスピード感。
抑揚と変化をつけた展開。
勇気と誇りに溢れたサビ。
冒頭から自信に満ちあふれている。とてもデビュー作の開幕曲とは思えない。
後半のソロパートのドラマティックさ、語りのパート、このあたりも好きな人にはたまらない。
さらに続く[Song for Salvation]。
一転し、天空飛翔乱舞キラキラポジティプ系スピードチューン。
もうね、こういうタイプの曲大好きなんですよ。
たまんないんですよ。
この曲でのAndyの歌唱がまた素晴らしい。強引なハイトーンで誇示するわけでなく、さりげなくメロディを撫でていく。
その「さりげなく」というのは、凄いことなのだ。このサウンドに埋もれることなく「さりげなく」歌えているのはその実力を示してくれています。
強い個性があるわけではない。でも、バンドの大きな武器としてサウンドを強いチカラで支えている。
Helloween、Galneryus、ThousandEyes‥「Salvation」がつく曲は名曲が多い。
舞い踊るようなリズムが印象的な[Evil'March]を経て‥
ラストを飾るのは[Betrayal of Flames]。
初期RHAPSODYを思わせる展開をベースにDragonGurdianのようなアレンジ、そしてラストに向かって劇的に駆け抜けていく垂涎のメロディラインはMinstreliXのよう。
心地よさと抑えられない昂りの余韻を残し、あっと言う間にこのアルバムは幕を閉じます。
そう、このアルバムは5曲構成のミニアルバム。
冒頭がイントロであることを差し引けば4曲。
物足りない?
いいのです。
このアルバムは
「アルバム3部作で完結する長編物語の第1部の序章となり、舞台は「遥か昔に存在した天に浮かぶ国」」
この世界観もたまりません。
だから、いいのです。
まだ彼のストーリーは始まったばかり。
ページを捲ったばかり。
このワクワクは、第二部までとっておきましょう。
Chaos O Sanctuary - Song for Salvation
そう。
そんな私のハートを射抜く、大好きなタイプのバンドが日本から生まれました。
Chaos O Sanctuary [KINGDOM OF THE GLORIFIED]

日本発。
2019年リリース、これがデビュー作となります。
そもそも私は全く知りませんでした。
が、たまたまtwitterで流れてきて、たまたま聞いて、もうカラダが勝手にamazonをクリックしていた‥という、ここまで数分の出来事。
そのくらい私のココロを瞬殺してくれました。
メロディ。
スピード。
シンフォ。
流麗。
荘厳。
華麗。
メロディックスピードメタル大好き。
シンフォニックメタル大好き。
ネオクラシカル大好き。
そんな人(私です)なら、その「好き」が全て詰まっています。パンパンに詰まっています。
そんな衝撃のデビューを飾った彼ら。なんといってもデビューと思えぬクオリティが驚きです。
そして国産バンドとはいえヴォーカルは違和感ない英語詩。
バンド結成の経緯はこのあたりのHPが分かりやすいと思いますが、要約するとですね‥。
「「ロールプレイングミュージック」をテーマとし、メロディックスピードメタルを基盤としつつ、クワイヤ等の導入により、シンフォニックかつオーケストラチックなサウンド要素が強く打ち出されている。」
もうココだけで「ありがとう‥ありがとう‥」と言いたくなりませんか。なりますよね。
・ヴォーカルのAndyはフランス人。
・紅一点のHikaruはプロのフロート奏者。美しい美貌だけでなく、フルートにシンセにクワイアの女性ヴォーカルも担当。
・アートワークはDragonForceの作品を手がけた人。
・プロダクションはNOCTURNAL BLOODLUSTやTHOUSAND EYES、CRYSTAL LAKE、Unlucky Morpheus、TEARS OF TRAGEDY、Serenity In Murderなどを手掛けた国内メタルシーンで数多くのアーティストのサウンドプロデュースを行ってきたSTUDIO PRISONERのHiro氏が制作を指揮
・アルファベットOの円の中を一つの空間、聖域とした
ワクワクする要素がテンコモリすぎますね。
そりゃ、これだけクオリティが高い作品になるのも頷けます。
音楽性は言わずもがな‥というか、目指していたものが一点の曇りもなく具現化された音像になっています。
ANGRAを思わせる「聖」なイメージを纏う崇高かつ荘厳なイントロダクション[Heaven's Gate]。
この手のジャンルではこういった音色のイントロダクションが用いられることが定番ではありますが、その盛り上げからのいわゆる「出オチ」になってしまうこともある。
が。
続くオープニングチューン、しかもタイトルトラックである[Kingkdom of the Glorified]でその懸念はいとも簡単に砕かれます。
シリアスなメロディをベースとしたスピード感。
抑揚と変化をつけた展開。
勇気と誇りに溢れたサビ。
冒頭から自信に満ちあふれている。とてもデビュー作の開幕曲とは思えない。
後半のソロパートのドラマティックさ、語りのパート、このあたりも好きな人にはたまらない。
さらに続く[Song for Salvation]。
一転し、天空飛翔乱舞キラキラポジティプ系スピードチューン。
もうね、こういうタイプの曲大好きなんですよ。
たまんないんですよ。
この曲でのAndyの歌唱がまた素晴らしい。強引なハイトーンで誇示するわけでなく、さりげなくメロディを撫でていく。
その「さりげなく」というのは、凄いことなのだ。このサウンドに埋もれることなく「さりげなく」歌えているのはその実力を示してくれています。
強い個性があるわけではない。でも、バンドの大きな武器としてサウンドを強いチカラで支えている。
Helloween、Galneryus、ThousandEyes‥「Salvation」がつく曲は名曲が多い。
舞い踊るようなリズムが印象的な[Evil'March]を経て‥
ラストを飾るのは[Betrayal of Flames]。
初期RHAPSODYを思わせる展開をベースにDragonGurdianのようなアレンジ、そしてラストに向かって劇的に駆け抜けていく垂涎のメロディラインはMinstreliXのよう。
心地よさと抑えられない昂りの余韻を残し、あっと言う間にこのアルバムは幕を閉じます。
そう、このアルバムは5曲構成のミニアルバム。
冒頭がイントロであることを差し引けば4曲。
物足りない?
いいのです。
このアルバムは
「アルバム3部作で完結する長編物語の第1部の序章となり、舞台は「遥か昔に存在した天に浮かぶ国」」
この世界観もたまりません。
だから、いいのです。
まだ彼のストーリーは始まったばかり。
ページを捲ったばかり。
このワクワクは、第二部までとっておきましょう。
Chaos O Sanctuary - Song for Salvation
2020年03月27日
福岡から降り注ぐ光
1stアルバムは衝撃的でした。
その驚きのクオリティの1stアルバムから、なんと5年。
ついに福岡の新進気鋭メロディックスピードメタルバンドが動き出しました。
GAUNTLET [Departure For The Frontier]

福岡県出身。
1stアルバムのリリースが2014年。
そしてこのアルバムが2019年リリース。
アルバムといっても4曲入りですから、2ndアルバムというよりはミニアルバムですね。
煌き、飛翔感、スピード、リフ、メロディ。
1stアルバムでは、その「国産メロスピに期待するもの」の全てが詰め込まれたサウンドで「ニッポン人でよかった!」という喜びを与えてくれました。
ただ、全体的なクオリティという点ではまだまだバラツキがあるかなという感覚が残りました。
それでも[Beyond The Wall]の衝撃だけで充分にその存在感を示してくれました。
そのアルバムから5年。
バンドメンバーの体調不良などもあったようですが、長かった‥。
まさに「待望」の活動再開からのこのミニアルバムリリースは、まずは挨拶代わりといったところでしょう。
オープニングを飾る[Departure]。
突き抜けるようなリフからキラキラとしたキーボードの音色とともに刻まれるメロディ。
前作よりも「陽」「光」「輝」といったポジティブな触感が前面に押し出されている気がしますね。
日本語詩を積極的に取り入れてくれたところも個人的には非常に大きなポイント。
前作でも「このメロディなら日本語で勝負してほしいな」と思っていた。
なので、とても嬉しい。
やはり日本人の紡ぐメロディには日本語が似合う。
日本のコブシには日本語が似合う。
Vo.であるYu-taの強靱なハイトーンは健在。
中音域のストロングでありながら柔和な声は彼の魅力であると思うのですが、サビで聞かせるややトンガったハイトーン、そのハイトーンに絡みつくヴィブラートは好みが別れるところでしょうか。
私個人としては、もうすこしナチュラルなトーンで勝負できる高さのほうがいいかなと思いました。
[Welcome To My Nightmare]は、ややモダンなオープニングから彼ららしいメロディへの転換が印象的。
サビでは私が一番好きだった頃のSTRATOVARIUSのような印象。
ギターソロパートでは「まるっきりインギーじゃないですか(笑)」という微笑ましさも。
こういう音楽的ルーツが如実に現れてるメロディ、大好きです。
ラストのコーラスパートもライブでの盛り上がりを想像してしまいますね。
[The Calling]は、最近のちょっと落ち着いたメロディを聞かせるDragonForceのようですね。
正統派な薫りが漂い、ちょっと硬派なメロスピチューン。
まるで[Back to Back]なゴリゴリとしたリフで幕を明ける[Glory Days]。
そこからの展開はやはりガントレ節といえる飛翔系メロディ。
そのゴリゴリ感とガントレらしいメロディが織り混ざり、曲の展開に抑揚が生まれていますね。
この曲でもギターソロはインギー風。そして後半はティモ・トルキ風。
ということで、前作を気に入った方にとっては期待を裏切らない仕上がりとなっています。
フルアルバムに向けて期待してよさそうです。
が‥
1曲目はともかく、その他が「すごく大好きなタイプの曲で、メロディも魅力的で高揚感あるのに、なんだか印象に残りにくい」という感覚もあったりします。
展開やリフに工夫が見られ、前作から進化しているのは間違いない。
しかもその進化は「正統」「期待通り」の進化。
そのあと一つ足りない「何か」を見つけ、Vo.が自分の最も輝くスタイルを見つけたとき、一気に日本のメタルシーンを代表する存在になってくれることでしょう。
GAUNTLET - Departure
その驚きのクオリティの1stアルバムから、なんと5年。
ついに福岡の新進気鋭メロディックスピードメタルバンドが動き出しました。
GAUNTLET [Departure For The Frontier]

福岡県出身。
1stアルバムのリリースが2014年。
そしてこのアルバムが2019年リリース。
アルバムといっても4曲入りですから、2ndアルバムというよりはミニアルバムですね。
煌き、飛翔感、スピード、リフ、メロディ。
1stアルバムでは、その「国産メロスピに期待するもの」の全てが詰め込まれたサウンドで「ニッポン人でよかった!」という喜びを与えてくれました。
ただ、全体的なクオリティという点ではまだまだバラツキがあるかなという感覚が残りました。
それでも[Beyond The Wall]の衝撃だけで充分にその存在感を示してくれました。
そのアルバムから5年。
バンドメンバーの体調不良などもあったようですが、長かった‥。
まさに「待望」の活動再開からのこのミニアルバムリリースは、まずは挨拶代わりといったところでしょう。
オープニングを飾る[Departure]。
突き抜けるようなリフからキラキラとしたキーボードの音色とともに刻まれるメロディ。
前作よりも「陽」「光」「輝」といったポジティブな触感が前面に押し出されている気がしますね。
日本語詩を積極的に取り入れてくれたところも個人的には非常に大きなポイント。
前作でも「このメロディなら日本語で勝負してほしいな」と思っていた。
なので、とても嬉しい。
やはり日本人の紡ぐメロディには日本語が似合う。
日本のコブシには日本語が似合う。
Vo.であるYu-taの強靱なハイトーンは健在。
中音域のストロングでありながら柔和な声は彼の魅力であると思うのですが、サビで聞かせるややトンガったハイトーン、そのハイトーンに絡みつくヴィブラートは好みが別れるところでしょうか。
私個人としては、もうすこしナチュラルなトーンで勝負できる高さのほうがいいかなと思いました。
[Welcome To My Nightmare]は、ややモダンなオープニングから彼ららしいメロディへの転換が印象的。
サビでは私が一番好きだった頃のSTRATOVARIUSのような印象。
ギターソロパートでは「まるっきりインギーじゃないですか(笑)」という微笑ましさも。
こういう音楽的ルーツが如実に現れてるメロディ、大好きです。
ラストのコーラスパートもライブでの盛り上がりを想像してしまいますね。
[The Calling]は、最近のちょっと落ち着いたメロディを聞かせるDragonForceのようですね。
正統派な薫りが漂い、ちょっと硬派なメロスピチューン。
まるで[Back to Back]なゴリゴリとしたリフで幕を明ける[Glory Days]。
そこからの展開はやはりガントレ節といえる飛翔系メロディ。
そのゴリゴリ感とガントレらしいメロディが織り混ざり、曲の展開に抑揚が生まれていますね。
この曲でもギターソロはインギー風。そして後半はティモ・トルキ風。
ということで、前作を気に入った方にとっては期待を裏切らない仕上がりとなっています。
フルアルバムに向けて期待してよさそうです。
が‥
1曲目はともかく、その他が「すごく大好きなタイプの曲で、メロディも魅力的で高揚感あるのに、なんだか印象に残りにくい」という感覚もあったりします。
展開やリフに工夫が見られ、前作から進化しているのは間違いない。
しかもその進化は「正統」「期待通り」の進化。
そのあと一つ足りない「何か」を見つけ、Vo.が自分の最も輝くスタイルを見つけたとき、一気に日本のメタルシーンを代表する存在になってくれることでしょう。
GAUNTLET - Departure
2019年12月09日
変化。それは進化。
このバンドの新譜を前にすると、高い期待値、高いハードルになってしまいます。
が、そのハードルを毎回軽々と越えてくる。
路線が変わろうが、メンバーが変わろうが、越えてきてくれるのです。
GALNERYUS [ INTO THE PURGATORY ]

ジャパニーズメタルシーンの代表格と言っていいでしょう。
とくに国内メロディックメタルの中では最高峰だと思っているバンドの‥もう12枚目になりますか。
YAMA-B期で5枚。
そして"SHO"こと小野正利が加入して7枚目。
もうすっかり小野さんのイメージが定着してきましたね。
アンダーグラウンド感を漂わせながらもワールドワイド志向だった初期。
日本語詩を交えつつ路線を模索したYAMA-B時代後期。
小野さんが加入し、一気にJ-POP的華やかさで彩られた小野さん前期。
そして、前々作~前作ではややダークな色彩と重い歌詞が印象的なコンセプトアルバム。
こう挙げていくと、好きな時期と苦手な時期があってもよさそうなものですが、私はどの時代も大好きだ。
そして毎回、「今回もスゲェ」と感嘆させられます。
二枚のコンセプトアルバムを経て、今回はコンセプトアルバムからは離れるとの報があった。
個人的には「小野さんの魅力が光る、VETELGYUS みたいなアルバムだといいなぁ」と、ぼんやりイメージしていました。
が、事前に公開されたMV [THE FOLLOWERS] は意表をつくものでした。
ヘヴィなリフ、YAMA-B時代を思わせるムード、今までに聞かれなかった小野さんの声。
いわゆる「ガルネリウス節」とは一線を画す曲調に「‥新譜、大丈夫か?」と思ったファンも多いのではないでしょうか。
そんな中リリースされたこのアルバム。
結論から言うと、コンセプトアルバムではないとはいえ、世界観は前々作~前作の雰囲気を踏襲しています。
その雰囲気の中でコンパクトになった分、YAMA-B後期のような触感を感じます。
そして楽器隊の難解でテクニカルなインストパートが印象的。
ヴォーカルの小野さんを含め、メンバー全員のテクニックが怒濤のように、けどバランスよく押し寄せてくるような圧力を感じます。
オープニングのインスト曲[PURGATORIAL FLAME]から導かれる[MY HOPE IS GONE]。
ガルネリらしいスピード感で駆け抜ける、ガルネリらしい曲だ。
が、いわゆる小野さんのオープニングトラックの印象である(というか、期待している)「天空飛翔感」「ポジティブ感」はやや控えめ。
そういった意味では[RAISE MY SWARD]あたりに近いわけですが、さらに鈍色で鋭利になったアグレッションを感じます。
このアルバム全体に感じる、強靱な音のカタマリが雪崩のように襲いかかってくる威圧感とスキのなさ。
いい意味で息がつまる緊張感が漲ります。
ここ二作の路線をそのまま引き継いだかのように疾走する[FIGHTING OF ETERNITY]。
勇壮な歌詞、勇壮なメロディは、すっかり耳慣れた安心感すらあります。
中盤に配された[NEVER AGAIN]~MVとなった[THE FOLLOWERS]は、[REINCARNATION]あたりの空気を感じて、YAMA-B脱退後のアルバムがこの路線でも不思議じゃないな‥と思わせる雰囲気。
事前公開された[THE FOLLOWERS]は、アルバムのこの位置に挟まれていると「この曲は必然だ」と思わせてくれる存在感。
ここまで印象が変わるのは衝撃的もあり、SYUの「してやったり」の顔が目に浮かぶようです。
間髪いれず続く[COME BACK TO ME AGAIN]の強靱なリフは、[THE FOLLOWERS]のエンディングからの繋ぎかたでさらに魅力が増しています。
実質ラストとなる[THE END OF THE LINE]は、コンセプトアルバムではないと言いつつ、コンセプトアルバムのエンディングのような劇的さ。
ここ二枚のエンディングに近いものを感じつつ、[REINCARNATION]に於ける[THE FLAG OF REINCARNATION]的存在感でもあります。
ヘヴィなムードに包まれているアルバムの最後に優しい光が射し込んでくるかのような、仄かな温かさが心地いい。
こういう「温かさ」は、小野さんの魅力だなぁ‥と嬉しくなります。
SYUのソロパートも印象的で、超絶名曲[ANGEL OF SALVATION]での自由奔放なソロパートを思い出しますね。
‥と、やはり今回も期待通りの素晴らしさ。
が、圧倒的キラーチューンという意味では、ここ数作を思うと若干弱いでしょうか。
その代わり‥というわけではありませんが、アルバム全体のクオリティの高さは特筆すべきレベルだと思います。
ホームランバッターはいないけど、打率の高いバッターを並べたスキのない打線のような。
コンセプトアルバムではないので、ここ二作とは線をひくべき作品だろうなとは思うのですが、私の印象では完全にその二作に続く「三作目の続編」。
前作が私のガルネリ史の中でも指折りのリピート率だったこともあり、ついそのアルバムと比べてしまいますね。
そろそろ[ENDLESS STORY]のような曲を‥という思いが脳裏をよぎりますが、SYUのことですからそんなファンの思いも織り込み済みでしょう。
私と同様にガルネリウスを愛している友人が「ガルネリの変化は、すべて進化」と話していましたが、的確な表現だなと思いました。
コンスタントにアルバムをリリースしてくれている彼ら。次の進化も目が離せません。
GALNERYUS – THE FOLLOWERS
が、そのハードルを毎回軽々と越えてくる。
路線が変わろうが、メンバーが変わろうが、越えてきてくれるのです。
GALNERYUS [ INTO THE PURGATORY ]

ジャパニーズメタルシーンの代表格と言っていいでしょう。
とくに国内メロディックメタルの中では最高峰だと思っているバンドの‥もう12枚目になりますか。
YAMA-B期で5枚。
そして"SHO"こと小野正利が加入して7枚目。
もうすっかり小野さんのイメージが定着してきましたね。
アンダーグラウンド感を漂わせながらもワールドワイド志向だった初期。
日本語詩を交えつつ路線を模索したYAMA-B時代後期。
小野さんが加入し、一気にJ-POP的華やかさで彩られた小野さん前期。
そして、前々作~前作ではややダークな色彩と重い歌詞が印象的なコンセプトアルバム。
こう挙げていくと、好きな時期と苦手な時期があってもよさそうなものですが、私はどの時代も大好きだ。
そして毎回、「今回もスゲェ」と感嘆させられます。
二枚のコンセプトアルバムを経て、今回はコンセプトアルバムからは離れるとの報があった。
個人的には「小野さんの魅力が光る、VETELGYUS みたいなアルバムだといいなぁ」と、ぼんやりイメージしていました。
が、事前に公開されたMV [THE FOLLOWERS] は意表をつくものでした。
ヘヴィなリフ、YAMA-B時代を思わせるムード、今までに聞かれなかった小野さんの声。
いわゆる「ガルネリウス節」とは一線を画す曲調に「‥新譜、大丈夫か?」と思ったファンも多いのではないでしょうか。
そんな中リリースされたこのアルバム。
結論から言うと、コンセプトアルバムではないとはいえ、世界観は前々作~前作の雰囲気を踏襲しています。
その雰囲気の中でコンパクトになった分、YAMA-B後期のような触感を感じます。
そして楽器隊の難解でテクニカルなインストパートが印象的。
ヴォーカルの小野さんを含め、メンバー全員のテクニックが怒濤のように、けどバランスよく押し寄せてくるような圧力を感じます。
オープニングのインスト曲[PURGATORIAL FLAME]から導かれる[MY HOPE IS GONE]。
ガルネリらしいスピード感で駆け抜ける、ガルネリらしい曲だ。
が、いわゆる小野さんのオープニングトラックの印象である(というか、期待している)「天空飛翔感」「ポジティブ感」はやや控えめ。
そういった意味では[RAISE MY SWARD]あたりに近いわけですが、さらに鈍色で鋭利になったアグレッションを感じます。
このアルバム全体に感じる、強靱な音のカタマリが雪崩のように襲いかかってくる威圧感とスキのなさ。
いい意味で息がつまる緊張感が漲ります。
ここ二作の路線をそのまま引き継いだかのように疾走する[FIGHTING OF ETERNITY]。
勇壮な歌詞、勇壮なメロディは、すっかり耳慣れた安心感すらあります。
中盤に配された[NEVER AGAIN]~MVとなった[THE FOLLOWERS]は、[REINCARNATION]あたりの空気を感じて、YAMA-B脱退後のアルバムがこの路線でも不思議じゃないな‥と思わせる雰囲気。
事前公開された[THE FOLLOWERS]は、アルバムのこの位置に挟まれていると「この曲は必然だ」と思わせてくれる存在感。
ここまで印象が変わるのは衝撃的もあり、SYUの「してやったり」の顔が目に浮かぶようです。
間髪いれず続く[COME BACK TO ME AGAIN]の強靱なリフは、[THE FOLLOWERS]のエンディングからの繋ぎかたでさらに魅力が増しています。
実質ラストとなる[THE END OF THE LINE]は、コンセプトアルバムではないと言いつつ、コンセプトアルバムのエンディングのような劇的さ。
ここ二枚のエンディングに近いものを感じつつ、[REINCARNATION]に於ける[THE FLAG OF REINCARNATION]的存在感でもあります。
ヘヴィなムードに包まれているアルバムの最後に優しい光が射し込んでくるかのような、仄かな温かさが心地いい。
こういう「温かさ」は、小野さんの魅力だなぁ‥と嬉しくなります。
SYUのソロパートも印象的で、超絶名曲[ANGEL OF SALVATION]での自由奔放なソロパートを思い出しますね。
‥と、やはり今回も期待通りの素晴らしさ。
が、圧倒的キラーチューンという意味では、ここ数作を思うと若干弱いでしょうか。
その代わり‥というわけではありませんが、アルバム全体のクオリティの高さは特筆すべきレベルだと思います。
ホームランバッターはいないけど、打率の高いバッターを並べたスキのない打線のような。
コンセプトアルバムではないので、ここ二作とは線をひくべき作品だろうなとは思うのですが、私の印象では完全にその二作に続く「三作目の続編」。
前作が私のガルネリ史の中でも指折りのリピート率だったこともあり、ついそのアルバムと比べてしまいますね。
そろそろ[ENDLESS STORY]のような曲を‥という思いが脳裏をよぎりますが、SYUのことですからそんなファンの思いも織り込み済みでしょう。
私と同様にガルネリウスを愛している友人が「ガルネリの変化は、すべて進化」と話していましたが、的確な表現だなと思いました。
コンスタントにアルバムをリリースしてくれている彼ら。次の進化も目が離せません。
GALNERYUS – THE FOLLOWERS
2019年11月15日
ニッポン・プライド
台湾のバンド、ChthoniCが[Takasago Army]をリリースしたとき、驚愕とともに「なぜこれが日本で生まれないのか」と嫉妬した人もいたかと思います(私です)
その思い、いまこのバンドが晴らしてくれることでしょう。
GYZE [ASIAN CHAOS]

2019年リリース。このアルバムが4thアルバムになります。
ご存じの方には「なにをいまさら」と言われるかもしれませんが、「ギゼ」と読みますね。
北海道出身、日本が誇るメロディックデスメタルの若手の旗手ですね。
LOUDPARK15でオープニングアクトを飾った彼らのパフォーマンスは衝撃的でした。
朝一番からのウォールオブデスの爽快感は、LOUDPARK15の個人的ベストシーンに数えてもいいくらい。
その2015年あたりは、いわゆる北欧メロデスを踏襲した国産メロデスバンドの一つ、という位置づけでした。
が、前作[Northern Hell Song]では北海道の、北の大地の薫りを強く感じさせる個性を生み出すことに成功。
自分たちが生まれ育った土壌へのプライドが滲み出る‥いや、溢れ出ると言ったほうがいいでしょうか‥という作品となりました。
その印象的作品の次作となった今回のアルバム。
ドラムが体調不良で一時休養。
そして今までのトリオ体制からギターが一人加入。
過渡期の中でのアルバムリリースとなりました。
アルバムリリース前に公開されたMVは、凄まじいインパクトでした。
前作の北の大地の薫りから、一気に日本人のプライドを前面に押し出し、加速度的進化を遂げたように感じました。
冒頭に触れたChthoniCを思い出し、「これだよ‥私たちが日本のバンドに期待していたのはこれなんだよ!」という歓喜が全身を覆いました。
そしてそのMVで膨らんだ期待をもって対峙したこのアルバム。
期待通りです。MVで魅せた血流がアムバム全体に漲っています。
ジャケットからも、その魂が脈々と感じ伝わってきます。
日出ずる国。
八百万神。
そんな言葉が脳裏をよぎります。
雅楽(?)をモチーフにした荘厳なイントロダクション[Far Eastern Land]から、GYZEらしいアグレッションで爆走する[Asian Chaos]へ。
この[Asian Chaos]がMVになった曲。
メロデスの残虐性は残しつつも、その残虐性が逆にこのメロディの崇高さを演出しているかのようです。
オリエンタル&トライバルな空気とアグレッションの相乗効果がニッポン人の魂を揺さぶります。
続く[Eastern Spirits]は、サビの和風な歌いまわしが印象的。
スピード感はDragonForceを思わせるところすらあり、そういった意味では「メロディックデスメタル」の「メロディック」の方に力点を置いているように感じますね。
[Dragon Calling]はメロディックパワーメタル風の前半~徐々にChildren of Bodomを思わせるサビへ向かう高揚感が心地いい。
キーボードの使い方も「あぁ‥王道だよ」と感じさせてくれます。
[Japanese Elegy]は前作の流れを汲んで、さらに進化しているような曲ですね。
この曲だけでなく全編に通じて言えるのですが、緩急のつけかた‥その緩急は単なるスピードではなくで脳裏に描かれる場面展開がどんどん切り替わっていくという緩急のつけかたが素晴らしいと思うのです。
そして[1945 Hiroshima]という非常に重厚なテーマの曲で本編は締められるわけですが‥
ボーナストラック扱いの曲たちがまた素晴らしい。
[Forever Love]。そう、あのX-JAPANの名バラードがGYZE流メロデスとして生まれ変わっているのです。
X-JAPAN大好きな私ですが、実は彼らのバラードはそこまででも‥なのですが、「こんなにカッコよくなるのか!」とニヤニヤしてしまいした。
そして「やっぱりX-JAPANはスゲーわ」と再認識できました。
[Vivaldi Winter]は、メタル界隈ではある意味定番とも言えるヴィヴァルディの「冬」のアレンジ。
チョイスとしては定番でも、北海道出身の彼らが選んでいるところに意味があり、プライドを感じさせてくれますね。
もちろん曲としての求心力は言うまでもありません。
‥と、全編がジャパニーズプライド‥というか、日本語で「日本人の心」と書きたくなるほど日本への愛が満ちに満ちたアルバムとなっています。
和風なアレンジ、大幅に増えた日本語詩。
このアルバムだけがそういうコンセプトなのではなく、GYZEの生きる道として選択したのであれば、海外で通じるメロデスを志してきた彼らにとっては大きな英断ではないでしょうか。
やや狙いすぎ&あざとさを感じるシーンも無くはないですが、ここまで一気に振り切ってきたのはそのあざとさすら煙に巻くほどのスピリットを感じます。
普段あまりメロデスを聞かない私にとっての、2019年ベストアルバム候補。
日本人なら一度は触れてほしいアルバムです。
GYZE 【ASIAN CHAOS (Far Eastern Mix)】 Official MV
その思い、いまこのバンドが晴らしてくれることでしょう。
GYZE [ASIAN CHAOS]

2019年リリース。このアルバムが4thアルバムになります。
ご存じの方には「なにをいまさら」と言われるかもしれませんが、「ギゼ」と読みますね。
北海道出身、日本が誇るメロディックデスメタルの若手の旗手ですね。
LOUDPARK15でオープニングアクトを飾った彼らのパフォーマンスは衝撃的でした。
朝一番からのウォールオブデスの爽快感は、LOUDPARK15の個人的ベストシーンに数えてもいいくらい。
その2015年あたりは、いわゆる北欧メロデスを踏襲した国産メロデスバンドの一つ、という位置づけでした。
が、前作[Northern Hell Song]では北海道の、北の大地の薫りを強く感じさせる個性を生み出すことに成功。
自分たちが生まれ育った土壌へのプライドが滲み出る‥いや、溢れ出ると言ったほうがいいでしょうか‥という作品となりました。
その印象的作品の次作となった今回のアルバム。
ドラムが体調不良で一時休養。
そして今までのトリオ体制からギターが一人加入。
過渡期の中でのアルバムリリースとなりました。
アルバムリリース前に公開されたMVは、凄まじいインパクトでした。
前作の北の大地の薫りから、一気に日本人のプライドを前面に押し出し、加速度的進化を遂げたように感じました。
冒頭に触れたChthoniCを思い出し、「これだよ‥私たちが日本のバンドに期待していたのはこれなんだよ!」という歓喜が全身を覆いました。
そしてそのMVで膨らんだ期待をもって対峙したこのアルバム。
期待通りです。MVで魅せた血流がアムバム全体に漲っています。
ジャケットからも、その魂が脈々と感じ伝わってきます。
日出ずる国。
八百万神。
そんな言葉が脳裏をよぎります。
雅楽(?)をモチーフにした荘厳なイントロダクション[Far Eastern Land]から、GYZEらしいアグレッションで爆走する[Asian Chaos]へ。
この[Asian Chaos]がMVになった曲。
メロデスの残虐性は残しつつも、その残虐性が逆にこのメロディの崇高さを演出しているかのようです。
オリエンタル&トライバルな空気とアグレッションの相乗効果がニッポン人の魂を揺さぶります。
続く[Eastern Spirits]は、サビの和風な歌いまわしが印象的。
スピード感はDragonForceを思わせるところすらあり、そういった意味では「メロディックデスメタル」の「メロディック」の方に力点を置いているように感じますね。
[Dragon Calling]はメロディックパワーメタル風の前半~徐々にChildren of Bodomを思わせるサビへ向かう高揚感が心地いい。
キーボードの使い方も「あぁ‥王道だよ」と感じさせてくれます。
[Japanese Elegy]は前作の流れを汲んで、さらに進化しているような曲ですね。
この曲だけでなく全編に通じて言えるのですが、緩急のつけかた‥その緩急は単なるスピードではなくで脳裏に描かれる場面展開がどんどん切り替わっていくという緩急のつけかたが素晴らしいと思うのです。
そして[1945 Hiroshima]という非常に重厚なテーマの曲で本編は締められるわけですが‥
ボーナストラック扱いの曲たちがまた素晴らしい。
[Forever Love]。そう、あのX-JAPANの名バラードがGYZE流メロデスとして生まれ変わっているのです。
X-JAPAN大好きな私ですが、実は彼らのバラードはそこまででも‥なのですが、「こんなにカッコよくなるのか!」とニヤニヤしてしまいした。
そして「やっぱりX-JAPANはスゲーわ」と再認識できました。
[Vivaldi Winter]は、メタル界隈ではある意味定番とも言えるヴィヴァルディの「冬」のアレンジ。
チョイスとしては定番でも、北海道出身の彼らが選んでいるところに意味があり、プライドを感じさせてくれますね。
もちろん曲としての求心力は言うまでもありません。
‥と、全編がジャパニーズプライド‥というか、日本語で「日本人の心」と書きたくなるほど日本への愛が満ちに満ちたアルバムとなっています。
和風なアレンジ、大幅に増えた日本語詩。
このアルバムだけがそういうコンセプトなのではなく、GYZEの生きる道として選択したのであれば、海外で通じるメロデスを志してきた彼らにとっては大きな英断ではないでしょうか。
やや狙いすぎ&あざとさを感じるシーンも無くはないですが、ここまで一気に振り切ってきたのはそのあざとさすら煙に巻くほどのスピリットを感じます。
普段あまりメロデスを聞かない私にとっての、2019年ベストアルバム候補。
日本人なら一度は触れてほしいアルバムです。
GYZE 【ASIAN CHAOS (Far Eastern Mix)】 Official MV
2019年04月15日
群馬のクリエイティブ・ロック
洋/邦問わず、女性ヴォーカルバンドの活躍が華々しい。
国内ではALDIOUS/LOVEBITES/CYNTIA/FATE GEAR/陰陽座‥と、思いつくだけでもドンドン名前が挙がるほどに隆盛だ。
私はといえば、以前書いた Tears of Tragedy が大好きで、その音楽性のバンドがいないかなーと探していたわけですが‥
その中で出会ったバンドがこのバンドだ。
MAHATMA - Orchestra of the Life

群馬県出身。
このアルバムは2016年リリースの2ndになるようですね。
先に言っちゃいますが、1stアルバムも素晴らしいキラーチューンがあるのですよ。
YoutubeでTears of Tragedyからのオススメで流れてきたのですが、一目惚れでした。
美しいピアノに導かれるイントロダクション。
セピア色の協会。
バックを彩るオーケストラ & 合唱隊。
このフルコンボ。
もうね、私の大好物が詰まっているわけですよ。
最初に聞いたときは「ちょっとヴォーカルが弱いかな‥」と思いました。
声質はステキなのですが、外れそうで外れない、外れなさそうでちょっと外れそうで‥というギリギリのラインを綱渡りしているような感覚です。
が、この浮遊感もこのバンドの魅力だな、と思えるようになれば悪くないものです。
このバンドの魅力は、「なんでもあり」なところだと思う。
美しいハードロックタイプの曲。
ジャズっぽい彩りの曲。
ジャムってるような曲。
ちょっとファンキーな曲。
北欧ケルト色が見え隠れする曲。
自らを「クリエイティヴ・ロック・バンド」と標榜しているようですが、なるほど‥と頷けるものがあります。
純粋なメタルアルバムとして見ると物足りなさを感じるかもしれませんが、聞きはじめると知らぬ間にその世界へ入り込んでしまうのです。
音楽性の多彩さを物語るかのように、ゲストも多彩。
GALNERYUSのYUHKI。
Mardelas & LIGHT BRINGERのHIBIKI。
そしてALHAMBRAのメンバー。
このバンド名を見るだけで「そりゃ私が好きになるわけだな」という妙な説得力がありますね。
イントロとなる[Overture for Romance]。
1stアルバムでもこの[Overture for ****] がありましたが、キモになる曲の前にはこの[Overture]シリーズが配置される。
シンフォニックで重厚、かつリリカルなイントロは、このアルバムへの期待を昂らせるには充分な導入になっています。
そして美しさと鋭利さを備えたリフ、クラシカルなハーモニーを携えて幕を開ける[Romance]へ。
サビまでのメロディは、静かに揺れる水面を思わせる瑞々しさ。
そして力強く説得力のあるサビへ。
間奏で乱舞するクラシカルなキーボードとコーラス。
このバンドの魅力がパッケージングされている曲だと思います。
ポジティブなメロディ、そしてそのメロディを支えるベースラインが魅力的な[Brand New Wolrd]。
特徴的な歌詞が強く印象に残ります。
一般的なJ-POPとしてでもアピールできそうな[Last Tears]。
なんだかZARDあたりを思い出しますね。
ヴォーカルのNaNaさんの声が一番フィットしているのはこの曲かもしれません。
ケルティックで壮大な[精霊歌]は、私が大好きなZABADAKの世界を想起させます。
というか、ZABADAKのアルバムに入ってても全く違和感がない。
ため息が出る美しさです。
「ラッキー☆セブン」は、初期BABYMETALが歌ってそうなダンサブルチューン。
キャッチーな疾走感にパーカッションの彩りが楽しい[Starry Night]、
さらには変拍子からの飛翔感溢れるサビが魅力的な[Dragon's Fly]というコンボはアルバム終盤の魅力を一気に高めてくれています。
冒頭に触れた通り、実にバラエティに富んでいて、楽しい。
一曲一曲、万華鏡のように表情を変える。
ヘヴィメタルアルバムかと聞かれれば、そうじゃないんだろうな、と思います。
が、メロディ重視のメタルファンで、日本語に抵抗のない方にはアピールできるのではないかと思いますよ。
Romance / MAHATMA【MV】
国内ではALDIOUS/LOVEBITES/CYNTIA/FATE GEAR/陰陽座‥と、思いつくだけでもドンドン名前が挙がるほどに隆盛だ。
私はといえば、以前書いた Tears of Tragedy が大好きで、その音楽性のバンドがいないかなーと探していたわけですが‥
その中で出会ったバンドがこのバンドだ。
MAHATMA - Orchestra of the Life

群馬県出身。
このアルバムは2016年リリースの2ndになるようですね。
先に言っちゃいますが、1stアルバムも素晴らしいキラーチューンがあるのですよ。
YoutubeでTears of Tragedyからのオススメで流れてきたのですが、一目惚れでした。
美しいピアノに導かれるイントロダクション。
セピア色の協会。
バックを彩るオーケストラ & 合唱隊。
このフルコンボ。
もうね、私の大好物が詰まっているわけですよ。
最初に聞いたときは「ちょっとヴォーカルが弱いかな‥」と思いました。
声質はステキなのですが、外れそうで外れない、外れなさそうでちょっと外れそうで‥というギリギリのラインを綱渡りしているような感覚です。
が、この浮遊感もこのバンドの魅力だな、と思えるようになれば悪くないものです。
このバンドの魅力は、「なんでもあり」なところだと思う。
美しいハードロックタイプの曲。
ジャズっぽい彩りの曲。
ジャムってるような曲。
ちょっとファンキーな曲。
北欧ケルト色が見え隠れする曲。
自らを「クリエイティヴ・ロック・バンド」と標榜しているようですが、なるほど‥と頷けるものがあります。
純粋なメタルアルバムとして見ると物足りなさを感じるかもしれませんが、聞きはじめると知らぬ間にその世界へ入り込んでしまうのです。
音楽性の多彩さを物語るかのように、ゲストも多彩。
GALNERYUSのYUHKI。
Mardelas & LIGHT BRINGERのHIBIKI。
そしてALHAMBRAのメンバー。
このバンド名を見るだけで「そりゃ私が好きになるわけだな」という妙な説得力がありますね。
イントロとなる[Overture for Romance]。
1stアルバムでもこの[Overture for ****] がありましたが、キモになる曲の前にはこの[Overture]シリーズが配置される。
シンフォニックで重厚、かつリリカルなイントロは、このアルバムへの期待を昂らせるには充分な導入になっています。
そして美しさと鋭利さを備えたリフ、クラシカルなハーモニーを携えて幕を開ける[Romance]へ。
サビまでのメロディは、静かに揺れる水面を思わせる瑞々しさ。
そして力強く説得力のあるサビへ。
間奏で乱舞するクラシカルなキーボードとコーラス。
このバンドの魅力がパッケージングされている曲だと思います。
ポジティブなメロディ、そしてそのメロディを支えるベースラインが魅力的な[Brand New Wolrd]。
特徴的な歌詞が強く印象に残ります。
一般的なJ-POPとしてでもアピールできそうな[Last Tears]。
なんだかZARDあたりを思い出しますね。
ヴォーカルのNaNaさんの声が一番フィットしているのはこの曲かもしれません。
ケルティックで壮大な[精霊歌]は、私が大好きなZABADAKの世界を想起させます。
というか、ZABADAKのアルバムに入ってても全く違和感がない。
ため息が出る美しさです。
「ラッキー☆セブン」は、初期BABYMETALが歌ってそうなダンサブルチューン。
キャッチーな疾走感にパーカッションの彩りが楽しい[Starry Night]、
さらには変拍子からの飛翔感溢れるサビが魅力的な[Dragon's Fly]というコンボはアルバム終盤の魅力を一気に高めてくれています。
冒頭に触れた通り、実にバラエティに富んでいて、楽しい。
一曲一曲、万華鏡のように表情を変える。
ヘヴィメタルアルバムかと聞かれれば、そうじゃないんだろうな、と思います。
が、メロディ重視のメタルファンで、日本語に抵抗のない方にはアピールできるのではないかと思いますよ。
Romance / MAHATMA【MV】
2017年12月18日
その後の世界
一つの「頂」へ到達した感があった前作。
次はどんな一手を打ってくるのかという期待と不安が入り混じっている中。
まさかの前作の流れを汲むコンセプトアルバムです。
GALNERYUS - ULTIMATE SACRIFICE

大阪出身。
日本が誇る、正統派ジャパニーズヘヴィメタルの最高峰‥と言ってしまってもいいでしょう。
wikiによるとこのアルバムが11枚目‥11枚!? 早いものですねぇ。
そして"SHO"こと小野正利が加入して6枚目‥初代ヴォーカリストであるYAMA-B時代を上回ったわけですね。感慨深いものがあります。
このアルバム発売を前にドラムが交代。
なんとUnlucky Morpheus や THOUSAND EYES で活躍するFUMIYAが加入しました。
さらにはこのアルバムは大手レーベル、ワーナー・ミュージックからのリリース。
‥と、このアルバムは節目としても大きな意味を持つことになりそうです。
冒頭に述べた通り、前作[UNDER THE FORCE OF COURAGE]はGALNERYUSの歴史の集大成のようなアルバムでした。
過去の歴史すべてを俯瞰しつつ、濃密に圧縮して昇華させたような強靱な魂に満ちたアルバムでした。
おそらく、次のアルバムはその密度を解き放ち、自由奔放、小野さんのヴォーカルスタイルを生かしたワイドな方向性へ走るのではないかと勝手に想像していました。
が。
その[UNDER THE FORCE OF COURAGE]の世界観を受け継ぎ、「その後の世界」を描いたという今作。
スタイルは前作同様、シリアスな世界の中で展開していくコンセプトアルバムになっています。
あれだけクオリティの高いアルバムの後で、似たような方向性を目指してしまって大丈夫なのか。
まさか二番煎じになったりしないのか。
若干のマンネリを感じたりしないのか。
様々な不安が脳裏をよぎっていましたが‥すべて杞憂に終わりました。
素晴らしいです。
今作も素晴らしいです。
前作と同じようなスタイルを取っていながら、全く違うアルバムとして存在しています。
ガルネリウスの歴史を語っていく上での「両輪」となるような気がします。
単純に直感として感じたのは
・インパクト、激動の中で壮大なストーリーを描いた前作
・濃密な悲哀の中で深い深い情念を描いた今作
といった印象でしょうか。
直感的に訴えてくるのは前作。
聞けば聞くほど深みに沈んでいくのが今作。
実際、最初に聞いたときにはなんだか「突き刺さる」ものが前作より弱い気がしましたが、聞いている期間、聞いている回数は圧倒的に前作を凌ぐ。
いわゆる典型的「スルメ盤」だと思います。
そうして聞いている中でジワジワと浸透してくる今作の魅力。
それは「歌詞」にあると思う。
言葉の選び方、紡ぎ方。
曲とのフィット感。
SYUのギターの泣きのメロディに、慟哭の歌詞を歌いあげる小野さんの声が乗る。
この相乗効果は過去屈指の魅力だと思うのです。
イントロ[ENTER THE NEW AGE]に導かれ、幕を開ける[HEAVENLY PUNISHMENT]。
リリース前から「このタイトル‥絶対名曲に決まってるやん‥絶対間違いないやつやん‥」という期待がパンパンに膨らんでいたわけですが、そのパンパンの期待を余裕で上回ってきます。
FUMIYAのインパクトのあるドラム、小野さんの絶唱。そしてSYUのギターが追いかけてくる。
最初に聞いて、「オープニングチューンとしては[RAISE MY SWORD]ほどじゃないかな‥」と感じたわけですが、聞けば聞くほどすべての魅力が詰まった名曲であり、今では彼らの歴史の中でも指折りの名曲じゃないかというほど大好きな曲です。
「また巡りゆく、運命が螺旋の様に」
「もがき続ける、未だ哀しみの渦の中で」
「見上げ想いを馳せる空、繰り返し問いかける宿命、いつか掲げた立ち上がる意味は、今もこの大地に轟いてゆく。」
さきほど、このアルバムの「歌詞」の魅力を書きましたが、まさにこの曲が象徴的。
続く[WINGS OF JUSTICE]はGALNERYUS史上、最速の部類に入るでしょうか。
爪弾かれるリフは初期のSONATA ARCTICAを思わせます。
小野さんの「Ahhhhhhhhh........!!」の叫び。魂の叫びです。
後半では7分→11分→12分‥という大曲が続きます。
長尺な曲が大好きな私にとってはたまらない構成です。
[RISING INFURIATION]は、このアルバムの「起承転結」でいうところの「転」に位置するでしょうか。
ストーリーが後半に向けて加速していく手前の葛藤を描いているかのような、時折不協和音のようなテクニカルな展開を持ちます。
[BRUTAL SPIRAL OF EMOTIONS]は三部構成。
倒れそうになりながらも立ち上がっていくかのような力強さに満ちた曲になっているように感じます。
「今にも張り裂けそうな想いを嘘に変えてくれるなら、苦境の全てに身を投じるだろう」
「今にも崩れそうな想いを嘘に変えてくれるなら、絶望の淵でも絶えず抗うだろう」
この曲での歌詞も印象的なのですが、「投じるだろう」「抗うだろう」のリズムがたまりません。
静かに紡がれるパートも美しくも切ない。ラストへ向けての大きな布石として存在しています。
そして最後を飾る[ULTIMATE SACRIFICE]へ。
美しいピアノとシンフォニックな音色に導かれ、クライマックスへ向かっていきます。
前作のラストを飾る組曲[UNDER THE FORCE OF COURAGE]に近い世界観を感じますが、より歌詞の「クライマックス」感が強いように感じます。
リフやサビは典型的な「ガルネリ節」と言えると思いますが、そうでありながら孤高の感を感じるのは、やはり歌詞の魅力でしょうか。
「今願うならば、この時間を戻して、約束の地へ駆けるだろう。これ以上何を失えば赦されるのだろう。」
「今叶うならば、この手を差し出して、消え去った過去を掴むだろう。」
「今願うならば、この時間を戻して、あの手をもう離さないだろう。吐き出した全ての想いは解き放たれゆく。」
「今叶うならば、あなたのその影を、もう一度だけ思い出して、何も求めるものなど無く、穏やかな温もりの中でただ笑い合っていたい。」
この曲の一部はMVとして事前に公開されていましたが、この曲を選んだバンドの意図を感じ取るのも面白いところかもしれません。
:
:
ということで、珍しくたくさんの歌詞をそのまま貼り付けてしまいました。
そのくらい、私にとってこのアルバムの「歌詞」は大きな意味を持ち、前作との違いを如実にし、このアルバムの魅力の魅力に大きく寄与しています。
前作のときにも書いたかもしれませんが、ずっと好きだったファンにとっては前作に続いて圧倒的傑作として存在し続けるのではないでしょうか。
バンドの底力、ポテンシャルに敬服してしまいます。
が、このバンドのことを知らない人に勧めるかというと、ちょっと濃密すぎるのではないかとも感じます。
そろそろ賛否両論あった[VETELGYUS]のような路線の、「メタルを知らない人でもその魅力を伝えられる」ようなアルバムも聞いてみたいなと感じたりもします。
まぁ、そういう曲を書くこともできるSYU、そういう曲でも圧倒的な魅力を放ってくれる小野さんがいてくれるからこその贅沢な悩みですが。
GALNERYUS「ULTIMATE SACRIFICE」Official MV
次はどんな一手を打ってくるのかという期待と不安が入り混じっている中。
まさかの前作の流れを汲むコンセプトアルバムです。
GALNERYUS - ULTIMATE SACRIFICE

大阪出身。
日本が誇る、正統派ジャパニーズヘヴィメタルの最高峰‥と言ってしまってもいいでしょう。
wikiによるとこのアルバムが11枚目‥11枚!? 早いものですねぇ。
そして"SHO"こと小野正利が加入して6枚目‥初代ヴォーカリストであるYAMA-B時代を上回ったわけですね。感慨深いものがあります。
このアルバム発売を前にドラムが交代。
なんとUnlucky Morpheus や THOUSAND EYES で活躍するFUMIYAが加入しました。
さらにはこのアルバムは大手レーベル、ワーナー・ミュージックからのリリース。
‥と、このアルバムは節目としても大きな意味を持つことになりそうです。
冒頭に述べた通り、前作[UNDER THE FORCE OF COURAGE]はGALNERYUSの歴史の集大成のようなアルバムでした。
過去の歴史すべてを俯瞰しつつ、濃密に圧縮して昇華させたような強靱な魂に満ちたアルバムでした。
おそらく、次のアルバムはその密度を解き放ち、自由奔放、小野さんのヴォーカルスタイルを生かしたワイドな方向性へ走るのではないかと勝手に想像していました。
が。
その[UNDER THE FORCE OF COURAGE]の世界観を受け継ぎ、「その後の世界」を描いたという今作。
スタイルは前作同様、シリアスな世界の中で展開していくコンセプトアルバムになっています。
あれだけクオリティの高いアルバムの後で、似たような方向性を目指してしまって大丈夫なのか。
まさか二番煎じになったりしないのか。
若干のマンネリを感じたりしないのか。
様々な不安が脳裏をよぎっていましたが‥すべて杞憂に終わりました。
素晴らしいです。
今作も素晴らしいです。
前作と同じようなスタイルを取っていながら、全く違うアルバムとして存在しています。
ガルネリウスの歴史を語っていく上での「両輪」となるような気がします。
単純に直感として感じたのは
・インパクト、激動の中で壮大なストーリーを描いた前作
・濃密な悲哀の中で深い深い情念を描いた今作
といった印象でしょうか。
直感的に訴えてくるのは前作。
聞けば聞くほど深みに沈んでいくのが今作。
実際、最初に聞いたときにはなんだか「突き刺さる」ものが前作より弱い気がしましたが、聞いている期間、聞いている回数は圧倒的に前作を凌ぐ。
いわゆる典型的「スルメ盤」だと思います。
そうして聞いている中でジワジワと浸透してくる今作の魅力。
それは「歌詞」にあると思う。
言葉の選び方、紡ぎ方。
曲とのフィット感。
SYUのギターの泣きのメロディに、慟哭の歌詞を歌いあげる小野さんの声が乗る。
この相乗効果は過去屈指の魅力だと思うのです。
イントロ[ENTER THE NEW AGE]に導かれ、幕を開ける[HEAVENLY PUNISHMENT]。
リリース前から「このタイトル‥絶対名曲に決まってるやん‥絶対間違いないやつやん‥」という期待がパンパンに膨らんでいたわけですが、そのパンパンの期待を余裕で上回ってきます。
FUMIYAのインパクトのあるドラム、小野さんの絶唱。そしてSYUのギターが追いかけてくる。
最初に聞いて、「オープニングチューンとしては[RAISE MY SWORD]ほどじゃないかな‥」と感じたわけですが、聞けば聞くほどすべての魅力が詰まった名曲であり、今では彼らの歴史の中でも指折りの名曲じゃないかというほど大好きな曲です。
「また巡りゆく、運命が螺旋の様に」
「もがき続ける、未だ哀しみの渦の中で」
「見上げ想いを馳せる空、繰り返し問いかける宿命、いつか掲げた立ち上がる意味は、今もこの大地に轟いてゆく。」
さきほど、このアルバムの「歌詞」の魅力を書きましたが、まさにこの曲が象徴的。
続く[WINGS OF JUSTICE]はGALNERYUS史上、最速の部類に入るでしょうか。
爪弾かれるリフは初期のSONATA ARCTICAを思わせます。
小野さんの「Ahhhhhhhhh........!!」の叫び。魂の叫びです。
後半では7分→11分→12分‥という大曲が続きます。
長尺な曲が大好きな私にとってはたまらない構成です。
[RISING INFURIATION]は、このアルバムの「起承転結」でいうところの「転」に位置するでしょうか。
ストーリーが後半に向けて加速していく手前の葛藤を描いているかのような、時折不協和音のようなテクニカルな展開を持ちます。
[BRUTAL SPIRAL OF EMOTIONS]は三部構成。
倒れそうになりながらも立ち上がっていくかのような力強さに満ちた曲になっているように感じます。
「今にも張り裂けそうな想いを嘘に変えてくれるなら、苦境の全てに身を投じるだろう」
「今にも崩れそうな想いを嘘に変えてくれるなら、絶望の淵でも絶えず抗うだろう」
この曲での歌詞も印象的なのですが、「投じるだろう」「抗うだろう」のリズムがたまりません。
静かに紡がれるパートも美しくも切ない。ラストへ向けての大きな布石として存在しています。
そして最後を飾る[ULTIMATE SACRIFICE]へ。
美しいピアノとシンフォニックな音色に導かれ、クライマックスへ向かっていきます。
前作のラストを飾る組曲[UNDER THE FORCE OF COURAGE]に近い世界観を感じますが、より歌詞の「クライマックス」感が強いように感じます。
リフやサビは典型的な「ガルネリ節」と言えると思いますが、そうでありながら孤高の感を感じるのは、やはり歌詞の魅力でしょうか。
「今願うならば、この時間を戻して、約束の地へ駆けるだろう。これ以上何を失えば赦されるのだろう。」
「今叶うならば、この手を差し出して、消え去った過去を掴むだろう。」
「今願うならば、この時間を戻して、あの手をもう離さないだろう。吐き出した全ての想いは解き放たれゆく。」
「今叶うならば、あなたのその影を、もう一度だけ思い出して、何も求めるものなど無く、穏やかな温もりの中でただ笑い合っていたい。」
この曲の一部はMVとして事前に公開されていましたが、この曲を選んだバンドの意図を感じ取るのも面白いところかもしれません。
:
:
ということで、珍しくたくさんの歌詞をそのまま貼り付けてしまいました。
そのくらい、私にとってこのアルバムの「歌詞」は大きな意味を持ち、前作との違いを如実にし、このアルバムの魅力の魅力に大きく寄与しています。
前作のときにも書いたかもしれませんが、ずっと好きだったファンにとっては前作に続いて圧倒的傑作として存在し続けるのではないでしょうか。
バンドの底力、ポテンシャルに敬服してしまいます。
が、このバンドのことを知らない人に勧めるかというと、ちょっと濃密すぎるのではないかとも感じます。
そろそろ賛否両論あった[VETELGYUS]のような路線の、「メタルを知らない人でもその魅力を伝えられる」ようなアルバムも聞いてみたいなと感じたりもします。
まぁ、そういう曲を書くこともできるSYU、そういう曲でも圧倒的な魅力を放ってくれる小野さんがいてくれるからこその贅沢な悩みですが。
GALNERYUS「ULTIMATE SACRIFICE」Official MV
2017年05月26日
北の大地の誇り
メロディックデスメタル、というジャンルが定着して、ずいぶん時間が流れました。
CARCASS、ARCH ENEMY、今では音楽性が変わってしまいましたがIN FLAMES、DARK TRANQUILLITY‥。
そしてCHILDREN OF BODOMも。
その潮流は日本国内にも影響を及ぼしています。
メロディックデスメタルといえば、北欧。
ですが、日本のメロディックデスメタルバンドが、北欧とは一味違う「NORTHERN」テイストを産み出してくれました。
GYZE [NORTHERN HELL SONG]

北海道出身のスリーピース。
2013年に1stアルバムをリリース。これが3作目となります。
音楽性は、上述の通り。
北欧メロデスをベースにしています。
1st、2ndともに、充実の良作でした。
国産メロデスの中ではTHOUSAND EYESあたりと並んで若手の代表格と言えるでしょう。
そして、LOUDPARKでオープングアクトを努めた際には、圧巻のパフォーマンスを披露。
早朝からWall of Deathを発生させ、熱狂の渦を生み出しました。
が。
アルバムはたしかに素晴らしいのですが、個性という意味でズバ抜けたものは希薄でした。
「GYZEらしいメロディ」は纏いつつも、殻を破りきれていないような。
ベースとなっている北欧メロデスを意識しすぎるがゆえに(どうしても類似した音楽性になりがちなジャンルではありますが)、画一化されてる印象があった。
しかし、このアルバムで一気に化けました。
本人たち自らが「北海道の誇り」と語っている通り、北欧メロデスをベースにしながらも、漂う空気が全く異なる。
それは、同じ凍てつく北国でも、やはり生まれ育った空気を孕ませているからこそ、でしょう。
当然、1st/2ndの路線を継承しつつ‥なのですが、見事な相乗効果を見せてくれています。
吹きすさぶブリザードの中にも、キラキラと輝くダイヤモンドダストを見るかのような儚げな美しさ。
日本ならではの「わびさび」的テイスト。
GYZEにしか表現できない、そして日本人の、北海道の大地の誇りが自信として漲っています。
その自信の表れとして如実なのが、パワーメタル的なコーラスでしょうか。
意図的にライブでの盛り上がりを想定したかのような、分かりやすい大合唱。
そういったパートが随所に見受けられ、メジャー感とスケールの大きさに繋がっているように感じます。
流麗かつ泣きのリフに導かれ、一気に駆け抜けていくオープニングトラック[Pirates of Upas]。
分かりやすいサビのコーラス。
ライブでオーディエンスが拳を振り上げつつ叫びまくる姿が目に浮かびます。
間奏で見られる泣きまくりのギターソロもたまらない!
ちなみに[Upas]はアイヌ語で「雪」。
それを知って聞くと、またグっと感じるものがあります。
続く[Horkew]。
これはアイヌ語で「狼」のようですね。
明らかに初期チルボド的なキラキラした世界観。この時期のチルボドが好きな人(私です)には、たまらないのではないでしょうか。
[Black Shumari]で聞かれるリフのメロディは、BABYMETALを思い出すほどメロディアス。
[The Bloodthirsty Prince]は、パワーメタルのようなゴリゴリとした突進力を感じます。
エンディングは、彼らがYoutubeにアップした「メタル3兄弟」を想起するのは偶然でしょうか。狙いでしょうか。
(これも別の意味で素晴らしいので、見ていただきたいものです)
終盤に配置されたタイトルチューン[Northern Hell Song]は、このアルバムの一つのハイライトでしょう。
アルバムを象徴する美しいリフ、シンガロング必至のコーラス。
こういった明朗なチューンが自然と配置されているのも、このアルバムの素晴らしいところ。
ボーナストラック扱いの[Moonlight]は、もちろんベートーヴェンのあの名曲のアレンジ。
これも素晴らしい!
全般的に、私のようなメロディックパワーメタル好きにアピールできるような魅力が備わったことが、個人的には最も大きなプラス要因。
その新しい魅力は、おそらく旧知のファン、生粋のメロデスファンの嗜好を損ねることなく備わっている‥と思いたい。
そして語弊はあるかもしれませんが、ジャパニーズメタル的なメロディラインが見えるところも個人的には嬉しい。
ワールドワイドで活躍を目指すバンドが多いですが、どうしても海外指向だと海外のバンドの中に個性が埋もれてしまいがち。
持って生まれたバックグラウンド(風土)を生かせば、そういった要素が生まれてくるのは必然のことだと思います。
それを包み隠すことなく、己の武器として昇華させたとき、新しい魅力が生まれる。
目指すはヴァッケンのトリ。だそうだ。
まだ先は長いとは思いますが、一皮も二皮も剥けた感のあるGYZE。
ジャパニーズメタルシーンを語る上で外せないバンドになりました。
:
:
そして、2017/5/24には、PureRockJapanのステージに立ちます。
GALNERYUS、摩天楼オペラ、ALDIOUSと共に、ジャパニーズメタルの魅力を存分に魅せてくれることでしょう。
私も川崎に参戦します!
GYZE - Pirates of Upas 【Lyric Video】
CARCASS、ARCH ENEMY、今では音楽性が変わってしまいましたがIN FLAMES、DARK TRANQUILLITY‥。
そしてCHILDREN OF BODOMも。
その潮流は日本国内にも影響を及ぼしています。
メロディックデスメタルといえば、北欧。
ですが、日本のメロディックデスメタルバンドが、北欧とは一味違う「NORTHERN」テイストを産み出してくれました。
GYZE [NORTHERN HELL SONG]

北海道出身のスリーピース。
2013年に1stアルバムをリリース。これが3作目となります。
音楽性は、上述の通り。
北欧メロデスをベースにしています。
1st、2ndともに、充実の良作でした。
国産メロデスの中ではTHOUSAND EYESあたりと並んで若手の代表格と言えるでしょう。
そして、LOUDPARKでオープングアクトを努めた際には、圧巻のパフォーマンスを披露。
早朝からWall of Deathを発生させ、熱狂の渦を生み出しました。
が。
アルバムはたしかに素晴らしいのですが、個性という意味でズバ抜けたものは希薄でした。
「GYZEらしいメロディ」は纏いつつも、殻を破りきれていないような。
ベースとなっている北欧メロデスを意識しすぎるがゆえに(どうしても類似した音楽性になりがちなジャンルではありますが)、画一化されてる印象があった。
しかし、このアルバムで一気に化けました。
本人たち自らが「北海道の誇り」と語っている通り、北欧メロデスをベースにしながらも、漂う空気が全く異なる。
それは、同じ凍てつく北国でも、やはり生まれ育った空気を孕ませているからこそ、でしょう。
当然、1st/2ndの路線を継承しつつ‥なのですが、見事な相乗効果を見せてくれています。
吹きすさぶブリザードの中にも、キラキラと輝くダイヤモンドダストを見るかのような儚げな美しさ。
日本ならではの「わびさび」的テイスト。
GYZEにしか表現できない、そして日本人の、北海道の大地の誇りが自信として漲っています。
その自信の表れとして如実なのが、パワーメタル的なコーラスでしょうか。
意図的にライブでの盛り上がりを想定したかのような、分かりやすい大合唱。
そういったパートが随所に見受けられ、メジャー感とスケールの大きさに繋がっているように感じます。
流麗かつ泣きのリフに導かれ、一気に駆け抜けていくオープニングトラック[Pirates of Upas]。
分かりやすいサビのコーラス。
ライブでオーディエンスが拳を振り上げつつ叫びまくる姿が目に浮かびます。
間奏で見られる泣きまくりのギターソロもたまらない!
ちなみに[Upas]はアイヌ語で「雪」。
それを知って聞くと、またグっと感じるものがあります。
続く[Horkew]。
これはアイヌ語で「狼」のようですね。
明らかに初期チルボド的なキラキラした世界観。この時期のチルボドが好きな人(私です)には、たまらないのではないでしょうか。
[Black Shumari]で聞かれるリフのメロディは、BABYMETALを思い出すほどメロディアス。
[The Bloodthirsty Prince]は、パワーメタルのようなゴリゴリとした突進力を感じます。
エンディングは、彼らがYoutubeにアップした「メタル3兄弟」を想起するのは偶然でしょうか。狙いでしょうか。
(これも別の意味で素晴らしいので、見ていただきたいものです)
終盤に配置されたタイトルチューン[Northern Hell Song]は、このアルバムの一つのハイライトでしょう。
アルバムを象徴する美しいリフ、シンガロング必至のコーラス。
こういった明朗なチューンが自然と配置されているのも、このアルバムの素晴らしいところ。
ボーナストラック扱いの[Moonlight]は、もちろんベートーヴェンのあの名曲のアレンジ。
これも素晴らしい!
全般的に、私のようなメロディックパワーメタル好きにアピールできるような魅力が備わったことが、個人的には最も大きなプラス要因。
その新しい魅力は、おそらく旧知のファン、生粋のメロデスファンの嗜好を損ねることなく備わっている‥と思いたい。
そして語弊はあるかもしれませんが、ジャパニーズメタル的なメロディラインが見えるところも個人的には嬉しい。
ワールドワイドで活躍を目指すバンドが多いですが、どうしても海外指向だと海外のバンドの中に個性が埋もれてしまいがち。
持って生まれたバックグラウンド(風土)を生かせば、そういった要素が生まれてくるのは必然のことだと思います。
それを包み隠すことなく、己の武器として昇華させたとき、新しい魅力が生まれる。
目指すはヴァッケンのトリ。だそうだ。
まだ先は長いとは思いますが、一皮も二皮も剥けた感のあるGYZE。
ジャパニーズメタルシーンを語る上で外せないバンドになりました。
:
:
そして、2017/5/24には、PureRockJapanのステージに立ちます。
GALNERYUS、摩天楼オペラ、ALDIOUSと共に、ジャパニーズメタルの魅力を存分に魅せてくれることでしょう。
私も川崎に参戦します!
GYZE - Pirates of Upas 【Lyric Video】
2017年04月27日
咲き誇る
日本のバンドだから‥と、自分で一線を引いている人はさすがに少なくても、「日本語だから」という一線を引いている人は少なからずいると思う。
そして、キャッチーな音だと「メタルじゃない」と切り捨てる人もいるかもしれない。
が、ワタシはこういう音に出会えると、ココロの底から「ニッポン人でよかった」と思えるのです。
Tears of Tragedy [STATICE]

名前だけは聞いたことがあった。
これの前のアルバムのジャケットは記憶にあった。
けど、手は伸びてなかった。
が、これが素晴らしいのだ!
バンドの歴史を紐解いてみると、2008年結成。
このアルバムは3rdアルバムになるようです。
メロディックスピードメタル、シンフォニックメタルを基本に、儚く美しく柔和な世界。
そして、日本人らしい、J-POPを思わせるキャッチーなメロディ。
ジャパニーズメタル、かくあるべし。という一つの理想とも言えるのではないでしょうか。
疾走感に満ちた曲。
キラキラと煌きを纏った曲。
穏やかに、たゆたうような曲
アップテンポに刻まれていくポップな曲。
目眩くように美しい色彩と景色。
ジャケットのイメージそのままの世界が次々と紡ぎだされていきます。
この世界観を支えているのが、HARUKA嬢の歌声。
正直に言うと、最初聞いたときには「メロディは素晴らしいのに、ヴォーカルのパンチが足りないのが惜しい‥」と思った。
が、聞けば聞くほど、この声だからこそ、このバンドの音楽を美しく彩っていることに気がつく。
穏やかに、柔らかく、優しく。
ときに浮遊するように。
ときに力強く。
バンドのイメージを際立たせています。
ギターのTORUは、THOUSAND EYESでも活躍中。
千眼でのリフの刻みとは全くことなる、オーソドックスなハードロック的リフを聞かせてくれます。
穏やかにカウントダウンを奏でるように始まり、徐々に視界が広がっていくかのようなイントロ[BEYOND THE CHAOS]を経て‥
花たちが一斉に咲き誇るかのような華やかなオープニングで幕を開ける[VOID ACT]。
その美しさと相反するようなHARUKA嬢のシリアスな声が印象的。
ザクザクと刻まれるリズムとスピード感が心地よい[BE INCONSISTENT]を経て‥
アルバムの一つの象徴と言えるでしょう、[ALWAYS]へ。
太陽が燦々を降り注ぐ暖かさのような。
そして、一歩一歩、歩を進めていくようなポジティブなメロディ。
希望に満ちて、空に両手を広げているかのような世界が脳裏をよぎります。
J-POP的であり、メタルならではの様式美を孕みつつ、メタルファンにも一般的な音楽ファンにもアピールできそうな素晴らしい曲です。
そういった観点では、GALNERYUSの[ENDRESS STORY]を思いだします。
[BLUE LOTUS]では、美しくクールな疾走感。
サビでは氷上を、水面を舞うかのような透明感を携えつつ、メタリックなスピード感を体感できます。
[ACCEPT YOURSELF]は最もヘヴィメタリックな質感でしょうか。
その質感は、まさにメロディックスピードメタル+様式美。
そのメタリックな質感の中で、HARUKA嬢の声はさらに際立ちます。
その声のおかげで、こういった曲でもTEARS OF TRAGEDYであることを力強くアピール。
オペラチックな一面、そしてストロングな一面も見せてくれています。
終盤に配された[CURSE BRIDE]は、12分を越える大曲。
ROYAL HUNTを思わせる、閉ざされた空間で繰り広げられるような、いい意味で「息詰まる」展開。
脳裏にイメージされていく中世の城、教会。
大曲好き、中世好きのワタシにはたまらない展開。
印象としては、ワタシの大好きなXの名曲[ROSE OF PAIN]を思い出します。
さらには、これまたワタシの大好きな名曲、ANGRAの[Carolina IV]をダークにしたかのような。
[PASTEL COLOR]の優しい疾走感でエンディングを迎えて行くのも、このアルバムらしいなと感じます。
:
:
:
ガールズバンド、女性ヴォーカルバンド、百花繚乱の時代。
様々なベクトルへ突出した個性を求められる時代。
そんな中、ありそうでなかった、女性ならではの柔らかさと優しさに包まれたアルバム。
ヘヴィメタルでありながら、J-POPのいいところを吸収したその音楽性。
奇をてらったわけではない。
日本の女性の美しさを自然とクローズアップし、日本のヘヴィメタル「ジャパメタ」の王道を行くかのような音楽性。
次のアルバムも楽しみであると同時に、ヘヴィメタルファンだけでなく、幅広く活躍を願いたいバンドです。
TEARS OF TRAGEDY - Void Act (OFFICIAL VIDEO)
そして、キャッチーな音だと「メタルじゃない」と切り捨てる人もいるかもしれない。
が、ワタシはこういう音に出会えると、ココロの底から「ニッポン人でよかった」と思えるのです。
Tears of Tragedy [STATICE]

名前だけは聞いたことがあった。
これの前のアルバムのジャケットは記憶にあった。
けど、手は伸びてなかった。
が、これが素晴らしいのだ!
バンドの歴史を紐解いてみると、2008年結成。
このアルバムは3rdアルバムになるようです。
メロディックスピードメタル、シンフォニックメタルを基本に、儚く美しく柔和な世界。
そして、日本人らしい、J-POPを思わせるキャッチーなメロディ。
ジャパニーズメタル、かくあるべし。という一つの理想とも言えるのではないでしょうか。
疾走感に満ちた曲。
キラキラと煌きを纏った曲。
穏やかに、たゆたうような曲
アップテンポに刻まれていくポップな曲。
目眩くように美しい色彩と景色。
ジャケットのイメージそのままの世界が次々と紡ぎだされていきます。
この世界観を支えているのが、HARUKA嬢の歌声。
正直に言うと、最初聞いたときには「メロディは素晴らしいのに、ヴォーカルのパンチが足りないのが惜しい‥」と思った。
が、聞けば聞くほど、この声だからこそ、このバンドの音楽を美しく彩っていることに気がつく。
穏やかに、柔らかく、優しく。
ときに浮遊するように。
ときに力強く。
バンドのイメージを際立たせています。
ギターのTORUは、THOUSAND EYESでも活躍中。
千眼でのリフの刻みとは全くことなる、オーソドックスなハードロック的リフを聞かせてくれます。
穏やかにカウントダウンを奏でるように始まり、徐々に視界が広がっていくかのようなイントロ[BEYOND THE CHAOS]を経て‥
花たちが一斉に咲き誇るかのような華やかなオープニングで幕を開ける[VOID ACT]。
その美しさと相反するようなHARUKA嬢のシリアスな声が印象的。
ザクザクと刻まれるリズムとスピード感が心地よい[BE INCONSISTENT]を経て‥
アルバムの一つの象徴と言えるでしょう、[ALWAYS]へ。
太陽が燦々を降り注ぐ暖かさのような。
そして、一歩一歩、歩を進めていくようなポジティブなメロディ。
希望に満ちて、空に両手を広げているかのような世界が脳裏をよぎります。
J-POP的であり、メタルならではの様式美を孕みつつ、メタルファンにも一般的な音楽ファンにもアピールできそうな素晴らしい曲です。
そういった観点では、GALNERYUSの[ENDRESS STORY]を思いだします。
[BLUE LOTUS]では、美しくクールな疾走感。
サビでは氷上を、水面を舞うかのような透明感を携えつつ、メタリックなスピード感を体感できます。
[ACCEPT YOURSELF]は最もヘヴィメタリックな質感でしょうか。
その質感は、まさにメロディックスピードメタル+様式美。
そのメタリックな質感の中で、HARUKA嬢の声はさらに際立ちます。
その声のおかげで、こういった曲でもTEARS OF TRAGEDYであることを力強くアピール。
オペラチックな一面、そしてストロングな一面も見せてくれています。
終盤に配された[CURSE BRIDE]は、12分を越える大曲。
ROYAL HUNTを思わせる、閉ざされた空間で繰り広げられるような、いい意味で「息詰まる」展開。
脳裏にイメージされていく中世の城、教会。
大曲好き、中世好きのワタシにはたまらない展開。
印象としては、ワタシの大好きなXの名曲[ROSE OF PAIN]を思い出します。
さらには、これまたワタシの大好きな名曲、ANGRAの[Carolina IV]をダークにしたかのような。
[PASTEL COLOR]の優しい疾走感でエンディングを迎えて行くのも、このアルバムらしいなと感じます。
:
:
:
ガールズバンド、女性ヴォーカルバンド、百花繚乱の時代。
様々なベクトルへ突出した個性を求められる時代。
そんな中、ありそうでなかった、女性ならではの柔らかさと優しさに包まれたアルバム。
ヘヴィメタルでありながら、J-POPのいいところを吸収したその音楽性。
奇をてらったわけではない。
日本の女性の美しさを自然とクローズアップし、日本のヘヴィメタル「ジャパメタ」の王道を行くかのような音楽性。
次のアルバムも楽しみであると同時に、ヘヴィメタルファンだけでなく、幅広く活躍を願いたいバンドです。
TEARS OF TRAGEDY - Void Act (OFFICIAL VIDEO)
2017年04月05日
慟哭
彼の名を知っている人は、どのタイミングでその名を知ったでしょうか。
長い歴史を誇る、日本屈指の泣きのリフメーカー。
彼が紆余曲折を経て辿りついた、「今」の姿を映し出すバンドです。
VOLCANO / Juggernaut

ワタシが彼を知ったのは、XやZI:KILLが活躍していた、ジャパメタ百花繚乱の黎明期。
そんな中、GARGOYLEで燦然と現れたギターヒーロー、屍忌蛇。
その屍忌蛇が結成したジャパニーズヘヴィメタルバンド、VOLCANO。
この作品が5thになるようです。
GARGOYLEの後、アニメタルを経て、このバンドに辿り着きました。
ヴォーカルにはAIONのNOV。
AION、GARGOYLEといった名前でピンとくる方はワタシと同世代でしょう。
そして、そんな方がイメージする音‥
屍忌蛇の泣きのリフ。
NOVの熱い叫び。
どちらもタップリと詰め込まれた、その期待を裏切らない音になっています。
正統派ヘヴィメタルサウンドにNOVの力強く濃厚なシャウトが響く。
ときにスラッシーに、時にブルータルに。
そういった意味ではメロディックデスメタル的なな攻撃力を秘めてはいますが、そのメロディセンスが突出していることでパワーメタル的な風合いを感じさせます。
そしてバッキングリフは鋭利に、ギターソロでは徹底して泣きのソロ。
基本的なサウンドとしては、AIONに近いでしょうか。
‥まぁ、GARGOYLEがKIBAを中心としたオリエンタルかつ独創的すぎたこともありますが。
荘厳なオーケストレーションで幕を開ける[Dawn Attack]。
まるでSABATONを思わせるようなビッグスケールのインストナンバーに胸が高鳴ります。
そして一気呵成にザクザクとした強靱なリフとNOVの叫びに導かれて[Sacred Eternity]へ!
全てを薙ぎ倒して突き進むゴリゴリとした突進力は正統派パワーメタルの爽快感を思わせます。
中間部での屍忌蛇の泣きのギターソロ!
まさにGARGOYLEで聞いていた「あの音」が、メタリックでありながら、優しく、悲しく、全ての空間を支配します。
[Get Mad Child]は、OUTRAGEのリフを想起します。
そういった意味ではスラッシーな要素が感じられるということかもしれません。
いったんテンポを落としておいてからの、テクニカルに紡ぎつつ加速、泣きのリフからの再びスラッシーな流れへ。
一筋縄ではいかない展開が耳を離しません。
[Shadow]は哀愁に満ちたナンバー。
そんなナンバーの中でも、さらにその哀愁をヴォリュームアップさせるギターソロがたまりません。
[I Miss]は心の叫びを思わせます。
切ない。
もちろん、その切なさをさらに際立たせるギターソロ。
[Wait Until You Return]は、♪オーオーオーオー!!オーオーオーオー!!の大合唱が目に浮かぶパワーメタルチューン。
ジャーマンメタル的な泣きのギターソロ、必聴!
:
:
:
といった具合に、曲もクオリティも正統派であることを軸に、パワーメタル路線、スラッシュ路線と、「柱」がシッカリしてるからこそのブレのない中での幅広さ。
ですが、やはり耳は屍忌蛇のリフを捉えて離しません。
NOVの声も、「間違いなくNOV」という個性を放っており、この二人の相乗効果こそがこのバンドの魅力と言えるでしょう。
が、AION時代からワタシ自身が感じていた、若干のNOVに対する違和感(発音とか)は今も拭いきれないのも事実。
そういった意味でも、やはりこのアルバムは屍忌蛇のメロディの洪水を楽しむアルバムだな、と思います。
とはいえ、他のジャパニーズメタル勢では表現できない唯一無二の個性は間違いなくVOLCANO印。
このバンドが長く続いていることは、GARGOYLE時代から屍忌蛇のギターに惚れ込んでいたワタシとしては嬉しい限りだ。
屍忌蛇のスタイルもNOVのスタイルも全く変わっていない。
二人とも、確固たる信じた道があって、その道を邁進しているのだ。
VOLCANO / Sacred Eternity
長い歴史を誇る、日本屈指の泣きのリフメーカー。
彼が紆余曲折を経て辿りついた、「今」の姿を映し出すバンドです。
VOLCANO / Juggernaut

ワタシが彼を知ったのは、XやZI:KILLが活躍していた、ジャパメタ百花繚乱の黎明期。
そんな中、GARGOYLEで燦然と現れたギターヒーロー、屍忌蛇。
その屍忌蛇が結成したジャパニーズヘヴィメタルバンド、VOLCANO。
この作品が5thになるようです。
GARGOYLEの後、アニメタルを経て、このバンドに辿り着きました。
ヴォーカルにはAIONのNOV。
AION、GARGOYLEといった名前でピンとくる方はワタシと同世代でしょう。
そして、そんな方がイメージする音‥
屍忌蛇の泣きのリフ。
NOVの熱い叫び。
どちらもタップリと詰め込まれた、その期待を裏切らない音になっています。
正統派ヘヴィメタルサウンドにNOVの力強く濃厚なシャウトが響く。
ときにスラッシーに、時にブルータルに。
そういった意味ではメロディックデスメタル的なな攻撃力を秘めてはいますが、そのメロディセンスが突出していることでパワーメタル的な風合いを感じさせます。
そしてバッキングリフは鋭利に、ギターソロでは徹底して泣きのソロ。
基本的なサウンドとしては、AIONに近いでしょうか。
‥まぁ、GARGOYLEがKIBAを中心としたオリエンタルかつ独創的すぎたこともありますが。
荘厳なオーケストレーションで幕を開ける[Dawn Attack]。
まるでSABATONを思わせるようなビッグスケールのインストナンバーに胸が高鳴ります。
そして一気呵成にザクザクとした強靱なリフとNOVの叫びに導かれて[Sacred Eternity]へ!
全てを薙ぎ倒して突き進むゴリゴリとした突進力は正統派パワーメタルの爽快感を思わせます。
中間部での屍忌蛇の泣きのギターソロ!
まさにGARGOYLEで聞いていた「あの音」が、メタリックでありながら、優しく、悲しく、全ての空間を支配します。
[Get Mad Child]は、OUTRAGEのリフを想起します。
そういった意味ではスラッシーな要素が感じられるということかもしれません。
いったんテンポを落としておいてからの、テクニカルに紡ぎつつ加速、泣きのリフからの再びスラッシーな流れへ。
一筋縄ではいかない展開が耳を離しません。
[Shadow]は哀愁に満ちたナンバー。
そんなナンバーの中でも、さらにその哀愁をヴォリュームアップさせるギターソロがたまりません。
[I Miss]は心の叫びを思わせます。
切ない。
もちろん、その切なさをさらに際立たせるギターソロ。
[Wait Until You Return]は、♪オーオーオーオー!!オーオーオーオー!!の大合唱が目に浮かぶパワーメタルチューン。
ジャーマンメタル的な泣きのギターソロ、必聴!
:
:
:
といった具合に、曲もクオリティも正統派であることを軸に、パワーメタル路線、スラッシュ路線と、「柱」がシッカリしてるからこそのブレのない中での幅広さ。
ですが、やはり耳は屍忌蛇のリフを捉えて離しません。
NOVの声も、「間違いなくNOV」という個性を放っており、この二人の相乗効果こそがこのバンドの魅力と言えるでしょう。
が、AION時代からワタシ自身が感じていた、若干のNOVに対する違和感(発音とか)は今も拭いきれないのも事実。
そういった意味でも、やはりこのアルバムは屍忌蛇のメロディの洪水を楽しむアルバムだな、と思います。
とはいえ、他のジャパニーズメタル勢では表現できない唯一無二の個性は間違いなくVOLCANO印。
このバンドが長く続いていることは、GARGOYLE時代から屍忌蛇のギターに惚れ込んでいたワタシとしては嬉しい限りだ。
屍忌蛇のスタイルもNOVのスタイルも全く変わっていない。
二人とも、確固たる信じた道があって、その道を邁進しているのだ。
VOLCANO / Sacred Eternity
2016年11月30日
不死鳥、舞う
ありがちなタイトルだな‥と思った。
そして、「まぁ、以前のレベルを期待しちゃいけないだろうな」と、自らハードルを下げてたこともあった。
そんな失礼なスタンスでCDをトレイに乗せて‥驚いた。
まさに不死鳥だ。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING

このブログをご覧いただいてる方なら、ときどき目にするバンド名だと思います。
Wikiによると、結成は2007年。もうすぐ10年ですね。
メジャーからリリースされたアルバムは4枚。
そして、このアルバムはミニアルバムとなっています。
私が摩天楼オペラと出会ったのは、2ndアルバムリリース前。
何がキッカケだったか覚えてないのですが、フと聞くことになった[GLORIA]は衝撃だった。
和製RHAPSODYだ。
和製[Emerald Sword]だ。
一気に虜になった。
さらに[Innovational Symphonia]。
そして、「グロリア三部作」(と、勝手に呼んでいる)のラストとなる「喝采と激情のグロリア」。
全てが素晴らしく、全てが劇的だった。
見た目はいかにもヴィジュアル系。
ヴォーカルの歌い回しやビブラートもヴィジュアル系。
耽美的世界観もヴィジュアル系。
だから、洋楽指向のメタルファンにとっては嫌悪感を抱かれるかもしれない。
が、ワタシは元々、X、D'ERLANGER、ZI:KILLといったところを聞いてきた土壌があるからか、全く違和感がない。
だから、ヴィジュアル系に寄っているサウンドでも、メタル的素晴らしさがあればスムーズに咀嚼できる。
摩天楼オペラは、まさにその典型だ。
ヴィジュアル系でありながら、サウンドはメタル指向。
バンド名の由来であり、コンセプトでもある「現代的なものと伝統美の融合」。
それは、メタルとヴィジュアル系の融合でもある。
そんな彼らだが、上述したようた突出した名曲たちがあるのに対して、アルバム全体で見ると曲単位でクオリティの差がある気がしていた。
歌詞も含めて、「もう少し全体的に底上げできればなぁ」という感があった。
そんな中。
ギターのAnziが脱退。
Anziは、国内のメロパワシーンでは伝説とも言えるMasterpieceのメンバーだった。
そのAnziが抜けた影響は大きいだろうな、と思った。
その想いが、冒頭の印象の一部に繋がっていることもあった。
が。
素晴らしいのだ。
ヴィジュアルもシンプルに、黒を基調としたメンバー写真に。
より一層、メタル寄りになってきた感があります。
前作の[BURNING SOUL]でもメタル色を意図的に強めてきた感がありましたが、若干無理してるムードを感じた。
今回はそれを感じない。
まさに不死鳥が羽ばたくかのような、自然かつ力みのない、大きなスケールアップを見せてくれています。
オープニングを飾るイントロダクションとなる[THE RISING]。
Xの名作[BLUE BLOOD]に於ける[PROLOGUE (WORLD ANTHEM)]のような雄大な世界観を魅せてくれます。
そして、シンフォニックかつ強靱な疾走感を伴って[PHOENIX]へ!
以前は「和製RHAPSODYのよう」と表現しましたが、これはまるで和製SONATA ARCTICA。
いや、SONATA ARCTICA的な疾走感に、さらに摩天楼オペラならではの、そしていい意味でのヴィジュアル系的なゴージャスな装飾。
この装飾がさらに荘厳さを印象づけます。
生きる意味。
大地や地球への賛美。
感謝。
希望。
歌詞も実に魅力的。
以前の「グロリア三部作」、そしてその後のアルバムを経て、「あー、やっぱりあの頃がピークだったか」という想いを覆す、まさに起死回生の一曲。
そして後半に配置された[MASK]も魅力的。
リフの刻み方、キーボードの追随は、これまたSONATA ARCTICAの名曲[Abandoned, Pleased, Brainwashed, Exploited]を思い出します。
この曲でも[PHOENIX]でも、サビでの展開、そしてラストに向けてのリズムチェンジ‥このあたりのテクニカルなところも摩天楼オペラの魅力です。
「何十年先も今日みたいに」は、ラストを締めくくるにふさわしい、穏やかで美しく、スケールの大きなパワーバラード。
聞き終えた後の心地よさを演出してくれます。
:
:
:
BABYMETALだけでなく、ヴィジュアル系のバンドも、メタルファンには受け入れられづらいことは分かっている。
どのあたりが、そのハードルになっているかも分かる。
が、これまたBABYMETALのときにも書いたかもしれないけど、メタルかどうかなんて境界線は必要ない。
もし、そういう先入観だけで敬遠しているのであれば、一度は触れてみてほしい。
そして、敬遠するのはそのあとでもいい。
個人的には、毎年LOUDPARKへの参戦を楽しみにしているバンド。
このミニアルバムで、またその扉への距離は縮まったと感じます。
下記に貼るアルバムトレイラーには
「自分の愛した音楽、バンドが愛した音楽、ファンが愛してくれた音楽‥それはきっとこんな音」
という言葉が綴られています。
この言葉が、現在のバンドのモチベーションを物語ってくれています。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING [全曲試聴]
全曲ブツ切りになってるのが勿体ない、全ての魅力は伝えられないのが残念ですが、雰囲気だけでも。
GLORIA/摩天楼オペラ
2012年リリース。サビの高揚感は、まさに和製[Emerald Sword]。
そして、「まぁ、以前のレベルを期待しちゃいけないだろうな」と、自らハードルを下げてたこともあった。
そんな失礼なスタンスでCDをトレイに乗せて‥驚いた。
まさに不死鳥だ。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING

このブログをご覧いただいてる方なら、ときどき目にするバンド名だと思います。
Wikiによると、結成は2007年。もうすぐ10年ですね。
メジャーからリリースされたアルバムは4枚。
そして、このアルバムはミニアルバムとなっています。
私が摩天楼オペラと出会ったのは、2ndアルバムリリース前。
何がキッカケだったか覚えてないのですが、フと聞くことになった[GLORIA]は衝撃だった。
和製RHAPSODYだ。
和製[Emerald Sword]だ。
一気に虜になった。
さらに[Innovational Symphonia]。
そして、「グロリア三部作」(と、勝手に呼んでいる)のラストとなる「喝采と激情のグロリア」。
全てが素晴らしく、全てが劇的だった。
見た目はいかにもヴィジュアル系。
ヴォーカルの歌い回しやビブラートもヴィジュアル系。
耽美的世界観もヴィジュアル系。
だから、洋楽指向のメタルファンにとっては嫌悪感を抱かれるかもしれない。
が、ワタシは元々、X、D'ERLANGER、ZI:KILLといったところを聞いてきた土壌があるからか、全く違和感がない。
だから、ヴィジュアル系に寄っているサウンドでも、メタル的素晴らしさがあればスムーズに咀嚼できる。
摩天楼オペラは、まさにその典型だ。
ヴィジュアル系でありながら、サウンドはメタル指向。
バンド名の由来であり、コンセプトでもある「現代的なものと伝統美の融合」。
それは、メタルとヴィジュアル系の融合でもある。
そんな彼らだが、上述したようた突出した名曲たちがあるのに対して、アルバム全体で見ると曲単位でクオリティの差がある気がしていた。
歌詞も含めて、「もう少し全体的に底上げできればなぁ」という感があった。
そんな中。
ギターのAnziが脱退。
Anziは、国内のメロパワシーンでは伝説とも言えるMasterpieceのメンバーだった。
そのAnziが抜けた影響は大きいだろうな、と思った。
その想いが、冒頭の印象の一部に繋がっていることもあった。
が。
素晴らしいのだ。
ヴィジュアルもシンプルに、黒を基調としたメンバー写真に。
より一層、メタル寄りになってきた感があります。
前作の[BURNING SOUL]でもメタル色を意図的に強めてきた感がありましたが、若干無理してるムードを感じた。
今回はそれを感じない。
まさに不死鳥が羽ばたくかのような、自然かつ力みのない、大きなスケールアップを見せてくれています。
オープニングを飾るイントロダクションとなる[THE RISING]。
Xの名作[BLUE BLOOD]に於ける[PROLOGUE (WORLD ANTHEM)]のような雄大な世界観を魅せてくれます。
そして、シンフォニックかつ強靱な疾走感を伴って[PHOENIX]へ!
以前は「和製RHAPSODYのよう」と表現しましたが、これはまるで和製SONATA ARCTICA。
いや、SONATA ARCTICA的な疾走感に、さらに摩天楼オペラならではの、そしていい意味でのヴィジュアル系的なゴージャスな装飾。
この装飾がさらに荘厳さを印象づけます。
生きる意味。
大地や地球への賛美。
感謝。
希望。
歌詞も実に魅力的。
以前の「グロリア三部作」、そしてその後のアルバムを経て、「あー、やっぱりあの頃がピークだったか」という想いを覆す、まさに起死回生の一曲。
そして後半に配置された[MASK]も魅力的。
リフの刻み方、キーボードの追随は、これまたSONATA ARCTICAの名曲[Abandoned, Pleased, Brainwashed, Exploited]を思い出します。
この曲でも[PHOENIX]でも、サビでの展開、そしてラストに向けてのリズムチェンジ‥このあたりのテクニカルなところも摩天楼オペラの魅力です。
「何十年先も今日みたいに」は、ラストを締めくくるにふさわしい、穏やかで美しく、スケールの大きなパワーバラード。
聞き終えた後の心地よさを演出してくれます。
:
:
:
BABYMETALだけでなく、ヴィジュアル系のバンドも、メタルファンには受け入れられづらいことは分かっている。
どのあたりが、そのハードルになっているかも分かる。
が、これまたBABYMETALのときにも書いたかもしれないけど、メタルかどうかなんて境界線は必要ない。
もし、そういう先入観だけで敬遠しているのであれば、一度は触れてみてほしい。
そして、敬遠するのはそのあとでもいい。
個人的には、毎年LOUDPARKへの参戦を楽しみにしているバンド。
このミニアルバムで、またその扉への距離は縮まったと感じます。
下記に貼るアルバムトレイラーには
「自分の愛した音楽、バンドが愛した音楽、ファンが愛してくれた音楽‥それはきっとこんな音」
という言葉が綴られています。
この言葉が、現在のバンドのモチベーションを物語ってくれています。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING [全曲試聴]
全曲ブツ切りになってるのが勿体ない、全ての魅力は伝えられないのが残念ですが、雰囲気だけでも。
GLORIA/摩天楼オペラ
2012年リリース。サビの高揚感は、まさに和製[Emerald Sword]。
2016年11月08日
ようこそ!
今、国内屈指の女性ヴォーカリストだと思います。
が、前バンドは「さぁ、これから」というところで瓦解してしまった。
そして、新たな船出となるアルバムです。
Fuki Commune / Welcome!

元、LIGHT BRINGERのFUKIちゃんとして。
現、Unlucky Morpheusの天外冬黄として。
時にメタルアーティストとして。
時に同人音楽アーティストとして。
時にアニソンヴォーカリストとして。
様々な顔を持つ女性ヴォーカリストである彼女のソロプロジェクトのアルバムです。
ワタシが彼女の存在を知ったのは、Dragon GuardianのDRAGONVARIUSというアルバム。
元々、同人のメロディックスピードメタルプロジェクトだったDragonGuardianは、このアルバムでFUKIちゃんを迎えたことで一気に花開きました。
メジャー感を纏い、大きくステップアップしました。
このアルバムでのFUKIちゃんの力強くキュートな声はインパクト充分でした。
その後、彼女が参加しているLIGHT BRINGERを知り、いまや伝説とも言える、東京キネマ倶楽部でのDragonGuardian / MinstreliX / LightBringerのライブに参戦。
ナマで見る彼女を見て「・・やっぱりすげぇ!」と確信、惚れ込みました。
そしてLightBringerも素晴らしいアルバムをリリース。
FUKIちゃんの魅力が堪能できるキャッチーな曲が粒揃い。まさに「これからだな!」というところでの活動休止。
Unlucky Morpheusも悪くないのですが、やはりLightBringerと比べるとやや魅力に劣る感があり、「FUKIちゃん、どうなるんだよ‥これだけの才能を埋もれさせるなよ‥」と思ってました。
そんな中、リリースされた「FUKI」の名を冠に据えたプロジェクトのアルバムです。
全体的には、上述した彼女の魅力が満遍なく散りばめられている印象です。
LightBringerやDragonGuardianのような、ひとつのコンセプトで統一されているというアルバムとは異なります。
彼女の声は快活であり、実にカラフルだ。
キュートな声色。
パワフルな声色。
キャッチーな声色。
シリアスな声色。
曲によって様々な表情を魅せてくれます。
そして、どの曲でも強い芯を持ち、彼女の周辺に乱反射するようなキラキラとした華やかさを持っています。
この華やかさはFUKIちゃんならでは。
若干、近未来的&ヘヴィな装いのイントロで「・・お?」と身構えてしまいますが‥
LightBringer時代を思い出させるキャッチーなメタルチューン[月が満ちる前に]で「これだよ!」と安堵を覚えます。
挑発すら感じるような余裕。
一曲目にして、彼女の掌の上で踊らされるかのような錯覚。
やっぱりFUKIちゃんにはこういう曲が似合う。
続く[輝く夜へようこそ]は、アニソン的チューン。
まるで声優のようなメリハリと表情が見え隠れする、万華鏡のような煌きとアニソンならではの高揚感がたまりません。
こういう曲にも対応できちゃう、そしてこういう曲でも圧倒的存在感を見せるのです。
[I'll never let you down!]はスピーディーでメタリック、そして彼女のシリアスな一面を見ることができる曲。
タイプとしては、[月が満ちる前に][輝く夜へようこそ]のような歌唱こそFUKIちゃんの魅力であるなぁと思うわけですが、メタルヴォーカリストとしての存在感を見ることができます。
[僕が生きる世界]は、アニソン的な魅力に加え、J-POP的なコマーシャルな一面も見え隠れします。
[狂い咲け雪月華]は陰陽座のようなオリエンタルな世界観。
今までにないタイプの曲ですが、これもまた彼女の色に染められています。
[青い季節に]は、シングルカット向きのキャッチーな曲、でしょうか。
爽やかで透き通るような、ピュアな輝きに満ちています。
ラストを飾る[Sail on my love]では、再びLightBringerを思わせる明朗な疾走感。
新しい一歩にふさわしい歌詞は、今後をポジティブに見据える姿が。
歌詞通り、大海原に漕ぎだすかのようなスケールの大きい、それでいて自然体な彼女の声が際立ちます。
アルバムのタイトル通り、これが初FUKIちゃんとなる方々には「ようこそ!!」という名刺代わり。
既にFUKIちゃんをご存じの方にとっては、今までの集大成でもあり、今の彼女の現在進行形であり、ひとまず表舞台に立ってくれたことに安堵。
ただし、純粋なヘヴィメタルヴォーカリストとして対峙すると、アニソンっぽい快活さが鼻につく可能性があります。
まぁ、既知の方々にとってはそれがFUKIちゃんの魅力でもあるわけですが‥。
冒頭に書いた通り、方向性という意味では若干のバラつきがあり、この後の音楽性という意味では不透明な感もあります。
が、これは2nd、もしくは他のプロジェクトの兼ね合いで柔軟に構えているのではないでしょうか。
今はFUKIちゃんがやりたいことを、なんでもチャレンジしている、そしてその姿勢がアルバムに映し出されている気がします。
FUKIちゃんの魅力が十二分に堪能できるアルバムとなりました。
Fuki Commune - 「輝く夜へようこそ!」(Music Video Short ver.)
が、前バンドは「さぁ、これから」というところで瓦解してしまった。
そして、新たな船出となるアルバムです。
Fuki Commune / Welcome!

元、LIGHT BRINGERのFUKIちゃんとして。
現、Unlucky Morpheusの天外冬黄として。
時にメタルアーティストとして。
時に同人音楽アーティストとして。
時にアニソンヴォーカリストとして。
様々な顔を持つ女性ヴォーカリストである彼女のソロプロジェクトのアルバムです。
ワタシが彼女の存在を知ったのは、Dragon GuardianのDRAGONVARIUSというアルバム。
元々、同人のメロディックスピードメタルプロジェクトだったDragonGuardianは、このアルバムでFUKIちゃんを迎えたことで一気に花開きました。
メジャー感を纏い、大きくステップアップしました。
このアルバムでのFUKIちゃんの力強くキュートな声はインパクト充分でした。
その後、彼女が参加しているLIGHT BRINGERを知り、いまや伝説とも言える、東京キネマ倶楽部でのDragonGuardian / MinstreliX / LightBringerのライブに参戦。
ナマで見る彼女を見て「・・やっぱりすげぇ!」と確信、惚れ込みました。
そしてLightBringerも素晴らしいアルバムをリリース。
FUKIちゃんの魅力が堪能できるキャッチーな曲が粒揃い。まさに「これからだな!」というところでの活動休止。
Unlucky Morpheusも悪くないのですが、やはりLightBringerと比べるとやや魅力に劣る感があり、「FUKIちゃん、どうなるんだよ‥これだけの才能を埋もれさせるなよ‥」と思ってました。
そんな中、リリースされた「FUKI」の名を冠に据えたプロジェクトのアルバムです。
全体的には、上述した彼女の魅力が満遍なく散りばめられている印象です。
LightBringerやDragonGuardianのような、ひとつのコンセプトで統一されているというアルバムとは異なります。
彼女の声は快活であり、実にカラフルだ。
キュートな声色。
パワフルな声色。
キャッチーな声色。
シリアスな声色。
曲によって様々な表情を魅せてくれます。
そして、どの曲でも強い芯を持ち、彼女の周辺に乱反射するようなキラキラとした華やかさを持っています。
この華やかさはFUKIちゃんならでは。
若干、近未来的&ヘヴィな装いのイントロで「・・お?」と身構えてしまいますが‥
LightBringer時代を思い出させるキャッチーなメタルチューン[月が満ちる前に]で「これだよ!」と安堵を覚えます。
挑発すら感じるような余裕。
一曲目にして、彼女の掌の上で踊らされるかのような錯覚。
やっぱりFUKIちゃんにはこういう曲が似合う。
続く[輝く夜へようこそ]は、アニソン的チューン。
まるで声優のようなメリハリと表情が見え隠れする、万華鏡のような煌きとアニソンならではの高揚感がたまりません。
こういう曲にも対応できちゃう、そしてこういう曲でも圧倒的存在感を見せるのです。
[I'll never let you down!]はスピーディーでメタリック、そして彼女のシリアスな一面を見ることができる曲。
タイプとしては、[月が満ちる前に][輝く夜へようこそ]のような歌唱こそFUKIちゃんの魅力であるなぁと思うわけですが、メタルヴォーカリストとしての存在感を見ることができます。
[僕が生きる世界]は、アニソン的な魅力に加え、J-POP的なコマーシャルな一面も見え隠れします。
[狂い咲け雪月華]は陰陽座のようなオリエンタルな世界観。
今までにないタイプの曲ですが、これもまた彼女の色に染められています。
[青い季節に]は、シングルカット向きのキャッチーな曲、でしょうか。
爽やかで透き通るような、ピュアな輝きに満ちています。
ラストを飾る[Sail on my love]では、再びLightBringerを思わせる明朗な疾走感。
新しい一歩にふさわしい歌詞は、今後をポジティブに見据える姿が。
歌詞通り、大海原に漕ぎだすかのようなスケールの大きい、それでいて自然体な彼女の声が際立ちます。
アルバムのタイトル通り、これが初FUKIちゃんとなる方々には「ようこそ!!」という名刺代わり。
既にFUKIちゃんをご存じの方にとっては、今までの集大成でもあり、今の彼女の現在進行形であり、ひとまず表舞台に立ってくれたことに安堵。
ただし、純粋なヘヴィメタルヴォーカリストとして対峙すると、アニソンっぽい快活さが鼻につく可能性があります。
まぁ、既知の方々にとってはそれがFUKIちゃんの魅力でもあるわけですが‥。
冒頭に書いた通り、方向性という意味では若干のバラつきがあり、この後の音楽性という意味では不透明な感もあります。
が、これは2nd、もしくは他のプロジェクトの兼ね合いで柔軟に構えているのではないでしょうか。
今はFUKIちゃんがやりたいことを、なんでもチャレンジしている、そしてその姿勢がアルバムに映し出されている気がします。
FUKIちゃんの魅力が十二分に堪能できるアルバムとなりました。
Fuki Commune - 「輝く夜へようこそ!」(Music Video Short ver.)
2016年04月20日
少女たちは世界を駆ける
ここまでの存在になると誰が予想したでしょうか。
海外のフェス(もちろんメタル系含む)で旋風を巻き起こし、ビルボードチャートで39位。
全世界待望と言っても過言ではないセカンドアルバムがリリースされました。
BABYMETAL / METAL RESISTANCE

まぁ、もう説明不要でしょうかね。
アイドルユニットから派生した三人組女子によるメタル(風)プロジェクトのセカンドアルバムです。
ワタシがLOUDPARK13で見たときが平均年齢14歳くらいだったと思うので、今は平均年齢17歳くらいになっているでしょうか。
メタル+アイドルのハイブッド。
メタルは正義。カワイイも正義。が旗印。
ジャパニーズカルチャーの象徴的な存在のような側面もあり、海外では圧倒的な支持を得ています。
が、ワタシの周り(もちろんメタル関係中心)では賛否両論が多いのも事実。
この「賛否両論」は両極端に分かれている感があり、「メタルだ」「メタルじゃない」という論争は尽きることがないようです。
まぁ、このあたりについてのワタシの思いは前作の記事を参照していただければと思いますが‥(また最後に書いちゃう気がしますが)
純粋にアルバムとしての感想にいきましょうかね。
前作はデビュー当時からの、そしてキャラクターや立ち位置を確立させるまでの過渡期の曲が詰め込まれていました。
そういう意味では若干のバラつきを感じました。
圧倒的キラーチューンが含まれている反面、初期の曲あたりは「これはちょっとキツいかな」という曲もありました。
が、リリースまでの「ベスト」的な構成になっていたこともあり、実にボリュームを感じさせる内容でした。
そして今作。
海外にも知名度が浸透し、彼女たちのキャラクターも確固たるものになり、満を持してリリースされるアルバム。
まさに真価を問われる作品。
結論から言うと‥「メタルかどうかなんて議論が吹っ飛んでしまうようなBABYMETALの王道」というのが最初の感想。
前作で感じた「バラつき」は、一つの個性として、確信的に、革新的に、意図的に、戦略的に全体を覆っています。
個人的には事前に「もう少しメタル色が強いアルバムだといいけどなー」と思ってたわけですが、世界が見た、世界が望むBABYMETAL像を造り上げてきたなと感じます。
彼女たち(というよりは背後の人たち)は実に頭脳的かつ先見の明があることを感じ、いかに自分が閉鎖的かを感じます。
ザックリなイメージとして、
・メチャンコカッコイイ曲 1/3
・そこそこ好きな曲 1/3
・ちょっと厳しいかなという曲 1/3
というバランスは前作と同じ。
メタリックな曲、スピード感がある好きな系統になる傾向は当然だ。
BABYMETALはその「好きな系統」の曲がワタシの嗜好にドンピシャだから、ハマる。
だから上述のようなバランスでもなんの不満もない。
そういう意味ではオープニングを飾る「どこを切ってもDRAGONFORCE」な[Road of Resistance]はアルバムリリース前からワタシ垂涎の名曲だ。
この曲はなんとなく「一曲目ではないんじゃないかな」と思ってたから、初めてアルバムを聞いて冒頭で流れたときには「お!一曲目か!」と驚いた。
けど、一通り聞いてみれば「これしかない」と言える配置だ。
先行リリースされた[KARATE]。正直、先行で聞いたときは「うーん‥」と思ったが、アルバムの中に入ると必要不可欠な個性を放つ。
前作における[ギミチョコ!]と似たような印象だ。
[あわだまフィーバー]が流れるあたりで「やはりこういう曲も入れてくるんだな」と、先程の「バラつき」を感じ始めます。
[ヤバッ!]での、やや冷淡でタテノリのリフの刻み方やリズム感はZI:KILLあたりを想起します。
サビ以降のスペーシーな装飾も前作で見え隠れしていた要素。
[Amore -蒼星-]は、前作のキラーチューン[紅月]と対をなす、双璧ともいえる、これまた絶品のキラーチューンとなっています。
「♪紅き月に照らされて」という歌詞。
紅月に対しての蒼星。
SU-METALのソロ曲にはこういう曲、という策略を感じますが、曲が素晴らしい!
[紅月]はXの[Silent Jealousy]をリスペクト、オマージュした感がありましたが、今作はさらにメジャー感とスケールアップした感が[DAHLIA]のムードを感じます。
[META!メタ太郎]は曲名といい歌詞といいメタルファンの嫌悪の声が聞こえてきそうです。
ワタシ個人も大きな違和感を覚えましたが、中毒性があることは否定できません。
ジャパメタ的な旋律、もっといえばLUNA SEAあたりに通じる感がある「シンコベーション」。
歌詞のループ感あたりに特にその要素を強く感じてニヤニヤしてしまいますね。
ラップ調なリズムがこれまたメタルファンの反感を買いそうな「GJ!」。
YUI&MOAの曲ということで、これも前作からの流れで個性を確立しつつあります。
続く[Sis.Anger]は曲名だけでニヤリとしてしまいますね。
[NO RAIN , NO RAINBOW]はSU-METALのソロ曲。
「♪止まない雨が降り続いても 絶望さえも光になる 悲しい雨が虹をかけるよ」という歌詞。
そしてピアノとギター。
これはXの[ENDRESS RAIN]的(というか、そのリスペクト)でしょうか。
[Tales of The Destinies]は変拍子とサビの心地よさの組み合わせが新鮮ですね。
ラストを飾る[THE ONE]。実に壮大です。この曲がラストにあるからこそ、「一曲目がRoad of Resistanceで正解だった!」と思える一貫性を生み出してます。
:
:
ということで、このアルバム、前作よりも売れることでしょうし、一般的にも浸透することは間違いありません。
が、「聴きやすさ」という点では前作のほうが聴きやすいかなと感じました。
冒頭から書いている「バラつき」を、さらに拡散させて、そのそれぞれのベクトルに強い個性を持たせてきた感があります。
それぞれの曲が方向性が異なるにも関わらず力強い個性を宿っています。
そして今作で印象的だった点の一つ目。
歌詞の中での「メタル」というキーワードをよりクローズアップしてきていること。
SEX MACHINEGUNSに通じるような、PHANTOM EXCALIVERに通じるような、意図的な盛り込み方です。
キャラクターとして必要だったのかもしれませんが、若干気になりました。
そしてもう一つは、YUI-METALとMOA-METALのポジション。
SU-METALの声、そして彼女がフィットする曲は前作で確立され、それを今作でも継承しています。
YUI&MOAについては、前作の「4の歌」で驚きの個性を放ちました。
今作では(特に二人だけの曲では)、声の抑揚を押さえ、時に無機質に、時に平坦に、それでいて歌詞は怒りだったりメタルだったりというコントラストが印象的。
SU-METALとの棲み分けを図ろうという意図でしょうか。
が、まさに「少女」だった時期を経て、今まさに成長期の二人にとっては、この「個性」は次作以降も武器になりえる、そしてその武器を磨くことができる。
実にうまく二人のポジションを確立したなと思います。
今作でも
「メタルだ」「メタルじゃない」
「世界は認めてるのに日本のメタルファンは閉鎖的」「アイドルがメタルのマネしてるだけで不快」
といった議論が繰り広げられています。
もしLOUDPARKに参戦したりしたら、この議論はさらにヒートアップしてくることでしょう。
ワタシの思いとしてはですね。
メタルかどうかといえばメタルではないでしょう。
が、メタルじゃない!!とムキになる必要もない。
ワタシの大好きなタイプの曲を、しかも高いクオリティの曲を、素晴らしい声の女性ヴォーカルが歌ってくれる。
そのポイントだけで充分評価に値するし、好きでいられる。
が、当然メタル的な曲を求めちゃう身としては、アルバム全体でいうと好きな曲もそうじゃない曲もある。
それでもいい。
いつも書いてるけど「80点の曲ばかりのアルバムより、90点以上の曲は1~2曲あればあとは70点でもOK」というヒトだから。
これも前作で書いたかもしれないけど、BABYMETALはプロレスに通じるものがあると思う。
マッチメイク、ギミック、キャラクター。
そういったものもひっくるめて楽しめるかどうか。だと思う。
総合格闘技一筋の人にとってはプロレスなんかショーであり、真剣勝負じゃないと笑い飛ばすことだろう。
「セメントじゃない」と叩くかもしれない。
純粋なメタルファンが叩くのは、この総合格闘技から見たプロレスに通じるものがあるような気がします。
BABYMETALもショーだ。綿密に計算されたショーだ。ショーとして楽しめる人が楽しめばいい。
純粋なメタルではないけど、メタルというフィールドに真剣勝負で立ち向かっていることは間違いない。
海外で認められているのも、純粋にメタルとしての評価ではなく、ジャパニーズカルチャーとしての人気の要素が強い気がします。
そしてワタシの周りでは、彼女たちをキッカケに「メタルってこういう感じなんだね」「DRAGONFORCEってのを聞いてみたいけど、持ってる?」といった声が聞かれることも事実。
だからメタルファンには「へー、これだけ海外で売れるって凄いね。個人的には興味ないけど」って感じでユルく眺めててほしいなーと思います。
そして、彼女たちをキッカケにメタルに興味を持った人たちに「あんなものでメタルを語るな」ではなく、ココロの門戸を広く開けて、メタルへ誘ってあげてほしいなと思います。
BABYMETAL - Road of Resistance - Live in Japan (OFFICIAL)
フラッグを掲げて高揚させ、タメを作ってからのウォールオブデス。もう彼女たちの様式美と言える境地です。
海外のフェス(もちろんメタル系含む)で旋風を巻き起こし、ビルボードチャートで39位。
全世界待望と言っても過言ではないセカンドアルバムがリリースされました。
BABYMETAL / METAL RESISTANCE

まぁ、もう説明不要でしょうかね。
アイドルユニットから派生した三人組女子によるメタル(風)プロジェクトのセカンドアルバムです。
ワタシがLOUDPARK13で見たときが平均年齢14歳くらいだったと思うので、今は平均年齢17歳くらいになっているでしょうか。
メタル+アイドルのハイブッド。
メタルは正義。カワイイも正義。が旗印。
ジャパニーズカルチャーの象徴的な存在のような側面もあり、海外では圧倒的な支持を得ています。
が、ワタシの周り(もちろんメタル関係中心)では賛否両論が多いのも事実。
この「賛否両論」は両極端に分かれている感があり、「メタルだ」「メタルじゃない」という論争は尽きることがないようです。
まぁ、このあたりについてのワタシの思いは前作の記事を参照していただければと思いますが‥(また最後に書いちゃう気がしますが)
純粋にアルバムとしての感想にいきましょうかね。
前作はデビュー当時からの、そしてキャラクターや立ち位置を確立させるまでの過渡期の曲が詰め込まれていました。
そういう意味では若干のバラつきを感じました。
圧倒的キラーチューンが含まれている反面、初期の曲あたりは「これはちょっとキツいかな」という曲もありました。
が、リリースまでの「ベスト」的な構成になっていたこともあり、実にボリュームを感じさせる内容でした。
そして今作。
海外にも知名度が浸透し、彼女たちのキャラクターも確固たるものになり、満を持してリリースされるアルバム。
まさに真価を問われる作品。
結論から言うと‥「メタルかどうかなんて議論が吹っ飛んでしまうようなBABYMETALの王道」というのが最初の感想。
前作で感じた「バラつき」は、一つの個性として、確信的に、革新的に、意図的に、戦略的に全体を覆っています。
個人的には事前に「もう少しメタル色が強いアルバムだといいけどなー」と思ってたわけですが、世界が見た、世界が望むBABYMETAL像を造り上げてきたなと感じます。
彼女たち(というよりは背後の人たち)は実に頭脳的かつ先見の明があることを感じ、いかに自分が閉鎖的かを感じます。
ザックリなイメージとして、
・メチャンコカッコイイ曲 1/3
・そこそこ好きな曲 1/3
・ちょっと厳しいかなという曲 1/3
というバランスは前作と同じ。
メタリックな曲、スピード感がある好きな系統になる傾向は当然だ。
BABYMETALはその「好きな系統」の曲がワタシの嗜好にドンピシャだから、ハマる。
だから上述のようなバランスでもなんの不満もない。
そういう意味ではオープニングを飾る「どこを切ってもDRAGONFORCE」な[Road of Resistance]はアルバムリリース前からワタシ垂涎の名曲だ。
この曲はなんとなく「一曲目ではないんじゃないかな」と思ってたから、初めてアルバムを聞いて冒頭で流れたときには「お!一曲目か!」と驚いた。
けど、一通り聞いてみれば「これしかない」と言える配置だ。
先行リリースされた[KARATE]。正直、先行で聞いたときは「うーん‥」と思ったが、アルバムの中に入ると必要不可欠な個性を放つ。
前作における[ギミチョコ!]と似たような印象だ。
[あわだまフィーバー]が流れるあたりで「やはりこういう曲も入れてくるんだな」と、先程の「バラつき」を感じ始めます。
[ヤバッ!]での、やや冷淡でタテノリのリフの刻み方やリズム感はZI:KILLあたりを想起します。
サビ以降のスペーシーな装飾も前作で見え隠れしていた要素。
[Amore -蒼星-]は、前作のキラーチューン[紅月]と対をなす、双璧ともいえる、これまた絶品のキラーチューンとなっています。
「♪紅き月に照らされて」という歌詞。
紅月に対しての蒼星。
SU-METALのソロ曲にはこういう曲、という策略を感じますが、曲が素晴らしい!
[紅月]はXの[Silent Jealousy]をリスペクト、オマージュした感がありましたが、今作はさらにメジャー感とスケールアップした感が[DAHLIA]のムードを感じます。
[META!メタ太郎]は曲名といい歌詞といいメタルファンの嫌悪の声が聞こえてきそうです。
ワタシ個人も大きな違和感を覚えましたが、中毒性があることは否定できません。
ジャパメタ的な旋律、もっといえばLUNA SEAあたりに通じる感がある「シンコベーション」。
歌詞のループ感あたりに特にその要素を強く感じてニヤニヤしてしまいますね。
ラップ調なリズムがこれまたメタルファンの反感を買いそうな「GJ!」。
YUI&MOAの曲ということで、これも前作からの流れで個性を確立しつつあります。
続く[Sis.Anger]は曲名だけでニヤリとしてしまいますね。
[NO RAIN , NO RAINBOW]はSU-METALのソロ曲。
「♪止まない雨が降り続いても 絶望さえも光になる 悲しい雨が虹をかけるよ」という歌詞。
そしてピアノとギター。
これはXの[ENDRESS RAIN]的(というか、そのリスペクト)でしょうか。
[Tales of The Destinies]は変拍子とサビの心地よさの組み合わせが新鮮ですね。
ラストを飾る[THE ONE]。実に壮大です。この曲がラストにあるからこそ、「一曲目がRoad of Resistanceで正解だった!」と思える一貫性を生み出してます。
:
:
ということで、このアルバム、前作よりも売れることでしょうし、一般的にも浸透することは間違いありません。
が、「聴きやすさ」という点では前作のほうが聴きやすいかなと感じました。
冒頭から書いている「バラつき」を、さらに拡散させて、そのそれぞれのベクトルに強い個性を持たせてきた感があります。
それぞれの曲が方向性が異なるにも関わらず力強い個性を宿っています。
そして今作で印象的だった点の一つ目。
歌詞の中での「メタル」というキーワードをよりクローズアップしてきていること。
SEX MACHINEGUNSに通じるような、PHANTOM EXCALIVERに通じるような、意図的な盛り込み方です。
キャラクターとして必要だったのかもしれませんが、若干気になりました。
そしてもう一つは、YUI-METALとMOA-METALのポジション。
SU-METALの声、そして彼女がフィットする曲は前作で確立され、それを今作でも継承しています。
YUI&MOAについては、前作の「4の歌」で驚きの個性を放ちました。
今作では(特に二人だけの曲では)、声の抑揚を押さえ、時に無機質に、時に平坦に、それでいて歌詞は怒りだったりメタルだったりというコントラストが印象的。
SU-METALとの棲み分けを図ろうという意図でしょうか。
が、まさに「少女」だった時期を経て、今まさに成長期の二人にとっては、この「個性」は次作以降も武器になりえる、そしてその武器を磨くことができる。
実にうまく二人のポジションを確立したなと思います。
今作でも
「メタルだ」「メタルじゃない」
「世界は認めてるのに日本のメタルファンは閉鎖的」「アイドルがメタルのマネしてるだけで不快」
といった議論が繰り広げられています。
もしLOUDPARKに参戦したりしたら、この議論はさらにヒートアップしてくることでしょう。
ワタシの思いとしてはですね。
メタルかどうかといえばメタルではないでしょう。
が、メタルじゃない!!とムキになる必要もない。
ワタシの大好きなタイプの曲を、しかも高いクオリティの曲を、素晴らしい声の女性ヴォーカルが歌ってくれる。
そのポイントだけで充分評価に値するし、好きでいられる。
が、当然メタル的な曲を求めちゃう身としては、アルバム全体でいうと好きな曲もそうじゃない曲もある。
それでもいい。
いつも書いてるけど「80点の曲ばかりのアルバムより、90点以上の曲は1~2曲あればあとは70点でもOK」というヒトだから。
これも前作で書いたかもしれないけど、BABYMETALはプロレスに通じるものがあると思う。
マッチメイク、ギミック、キャラクター。
そういったものもひっくるめて楽しめるかどうか。だと思う。
総合格闘技一筋の人にとってはプロレスなんかショーであり、真剣勝負じゃないと笑い飛ばすことだろう。
「セメントじゃない」と叩くかもしれない。
純粋なメタルファンが叩くのは、この総合格闘技から見たプロレスに通じるものがあるような気がします。
BABYMETALもショーだ。綿密に計算されたショーだ。ショーとして楽しめる人が楽しめばいい。
純粋なメタルではないけど、メタルというフィールドに真剣勝負で立ち向かっていることは間違いない。
海外で認められているのも、純粋にメタルとしての評価ではなく、ジャパニーズカルチャーとしての人気の要素が強い気がします。
そしてワタシの周りでは、彼女たちをキッカケに「メタルってこういう感じなんだね」「DRAGONFORCEってのを聞いてみたいけど、持ってる?」といった声が聞かれることも事実。
だからメタルファンには「へー、これだけ海外で売れるって凄いね。個人的には興味ないけど」って感じでユルく眺めててほしいなーと思います。
そして、彼女たちをキッカケにメタルに興味を持った人たちに「あんなものでメタルを語るな」ではなく、ココロの門戸を広く開けて、メタルへ誘ってあげてほしいなと思います。
BABYMETAL - Road of Resistance - Live in Japan (OFFICIAL)
フラッグを掲げて高揚させ、タメを作ってからのウォールオブデス。もう彼女たちの様式美と言える境地です。
2015年12月16日
「頂」へ
期待に応え続ける、ってことは大変なことだ。
しかも自らそのハードルを上げ続けているバンドであれば尚更だ。
LOUDPARKでのパフォーマンスも記憶に新しい彼らのニューアルバム。
今年最後を飾るにふさわしいアルバムとなりました。
GALNERYUS / UNDER THE FORCE OF COURAGE

今さら説明不要かもしれませんが‥
日本が誇るメロディックメタルバンドの節目となる10作目ですね。
デビュー作が2003年ですから、12年で10枚!驚くべきハイペースです。
そして奇跡ともいえる小野正利(以下「小野さん」)の加入から5枚目ということで、初代ヴォーカリストであるYAMA-Bの歴史と肩を並べたことになりますね。
早いものです。
いい意味でのアンダーグラウンド感、YAMA-Bの声もあってソリッドで荒々しくザラついた印象の初期から、小野さんに変わってから一気にメジャー感を纏うようになりました。
このあたりの変遷については好みが分かれるところでしょう。
ちなみにワタシはどちらも大好きですよ。
日本語詩、そのJ-POP然としたメロディも含めて、「これじゃないんだよ!」という初期のファンはもう見切りをつけている人もいるかもしれませんね。
が、もうすっかり「ガルネリウスの声」であり、最も強力な武器であるとも言える小野さんの声。
小野さんを迎えて新生GALNERYUSとして想像をはるかに超える名作となった[RESURRECTION]。
順当な進化を見せた[PHOENIX RISING]。
唯一無二、孤高の名曲を生んだ[ANGEL OF SALVATION]。
小野さんのカラーをさらに押し出してきた[VETELGYUS]。
着実に前へ進み続けてきた彼ら、節目となる作品は初のコンセプトアルバム!
そして組曲形式の曲が2曲!
「コンセプトアルバム」「組曲」どっちも大好物ですよ、えぇ。
最初に聞いたときは、[VETELGYUS]の延長で考えていると「ん?」「けっこう冒険的な作品だな」という印象をうけます。
順当に「小野さんを生かす」路線へ向かってきた中、少しベクトルを変えてきた感があります
小野さん加入後以降では、最もシリアスであり、初期YAMA-B時代の薫りが漂う場面も。
が、繰り返し聞けば聞くほど、GALNERYUSが積み重ねてきた歴史を小野さんという最強の武器を駆使して体現してきたかのような充実感を感じるようになります。
10作目という節目を意識したから、コンセプトアルバムという方向性によるものなのかは分かりません。
が、積み重ねたきた歴史からいったん原点に還り、それを緻密に緻密に組立て直し、小野さんという魅力でまんべんなく彩ったかのような。
息苦しさすら感じる、実に濃密なスクラップアンドビルド。
ここでいう「息苦しさ」は、息をすることすら躊躇する緊張感という意味での、ワタシにとって最上級のほめ言葉だと思って頂きたい。
そういった意味では「最高傑作」というよりは「最高峰」に登り詰めた。という印象だ。
どの方向(音楽性)から、どの高さ(リリース時期)から見ても素晴らしかったGALNERYUSたちの作品を、テッペンから見下ろして包んでしまうような作品だと思う。
今まで30年近くヘヴィメタルを聞き続けてきましたが、この「あぁ、このバンドはここまでたどり着いてしまったか」という「圧倒的征服感」を感じたアルバムは数少ない。
そんなアルバムたちと並ぶ素晴らしさだ。
穏やかに爪弾かれるギターからシンフォニックなバックサウンドで語られるプレリュード[PREMONITION]。
そこから一気に‥と言いたいところですが、なんと再びインストナンバー[THE TIME BEFORE DAWN]へ。
DREAM THEATERを思わせるようなテクニカルに構築されたナンバーですね。この曲を中盤ではなくオープニングに配置するあたり、そしてインストナンバーを2曲続けるあたりは自信の表れでしょう。
そしてLOUDPARK15でも披露された[RAISE MY SWORD]へ!
ガルネリ節全開、緊張感を内包し、反射するかのような美しさを撒き散らして疾走してく、メンバー全員の超絶テクニックと小野さんの魅力、全てが詰め込まれた、ガルネリウスの「今」を象徴する名曲です。
細かいところですが強靱なリフの中に配置されるゼロコンマ数秒の「間」がたまらないのです。
間髪いれず解放感と飛翔感に満ちた[THE VOICE OF GRIEVOUS CRY]へ。
この曲へと移行する曲間ひとつとってもコンセプトアルバムであることへのこだわりを感じます。
[RAISE MY SWORD]の「間」も含めて、この感覚が絶妙なのだ。
組曲の一曲目となる[RAIN OF TEARS]では、小野さんの魅力的な中低音域を味わうことができます。
テクニカルな間奏、デスヴォイスによるパートなどを経て、感動的なメロディが彩る終盤[Ⅳ: ENDLESS CONFLICTION]へ。
ROYALHUNTの[PARADOX]のラストを思わせる、緊張感と穏やかさが同居する世界観。もうこれがエピローグじゃないかと勘違いしてしまうほどの劇的な構成となっています。
勇壮なオーケストレーションに導かれ、スケールの大きなパワーメタルチューンへと雪崩込む[SOUL OF THE FIELD]。
最もアルバムコンセプトにフィットした曲かもしれません。
そしてラストを飾る二つ目の組曲、[THE FORCE OF COURAGE]。
崇高なインストレーションから、最後を飾るにふさわしいドラマティックな高揚感へと導いていきます。
この一曲だけでアルバム一枚を聞いたかのような充足感を感じます。
歌詞に散りばめられたキーワードひとつひとつに、ファンは胸を打たれることでしょう。
オープニングから、幾度ものクライマックスが訪れる、そして緊張感が最後まで途絶えることのない、まさに「孤高」の作品ではないでしょうか。
聞き終えて、大きなため息と同時に脳内が真っ白に、そして蓄積した興奮物質が放出されていくような心地よさ。
おそらくガルネリウスの最高傑作として挙げる人も多いことでしょう。
が、あくまで集大成としての傑作であり、ガルネリウスを初めて聞く人にとってはハードルが高いかもしれないなと感じます。
コンパクトに現メンバーの魅力を感じられる[RESURRECTION]。
歴史に残る名曲[ANGEL OF SALVATION]を収録した[ANGEL OF SALVATION]。
そして初期GALNERYUSの魅力の詰まった[THE FLAG OF PUNISHMENT]。
そういった作品を最初に聞いて、この作品に辿り着いてもらえると、さらに魅力を感じることができるのではないでしょうか。
一つの山を登り切った感のあるGALNERYUS。
キーマンであるSYUの視線の先には何が見えているのでしょうか。
が、今回の作品を聞いて「SYUは以前からこの頂を見通していた、そして計算していたのではないか」と感じました。
次に目指す方向も、きっと明確に見えていることでしょう。
【MV】RAISE MY SWORD - GALNERYUS
しかも自らそのハードルを上げ続けているバンドであれば尚更だ。
LOUDPARKでのパフォーマンスも記憶に新しい彼らのニューアルバム。
今年最後を飾るにふさわしいアルバムとなりました。
GALNERYUS / UNDER THE FORCE OF COURAGE

今さら説明不要かもしれませんが‥
日本が誇るメロディックメタルバンドの節目となる10作目ですね。
デビュー作が2003年ですから、12年で10枚!驚くべきハイペースです。
そして奇跡ともいえる小野正利(以下「小野さん」)の加入から5枚目ということで、初代ヴォーカリストであるYAMA-Bの歴史と肩を並べたことになりますね。
早いものです。
いい意味でのアンダーグラウンド感、YAMA-Bの声もあってソリッドで荒々しくザラついた印象の初期から、小野さんに変わってから一気にメジャー感を纏うようになりました。
このあたりの変遷については好みが分かれるところでしょう。
ちなみにワタシはどちらも大好きですよ。
日本語詩、そのJ-POP然としたメロディも含めて、「これじゃないんだよ!」という初期のファンはもう見切りをつけている人もいるかもしれませんね。
が、もうすっかり「ガルネリウスの声」であり、最も強力な武器であるとも言える小野さんの声。
小野さんを迎えて新生GALNERYUSとして想像をはるかに超える名作となった[RESURRECTION]。
順当な進化を見せた[PHOENIX RISING]。
唯一無二、孤高の名曲を生んだ[ANGEL OF SALVATION]。
小野さんのカラーをさらに押し出してきた[VETELGYUS]。
着実に前へ進み続けてきた彼ら、節目となる作品は初のコンセプトアルバム!
そして組曲形式の曲が2曲!
「コンセプトアルバム」「組曲」どっちも大好物ですよ、えぇ。
最初に聞いたときは、[VETELGYUS]の延長で考えていると「ん?」「けっこう冒険的な作品だな」という印象をうけます。
順当に「小野さんを生かす」路線へ向かってきた中、少しベクトルを変えてきた感があります
小野さん加入後以降では、最もシリアスであり、初期YAMA-B時代の薫りが漂う場面も。
が、繰り返し聞けば聞くほど、GALNERYUSが積み重ねてきた歴史を小野さんという最強の武器を駆使して体現してきたかのような充実感を感じるようになります。
10作目という節目を意識したから、コンセプトアルバムという方向性によるものなのかは分かりません。
が、積み重ねたきた歴史からいったん原点に還り、それを緻密に緻密に組立て直し、小野さんという魅力でまんべんなく彩ったかのような。
息苦しさすら感じる、実に濃密なスクラップアンドビルド。
ここでいう「息苦しさ」は、息をすることすら躊躇する緊張感という意味での、ワタシにとって最上級のほめ言葉だと思って頂きたい。
そういった意味では「最高傑作」というよりは「最高峰」に登り詰めた。という印象だ。
どの方向(音楽性)から、どの高さ(リリース時期)から見ても素晴らしかったGALNERYUSたちの作品を、テッペンから見下ろして包んでしまうような作品だと思う。
今まで30年近くヘヴィメタルを聞き続けてきましたが、この「あぁ、このバンドはここまでたどり着いてしまったか」という「圧倒的征服感」を感じたアルバムは数少ない。
そんなアルバムたちと並ぶ素晴らしさだ。
穏やかに爪弾かれるギターからシンフォニックなバックサウンドで語られるプレリュード[PREMONITION]。
そこから一気に‥と言いたいところですが、なんと再びインストナンバー[THE TIME BEFORE DAWN]へ。
DREAM THEATERを思わせるようなテクニカルに構築されたナンバーですね。この曲を中盤ではなくオープニングに配置するあたり、そしてインストナンバーを2曲続けるあたりは自信の表れでしょう。
そしてLOUDPARK15でも披露された[RAISE MY SWORD]へ!
ガルネリ節全開、緊張感を内包し、反射するかのような美しさを撒き散らして疾走してく、メンバー全員の超絶テクニックと小野さんの魅力、全てが詰め込まれた、ガルネリウスの「今」を象徴する名曲です。
細かいところですが強靱なリフの中に配置されるゼロコンマ数秒の「間」がたまらないのです。
間髪いれず解放感と飛翔感に満ちた[THE VOICE OF GRIEVOUS CRY]へ。
この曲へと移行する曲間ひとつとってもコンセプトアルバムであることへのこだわりを感じます。
[RAISE MY SWORD]の「間」も含めて、この感覚が絶妙なのだ。
組曲の一曲目となる[RAIN OF TEARS]では、小野さんの魅力的な中低音域を味わうことができます。
テクニカルな間奏、デスヴォイスによるパートなどを経て、感動的なメロディが彩る終盤[Ⅳ: ENDLESS CONFLICTION]へ。
ROYALHUNTの[PARADOX]のラストを思わせる、緊張感と穏やかさが同居する世界観。もうこれがエピローグじゃないかと勘違いしてしまうほどの劇的な構成となっています。
勇壮なオーケストレーションに導かれ、スケールの大きなパワーメタルチューンへと雪崩込む[SOUL OF THE FIELD]。
最もアルバムコンセプトにフィットした曲かもしれません。
そしてラストを飾る二つ目の組曲、[THE FORCE OF COURAGE]。
崇高なインストレーションから、最後を飾るにふさわしいドラマティックな高揚感へと導いていきます。
この一曲だけでアルバム一枚を聞いたかのような充足感を感じます。
歌詞に散りばめられたキーワードひとつひとつに、ファンは胸を打たれることでしょう。
オープニングから、幾度ものクライマックスが訪れる、そして緊張感が最後まで途絶えることのない、まさに「孤高」の作品ではないでしょうか。
聞き終えて、大きなため息と同時に脳内が真っ白に、そして蓄積した興奮物質が放出されていくような心地よさ。
おそらくガルネリウスの最高傑作として挙げる人も多いことでしょう。
が、あくまで集大成としての傑作であり、ガルネリウスを初めて聞く人にとってはハードルが高いかもしれないなと感じます。
コンパクトに現メンバーの魅力を感じられる[RESURRECTION]。
歴史に残る名曲[ANGEL OF SALVATION]を収録した[ANGEL OF SALVATION]。
そして初期GALNERYUSの魅力の詰まった[THE FLAG OF PUNISHMENT]。
そういった作品を最初に聞いて、この作品に辿り着いてもらえると、さらに魅力を感じることができるのではないでしょうか。
一つの山を登り切った感のあるGALNERYUS。
キーマンであるSYUの視線の先には何が見えているのでしょうか。
が、今回の作品を聞いて「SYUは以前からこの頂を見通していた、そして計算していたのではないか」と感じました。
次に目指す方向も、きっと明確に見えていることでしょう。
【MV】RAISE MY SWORD - GALNERYUS
2015年12月11日
若武者の咆哮
LOUDPARK15ではオープニングアクトを飾ってくれた彼ら。
朝の10時すぎだというのに巨大なウォールオブデスを作り出し、「オープニングアクトをクライマックスにするぜ!」というMCがハッタリではないレベルの盛り上がりを見せました。
その好印象もあって、今さらですが聞く機会が増えてます。
GYZE / FASCINATING VIOLENCE
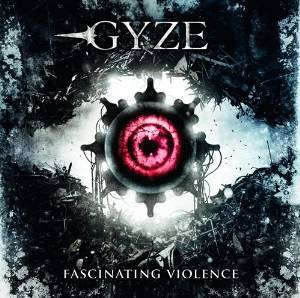
北海道は札幌で結成された若きトリオによる、メロディックデスメタルバンドですね。
このアルバムが1st、リリースは2013年。
このバンド名の読み方、私は最初「・・ガイズ?」とかって感じでしたが、正解は「ギゼ」であります。
:
:
:
日本のメタルバンドってのは、どれだけグローバルなフィールドを目指そうが、英語詩を連ねようが、拭いきれない「ニッポンらしさ」が漂う。
それが海外至上主義のメタラーに受け入れられない理由であると思う。
逆に言うと、それこそがジャパニーズメタルの魅力であり武器だと思う。
その「ニッポンらしさ」をどう評価するか、受け入れられるかでこのアルバムの評価は分かれるのではないかと思います。
冒頭に「メロディックデスメタル」とカテゴライズしましたが、とにかくそのメロディのワビサビがズバ抜けています。
それは「泣き」と呼んだり「クサい」と形容したりするわけですが、そういった要素が満載だ。
が、海外(特に欧州)の「泣き」「クサさ」とは一線を画す、いや、二線も三線も画すのだ。
どこが、ということでなはく、「日本人ならではのメロディ」が全編を覆い尽くしています。
そしてそのメロディの印象もあって、純粋なメロディックデスメタルというよりは、メロディックスピードメタルにデスヴォイスが乗っているような、とも表現できるかもしれません。
そういう意味では、デスヴォイスとはいて、幅広い間口に受け入れられそうな気がします。
・・上述した通り、いかにもニッポン然としたメロディラインが大丈夫なら、ですがね。
キャッチーでドラマティックなリフから疾走感溢れる泣きメロへ雪崩込んでいく[DESIRE]。
オープニングにふさわしい曲であり、GYZEの「ひとまずの名刺がわり」として抜群のインパクトです。
ソロパートの緊張感と高揚感も素晴らしい!
一枚目の一曲目に、そのバンドの象徴となっていくであろう曲を叩き込んできたという意味では、GALNERYUSの[STRUGGLE FOR THE FREEDOM FLAG]を思い出しました。
タイトルトラックである[FASCINATING VIOLENCE]ではクラシカルなオーケストレーションから一気に加速、ピアノの美しさとデスヴォイスのコントラストがドラマを演出します。
ピアノの音階とリズムがSKYLARKを思い出しますね。やはりクサい!
LOUDPARK15で巨大なWall of Deathとサークルピットを作り出した[FINAL REVENGE]。
オープニングのリフで大きな空洞ができて‥咆哮とともに疾走するシーンを思い出します。
中盤のガッツ溢れるコーラスも好印象。
[TRIGGER OF THE ANGER]では、メロディックデスメタルバンドらしい(?)、ブルータルな面を見せてくれます。
それでもサビからのメロディはやはり日本的。
[DAYS OF THE FUNERAL]は完全にメロディックパワーメタルですね。
こういう曲、大好きですよ。
そしてこういう曲が書けちゃうところに、「あー、同じ音楽の土壌を通過してきたんだなー」という共感を感じます。
[MIDNIGHT DARKNESS]もキャッチーな泣きメロ満載!
といった具合に、メロディックデスメタルでありながら、キャッチーな要素が満載。
普段、海外のメロディックデスメタルを聞いている人よりも、メロディックパワーメタルを聞いてる人(ワタシです)、ジャパメタが好きな人(ワタシです)がメインターゲットじゃないかと思うほどです。
見た目がちょっとヴィジュアル系っぽい風味が漂うところも、本格メロデス愛好家にとっては鼻につくかもしれませんん。
それでも、そういったフィルターを取っ払って見れば、デビュー作でここまで高いレベルの作品をリリースしてくれたのは驚きです。
小野さん加入後のGALNERYUSの記事でも何度か書いたかもしれませんが、ワタシはジャパメタは無理して海外勢の音を目指さなくても、日本独自の文化と嗜好の中で充分に勝負できると思っています。
そして、むしろそれこそが日本のバンドの最大の武器であり、得意なフィールドだと思います。
そのバランスを保ちつつ、スケールアップしていってくれれば更に魅力は増していくことでしょう。
楽しみな若武者が現れました。
GYZE - DESIRE [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
朝の10時すぎだというのに巨大なウォールオブデスを作り出し、「オープニングアクトをクライマックスにするぜ!」というMCがハッタリではないレベルの盛り上がりを見せました。
その好印象もあって、今さらですが聞く機会が増えてます。
GYZE / FASCINATING VIOLENCE
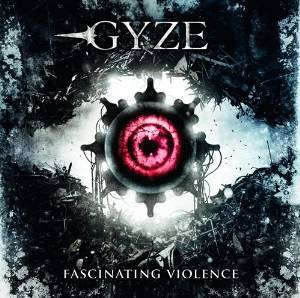
北海道は札幌で結成された若きトリオによる、メロディックデスメタルバンドですね。
このアルバムが1st、リリースは2013年。
このバンド名の読み方、私は最初「・・ガイズ?」とかって感じでしたが、正解は「ギゼ」であります。
:
:
:
日本のメタルバンドってのは、どれだけグローバルなフィールドを目指そうが、英語詩を連ねようが、拭いきれない「ニッポンらしさ」が漂う。
それが海外至上主義のメタラーに受け入れられない理由であると思う。
逆に言うと、それこそがジャパニーズメタルの魅力であり武器だと思う。
その「ニッポンらしさ」をどう評価するか、受け入れられるかでこのアルバムの評価は分かれるのではないかと思います。
冒頭に「メロディックデスメタル」とカテゴライズしましたが、とにかくそのメロディのワビサビがズバ抜けています。
それは「泣き」と呼んだり「クサい」と形容したりするわけですが、そういった要素が満載だ。
が、海外(特に欧州)の「泣き」「クサさ」とは一線を画す、いや、二線も三線も画すのだ。
どこが、ということでなはく、「日本人ならではのメロディ」が全編を覆い尽くしています。
そしてそのメロディの印象もあって、純粋なメロディックデスメタルというよりは、メロディックスピードメタルにデスヴォイスが乗っているような、とも表現できるかもしれません。
そういう意味では、デスヴォイスとはいて、幅広い間口に受け入れられそうな気がします。
・・上述した通り、いかにもニッポン然としたメロディラインが大丈夫なら、ですがね。
キャッチーでドラマティックなリフから疾走感溢れる泣きメロへ雪崩込んでいく[DESIRE]。
オープニングにふさわしい曲であり、GYZEの「ひとまずの名刺がわり」として抜群のインパクトです。
ソロパートの緊張感と高揚感も素晴らしい!
一枚目の一曲目に、そのバンドの象徴となっていくであろう曲を叩き込んできたという意味では、GALNERYUSの[STRUGGLE FOR THE FREEDOM FLAG]を思い出しました。
タイトルトラックである[FASCINATING VIOLENCE]ではクラシカルなオーケストレーションから一気に加速、ピアノの美しさとデスヴォイスのコントラストがドラマを演出します。
ピアノの音階とリズムがSKYLARKを思い出しますね。やはりクサい!
LOUDPARK15で巨大なWall of Deathとサークルピットを作り出した[FINAL REVENGE]。
オープニングのリフで大きな空洞ができて‥咆哮とともに疾走するシーンを思い出します。
中盤のガッツ溢れるコーラスも好印象。
[TRIGGER OF THE ANGER]では、メロディックデスメタルバンドらしい(?)、ブルータルな面を見せてくれます。
それでもサビからのメロディはやはり日本的。
[DAYS OF THE FUNERAL]は完全にメロディックパワーメタルですね。
こういう曲、大好きですよ。
そしてこういう曲が書けちゃうところに、「あー、同じ音楽の土壌を通過してきたんだなー」という共感を感じます。
[MIDNIGHT DARKNESS]もキャッチーな泣きメロ満載!
といった具合に、メロディックデスメタルでありながら、キャッチーな要素が満載。
普段、海外のメロディックデスメタルを聞いている人よりも、メロディックパワーメタルを聞いてる人(ワタシです)、ジャパメタが好きな人(ワタシです)がメインターゲットじゃないかと思うほどです。
見た目がちょっとヴィジュアル系っぽい風味が漂うところも、本格メロデス愛好家にとっては鼻につくかもしれませんん。
それでも、そういったフィルターを取っ払って見れば、デビュー作でここまで高いレベルの作品をリリースしてくれたのは驚きです。
小野さん加入後のGALNERYUSの記事でも何度か書いたかもしれませんが、ワタシはジャパメタは無理して海外勢の音を目指さなくても、日本独自の文化と嗜好の中で充分に勝負できると思っています。
そして、むしろそれこそが日本のバンドの最大の武器であり、得意なフィールドだと思います。
そのバランスを保ちつつ、スケールアップしていってくれれば更に魅力は増していくことでしょう。
楽しみな若武者が現れました。
GYZE - DESIRE [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
2015年08月06日
母なる大地よ!
ネタバンドだと笑われているかもしれない。
イロモノだと笑われているかもしれない。
それどころか、見向きもされないかもしれない。
それでもその愚直さは、見た人たちの魂を揺さぶる…と思いたい。
Phantom Excaliver [鋼鉄の誓い]

東京都立川市出身、これが1stアルバムですね。
このバンドを知ったのはtwitter上でリツイートされてきたPV、「Mother Earth」だった。
最近はジャパメタ勢の隆盛を肌で感じつつあることもあり、とりあえずクリック。
・・驚いた。
フロントマンである男の、デップリとした体型、レザーベストからむき出しの腹、Yoshikiをオマージュしたであろうあの髪形。
その彼から吐き出される、咆哮型のヴォーカル。
サビで突如現れる、ギターのヨレったハイトーンヴォーカル。(←B級メロスピファンにとっては褒め言葉です)
サウンドは完全にメロディックスピードメタルであり、ヴォーカルはデスメタルとメロスピ的ハイトーンを融和。
歌詞は感謝と感激を歌いあげる。
B級だ。B級だけど、ずっと愛してやまないB級メロスピの新しい解釈がここにはあった。
一発で惚れた。
昨年の年末の記事でも「今年一番聞いた曲」に挙げたけど、それはネタじゃない。
ホントに繰り返し繰り返し聞いた。
そしてLOUDPARK14の終焉後、けやき広場でCDを配布する、あの独特な体型&髪形の彼。
ラウパの時期って結構寒いんだよ。
それでも頑なにあのファッションでCDを配る。
そしてCDを受け取って「応援してます!」と話したあとの「ありがとうございます!」という本当に嬉しそうな彼の表情。
また惚れた。
けど、人に自信をもって勧められるか…というと、見た目も含めてちょっと躊躇する感じだった。
ヒッソリとYouTubeで楽しんでいたのですが…
まさかのメジャーデビューですよ!!
「メロディックスピードデスメタルバンド」を名乗り、ジャパニーズメタル界に殴り込みですよ!!
「すべてのものに“ありがとう”のメッセージを込めた、感動のメロディック・スピード・デス・メタル!! 」らしいですよ!!
いろんな思い入れが交錯するところですが、冷静にアルバムを聞いてみるとですね…
基本的には「Mother Earth」のイメージ通りの路線をアルバム全体で貫いています。
最初に触れた通り、どうしてもイロモノ的扱いが全面に出てしまいますが、リフや展開はけっこうテクニカル。
徹底的&意図的に「ヘヴィメタル的世界観&鋼鉄感」を押し出してるあたりは、SEX MACHINEGUNSあたりを彷彿させます。
そして語りを入れたりしつつドラマ性を築いていく手法はDragonGuardian的。
そしてその「なりきり度」は、忍者になりきろうとしているLIGHTNINGのようでもあります。
ドラマティック&ガッツに満ちた、戦いの狼煙をあげるかのようなイントロダクション「聖歌ZEUS」に続いて、MVにもなった「鋼鉄の誓い」へ。
正統派ヨーロピアンヘヴィメタルのような突進力、ヒロイックな歌詞世界。
デスヴォイスとハイトーンヴォーカルの両輪。
「MOTHER EARTH」と並んで彼らのアンセムとなっていくことでしょう。
「ヘヴィメタルを死語とは言わせねぇ!!」という叫びから導かれる「METAL HEART」。
スラッシーな刻みと疾走感、その力強さはネタ的パワーメタル一辺倒じゃないことを証明してくれます。
壮大なイントロがXの名作の序曲「PROLOGUE(WORLD ANTHEM)」を思わせる「Remember X」。
曲名からしてニヤリとしてしまうわけですが、そのXへのオマージュでしょうか。それとも彼らの前身である「PHANTOM X」への思いでしょうか。
高揚感に満ちたサビ、「リメンバー!!」「エーーックス!!!」の掛け合いはライブで盛り上がること必至。
間奏のインストパートでは、YOSHIKIを思い出すドラミングとANGRAのような美しいギターソロが印象的。
そうそう、どうしても見た目のインパクトやツインヴォーカルの存在感が際立つわけですが、アルバム内におけるインストパートの求心力は素晴らしいものがあります。
穏やか&美しいインストチューン「LIFE~俺達の旅は終わらない~」からの名曲「MOTHER EARTH」へなだれこむ様式美はアルバムに二度目のクライマックス感をもたらしてくれます。
鉄板でありながらやはりゾクゾクしますね。
「MOTHER EARTH」については最初に書いた通りですね。もう「母なる大地よヴァァァァァァー!!!」からフルスロットル。名曲です。
さらにラストに配置された「聖剣伝説 Episode Ⅰ」も素晴らしい!
「BLUE BLOOD」での「ROSE OF PAIN」のような、ドラマと終焉の心地よさを演出してくれます。
最初に聞いたときは「捨て曲なしかよ!」とコーフンしましたが、何度か聴き進めていくと、やはり曲のレベルにバラつきはあるなと感じます。
ですが、瞬間風速的破壊力とそのフックのあるメロディが、彼らの個性と相乗効果を生み出したキラーチューンの存在感は称賛に値するもの。
その破壊力ある曲が一曲だけでなくアルバム全体に置かれているのが好感度をグッと向上させています。
ヴィジュアル的にダメ…というのは、洋楽メタルファンが国産メタル(特にヴィジュアル系)に対して抱く嫌悪感の最たるものなので、それがダメな人は残念ですが仕方ないですね。
そしてヴィジュアルの次にハードルになりそうなのが、ちょっとクセのあるハイトーンヴォイス。
さらにはその歌詞世界&なりきり感。
…と、洋楽メタルを愛する人たちにオススメするにはいくつかのハードルがあることは重々承知。
それでも、このピュアな鋼鉄サウンド、一度は触れてみてほしいなと思います。
ネタ的要素は強いものの、そのテクニックと曲のクオリティはホンモノです。
DRAGONFORCEだって、最初は笑われたし叩かれた。
それでも、信じた道を歩み続けて今の地位を手に入れている。
彼らの信念がブレることはないと思うけど、このまま走り続けてほしい。
「♪俺たちは決して、負けない!」と歌っている「鋼鉄の誓い」そのままに。
Phantom Excaliver 「Mother Earth」 Official Music Video
…まぁ、ダマされたと思って一度どうぞ。
イロモノだと笑われているかもしれない。
それどころか、見向きもされないかもしれない。
それでもその愚直さは、見た人たちの魂を揺さぶる…と思いたい。
Phantom Excaliver [鋼鉄の誓い]

東京都立川市出身、これが1stアルバムですね。
このバンドを知ったのはtwitter上でリツイートされてきたPV、「Mother Earth」だった。
最近はジャパメタ勢の隆盛を肌で感じつつあることもあり、とりあえずクリック。
・・驚いた。
フロントマンである男の、デップリとした体型、レザーベストからむき出しの腹、Yoshikiをオマージュしたであろうあの髪形。
その彼から吐き出される、咆哮型のヴォーカル。
サビで突如現れる、ギターのヨレったハイトーンヴォーカル。(←B級メロスピファンにとっては褒め言葉です)
サウンドは完全にメロディックスピードメタルであり、ヴォーカルはデスメタルとメロスピ的ハイトーンを融和。
歌詞は感謝と感激を歌いあげる。
B級だ。B級だけど、ずっと愛してやまないB級メロスピの新しい解釈がここにはあった。
一発で惚れた。
昨年の年末の記事でも「今年一番聞いた曲」に挙げたけど、それはネタじゃない。
ホントに繰り返し繰り返し聞いた。
そしてLOUDPARK14の終焉後、けやき広場でCDを配布する、あの独特な体型&髪形の彼。
ラウパの時期って結構寒いんだよ。
それでも頑なにあのファッションでCDを配る。
そしてCDを受け取って「応援してます!」と話したあとの「ありがとうございます!」という本当に嬉しそうな彼の表情。
また惚れた。
けど、人に自信をもって勧められるか…というと、見た目も含めてちょっと躊躇する感じだった。
ヒッソリとYouTubeで楽しんでいたのですが…
まさかのメジャーデビューですよ!!
「メロディックスピードデスメタルバンド」を名乗り、ジャパニーズメタル界に殴り込みですよ!!
「すべてのものに“ありがとう”のメッセージを込めた、感動のメロディック・スピード・デス・メタル!! 」らしいですよ!!
いろんな思い入れが交錯するところですが、冷静にアルバムを聞いてみるとですね…
基本的には「Mother Earth」のイメージ通りの路線をアルバム全体で貫いています。
最初に触れた通り、どうしてもイロモノ的扱いが全面に出てしまいますが、リフや展開はけっこうテクニカル。
徹底的&意図的に「ヘヴィメタル的世界観&鋼鉄感」を押し出してるあたりは、SEX MACHINEGUNSあたりを彷彿させます。
そして語りを入れたりしつつドラマ性を築いていく手法はDragonGuardian的。
そしてその「なりきり度」は、忍者になりきろうとしているLIGHTNINGのようでもあります。
ドラマティック&ガッツに満ちた、戦いの狼煙をあげるかのようなイントロダクション「聖歌ZEUS」に続いて、MVにもなった「鋼鉄の誓い」へ。
正統派ヨーロピアンヘヴィメタルのような突進力、ヒロイックな歌詞世界。
デスヴォイスとハイトーンヴォーカルの両輪。
「MOTHER EARTH」と並んで彼らのアンセムとなっていくことでしょう。
「ヘヴィメタルを死語とは言わせねぇ!!」という叫びから導かれる「METAL HEART」。
スラッシーな刻みと疾走感、その力強さはネタ的パワーメタル一辺倒じゃないことを証明してくれます。
壮大なイントロがXの名作の序曲「PROLOGUE(WORLD ANTHEM)」を思わせる「Remember X」。
曲名からしてニヤリとしてしまうわけですが、そのXへのオマージュでしょうか。それとも彼らの前身である「PHANTOM X」への思いでしょうか。
高揚感に満ちたサビ、「リメンバー!!」「エーーックス!!!」の掛け合いはライブで盛り上がること必至。
間奏のインストパートでは、YOSHIKIを思い出すドラミングとANGRAのような美しいギターソロが印象的。
そうそう、どうしても見た目のインパクトやツインヴォーカルの存在感が際立つわけですが、アルバム内におけるインストパートの求心力は素晴らしいものがあります。
穏やか&美しいインストチューン「LIFE~俺達の旅は終わらない~」からの名曲「MOTHER EARTH」へなだれこむ様式美はアルバムに二度目のクライマックス感をもたらしてくれます。
鉄板でありながらやはりゾクゾクしますね。
「MOTHER EARTH」については最初に書いた通りですね。もう「母なる大地よヴァァァァァァー!!!」からフルスロットル。名曲です。
さらにラストに配置された「聖剣伝説 Episode Ⅰ」も素晴らしい!
「BLUE BLOOD」での「ROSE OF PAIN」のような、ドラマと終焉の心地よさを演出してくれます。
最初に聞いたときは「捨て曲なしかよ!」とコーフンしましたが、何度か聴き進めていくと、やはり曲のレベルにバラつきはあるなと感じます。
ですが、瞬間風速的破壊力とそのフックのあるメロディが、彼らの個性と相乗効果を生み出したキラーチューンの存在感は称賛に値するもの。
その破壊力ある曲が一曲だけでなくアルバム全体に置かれているのが好感度をグッと向上させています。
ヴィジュアル的にダメ…というのは、洋楽メタルファンが国産メタル(特にヴィジュアル系)に対して抱く嫌悪感の最たるものなので、それがダメな人は残念ですが仕方ないですね。
そしてヴィジュアルの次にハードルになりそうなのが、ちょっとクセのあるハイトーンヴォイス。
さらにはその歌詞世界&なりきり感。
…と、洋楽メタルを愛する人たちにオススメするにはいくつかのハードルがあることは重々承知。
それでも、このピュアな鋼鉄サウンド、一度は触れてみてほしいなと思います。
ネタ的要素は強いものの、そのテクニックと曲のクオリティはホンモノです。
DRAGONFORCEだって、最初は笑われたし叩かれた。
それでも、信じた道を歩み続けて今の地位を手に入れている。
彼らの信念がブレることはないと思うけど、このまま走り続けてほしい。
「♪俺たちは決して、負けない!」と歌っている「鋼鉄の誓い」そのままに。
Phantom Excaliver 「Mother Earth」 Official Music Video
…まぁ、ダマされたと思って一度どうぞ。
2015年05月19日
Xの幻影
先日、東京出張がありましてですね。
特に大きな目玉になるような来日公演はなかたったんですがね。
(いや、The Hauntedが来てたけど、完全に忘れてた)
ライブハウスでX-JAPAN(いや、我々世代にとっては「JAPAN」のない「X」だな)のカバーバンドが出演するという情報を知り、駆けつけましたよ。
会場は目黒鹿鳴館。
名前は聞いたことあったけど、行くのは初めて。
東京はたくさんライブハウスがあって、たくさんライブが見られて羨ましいですね。
twitterでメンバーにチケットの取り置きをお願いし、前売り価格2500円+ドリンク台600円。合計3100円。安いね。
急に決めたから、事前情報皆無。
とりあえずエックスのカバーバンドがメイン、あとは大阪の様式美バンドが参加するということで、それも楽しみ。
開演時間になってもスッカスカのフロアを見て不安に駆られますが、そんな中スタート!
< NORTH WIND SAGA >
オープニングは大阪のメロディック&様式美なバンド。
女性ヴォーカル、キーボードも女性。
中世から飛び出してきたような華やかなドレスを纏った姿は、いかにもジャパニーズメタル的佇まい。
たぶん、この世界観がダメな人は受け付けられないだろうなと思います。
ワタシはジャパメタ大好きだから問題なし。
そして背後に陣取るドラムの男性だけが落ち武者のようなオーラを漂わせており、きらびやかなヴォーカルとのコントラストが印象的です。
キラキラドコドコと疾走するチューンは、時にSTRATOVARIUS的だったり、ANGRA的なリフが聞こえたり、と、実に美しく攻撃的。
かなり好きなタイプのバンドです。
疾走曲を中心にセットリストを組んできてくれたのも好印象につながりましたね。
後半に出てくるバンドをメインにして、これには間に合わなかった人も多かったせいか、とにかくスカスカだったのが気の毒。
「いち、に、さん…」と数えても数えられる程度でしたからね。
それでも応援したくなるバンドでした。
ただ、女性ヴォーカルを据えてのこういうヴィジュアル、こういう音楽というのは期待通りではあるものの、競争率が高いジャンルだろうなと思うので、ここから個性を発揮して抜きんでてほしいなと思います。
< ROW★ZA >
SHOW-YAのカバーバンドでしたね。「ローザ」と呼ぶそうです。
MCによると、まだライヴは二回目とのことでしたが、それを感じさせない安定感でした。
ヴォーカルのコは、印象的には全くSHOW-YAっぽくない風情で、なんだかFUKIちゃんっぽい感じ。
特に気になったのが、イングヴェイがメガネをかけたようなスタイルのギター氏。
立ち振る舞い、見た目(とかシルエット)、ギターソロ…もう彼の一挙手一投足が気になって気になって釘付けでしたよ。
そういったメンバーの印象もあって、SHOW-YAのゴリゴリした感じとは一線を画した、華やかなショーでした。
後で登場するエックスのカバーバンドは見た目も含めてのトリビュートでしたが、このバンドは自分たちのスタイルはスタイルとして、SHOW-YAの曲を敬愛しているという印象。
これはこれでアリだなーと思いましたよ。
そして改めてSHOW-YAの曲のクオリティの高さを感じましたね。
ラスト2曲は「私は嵐」「限界LOVERS」という有名どころでシメ。
個人的には「水の中の逃亡者」を聞きたかったな。
< Belzebuth >
待望のエックスカバーバンド。
エックスのカバーといえば、X-HIROSHIMAが思い浮かぶわけですが、このバンドは初耳。
一応、バンドメンバー経由でチケットを取り置きしてもらったのですが、チケットカウンターで「どのバンドの取り置きですか?」って聞かれて
「・・(読めない)・・えっと…あの…エックスの…」
と、挙動不審になってしまいました。
バンドの紹介のときに「ベルゼビュート」って言ってた気がします。
バンドのtwitterによると「鬼カバー」とのこと。
この紹介だけでは「?」ですが、ショウを見れば何かが分かることでしょう。
このときにはフロアがずいぶん埋まってきていました。
圧倒的な女性率。しかも年代は明らかに我々世代が多数。
客層を見たときに「LOUDPARKのRECKLESS LOVEのときみたいだな…」と思いましたよ。
場内が暗転し、歓声(女性中心ですね)が上がります。
流れているイントロは「WORLD ANTHEM」でしょうか。それっぽいんですが、音がハッキリせず。
そしてオープニングは「BLUE BLOOD」!
TOSHI、HIDE、TAIJIの担当のメンバーは、衣装や化粧から気合の入ったコピーっぷり。
PATAは「まぁ、そんな雰囲気のときもあったよね」という感じ。
YOSHIKIは…見かけはともかく、途中でコルセット巻いたりしてネタ的な感じでしょうか。(あまり受けてなかったけど)
しかし彼のドラミングは凄まじいものがありました。
続いて「STAB ME IN THE BACK」。エックスの中での指折りのアグレッションを誇る名曲。
お客さんも「STAB ME IN THE BACK!!!」と叫んでますよ。
もちろんワタシも背後で叫んでますよ。
さらに「オルガズム」へ。
ここで気づいた。「鬼カバー」の「鬼」とは、セットリストが鬼なのだ。きっと。
ヴォーカルはTOSHIと比べるとクリーンで、改めて「TOSHIは上手い/下手の問題じゃなくて、あの個性は唯一無二だったんだな」と感じました。
前半は違和感あったけど、徐々に耳に馴染んできましたよ。
そして煽りも上手い。というか、笑っちゃうほどコピー。
セリフの言い回し、曲のブレイクでの叫び。こちらがニマニマしてしまうのだ。
「SADISTIC DESIRE」をはさみ、まさかのイントロが!
これは「ROSE OF PAIN」!!! ワタシがエックスで一番好きな曲なのだ。
けど、長いし、まさかチョイスされないだろうなと思っていたから背中にゾクゾクしたものが走りましたよ。
すべての歌詞を記憶していたワタシは完全にカラオケ状態。すばらしい時間でした。
そして「紅」→「X」という鉄板でシメ。
「X」での各種お約束、各種MC、各種煽りも完全再現。
フロアもXジャンプの嵐。
前半はバンドのテンションにフロアがついていけない感じでしたが、最終的には全部持っていった感じでしたね。
Xジャンプがあったり、お約束の振り付けがあったり、ラウパのガゼットのときに見たようなバンドギャルの高速回転イソギンチャク風ヘッドバンギングもあったり。
エックスのライブってのは、今のジャパメタの礎を築いたんだなと痛感しました。
その観客のパフォーマンスは未だにちょっと馴染めないというか入っていけませんでしたが。
そしてそのライブのスタイルは、「これがエックスのライブ」というフォーマットが確立されているからこそ、バンド側もオーディエンス側も一体になれる。
吉本新喜劇や笑点のような、鉄板の伝統芸能的な印象すら受けました。
ホント、楽しいライブだったよ。
ラストには「5X」というバンドが登場したようですが、ワタシはココで帰路へ。
その後、カラオケへ行って「ROSE OF PAIN」を歌ってきたのは言うまでもありません。
:
:
:
以下、「その時代」を過ごしてきたオッサンの独り言ですが‥
やっぱりXの存在であったり影響というのは大きかったな、と痛感しました。
Xでメタルと出会ったワタシのような世代にとっては、あれこそが「メタル」だった。
が、そこから海外のヘヴィメタルと出会い、一時期は
「なんだよ、Xって海外のメタルのパクリかよ」
「Xのヴィジュアルのせいでメタルが誤解されてヘビメタって呼ばれるんだよ」
「ヘビメタって言うな。ヘビメタとヘヴィメタルは違う」
と頑になった。
おそらく今のヘヴィメタルファンの中でも、「ヘビメタ」を嫌悪し、日本のメタルをメタルと認めたくない人は多いと思う。
ワタシもそういう時期があったから、よく分かる。
けど、そこそこ一通りのメタルに触れてきて、「一周回って」ということではないかもしれないけど、Xは偉大だと思う。
いろいろな要素が絡んだとはいえ、あれだけヘヴィメタリックな曲がお茶の間に浸透するなんて奇跡だと思う。
たしかに欧州パワーメタルの要素をふんだんに取りいれているけど、それをうまく料理していると思う。
HELLOWEENのヴァイキーも「Xは俺たちの曲をマネしたから、今回はXのマネをしてピアノのイントロからパワーメタル、って曲を作ったんだ」とか言ってたし。
耽美と激烈が同居する、いわゆるヴィジュアル系の流れはやはりXが源なのだなと感じました。
彼らのキャッチコピー「PSYCHEDELIC VIOLENCE CRIME OF VISUAL SHOCK」。ホントうまくつけてるなと思います。
ワタシのブログタイトルは「ヘビメタでもヘヴィメタルでもいいじゃん。みんなにそういうジャンルに触れる機会があるといいな」という思いで、あえて洋楽ヘヴィメタル嗜好の方から嫌悪される「ヘビメタ」という言葉を使った。
この思想の根本は、もちろんXの存在にあります。
XがキッカケでHELLOWEENを知ったワタシのように。
BABYMETALがキッカケでDRAGONFORCEを知ったという最近の若者のように。
良くも悪くも「ヘビメタ」を浸透させたXは、これからも「日本のヘビメタ」の象徴であり続けるのだろうなと思いました。
特に大きな目玉になるような来日公演はなかたったんですがね。
(いや、The Hauntedが来てたけど、完全に忘れてた)
ライブハウスでX-JAPAN(いや、我々世代にとっては「JAPAN」のない「X」だな)のカバーバンドが出演するという情報を知り、駆けつけましたよ。
会場は目黒鹿鳴館。
名前は聞いたことあったけど、行くのは初めて。
東京はたくさんライブハウスがあって、たくさんライブが見られて羨ましいですね。
twitterでメンバーにチケットの取り置きをお願いし、前売り価格2500円+ドリンク台600円。合計3100円。安いね。
急に決めたから、事前情報皆無。
とりあえずエックスのカバーバンドがメイン、あとは大阪の様式美バンドが参加するということで、それも楽しみ。
開演時間になってもスッカスカのフロアを見て不安に駆られますが、そんな中スタート!
< NORTH WIND SAGA >
オープニングは大阪のメロディック&様式美なバンド。
女性ヴォーカル、キーボードも女性。
中世から飛び出してきたような華やかなドレスを纏った姿は、いかにもジャパニーズメタル的佇まい。
たぶん、この世界観がダメな人は受け付けられないだろうなと思います。
ワタシはジャパメタ大好きだから問題なし。
そして背後に陣取るドラムの男性だけが落ち武者のようなオーラを漂わせており、きらびやかなヴォーカルとのコントラストが印象的です。
キラキラドコドコと疾走するチューンは、時にSTRATOVARIUS的だったり、ANGRA的なリフが聞こえたり、と、実に美しく攻撃的。
かなり好きなタイプのバンドです。
疾走曲を中心にセットリストを組んできてくれたのも好印象につながりましたね。
後半に出てくるバンドをメインにして、これには間に合わなかった人も多かったせいか、とにかくスカスカだったのが気の毒。
「いち、に、さん…」と数えても数えられる程度でしたからね。
それでも応援したくなるバンドでした。
ただ、女性ヴォーカルを据えてのこういうヴィジュアル、こういう音楽というのは期待通りではあるものの、競争率が高いジャンルだろうなと思うので、ここから個性を発揮して抜きんでてほしいなと思います。
< ROW★ZA >
SHOW-YAのカバーバンドでしたね。「ローザ」と呼ぶそうです。
MCによると、まだライヴは二回目とのことでしたが、それを感じさせない安定感でした。
ヴォーカルのコは、印象的には全くSHOW-YAっぽくない風情で、なんだかFUKIちゃんっぽい感じ。
特に気になったのが、イングヴェイがメガネをかけたようなスタイルのギター氏。
立ち振る舞い、見た目(とかシルエット)、ギターソロ…もう彼の一挙手一投足が気になって気になって釘付けでしたよ。
そういったメンバーの印象もあって、SHOW-YAのゴリゴリした感じとは一線を画した、華やかなショーでした。
後で登場するエックスのカバーバンドは見た目も含めてのトリビュートでしたが、このバンドは自分たちのスタイルはスタイルとして、SHOW-YAの曲を敬愛しているという印象。
これはこれでアリだなーと思いましたよ。
そして改めてSHOW-YAの曲のクオリティの高さを感じましたね。
ラスト2曲は「私は嵐」「限界LOVERS」という有名どころでシメ。
個人的には「水の中の逃亡者」を聞きたかったな。
< Belzebuth >
待望のエックスカバーバンド。
エックスのカバーといえば、X-HIROSHIMAが思い浮かぶわけですが、このバンドは初耳。
一応、バンドメンバー経由でチケットを取り置きしてもらったのですが、チケットカウンターで「どのバンドの取り置きですか?」って聞かれて
「・・(読めない)・・えっと…あの…エックスの…」
と、挙動不審になってしまいました。
バンドの紹介のときに「ベルゼビュート」って言ってた気がします。
バンドのtwitterによると「鬼カバー」とのこと。
この紹介だけでは「?」ですが、ショウを見れば何かが分かることでしょう。
このときにはフロアがずいぶん埋まってきていました。
圧倒的な女性率。しかも年代は明らかに我々世代が多数。
客層を見たときに「LOUDPARKのRECKLESS LOVEのときみたいだな…」と思いましたよ。
場内が暗転し、歓声(女性中心ですね)が上がります。
流れているイントロは「WORLD ANTHEM」でしょうか。それっぽいんですが、音がハッキリせず。
そしてオープニングは「BLUE BLOOD」!
TOSHI、HIDE、TAIJIの担当のメンバーは、衣装や化粧から気合の入ったコピーっぷり。
PATAは「まぁ、そんな雰囲気のときもあったよね」という感じ。
YOSHIKIは…見かけはともかく、途中でコルセット巻いたりしてネタ的な感じでしょうか。(あまり受けてなかったけど)
しかし彼のドラミングは凄まじいものがありました。
続いて「STAB ME IN THE BACK」。エックスの中での指折りのアグレッションを誇る名曲。
お客さんも「STAB ME IN THE BACK!!!」と叫んでますよ。
もちろんワタシも背後で叫んでますよ。
さらに「オルガズム」へ。
ここで気づいた。「鬼カバー」の「鬼」とは、セットリストが鬼なのだ。きっと。
ヴォーカルはTOSHIと比べるとクリーンで、改めて「TOSHIは上手い/下手の問題じゃなくて、あの個性は唯一無二だったんだな」と感じました。
前半は違和感あったけど、徐々に耳に馴染んできましたよ。
そして煽りも上手い。というか、笑っちゃうほどコピー。
セリフの言い回し、曲のブレイクでの叫び。こちらがニマニマしてしまうのだ。
「SADISTIC DESIRE」をはさみ、まさかのイントロが!
これは「ROSE OF PAIN」!!! ワタシがエックスで一番好きな曲なのだ。
けど、長いし、まさかチョイスされないだろうなと思っていたから背中にゾクゾクしたものが走りましたよ。
すべての歌詞を記憶していたワタシは完全にカラオケ状態。すばらしい時間でした。
そして「紅」→「X」という鉄板でシメ。
「X」での各種お約束、各種MC、各種煽りも完全再現。
フロアもXジャンプの嵐。
前半はバンドのテンションにフロアがついていけない感じでしたが、最終的には全部持っていった感じでしたね。
Xジャンプがあったり、お約束の振り付けがあったり、ラウパのガゼットのときに見たようなバンドギャルの高速回転イソギンチャク風ヘッドバンギングもあったり。
エックスのライブってのは、今のジャパメタの礎を築いたんだなと痛感しました。
その観客のパフォーマンスは未だにちょっと馴染めないというか入っていけませんでしたが。
そしてそのライブのスタイルは、「これがエックスのライブ」というフォーマットが確立されているからこそ、バンド側もオーディエンス側も一体になれる。
吉本新喜劇や笑点のような、鉄板の伝統芸能的な印象すら受けました。
ホント、楽しいライブだったよ。
ラストには「5X」というバンドが登場したようですが、ワタシはココで帰路へ。
その後、カラオケへ行って「ROSE OF PAIN」を歌ってきたのは言うまでもありません。
:
:
:
以下、「その時代」を過ごしてきたオッサンの独り言ですが‥
やっぱりXの存在であったり影響というのは大きかったな、と痛感しました。
Xでメタルと出会ったワタシのような世代にとっては、あれこそが「メタル」だった。
が、そこから海外のヘヴィメタルと出会い、一時期は
「なんだよ、Xって海外のメタルのパクリかよ」
「Xのヴィジュアルのせいでメタルが誤解されてヘビメタって呼ばれるんだよ」
「ヘビメタって言うな。ヘビメタとヘヴィメタルは違う」
と頑になった。
おそらく今のヘヴィメタルファンの中でも、「ヘビメタ」を嫌悪し、日本のメタルをメタルと認めたくない人は多いと思う。
ワタシもそういう時期があったから、よく分かる。
けど、そこそこ一通りのメタルに触れてきて、「一周回って」ということではないかもしれないけど、Xは偉大だと思う。
いろいろな要素が絡んだとはいえ、あれだけヘヴィメタリックな曲がお茶の間に浸透するなんて奇跡だと思う。
たしかに欧州パワーメタルの要素をふんだんに取りいれているけど、それをうまく料理していると思う。
HELLOWEENのヴァイキーも「Xは俺たちの曲をマネしたから、今回はXのマネをしてピアノのイントロからパワーメタル、って曲を作ったんだ」とか言ってたし。
耽美と激烈が同居する、いわゆるヴィジュアル系の流れはやはりXが源なのだなと感じました。
彼らのキャッチコピー「PSYCHEDELIC VIOLENCE CRIME OF VISUAL SHOCK」。ホントうまくつけてるなと思います。
ワタシのブログタイトルは「ヘビメタでもヘヴィメタルでもいいじゃん。みんなにそういうジャンルに触れる機会があるといいな」という思いで、あえて洋楽ヘヴィメタル嗜好の方から嫌悪される「ヘビメタ」という言葉を使った。
この思想の根本は、もちろんXの存在にあります。
XがキッカケでHELLOWEENを知ったワタシのように。
BABYMETALがキッカケでDRAGONFORCEを知ったという最近の若者のように。
良くも悪くも「ヘビメタ」を浸透させたXは、これからも「日本のヘビメタ」の象徴であり続けるのだろうなと思いました。