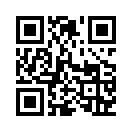ヘビメタパパの書斎 › 2013年12月
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2013年12月28日
Bye!! 2013!!
さて、2013年もいよいよ終わってしまいますね。
毎年毎年、歳を重ねるごとに思うのですが、好きな音楽を聞き続けてきた年輪に反比例するかのように、感動や新鮮さが薄くなりつつあることを痛感します。
以前は何を聞いても「うぉ!」「すげ!」と思っていたのですが、最近は「なんだか●●っぽい」「○○のほうが良かった」と、記憶の中の名盤と比較してしまって、ついハードルが高くなりがち。
でも、それに流されてしまうとドンドンと老け込んでいきそうなので、気持ちと情熱だけは持ち続けて、いろいろな音楽にチャレンジして、新しい出会いを見つけられるとシアワセであるなぁと感じておりますよ。
で、今年を振り返ってみると・・・
まずプライベートでは・・とにかくラウドパーク直前に骨折してしまったことがショッキングでしたね。
仕事では、5~6年がかりだったビッグプロジェクトがついに始動して、それに時間を費やしたという印象。
仕事しか記憶に残らない一年ってのも寂しいもんですが、自分の中でも大きな節目/転機になったことは間違いない。
5年生のムスメは、ももクロに没頭した一年でしたね。
そういえば、去年の今頃はワタシ自身もその存在すら知らず興味もなく、紅白ももちろんノーチェックだったわけで。
たぶん後で触れると思いますが、今年一番の衝撃はももクロだったかもしれません。
二人でライブビューイングへ行ったこともいい思い出ですね。ムスメは完全に「おとうさんとデート!」気分だったようで、こういうときに女の子の親で良かったと思うわけでありますよ。
3年生のボウズは、プロレスに没頭した一年でしたね。
プロレスに関する知識をドンドン蓄えていこうとする貪欲さは「それを勉強に生かせよオイコラタココラ(長州力風)」と思ってしまいますが・・
ワタシ自身がプロレスが大好きだったことを思えば、DNAってのはスゲーな、と実感します。
一緒に全日本プロレスを見に行ったときの、あのキラキラとした眼差しは、ワタシの脳裏に焼きついておりますよ。
風呂入りながら「プロレスの技、たくさん言った人が勝ち!」とか、「ジャンボ鶴田って、どのくらい強かったの?」と聞かれたり・・男の子の親で良かったと思うわけですよ。
メタル界では、LOUDPARKのイロイロは以前の記事を参照して頂くとして・・とはいえ、KING DIAMONDのキャンセルは最大の事件だったかもしれませんね。
オズフェストが開催されたのは今年でしたか・・メンツには賛否両論あったわけですが、今となっては「開催された」という事実が重要だった気がしますね。
BON JOVIからリッチー・サンボラが離脱(脱退ではない・・よね)したことは残念ながらも「・・まぁ、仕方ないよね」と思った人も多いのでは。
METALLICAの映画は、彼らの熱狂的ファンではないワタシも興奮の坩堝でした。
CARCASSの再結成は、メロデスのオリジネイターとしての存在感を充分に知らしめましたね。
そしてなんといってもSLAYERのジェフ・ハンネマンの死去というニュースは衝撃的でした。
ということで、今年も音楽との出会い、このブログを通してのたくさんの出会いに感謝。
日常を支えてくれる、愛する奥様と子供たちに感謝。
そして、愛すべき音楽を提供してくれるアーティストに感謝。
FACEBOOKやTWITTERやMIXIが主流になってきても、なんとかモチベーションを維持していきたいものです。
で、毎年恒例。今年よく聞いた曲をランダムに貼り付けていこうと思いますよ。
そんなわけで、こんな駄ブログですが、よろしかったら来年も覗いてくださいませ。
:
:
:
BABYMETAL 紅月 -アカツキ-
LOUDPARKへの参戦、そしてその熱狂。賛否両論あった(いや、ピュアメタラーには圧倒的に否定的だった)ことは重々承知してますが、今年一番聞いた曲ですね。
X世代(X JAPANじゃなくて)にはたまらないギミックと曲展開。完全にサイレントジェラシー。
ヴォーカルは上手いと思うんだ。贔屓目抜きで。
Dark Moor - First Lance of Spain
まさかの来日の記憶も新しいDARK MOOR。完全復活、と諸手を挙げるほどではないですが、新路線で充分に戦っていけるという自信に満ちた名曲です。
Helloween - Years
過去の名作には及ばないものの、彼らの底力を見せつけてくれた新作からの一曲。
最近はヘヴィな路線に傾倒していましたが、やはりこういったメロディの曲を作らせたら格が違う。
The Poodles - 40 Days And 40 Nights
待望の新作を発表。これまた過去の名作には及ばないものの、「ワタシはやっぱりPOODLESが大好きだな」と思わせてくれるメロディを提供してくれました。
今年も来日は叶わなかったけど、いつかきっと!
GLORYHAMMER - Angus McFife
国産RPGメタルといえばDRAGON GUARDIANなわけですが、海外でそれに対抗しうるバンドが登場しましたね。
RPGが好きでメロディックなパワーメタルが好きならニヤニヤ間違いなし。
POWERWOLF - Amen & Attack
まだ日本デビュー前でありながら絶大なインパクト、そして海外ではヘッドライナークラスの人気を誇るバンドの新作。
RUNNING WILDやRHAPSODYを思わせるスケールと攻撃力は日本人受けすると思うんですがね。
MOKOMAあたりが来日できるなら、このバンドをLOUDPARKで見たいものです。
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 - ももいろクローバーZ
ずいぶん長くももクロを聞いてる気がしますが、知ったのは今年だったんですよね。
そのキッカケとなった、ももいろクリスマス2011でのマーティ・フリードマンとのコラボレーションは軒並み削除されてしまっているので載せられませんが、メタルファンならあの熱狂、合唱団のクワイア、マーティのギターを聞くためにDVDを買うべし、と断言できますよ。
では皆様、よいお年を!
毎年毎年、歳を重ねるごとに思うのですが、好きな音楽を聞き続けてきた年輪に反比例するかのように、感動や新鮮さが薄くなりつつあることを痛感します。
以前は何を聞いても「うぉ!」「すげ!」と思っていたのですが、最近は「なんだか●●っぽい」「○○のほうが良かった」と、記憶の中の名盤と比較してしまって、ついハードルが高くなりがち。
でも、それに流されてしまうとドンドンと老け込んでいきそうなので、気持ちと情熱だけは持ち続けて、いろいろな音楽にチャレンジして、新しい出会いを見つけられるとシアワセであるなぁと感じておりますよ。
で、今年を振り返ってみると・・・
まずプライベートでは・・とにかくラウドパーク直前に骨折してしまったことがショッキングでしたね。
仕事では、5~6年がかりだったビッグプロジェクトがついに始動して、それに時間を費やしたという印象。
仕事しか記憶に残らない一年ってのも寂しいもんですが、自分の中でも大きな節目/転機になったことは間違いない。
5年生のムスメは、ももクロに没頭した一年でしたね。
そういえば、去年の今頃はワタシ自身もその存在すら知らず興味もなく、紅白ももちろんノーチェックだったわけで。
たぶん後で触れると思いますが、今年一番の衝撃はももクロだったかもしれません。
二人でライブビューイングへ行ったこともいい思い出ですね。ムスメは完全に「おとうさんとデート!」気分だったようで、こういうときに女の子の親で良かったと思うわけでありますよ。
3年生のボウズは、プロレスに没頭した一年でしたね。
プロレスに関する知識をドンドン蓄えていこうとする貪欲さは「それを勉強に生かせよオイコラタココラ(長州力風)」と思ってしまいますが・・
ワタシ自身がプロレスが大好きだったことを思えば、DNAってのはスゲーな、と実感します。
一緒に全日本プロレスを見に行ったときの、あのキラキラとした眼差しは、ワタシの脳裏に焼きついておりますよ。
風呂入りながら「プロレスの技、たくさん言った人が勝ち!」とか、「ジャンボ鶴田って、どのくらい強かったの?」と聞かれたり・・男の子の親で良かったと思うわけですよ。
メタル界では、LOUDPARKのイロイロは以前の記事を参照して頂くとして・・とはいえ、KING DIAMONDのキャンセルは最大の事件だったかもしれませんね。
オズフェストが開催されたのは今年でしたか・・メンツには賛否両論あったわけですが、今となっては「開催された」という事実が重要だった気がしますね。
BON JOVIからリッチー・サンボラが離脱(脱退ではない・・よね)したことは残念ながらも「・・まぁ、仕方ないよね」と思った人も多いのでは。
METALLICAの映画は、彼らの熱狂的ファンではないワタシも興奮の坩堝でした。
CARCASSの再結成は、メロデスのオリジネイターとしての存在感を充分に知らしめましたね。
そしてなんといってもSLAYERのジェフ・ハンネマンの死去というニュースは衝撃的でした。
ということで、今年も音楽との出会い、このブログを通してのたくさんの出会いに感謝。
日常を支えてくれる、愛する奥様と子供たちに感謝。
そして、愛すべき音楽を提供してくれるアーティストに感謝。
FACEBOOKやTWITTERやMIXIが主流になってきても、なんとかモチベーションを維持していきたいものです。
で、毎年恒例。今年よく聞いた曲をランダムに貼り付けていこうと思いますよ。
そんなわけで、こんな駄ブログですが、よろしかったら来年も覗いてくださいませ。
:
:
:
BABYMETAL 紅月 -アカツキ-
LOUDPARKへの参戦、そしてその熱狂。賛否両論あった(いや、ピュアメタラーには圧倒的に否定的だった)ことは重々承知してますが、今年一番聞いた曲ですね。
X世代(X JAPANじゃなくて)にはたまらないギミックと曲展開。完全にサイレントジェラシー。
ヴォーカルは上手いと思うんだ。贔屓目抜きで。
Dark Moor - First Lance of Spain
まさかの来日の記憶も新しいDARK MOOR。完全復活、と諸手を挙げるほどではないですが、新路線で充分に戦っていけるという自信に満ちた名曲です。
Helloween - Years
過去の名作には及ばないものの、彼らの底力を見せつけてくれた新作からの一曲。
最近はヘヴィな路線に傾倒していましたが、やはりこういったメロディの曲を作らせたら格が違う。
The Poodles - 40 Days And 40 Nights
待望の新作を発表。これまた過去の名作には及ばないものの、「ワタシはやっぱりPOODLESが大好きだな」と思わせてくれるメロディを提供してくれました。
今年も来日は叶わなかったけど、いつかきっと!
GLORYHAMMER - Angus McFife
国産RPGメタルといえばDRAGON GUARDIANなわけですが、海外でそれに対抗しうるバンドが登場しましたね。
RPGが好きでメロディックなパワーメタルが好きならニヤニヤ間違いなし。
POWERWOLF - Amen & Attack
まだ日本デビュー前でありながら絶大なインパクト、そして海外ではヘッドライナークラスの人気を誇るバンドの新作。
RUNNING WILDやRHAPSODYを思わせるスケールと攻撃力は日本人受けすると思うんですがね。
MOKOMAあたりが来日できるなら、このバンドをLOUDPARKで見たいものです。
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 - ももいろクローバーZ
ずいぶん長くももクロを聞いてる気がしますが、知ったのは今年だったんですよね。
そのキッカケとなった、ももいろクリスマス2011でのマーティ・フリードマンとのコラボレーションは軒並み削除されてしまっているので載せられませんが、メタルファンならあの熱狂、合唱団のクワイア、マーティのギターを聞くためにDVDを買うべし、と断言できますよ。
では皆様、よいお年を!
2013年12月17日
ド真ん中
様式美が好きな方なら垂涎でありながらも、既に忘れてた人も多いのではないでしょうか。
その筋では「スーパーバンド」と言っても過言ではない、あのバンドが復活するそうですよ。
RING OF FIRE [THE ORACLE]

元ARTENSIONのヴィタリ・クープリ。
そしてあのマーク・ボールズ。
この二人が中心となって結成された RING OF FIRE。
この作品は2001年ですから、もう10年以上経過しているわけですね。
個人的には、この頃は「新世代のキーボードプレイヤー」によるネオクラシカルの名作が続々と生まれたことで印象深い。
名手イェンス・ヨハンソンのように「凄腕だけど、あくまでバンドの一員」という存在から、「キーボーディストでありながら、バンドの中心」という形態が増えてきた時期だった。
ROYALHUNTのブレインである、アンドレ・アンダーセン。
MAJESTICやTIME REQUIEMでお馴染みのリチャード・アンダーソン。
そしてこのバンドの柱であるヴィタリ・クープリ。
欧州キラキラネオクラシカル様式美が好きな人にとっては、このあたりは即座に指折りで名前が挙がることでしょう。
ヴィタリ・クープリといえば、ARTENSIONの印象が強い人も多いのではないでしょうか。
ARTENSIONのヴォーカルはジョン・ウェスト。
彼が後にROYAL HUNTに加入するあたりも、不思議な因果を感じます。
さて、このヴィタリ・クープリ。
個人的には前述の二人と比べると「悪くないんだが、なんつーかもう一押し」という印象が拭えない。
ARTENSIONが特にそんな印象が強かったせいだろうか。
とはいえ、ネオクラシカルを歌わせたら右に出る人はいない、と言われるマーク・ボールズと組んだとなると話は別だ。
ジャケットとい、バンドロゴといい、「ド真ん中」「「王道」感が満載だ。
そして生み出されたそのアルバムは・・・
悪くない。
悪くないんだ。
だけど、やっぱり「何か足りない」のだ。
ヴィタリ・クープリのプレイは、期待通りに縦横無尽に個性を発揮している。
マーク・ボールズのヴォーカルは、言うまでもない。こういう音楽性にフィットしないはずがない。
アレンジの美しさも秀逸。
適度な疾走感と荘厳さを伴い、構築された様式美。
大げさではなく、「ネオクラシカルに期待した全て」が詰まっている典型的なアルバムなのだ。
典型的なアルバムなのだが、「RING OF FIRE という個性」が乏しい気がするんだな。
アンドレ・アンダーセンが魅せる、窒息しそうなまでの張りつめた空気。
リチャード・アンダーソンが魅せる、絢爛豪華かつ超絶な空間。
それらと比べると、王道すぎる、愚直すぎるんだろうか。
収録されている曲は、どの曲も悪くない。
が、以前にも書いたかと思うが、個人的には「すべてが80点~85点のアルバム」よりも「一曲だけ95点の曲があれば、あとは80点以下でもいい」のアルバムのほうが印象に残る。
その「万遍なく80点台」のアルバムに該当する気がするんだよね。
だから、決して駄作ではない。
むしろ語り継がれるレベルの良作だと思う。
「ネオクラシカルの名作」といえば、この作品を挙げる人も多いのではないかと。
ROYAL HUNTが少し落ち着きを見せ、リチャード・アンダーソンも音沙汰がない(よね?)状態の今。
このバンドの復活を聞いて「おぉ!」と期待を膨らませてる人も多いと思う。
そして、おそらく期待通りのアルバムをリリースしてくれることだと思う。
そして、その期待を大きく上回って、ワタシのようなベタなのが好きなネオクラファンに叩きつけてほしいものだ。
RING OF FIRE - Circle of Time
その筋では「スーパーバンド」と言っても過言ではない、あのバンドが復活するそうですよ。
RING OF FIRE [THE ORACLE]

元ARTENSIONのヴィタリ・クープリ。
そしてあのマーク・ボールズ。
この二人が中心となって結成された RING OF FIRE。
この作品は2001年ですから、もう10年以上経過しているわけですね。
個人的には、この頃は「新世代のキーボードプレイヤー」によるネオクラシカルの名作が続々と生まれたことで印象深い。
名手イェンス・ヨハンソンのように「凄腕だけど、あくまでバンドの一員」という存在から、「キーボーディストでありながら、バンドの中心」という形態が増えてきた時期だった。
ROYALHUNTのブレインである、アンドレ・アンダーセン。
MAJESTICやTIME REQUIEMでお馴染みのリチャード・アンダーソン。
そしてこのバンドの柱であるヴィタリ・クープリ。
欧州キラキラネオクラシカル様式美が好きな人にとっては、このあたりは即座に指折りで名前が挙がることでしょう。
ヴィタリ・クープリといえば、ARTENSIONの印象が強い人も多いのではないでしょうか。
ARTENSIONのヴォーカルはジョン・ウェスト。
彼が後にROYAL HUNTに加入するあたりも、不思議な因果を感じます。
さて、このヴィタリ・クープリ。
個人的には前述の二人と比べると「悪くないんだが、なんつーかもう一押し」という印象が拭えない。
ARTENSIONが特にそんな印象が強かったせいだろうか。
とはいえ、ネオクラシカルを歌わせたら右に出る人はいない、と言われるマーク・ボールズと組んだとなると話は別だ。
ジャケットとい、バンドロゴといい、「ド真ん中」「「王道」感が満載だ。
そして生み出されたそのアルバムは・・・
悪くない。
悪くないんだ。
だけど、やっぱり「何か足りない」のだ。
ヴィタリ・クープリのプレイは、期待通りに縦横無尽に個性を発揮している。
マーク・ボールズのヴォーカルは、言うまでもない。こういう音楽性にフィットしないはずがない。
アレンジの美しさも秀逸。
適度な疾走感と荘厳さを伴い、構築された様式美。
大げさではなく、「ネオクラシカルに期待した全て」が詰まっている典型的なアルバムなのだ。
典型的なアルバムなのだが、「RING OF FIRE という個性」が乏しい気がするんだな。
アンドレ・アンダーセンが魅せる、窒息しそうなまでの張りつめた空気。
リチャード・アンダーソンが魅せる、絢爛豪華かつ超絶な空間。
それらと比べると、王道すぎる、愚直すぎるんだろうか。
収録されている曲は、どの曲も悪くない。
が、以前にも書いたかと思うが、個人的には「すべてが80点~85点のアルバム」よりも「一曲だけ95点の曲があれば、あとは80点以下でもいい」のアルバムのほうが印象に残る。
その「万遍なく80点台」のアルバムに該当する気がするんだよね。
だから、決して駄作ではない。
むしろ語り継がれるレベルの良作だと思う。
「ネオクラシカルの名作」といえば、この作品を挙げる人も多いのではないかと。
ROYAL HUNTが少し落ち着きを見せ、リチャード・アンダーソンも音沙汰がない(よね?)状態の今。
このバンドの復活を聞いて「おぉ!」と期待を膨らませてる人も多いと思う。
そして、おそらく期待通りのアルバムをリリースしてくれることだと思う。
そして、その期待を大きく上回って、ワタシのようなベタなのが好きなネオクラファンに叩きつけてほしいものだ。
RING OF FIRE - Circle of Time
2013年12月05日
8年目、突入。
2006年12月4日にスタートしたこのブログ。
始めた年から・・いち・・に・・さん・・し・・(指折り数えてる)・・7年を経過しましたかね。
ってことは、8年目ですかね。
よくもまぁ誰も興味ないような話をダラダラと垂れ流してきたもんだな、と若干自分に痛々しさを感じつつ、とりあえず今年も節目を迎えられたことはありがたいことであります。
その当時、ムスメは4歳。年中さんですかね。
ボウズは2歳。まだ乳飲み子ですかね。
その子供たちも今は5年生と3年生。
ところどころで子供たちとの記憶を綴ってこれたのは、今にして思えば意味のあることかもしれないな、と思いますね。
以前にも何度か書いてるかと思いますが・・(基本的に過去の記事は見ないようにしてるので、内容の重複は御容赦で)
もともと、プレゼンで連戦連敗で「もっと語彙を身につけないと」という理由でスタートしたこのブログ。
多少は「飛騨というローカルな地域で、メタルの話がどの程度通じるのかなー。同じ世代の子育てしている方々は、どんな苦労してるのかなー。そういう反応があるかもしれないなー」という思いもなかったわけではない。
けど、ブログなんて独り言だし、言葉を紡いでいく練習だから、無反応でもいいや。というのが基本スタンス。
が、コメント頂いた方と実際に繋がり、その繋がりからまた繋がり・・
こんなローカルなネタのブログをキッカケにして、たくさんの人と今も繋がっている。
実際に出会うことができた人。
面識はないけど、ブログ上のやりとりをしてくれてる人。
みなさんとの繋がりは、ワタシがブログを続ける推進力になっています。
facebookだのtwitterだのといったSNSが存在しなかった時代、ブログから生まれた繋がりは今でも自分にとって特別なものだ。
逆にfacebookやtwitterは、ブログつながりの延長といった感が強いし、書きたいことが書けない場面も多い。
そういう意味でも、やはりブログが原点であるなぁと思うのです。
だから、ブログをやめちゃうとその礎を失ってしまいそうで、ダラダラと続けているのかもしれませんね。
というわけで、8年目に突入した「ヘビメタパパの書斎」。
適度にユルく、適度にメタルと家族への愛を織りまぜつつ、適度に続けていけたらと思っておりますよ。
:
:
さて、毎年この節目には、原点回帰の意味も含めて、最初に取り上げたバンドについて書くわけですが・・
そういう事情もあって、このバンドだけは同じアルバムを取り上げることを自分の中で許可しております。
どのアルバムが何度取り上げたかは振り返らないようにしてますが、今回はこのアルバムを。
ANGRA [FIREWORKS]

アンドレ・マトス率いるブラジルの至宝の3枚目ですね。1998年リリースですね。
VIPER時代に培ったものを一気に昇華し、全メタルファンのド肝をぬいた名盤[ANGELS CRY]。
自らのルーツを如実に具現化し、個人的に一番ANGRAらしくて大好きな[HOLY LAND]。
その二つの名作の後にリリースされたこの作品。
そういえば、ANGRAが好きな人と話をしてても、このアルバムの話題にあまりならないんですよね。
ANGRAの歴史の中にヒッソリと佇んでる感じ。
悪くない。悪くないんだよ。実際、今でもライブに選曲されてる曲もいくつかあるし。
悪くないんですが、ANGRAらしさが希薄な気がします。
[WINGS OF REALITY][METAL ICARUS][SPEED]といったスピードチューンでは、アンドレ・マトスの個性も相まって「間違いなくANGRA」な高揚感を見せます。
が、やっぱり他の代表曲と比べると個性に欠ける感。
いや、いい曲なんだけどね。
2nd大好きな人にとっては、そのテイストが見え隠れする[PETRIFIED EYS]がハイライトかもしれません。
イントロ、途中のリズムチェンジ、不可思議な浮遊感を伴ったメロディが印象的ですね。
[LISBON]は、「FIREWORKSといえば、どの曲?」と言われると、曲の良し悪しは関係なく、なぜか名前が挙がります。このアルバムを象徴する曲なのかもしれませんね。
こうして並べると良曲が揃っているのだ。
なのに、「なんか話題にしづらい」アルバムなのだ。
こういった方向性が影響してか、このアルバムを最後にブレインのアンドレ・マトスが脱退。
VIPER時代から彼を追いかけてきたファンは「・・ANGRA、終わった」と悲嘆にくれました。
が、これまたこのアルバムのおかげか、新ヴォーカルのエドゥ・ファラスキを迎えたANGRAはプロデューサーと共に「ANGRAらしさとは何なのか」と徹底的に追求した奇跡の復活作[REBIRTH]へと繋がっていくのでした。
・・このアルバムが素晴らしすぎて「なんだよ、マトスいらねーじゃん」という風潮になったのは、マトスファンのワタシとしては若干寂しさを覚えるものの、アルバムの素晴らしさは異論を挟む余地は全くないので、反論もできないのですがね。
[FIREWORKS]が1stや2ndの延長線上にあったとするならば、エドゥの活躍もその後の名作も生まれなかった。
こういった背景、今に至るプロセスを語る上では、まさにバンドの命運を分けたアルバムと言えるでしょう。
ANGRAを後追いで聞くのであれば後回しにしていいアルバムだと思うのですが、そういった歴史を遡る意味では絶対に外せませんね。
:
:
というわけで、8年目もよろしくお願いしたしますね。
Angra - Petrified Eyes
始めた年から・・いち・・に・・さん・・し・・(指折り数えてる)・・7年を経過しましたかね。
ってことは、8年目ですかね。
よくもまぁ誰も興味ないような話をダラダラと垂れ流してきたもんだな、と若干自分に痛々しさを感じつつ、とりあえず今年も節目を迎えられたことはありがたいことであります。
その当時、ムスメは4歳。年中さんですかね。
ボウズは2歳。まだ乳飲み子ですかね。
その子供たちも今は5年生と3年生。
ところどころで子供たちとの記憶を綴ってこれたのは、今にして思えば意味のあることかもしれないな、と思いますね。
以前にも何度か書いてるかと思いますが・・(基本的に過去の記事は見ないようにしてるので、内容の重複は御容赦で)
もともと、プレゼンで連戦連敗で「もっと語彙を身につけないと」という理由でスタートしたこのブログ。
多少は「飛騨というローカルな地域で、メタルの話がどの程度通じるのかなー。同じ世代の子育てしている方々は、どんな苦労してるのかなー。そういう反応があるかもしれないなー」という思いもなかったわけではない。
けど、ブログなんて独り言だし、言葉を紡いでいく練習だから、無反応でもいいや。というのが基本スタンス。
が、コメント頂いた方と実際に繋がり、その繋がりからまた繋がり・・
こんなローカルなネタのブログをキッカケにして、たくさんの人と今も繋がっている。
実際に出会うことができた人。
面識はないけど、ブログ上のやりとりをしてくれてる人。
みなさんとの繋がりは、ワタシがブログを続ける推進力になっています。
facebookだのtwitterだのといったSNSが存在しなかった時代、ブログから生まれた繋がりは今でも自分にとって特別なものだ。
逆にfacebookやtwitterは、ブログつながりの延長といった感が強いし、書きたいことが書けない場面も多い。
そういう意味でも、やはりブログが原点であるなぁと思うのです。
だから、ブログをやめちゃうとその礎を失ってしまいそうで、ダラダラと続けているのかもしれませんね。
というわけで、8年目に突入した「ヘビメタパパの書斎」。
適度にユルく、適度にメタルと家族への愛を織りまぜつつ、適度に続けていけたらと思っておりますよ。
:
:
さて、毎年この節目には、原点回帰の意味も含めて、最初に取り上げたバンドについて書くわけですが・・
そういう事情もあって、このバンドだけは同じアルバムを取り上げることを自分の中で許可しております。
どのアルバムが何度取り上げたかは振り返らないようにしてますが、今回はこのアルバムを。
ANGRA [FIREWORKS]

アンドレ・マトス率いるブラジルの至宝の3枚目ですね。1998年リリースですね。
VIPER時代に培ったものを一気に昇華し、全メタルファンのド肝をぬいた名盤[ANGELS CRY]。
自らのルーツを如実に具現化し、個人的に一番ANGRAらしくて大好きな[HOLY LAND]。
その二つの名作の後にリリースされたこの作品。
そういえば、ANGRAが好きな人と話をしてても、このアルバムの話題にあまりならないんですよね。
ANGRAの歴史の中にヒッソリと佇んでる感じ。
悪くない。悪くないんだよ。実際、今でもライブに選曲されてる曲もいくつかあるし。
悪くないんですが、ANGRAらしさが希薄な気がします。
[WINGS OF REALITY][METAL ICARUS][SPEED]といったスピードチューンでは、アンドレ・マトスの個性も相まって「間違いなくANGRA」な高揚感を見せます。
が、やっぱり他の代表曲と比べると個性に欠ける感。
いや、いい曲なんだけどね。
2nd大好きな人にとっては、そのテイストが見え隠れする[PETRIFIED EYS]がハイライトかもしれません。
イントロ、途中のリズムチェンジ、不可思議な浮遊感を伴ったメロディが印象的ですね。
[LISBON]は、「FIREWORKSといえば、どの曲?」と言われると、曲の良し悪しは関係なく、なぜか名前が挙がります。このアルバムを象徴する曲なのかもしれませんね。
こうして並べると良曲が揃っているのだ。
なのに、「なんか話題にしづらい」アルバムなのだ。
こういった方向性が影響してか、このアルバムを最後にブレインのアンドレ・マトスが脱退。
VIPER時代から彼を追いかけてきたファンは「・・ANGRA、終わった」と悲嘆にくれました。
が、これまたこのアルバムのおかげか、新ヴォーカルのエドゥ・ファラスキを迎えたANGRAはプロデューサーと共に「ANGRAらしさとは何なのか」と徹底的に追求した奇跡の復活作[REBIRTH]へと繋がっていくのでした。
・・このアルバムが素晴らしすぎて「なんだよ、マトスいらねーじゃん」という風潮になったのは、マトスファンのワタシとしては若干寂しさを覚えるものの、アルバムの素晴らしさは異論を挟む余地は全くないので、反論もできないのですがね。
[FIREWORKS]が1stや2ndの延長線上にあったとするならば、エドゥの活躍もその後の名作も生まれなかった。
こういった背景、今に至るプロセスを語る上では、まさにバンドの命運を分けたアルバムと言えるでしょう。
ANGRAを後追いで聞くのであれば後回しにしていいアルバムだと思うのですが、そういった歴史を遡る意味では絶対に外せませんね。
:
:
というわけで、8年目もよろしくお願いしたしますね。
Angra - Petrified Eyes