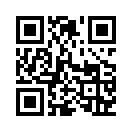ヘビメタパパの書斎 › W
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2015年11月12日
一目惚れ
10周年ということで、豪華ラインナップを揃え、大盛況で幕を閉じたLOUDPARK15。
大物揃い、有名どころが揃っていたこともあり、今年はあまり予習せずに参戦しました。
そして見たいバンドが明確だったこともあり、「これは諦めるか」と思っていたバンドも多数。
そんな中。
事前にYOUTUBEで一曲だけ聞いて「あ、これはまぁスルーでいっか」と思っていたバンドが彼ら。
が、ちょっと空いた時間にチラ見のつもりが、一気に引き込まれました。
WE ARE HARLOT / WE ARE HARLOT

全く彼らのことを知らないのでwikiで調べたところ‥うーん、載ってない。
ということで、リリースしたレーベルの紹介記事によると‥。
「若手モダン・メタル・シーンの中でも絶大なる支持を得る代表的バンド:アスキング・アレクサンドリアのフロントマン、ダニー・ワースノップが新たなプロジェクトを始動!セバスチャン・バック・バンドのジェフ・ジョージや、シルヴァータイドのブライアン・ウィーヴァーらを擁する、80年代HRを彷彿とさせる爽快なハード・ロック・バンド「ウィ・アー・ハーロット」が、セルフタイトルとなるデビュー・アルバム『ウィ・アー・ハーロット』を4月1日にリリース!」
とのこと。
モダンメタルと言われてもピンとこないし、並ぶバンド名といえばセバスチャン・バックくらいしか引っかからないわけですが‥。
とにかくライブを見て驚いた。
骨太なパフォーマンスの中に漂う繊細なメロディ。
アリーナロックのようなダイナミズムとガレージロックのような生々しさ。
アメリカンハードロックのカラッとしたムードとブリティッシュロックの憂い。
私は隣のアリーナで「ま、時間あるし見ておくか」とユルく見ていたわけですが、1曲目から「なんだよこれ!大好きなタイプじゃん!」と釘づけ。
2曲目、3曲目、と進むにつれ「素晴らしい‥いいバンドだ!」と涙腺が緩みました。
他にも素晴らしいバンドがいたわけですが、とりあえず帰宅後に真っ先に注文したのが彼らのCD。
到着して改めて聞いてみたわけですが、やはり素晴らしいです。
王道ド真ん中のような骨太ロックンロールでありながら、他のどのバンドに似ている、という表現ができない。
そして全体を覆うドライブ感の心地よさ。
そしてそれぞれの曲が実にキャッチー。
耳にビンビンとフックを残しつつ、一気に駆け抜けていく爽快さ。
ヴォーカルはハスキーで男の色気を漂わせ、このバンド独特の「カラッとしているのに、ウェットな触感」と実に相性がいい。
オープニングを飾る[Dancing On Nails]は、後期のCinderellaがキャッチーにドライヴィングしているかのような心地よさ。
ややモダンな風味もありつつ、ブルージーな側面もあるあたりにそういった印象が見え隠れするのです。
[Dirty Little Thing]は一曲目の流れを汲んだブルージーな音色を残しつつも、王道ロックンロールの直線的突進力が光ります。
リズミカルなピアノに導かれて始まる[Denial]はライブ映えしそうなスケールの大きさを感じます。
[Easier to Leave]は、メロハーファンにとっては一つのハイライトではないでしょうか。
HAREM SCAREMを思わせるような憂いのあるメロディーからの胸キュンのサビ。
中盤のブレイクの入れ方もたまりません。
前半だけでも、これだけバラエティに富んでいながら、それぞれのクオリティが素晴らしく高いのです。
レーベルの紹介では「モダンメタルシーンで絶大な支持を得るバンドのフロントマン」とのことでしたが、たしかにモダンな側面を見せつつも音楽性は80'sの魅力が溢れている気がします。
が、古いようで古くない。
上述した通り、大好きな時代のサウンドに満ちていながら、他のどのバンドとも比較しづらい魅力がある。
それがこのバンドの新鮮さ、ラウドパークの舞台でのインパクトに繋がっているのだと思います。
私のように「おぉ!」と思った人は多いかもしれない。
そして、その感銘を受けた人の年代幅はけっこう広いかもしれません。
王道でありながら、どの世代にとっても新鮮なインパクトを与えてくれたんじゃないかと思います。
絶対的なキラーチューンがあるかというとそうではないかもしれません。
が、このアルバムの心地よさ、その中毒性は、アルバム全体を覆っています。
WE ARE HARLOTのパフォーマンスを見て、「やっぱり少しでも時間があれば、少しでもたくさんのバンドを見ておかないといけないな」と痛感しましたよ。
We Are Harlot - Easier To Leave
素晴らしい!!
大物揃い、有名どころが揃っていたこともあり、今年はあまり予習せずに参戦しました。
そして見たいバンドが明確だったこともあり、「これは諦めるか」と思っていたバンドも多数。
そんな中。
事前にYOUTUBEで一曲だけ聞いて「あ、これはまぁスルーでいっか」と思っていたバンドが彼ら。
が、ちょっと空いた時間にチラ見のつもりが、一気に引き込まれました。
WE ARE HARLOT / WE ARE HARLOT

全く彼らのことを知らないのでwikiで調べたところ‥うーん、載ってない。
ということで、リリースしたレーベルの紹介記事によると‥。
「若手モダン・メタル・シーンの中でも絶大なる支持を得る代表的バンド:アスキング・アレクサンドリアのフロントマン、ダニー・ワースノップが新たなプロジェクトを始動!セバスチャン・バック・バンドのジェフ・ジョージや、シルヴァータイドのブライアン・ウィーヴァーらを擁する、80年代HRを彷彿とさせる爽快なハード・ロック・バンド「ウィ・アー・ハーロット」が、セルフタイトルとなるデビュー・アルバム『ウィ・アー・ハーロット』を4月1日にリリース!」
とのこと。
モダンメタルと言われてもピンとこないし、並ぶバンド名といえばセバスチャン・バックくらいしか引っかからないわけですが‥。
とにかくライブを見て驚いた。
骨太なパフォーマンスの中に漂う繊細なメロディ。
アリーナロックのようなダイナミズムとガレージロックのような生々しさ。
アメリカンハードロックのカラッとしたムードとブリティッシュロックの憂い。
私は隣のアリーナで「ま、時間あるし見ておくか」とユルく見ていたわけですが、1曲目から「なんだよこれ!大好きなタイプじゃん!」と釘づけ。
2曲目、3曲目、と進むにつれ「素晴らしい‥いいバンドだ!」と涙腺が緩みました。
他にも素晴らしいバンドがいたわけですが、とりあえず帰宅後に真っ先に注文したのが彼らのCD。
到着して改めて聞いてみたわけですが、やはり素晴らしいです。
王道ド真ん中のような骨太ロックンロールでありながら、他のどのバンドに似ている、という表現ができない。
そして全体を覆うドライブ感の心地よさ。
そしてそれぞれの曲が実にキャッチー。
耳にビンビンとフックを残しつつ、一気に駆け抜けていく爽快さ。
ヴォーカルはハスキーで男の色気を漂わせ、このバンド独特の「カラッとしているのに、ウェットな触感」と実に相性がいい。
オープニングを飾る[Dancing On Nails]は、後期のCinderellaがキャッチーにドライヴィングしているかのような心地よさ。
ややモダンな風味もありつつ、ブルージーな側面もあるあたりにそういった印象が見え隠れするのです。
[Dirty Little Thing]は一曲目の流れを汲んだブルージーな音色を残しつつも、王道ロックンロールの直線的突進力が光ります。
リズミカルなピアノに導かれて始まる[Denial]はライブ映えしそうなスケールの大きさを感じます。
[Easier to Leave]は、メロハーファンにとっては一つのハイライトではないでしょうか。
HAREM SCAREMを思わせるような憂いのあるメロディーからの胸キュンのサビ。
中盤のブレイクの入れ方もたまりません。
前半だけでも、これだけバラエティに富んでいながら、それぞれのクオリティが素晴らしく高いのです。
レーベルの紹介では「モダンメタルシーンで絶大な支持を得るバンドのフロントマン」とのことでしたが、たしかにモダンな側面を見せつつも音楽性は80'sの魅力が溢れている気がします。
が、古いようで古くない。
上述した通り、大好きな時代のサウンドに満ちていながら、他のどのバンドとも比較しづらい魅力がある。
それがこのバンドの新鮮さ、ラウドパークの舞台でのインパクトに繋がっているのだと思います。
私のように「おぉ!」と思った人は多いかもしれない。
そして、その感銘を受けた人の年代幅はけっこう広いかもしれません。
王道でありながら、どの世代にとっても新鮮なインパクトを与えてくれたんじゃないかと思います。
絶対的なキラーチューンがあるかというとそうではないかもしれません。
が、このアルバムの心地よさ、その中毒性は、アルバム全体を覆っています。
WE ARE HARLOTのパフォーマンスを見て、「やっぱり少しでも時間があれば、少しでもたくさんのバンドを見ておかないといけないな」と痛感しましたよ。
We Are Harlot - Easier To Leave
素晴らしい!!
2013年11月08日
期待と不安の復帰劇
「TNTにトニー・ハーネル復帰!」というニュースが駆けめぐっている。(ワタシの脳内だけかもしれませんがね)
TNTが大好きな人。(ワタシです)
過去のTNTでのゴタゴタでウンザリな人。(ワタシです)
音楽性の変移で興味を失いつつある人。(ワタシです)
だけどトニー・ハーネルが大好きな人。(ワタシです)
いまさら諸手を挙げて「ウッシャ!」というわけでもなく、だからといって「やっぱTNTはトニー・ハーネルだからな」という思いもありつつ、まぁあんまり期待しちゃアレだからさ、まぁ適度なところでゴニョゴニョ・・という複雑な心境でしょう。
上述の通り、TNT大好きなワタシなので、今までいくつかTNTのアルバムには触れてきました。
が、まだ一番の名作については書いていない。
思い入れがありすぎて、勇気が要るんだよね。
ならば今こそ!と思ったんですが、まぁまだ今はそのときじゃない。本格始動後「おかえり!」と言えたあとでもいいかな、と思ったりして。
ということで、トニーが参加したこのアルバムを。
WESTWORLD [WESTWORLD]

1998年リリース。
もう15年経ちますか・・そうですか・・・。
TNTのトニー・ハーネル、そして今は亡きRIOTのマーク・リアリが組んだプロジェクトだ。
1998年・・・ということで、Wikiで紐解いてみると・・・
TNTは解散状態から復活作[FIREFLY]をリリースした頃。(まぁ、このアルバムあたりからTNTの「復活」「再始動」はアテにしないことにしている)
RIOTはといえば、名作[THE BRETHREN OF THE LONG HOUSE][INISHMORE]という連作が終わったあと。
異色といえば異色、アリっちゃぁアリ。
両方のバンドが大好きだったワタシには驚愕の組み合わせだった。
何度も書いているかもしれませんが、ワタシのHR/HMの入り口はTNTの[INTUITION]とHELLOWEENの[LIVE IN UK]だった。
そしてその頃から20年近く、「好きなヴォーカルは?」と聞かれると「西のトニー・ハーネル、東のカル・スワン!」と自信と誇りを持って言い切るほど好きだった。
[REALIZED FANTASIES]での変化は容認できたものの(というか、むしろ好きなアルバム)、[FIREFLY]は高々と復活を宣言しておいて、自らそのハシゴを外すかのような出来ばえだった。
今にして思えば、そんな頃にリリースされていたアルバムだ。
RIOTにしても、この後数枚は低迷して、劇的復活作[IMMORTAL SOUL]のあとでマークを失ったわけで・・・なんとも複雑なところだ。
そんなWESTWORLD。
RIOTのブレインとTNTのフロントマンがどう融合するのかが見物ですね。
音楽性は、一言で言えば「正統派」でしょうか。
適度にメロディアス、キャッチー。
そこに切り込むマークのギター。
トニーのヴォーカルは、TNTのときよりも自由な表現力に満ちており、いわゆる「北欧メタル」を体現していたときよりも[REALIZED FANTASIES]でのスタイルに近いですかね。
FIREHOUSEか、TERRA NOVAか・・というほどセンチメンタルかつメランコリックかつ甘美なイントロに導かれてスタートする名曲[ILLUSIONS]。
サビでの高揚感もトニーの魅力が発揮されていますね。
[I BELONG]は、ややヘヴィでモダン風な展開ながらも、最終的にはキャッチーな印象を残します。
[LOVE YOU INSANE]でのサビは、TNTで魅せたあのトニーの「慟哭」が蘇るかのようです。
トータルでは多少地味かな、という感触は残りますが、この時期にこのアルバム、ということで評価すれば及第点ではないでしょうか。
特にTNTに失望していた人には、キラリと光明が差し込んだのではないでしょうか。(ワタシです)
:
:
話は元に戻って・・いまさらTNTに全盛期の「北欧然としたメロディ」を期待しても厳しいと思う。
まぁ、それを期待している人も少ないだろうし、それに固執して「過去の焼き直し」なんかも望んでない。
トニー・ハーネルを愛する身(いや、愛した、というべきか)としては、とにかくトニーのイキイキとしたヴォーカルが堪能できれば充分だ。
「名作INTUITIONから25年という節目だから」という彼本人の言葉から読み取ると、何か記念ツアー的なものもあるかもしれない。
・・FIREFLYツアーがイマイチだったから、こちらも微妙なんだけどね。実は。
とりあえず、来年のLOUDPARKに期待したいところ。
SONATA ARCTICAのようにセットリストを間違えなければ、間違いなく熱狂と感涙の渦になるはずだから。
Westworld - Illusions
TNTが大好きな人。(ワタシです)
過去のTNTでのゴタゴタでウンザリな人。(ワタシです)
音楽性の変移で興味を失いつつある人。(ワタシです)
だけどトニー・ハーネルが大好きな人。(ワタシです)
いまさら諸手を挙げて「ウッシャ!」というわけでもなく、だからといって「やっぱTNTはトニー・ハーネルだからな」という思いもありつつ、まぁあんまり期待しちゃアレだからさ、まぁ適度なところでゴニョゴニョ・・という複雑な心境でしょう。
上述の通り、TNT大好きなワタシなので、今までいくつかTNTのアルバムには触れてきました。
が、まだ一番の名作については書いていない。
思い入れがありすぎて、勇気が要るんだよね。
ならば今こそ!と思ったんですが、まぁまだ今はそのときじゃない。本格始動後「おかえり!」と言えたあとでもいいかな、と思ったりして。
ということで、トニーが参加したこのアルバムを。
WESTWORLD [WESTWORLD]

1998年リリース。
もう15年経ちますか・・そうですか・・・。
TNTのトニー・ハーネル、そして今は亡きRIOTのマーク・リアリが組んだプロジェクトだ。
1998年・・・ということで、Wikiで紐解いてみると・・・
TNTは解散状態から復活作[FIREFLY]をリリースした頃。(まぁ、このアルバムあたりからTNTの「復活」「再始動」はアテにしないことにしている)
RIOTはといえば、名作[THE BRETHREN OF THE LONG HOUSE][INISHMORE]という連作が終わったあと。
異色といえば異色、アリっちゃぁアリ。
両方のバンドが大好きだったワタシには驚愕の組み合わせだった。
何度も書いているかもしれませんが、ワタシのHR/HMの入り口はTNTの[INTUITION]とHELLOWEENの[LIVE IN UK]だった。
そしてその頃から20年近く、「好きなヴォーカルは?」と聞かれると「西のトニー・ハーネル、東のカル・スワン!」と自信と誇りを持って言い切るほど好きだった。
[REALIZED FANTASIES]での変化は容認できたものの(というか、むしろ好きなアルバム)、[FIREFLY]は高々と復活を宣言しておいて、自らそのハシゴを外すかのような出来ばえだった。
今にして思えば、そんな頃にリリースされていたアルバムだ。
RIOTにしても、この後数枚は低迷して、劇的復活作[IMMORTAL SOUL]のあとでマークを失ったわけで・・・なんとも複雑なところだ。
そんなWESTWORLD。
RIOTのブレインとTNTのフロントマンがどう融合するのかが見物ですね。
音楽性は、一言で言えば「正統派」でしょうか。
適度にメロディアス、キャッチー。
そこに切り込むマークのギター。
トニーのヴォーカルは、TNTのときよりも自由な表現力に満ちており、いわゆる「北欧メタル」を体現していたときよりも[REALIZED FANTASIES]でのスタイルに近いですかね。
FIREHOUSEか、TERRA NOVAか・・というほどセンチメンタルかつメランコリックかつ甘美なイントロに導かれてスタートする名曲[ILLUSIONS]。
サビでの高揚感もトニーの魅力が発揮されていますね。
[I BELONG]は、ややヘヴィでモダン風な展開ながらも、最終的にはキャッチーな印象を残します。
[LOVE YOU INSANE]でのサビは、TNTで魅せたあのトニーの「慟哭」が蘇るかのようです。
トータルでは多少地味かな、という感触は残りますが、この時期にこのアルバム、ということで評価すれば及第点ではないでしょうか。
特にTNTに失望していた人には、キラリと光明が差し込んだのではないでしょうか。(ワタシです)
:
:
話は元に戻って・・いまさらTNTに全盛期の「北欧然としたメロディ」を期待しても厳しいと思う。
まぁ、それを期待している人も少ないだろうし、それに固執して「過去の焼き直し」なんかも望んでない。
トニー・ハーネルを愛する身(いや、愛した、というべきか)としては、とにかくトニーのイキイキとしたヴォーカルが堪能できれば充分だ。
「名作INTUITIONから25年という節目だから」という彼本人の言葉から読み取ると、何か記念ツアー的なものもあるかもしれない。
・・FIREFLYツアーがイマイチだったから、こちらも微妙なんだけどね。実は。
とりあえず、来年のLOUDPARKに期待したいところ。
SONATA ARCTICAのようにセットリストを間違えなければ、間違いなく熱狂と感涙の渦になるはずだから。
Westworld - Illusions
2010年04月28日
春の音色
春。
春っつーのは、夏ほど爽やかじゃなくていいけどメロディアスなのを、秋ほどセンチメタルじゃなくていいけど哀愁のメロディーを、そんな季節じゃないですか?
そうですよね。
そういうことで話を進めます。
桜が咲いて、程よい日差しと心地よい風が舞うと、このアルバムのオープニングのイントロの音色が脳裏をよぎるのだ。
WHITE LION [BIG GAME]
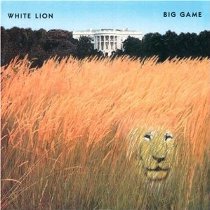
アメリカンハード史に残る名作、[PRIDE]の後を受けてリリースされたこのアルバム。
[PRIDE]がいわゆる典型的「アメリカンハード」と一線を画した、影と憂いを湛えた名作だっただけに大きな期待を背負っていたわけですが・・・
正直、イントロを聴いた瞬間、「!!」「??」が入り交じった驚きでした。
正直、「これは・・・やっちまった!」と思いました。
かなりコマーシャルな方向にシフトしてきたなというのが第一印象。
ジャケットの「WHITE LION」ってロゴも「ナンダコリャ」的印象。
バンドロゴって些細なことかもしれないけど、結構重要なのだ。音楽性変わるとロゴ変えるバンドも多いし。ステップアップの勝負作で変えてくることもあるし。
最初は前作とのギャップで駄作の予感すら漂ったのですが、聴けば聴くほど「・・・悪くない」「いや、むしろコレはコレで良い」と思い始めました。
確かにポップになった・・・とは思う。
売れ線狙いと批判することもできると思う。
が、ヴォーカルのマイク・トランプの声質もあってか「うんうん。やっぱりWHITE LIONだな。これは。」と納得できてしまうのだ。
個性があるってのは大きな武器だね。
曲のタイプも様々で前作よりもバラエティに富んでいるので、これまた前作と比較してしまうと「散漫」な印象になってしまうのですが、一曲一曲にはやはりWHITE LIONらしいウェットなメロディが光るのだ。
ヴィト・ブラッタのギターが生きるヘヴィな曲もあるしね。
でも、やっぱりWHITE LIONはマイクの声を生かした憂いに満ちた曲が似合うよね。
・・・で、そうなると前作が聞きたくなるんだな。
いやいや、でもホントにいいアルバムですよ。
メタルに縁がないヒトに勧めるならコッチのほうがいいんじゃないかと思うくらい。
オープニングを飾る[Goin' Home Tonight]は、WHITE LION 独特の空気とコマーシャルなメロディが相乗した名曲です。
でもゴメンナサイ。肝心の[Goin' Home Tonight]はYouTubeに無かったよ・・・。
別の曲でお茶濁しますね。
White Lion - Little Fighter
春っつーのは、夏ほど爽やかじゃなくていいけどメロディアスなのを、秋ほどセンチメタルじゃなくていいけど哀愁のメロディーを、そんな季節じゃないですか?
そうですよね。
そういうことで話を進めます。
桜が咲いて、程よい日差しと心地よい風が舞うと、このアルバムのオープニングのイントロの音色が脳裏をよぎるのだ。
WHITE LION [BIG GAME]
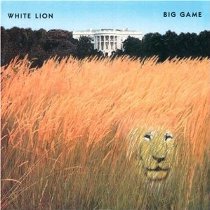
アメリカンハード史に残る名作、[PRIDE]の後を受けてリリースされたこのアルバム。
[PRIDE]がいわゆる典型的「アメリカンハード」と一線を画した、影と憂いを湛えた名作だっただけに大きな期待を背負っていたわけですが・・・
正直、イントロを聴いた瞬間、「!!」「??」が入り交じった驚きでした。
正直、「これは・・・やっちまった!」と思いました。
かなりコマーシャルな方向にシフトしてきたなというのが第一印象。
ジャケットの「WHITE LION」ってロゴも「ナンダコリャ」的印象。
バンドロゴって些細なことかもしれないけど、結構重要なのだ。音楽性変わるとロゴ変えるバンドも多いし。ステップアップの勝負作で変えてくることもあるし。
最初は前作とのギャップで駄作の予感すら漂ったのですが、聴けば聴くほど「・・・悪くない」「いや、むしろコレはコレで良い」と思い始めました。
確かにポップになった・・・とは思う。
売れ線狙いと批判することもできると思う。
が、ヴォーカルのマイク・トランプの声質もあってか「うんうん。やっぱりWHITE LIONだな。これは。」と納得できてしまうのだ。
個性があるってのは大きな武器だね。
曲のタイプも様々で前作よりもバラエティに富んでいるので、これまた前作と比較してしまうと「散漫」な印象になってしまうのですが、一曲一曲にはやはりWHITE LIONらしいウェットなメロディが光るのだ。
ヴィト・ブラッタのギターが生きるヘヴィな曲もあるしね。
でも、やっぱりWHITE LIONはマイクの声を生かした憂いに満ちた曲が似合うよね。
・・・で、そうなると前作が聞きたくなるんだな。
いやいや、でもホントにいいアルバムですよ。
メタルに縁がないヒトに勧めるならコッチのほうがいいんじゃないかと思うくらい。
オープニングを飾る[Goin' Home Tonight]は、WHITE LION 独特の空気とコマーシャルなメロディが相乗した名曲です。
でもゴメンナサイ。肝心の[Goin' Home Tonight]はYouTubeに無かったよ・・・。
別の曲でお茶濁しますね。
White Lion - Little Fighter
2009年05月21日
いまさらですが
そういえば、こないだ新宿のメタルバーGODZへ行ったときですけどね。(またその話か)
いつも座るカウンター席が満員だったのです。
そのこと自体がワタシの今までの経験では稀だったのですが、その日に限って全員スーツのサラリーマン。
轟音メタルサウンドをバックに酒を嗜むサラリーマン一同。
ミョーな違和感と親近感を覚えたのでした。
そんな中、そのサラリーマンの誰かがリクエストしたのがコレ。
懐かしいなぁ。
名盤だったなぁ。
きっとそのサラリーマン、同年代だなぁ。
さらに親近感は増したのです。
WHITELION / PRIDE
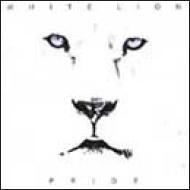
そんなわけで東京から戻ったらスグにCDラックへ直行して探しました。
どれどれ。
自分の性格だと、「アメリカンハードゾーン」よりも「メロディアスハードゾーン」だな。きっと。
いやいや、もしかしたら、最近聞かない「その他ゾーン」かも・・。
あったあった。結局、アメリカンハードゾーンに。
「全米トップ10トラック WAIT & TELL ME 収録」
「KISS,AEROSMITH,AC/DCとの全米ツアーを成し遂げ、ついにワールドワイドバンドとしての地位を築き上げたWHITE LION」
というオビタタキが懐かしくもオドロキだ。
KISS,AEROSMITH,AC/DC !!
で、そこにWHITELION!うーむ。
[LADY OF THE VALLEY][WAIT][TELL ME]あたりの印象が強いこのアルバムですが、改めて聞けば「あったあった、この曲もあったぞ。」という新鮮な発見がイッパイ。
発売当時、繰り返し繰り返し聞いたもんなぁ。
マイク・トランプのハスキーながら伸びやかな声質。
アメリカンな雰囲気とは一線を画す、哀愁に溢れ、物憂げでウェッティなサウンド。
全部の曲が口ずさめるほどキャッチーなのに、ポップすぎず、甘すぎず。
当時、独特の異彩を放っていたのを思い出し、やっぱり個性的だなぁと改めて実感したのです。
代表曲といえば[WAIT]でしょうかね。
上記のサラリーマンも、やはりこの曲をチョイスしていました。
いやー、いまさらですが、いい曲だ!
なんだか甘酸っぱいような記憶がたくさん蘇ってきますよ。
リリースは・・・1987年!
20年以上前かぁ。
こうやって「あの頃は良かった!」と思い出に耽って、オッサンになっていくわけですね。わかります。
WHITELION - WAIT (ヘンなクリップしか無くてゴメンナサイ)
※5/22追記です。----------------------------------------
コメントで「ヘリの音がするWHITELION関連の曲って・・」というコメントを頂いたので、コレかなと思った曲を貼りますね。
違ってたらゴメンナサイ。
WHITE LION - WARSONG
いつも座るカウンター席が満員だったのです。
そのこと自体がワタシの今までの経験では稀だったのですが、その日に限って全員スーツのサラリーマン。
轟音メタルサウンドをバックに酒を嗜むサラリーマン一同。
ミョーな違和感と親近感を覚えたのでした。
そんな中、そのサラリーマンの誰かがリクエストしたのがコレ。
懐かしいなぁ。
名盤だったなぁ。
きっとそのサラリーマン、同年代だなぁ。
さらに親近感は増したのです。
WHITELION / PRIDE
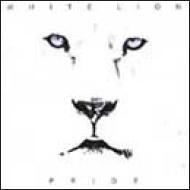
そんなわけで東京から戻ったらスグにCDラックへ直行して探しました。
どれどれ。
自分の性格だと、「アメリカンハードゾーン」よりも「メロディアスハードゾーン」だな。きっと。
いやいや、もしかしたら、最近聞かない「その他ゾーン」かも・・。
あったあった。結局、アメリカンハードゾーンに。
「全米トップ10トラック WAIT & TELL ME 収録」
「KISS,AEROSMITH,AC/DCとの全米ツアーを成し遂げ、ついにワールドワイドバンドとしての地位を築き上げたWHITE LION」
というオビタタキが懐かしくもオドロキだ。
KISS,AEROSMITH,AC/DC !!
で、そこにWHITELION!うーむ。
[LADY OF THE VALLEY][WAIT][TELL ME]あたりの印象が強いこのアルバムですが、改めて聞けば「あったあった、この曲もあったぞ。」という新鮮な発見がイッパイ。
発売当時、繰り返し繰り返し聞いたもんなぁ。
マイク・トランプのハスキーながら伸びやかな声質。
アメリカンな雰囲気とは一線を画す、哀愁に溢れ、物憂げでウェッティなサウンド。
全部の曲が口ずさめるほどキャッチーなのに、ポップすぎず、甘すぎず。
当時、独特の異彩を放っていたのを思い出し、やっぱり個性的だなぁと改めて実感したのです。
代表曲といえば[WAIT]でしょうかね。
上記のサラリーマンも、やはりこの曲をチョイスしていました。
いやー、いまさらですが、いい曲だ!
なんだか甘酸っぱいような記憶がたくさん蘇ってきますよ。
リリースは・・・1987年!
20年以上前かぁ。
こうやって「あの頃は良かった!」と思い出に耽って、オッサンになっていくわけですね。わかります。
WHITELION - WAIT (ヘンなクリップしか無くてゴメンナサイ)
※5/22追記です。----------------------------------------
コメントで「ヘリの音がするWHITELION関連の曲って・・」というコメントを頂いたので、コレかなと思った曲を貼りますね。
違ってたらゴメンナサイ。
WHITE LION - WARSONG
2008年07月22日
あの時代の憧憬
最近、ひだっちの新機能である「サークル」なるものに参加しています。
ま、ワタシが参加できるものといったら音楽くらいしかありません。
(実は、「きしめん一個半カケ、てんぷら2枚」が定番のワタシは「あらいんぐ」も気になってますが・・・)
その音楽サークル。
皆様、オススメを紹介してくださる際に、概ねYOU TUBEへのリンクを張ってくださいます。
YOU TUBEで「ここまでマニアックなものが!」というオドロキがあります。
そこで、「あれも見たいなぁ。これも見たいなぁ」と思うようになるのは必然の流れ。
で、何を見よっかなーと思ったとき、かえって「なんでも見れるよ~」ってことだと選べないもの。
いろいろなバンド、いろいろな曲がアタマをよぎり、最初に「コレダナ」って思ったのが・・・
WHITESNAKE [IS THIS LOVE]

YouTubeも張ってみる。
WHITESNAKE、「サーペンス・アルバス」は名作だし、ライブも行ったし、それなりにキライではないけど・・・
真っ先に「見たい!」と思うほど思い入れの強いバンドじゃない。
けど。
この[IS THIS LOVE]のPVは、MTVに代表される「あの時代」の象徴なのです。ワタシにとって。
何度も何度も繰り返し見たのを思い出します。
曲の切なさ、カヴァーデルのセクシーなヴォーカル、モノトーンで彩られた風景描写。
・・・だった記憶があったんですけどね。
・・・改めて見てみたんですけどね。
・・・チョッピリハズカシイモノでした。
・・・全然、モノトーンじゃなかったし。
でも、やっぱり名曲ですね。
そういや、最新アルバムは聴いてない。
WHITESNAKEというより、ダグ・アルドリッチがどんな存在感を見せてくれるかが気になります。
BAD MOON RISING、好きだったので・・・
ま、ワタシが参加できるものといったら音楽くらいしかありません。
(実は、「きしめん一個半カケ、てんぷら2枚」が定番のワタシは「あらいんぐ」も気になってますが・・・)
その音楽サークル。
皆様、オススメを紹介してくださる際に、概ねYOU TUBEへのリンクを張ってくださいます。
YOU TUBEで「ここまでマニアックなものが!」というオドロキがあります。
そこで、「あれも見たいなぁ。これも見たいなぁ」と思うようになるのは必然の流れ。
で、何を見よっかなーと思ったとき、かえって「なんでも見れるよ~」ってことだと選べないもの。
いろいろなバンド、いろいろな曲がアタマをよぎり、最初に「コレダナ」って思ったのが・・・
WHITESNAKE [IS THIS LOVE]

YouTubeも張ってみる。
WHITESNAKE、「サーペンス・アルバス」は名作だし、ライブも行ったし、それなりにキライではないけど・・・
真っ先に「見たい!」と思うほど思い入れの強いバンドじゃない。
けど。
この[IS THIS LOVE]のPVは、MTVに代表される「あの時代」の象徴なのです。ワタシにとって。
何度も何度も繰り返し見たのを思い出します。
曲の切なさ、カヴァーデルのセクシーなヴォーカル、モノトーンで彩られた風景描写。
・・・だった記憶があったんですけどね。
・・・改めて見てみたんですけどね。
・・・チョッピリハズカシイモノでした。
・・・全然、モノトーンじゃなかったし。
でも、やっぱり名曲ですね。
そういや、最新アルバムは聴いてない。
WHITESNAKEというより、ダグ・アルドリッチがどんな存在感を見せてくれるかが気になります。
BAD MOON RISING、好きだったので・・・
2008年05月19日
逢瀬
東京へ出張へ行った時に、ブログで知り合いになった女性と会った。
こんなローカルで、クダラナイ独り言のようなブログが縁で、こんなことがあるんだなぁ。
実際に会うまでは、自分の無知をさらけ出してしまう不安に駆られつつも、新宿駅で待ち合わせ。
お会いしたその女性は「メタルLove」なオーラを放ち、明朗な笑顔がステキな方だった。
聞けば、御夫婦でMetal好きとのこと。
さらに、ダンナ様の趣味がワタシに近いことにオドロキ。
夫婦でカイ・ハンセンの話で盛り上がれるなんて…人生の濃密度が違うだろなとウラヤマシイ限りだ。
で、ちょっとメシ喰って、その後はお約束のメタルバーGODZへ。
メシ喰ってる時に好きなヴォーカルについての話になった。
彼女はマイケル・キスクが好きらしい。ワタシも大好きだ。
ワタシは、ちょっと前なら「東のカル・スワン、西のトニー・ハーネル」といったところだった。
が、最近はこのバンドのヴォーカルが好きだ。
彼女は、このボーカルを知らないということでGODZでリクエスト。
彼が歌うアルバムなら、コレだな。
GOZDには置いてなかったようなので、ここでちょっと触れてみようかな。
Wuthering Heights [Far From The Madding Crowd]

デンマーク出身、個性的なテクニカルさとプログレ風味を併せ持つパワーメタルバンドですね。
前作[To Travel Forevermore]では、スピード感よりも複雑(変態的)に展開するメロディラインが印象的でした。
が、この作品では、その複雑な展開を継承しつつパワーメタル的な爆発力を身に纏い、強烈な相乗効果を生み出しました。
その象徴ともいえるのは、強力無比なニルス・パトリック・ヨハンソンのヴォーカル。
Richard Andersson's Space Odyssey や Astral Doors でお馴染みの彼ですが、Wuthering Heightsが一番合ってるんじゃないかな。。
テクニカルな楽曲群に埋もれるどころか、変幻自在に声色を使い分け存在感をアピールする彼の説得力はバツグンです。
ミドルテンポの楽曲では骨太さと力強さを増幅し、
スピーディな楽曲ではドラマティックな爆発力を演出します。
そして、民俗音楽的でケルティックともいえるエッセンスをまぶしたパワーメタルはBlind Guardianを彷彿させる場面もチラホラ。
[Longing For The Woods Part.1]での 疾走→民俗音楽的小休止→バゴーンと爆裂疾走 という構成はカンペキにワタシのツボなのです。
Heavenlyあたりがスキな方なら失禁モノでしょう。
[Longing For The Woods]Part.1/Part.2/Part.3 と、基本的なメロディが同じ楽曲を三曲収録しており、しかもその三曲全てのクオリティが突出しているところもオドロキです。
展開やアレンジに耳を奪われているうちにアルバムが終わってしまいます。
以前にココで記事にした最新作では、さらにパワーメタル寄りにシフトしています。
が…
メロディックパワーメタル的音楽性を軸に、シンフォニック・プログレッシブ・民族的アレンジ が三位一体のバランスで散りばめられたこのアルバムが最強でしょう。
購入時には悪名高きCCCDだったのが鬱でした…。
今はどうだか分かりませんが、もし「買ってみよう」なんて気になった方は要注意です。
こんなローカルで、クダラナイ独り言のようなブログが縁で、こんなことがあるんだなぁ。
実際に会うまでは、自分の無知をさらけ出してしまう不安に駆られつつも、新宿駅で待ち合わせ。
お会いしたその女性は「メタルLove」なオーラを放ち、明朗な笑顔がステキな方だった。
聞けば、御夫婦でMetal好きとのこと。
さらに、ダンナ様の趣味がワタシに近いことにオドロキ。
夫婦でカイ・ハンセンの話で盛り上がれるなんて…人生の濃密度が違うだろなとウラヤマシイ限りだ。
で、ちょっとメシ喰って、その後はお約束のメタルバーGODZへ。
メシ喰ってる時に好きなヴォーカルについての話になった。
彼女はマイケル・キスクが好きらしい。ワタシも大好きだ。
ワタシは、ちょっと前なら「東のカル・スワン、西のトニー・ハーネル」といったところだった。
が、最近はこのバンドのヴォーカルが好きだ。
彼女は、このボーカルを知らないということでGODZでリクエスト。
彼が歌うアルバムなら、コレだな。
GOZDには置いてなかったようなので、ここでちょっと触れてみようかな。
Wuthering Heights [Far From The Madding Crowd]

デンマーク出身、個性的なテクニカルさとプログレ風味を併せ持つパワーメタルバンドですね。
前作[To Travel Forevermore]では、スピード感よりも複雑(変態的)に展開するメロディラインが印象的でした。
が、この作品では、その複雑な展開を継承しつつパワーメタル的な爆発力を身に纏い、強烈な相乗効果を生み出しました。
その象徴ともいえるのは、強力無比なニルス・パトリック・ヨハンソンのヴォーカル。
Richard Andersson's Space Odyssey や Astral Doors でお馴染みの彼ですが、Wuthering Heightsが一番合ってるんじゃないかな。。
テクニカルな楽曲群に埋もれるどころか、変幻自在に声色を使い分け存在感をアピールする彼の説得力はバツグンです。
ミドルテンポの楽曲では骨太さと力強さを増幅し、
スピーディな楽曲ではドラマティックな爆発力を演出します。
そして、民俗音楽的でケルティックともいえるエッセンスをまぶしたパワーメタルはBlind Guardianを彷彿させる場面もチラホラ。
[Longing For The Woods Part.1]での 疾走→民俗音楽的小休止→バゴーンと爆裂疾走 という構成はカンペキにワタシのツボなのです。
Heavenlyあたりがスキな方なら失禁モノでしょう。
[Longing For The Woods]Part.1/Part.2/Part.3 と、基本的なメロディが同じ楽曲を三曲収録しており、しかもその三曲全てのクオリティが突出しているところもオドロキです。
展開やアレンジに耳を奪われているうちにアルバムが終わってしまいます。
以前にココで記事にした最新作では、さらにパワーメタル寄りにシフトしています。
が…
メロディックパワーメタル的音楽性を軸に、シンフォニック・プログレッシブ・民族的アレンジ が三位一体のバランスで散りばめられたこのアルバムが最強でしょう。
購入時には悪名高きCCCDだったのが鬱でした…。
今はどうだか分かりませんが、もし「買ってみよう」なんて気になった方は要注意です。
2007年04月13日
80年代
80年代の音楽シーンって華やかだったなぁ。
今ほど細かいカテゴライズもなくて、純粋に音楽が楽しめてたような。
アメリカでも、ロックバンドがどんどんランキングに入ったり。
「アリーナロック」っていう言葉がピッタリの元気印なバンドが次々と出てきてた。
こんな話をすると「昔話好きのオッサン」になりますが…。(実際、そうだけど)
そんな時代の空気を蘇らせてくれるアルバムに出会いました。
WIGWAM [WIGWAMANIA]
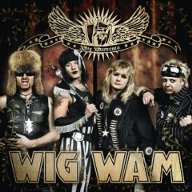
見た目、音楽性、歌詞。どれも80年代アリーナロックの香りがプンプン。
歌舞伎町のメタルバー GODZ でもPVが流れてたけど、BON JOVI の全盛期(自分にとっての、ね。)を思い出した。
ノルウェー出身で今どきコレをやるってことはカンペキに確信犯だな。
その当時を再現(?)したかのようなビジュアルも、最初に賛否両論としてもアルバムの素晴らしさに触れてしまえば必要不可欠な個性と思わせてくれます。
ま、それも計算ずくでしょうけど。
適度にポップでメロディアス。どの曲も耳にかかるフックがあり、知らぬ間にリピート。
うーん、80年代。うまくオイシイところを集めたなぁ。
今ほど細かいカテゴライズもなくて、純粋に音楽が楽しめてたような。
アメリカでも、ロックバンドがどんどんランキングに入ったり。
「アリーナロック」っていう言葉がピッタリの元気印なバンドが次々と出てきてた。
こんな話をすると「昔話好きのオッサン」になりますが…。(実際、そうだけど)
そんな時代の空気を蘇らせてくれるアルバムに出会いました。
WIGWAM [WIGWAMANIA]
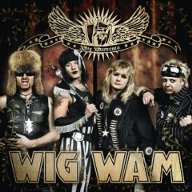
見た目、音楽性、歌詞。どれも80年代アリーナロックの香りがプンプン。
歌舞伎町のメタルバー GODZ でもPVが流れてたけど、BON JOVI の全盛期(自分にとっての、ね。)を思い出した。
ノルウェー出身で今どきコレをやるってことはカンペキに確信犯だな。
その当時を再現(?)したかのようなビジュアルも、最初に賛否両論としてもアルバムの素晴らしさに触れてしまえば必要不可欠な個性と思わせてくれます。
ま、それも計算ずくでしょうけど。
適度にポップでメロディアス。どの曲も耳にかかるフックがあり、知らぬ間にリピート。
うーん、80年代。うまくオイシイところを集めたなぁ。
2006年12月29日
振り返る。
2006年、最後の記事になりそうです。
12月からブログを始めて、毎日何人もの方が覗いてくれます。
毎回、節操のない戯言にお付き合いいただき、感謝感謝です。
「飛騨にHeavyMetalファンはどのくらいいるのか。」
「こんな父親でも、子供たちは真っ直ぐに伸びていくのか。」
といったことを気にしつつ、来年こそは自分も少しオトナになりたい…。
さ、音楽面で今年を振り返ろうかな。順不同に、サラっと。
< 期待以上!ありがとう!のアルバム3つ >
・Harem Scarem / Human Nature
・Wuthering Heights / The Shadow Cabinet
・In Flames / Come Clarity
< 期待通り。次回もよろしく!のアルバム3つ >
・Heavenly / Virus
・Zeno / Runway To The Gods
・Astral Doors / Astralism
< 期待しすぎてゴメン。なアルバム、3つ >
・Angra / Aurora Consurgens
・Blind Guardian / A Twist in the Myth
・Fair Warning / Brother's Keeper
…分かる人が見たら、「あぁ、コイツの主食はこういったジャンルか。」ってバレますね。
で、一番聴いたのは
Wuthering Heights / The Shadow Cabinet

前作、前々作の田舎っぽいフレーズというか、ケルティックな雰囲気が大好きだった自分としては、その部分が後退してしまったことは残念でした。
が、それをカバーして余りある全編に溢れるパワーと、ニルス・パトリック・ヨハンソンのヴォーカル。
期待した方向とは異なるものの、それを有無を言わさずねじ伏せてくれるようなアルバムでした。
…でも、前作の方がスキだ。
来年も名作揃いの年になりますように。
我が家の家族が全員健康でありますように。
…無宗教な自分が言っても、どの神様も聞いてくれないでしょうが。
では、よいお年を!
12月からブログを始めて、毎日何人もの方が覗いてくれます。
毎回、節操のない戯言にお付き合いいただき、感謝感謝です。
「飛騨にHeavyMetalファンはどのくらいいるのか。」
「こんな父親でも、子供たちは真っ直ぐに伸びていくのか。」
といったことを気にしつつ、来年こそは自分も少しオトナになりたい…。
さ、音楽面で今年を振り返ろうかな。順不同に、サラっと。
< 期待以上!ありがとう!のアルバム3つ >
・Harem Scarem / Human Nature
・Wuthering Heights / The Shadow Cabinet
・In Flames / Come Clarity
< 期待通り。次回もよろしく!のアルバム3つ >
・Heavenly / Virus
・Zeno / Runway To The Gods
・Astral Doors / Astralism
< 期待しすぎてゴメン。なアルバム、3つ >
・Angra / Aurora Consurgens
・Blind Guardian / A Twist in the Myth
・Fair Warning / Brother's Keeper
…分かる人が見たら、「あぁ、コイツの主食はこういったジャンルか。」ってバレますね。
で、一番聴いたのは
Wuthering Heights / The Shadow Cabinet

前作、前々作の田舎っぽいフレーズというか、ケルティックな雰囲気が大好きだった自分としては、その部分が後退してしまったことは残念でした。
が、それをカバーして余りある全編に溢れるパワーと、ニルス・パトリック・ヨハンソンのヴォーカル。
期待した方向とは異なるものの、それを有無を言わさずねじ伏せてくれるようなアルバムでした。
…でも、前作の方がスキだ。
来年も名作揃いの年になりますように。
我が家の家族が全員健康でありますように。
…無宗教な自分が言っても、どの神様も聞いてくれないでしょうが。
では、よいお年を!