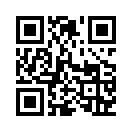ヘビメタパパの書斎 › 2011年04月
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2011年04月28日
至宝の行方
個性的なヴォーカルってのは、バンドのカラーまで決定づけるチカラがある。
彼の妖艶な声も、完全にバンドのカラーを決定づけるものだった。
スピード感のある曲を歌おうが、シンフォニックな曲を歌おうが、「彼の色」に染まっていた。
KAMELOTのロイ・カーン。
そのロイがバンドを脱退した。単なる「ヴォーカルの脱退」では片づけられない事態だと思う。
今回は、そのロイが加入したことでバンドが「カラー」を明確に打ち出すことに成功した節目の作品を。
KAMELOT [THE FOURTH LEGACY ]

アメリカ出身(ということに未だに違和感があるわけですが)、4th。
まさに「化けた」という表現がピッタリで、バンドの分岐点になったということについては異論がないところでしょう。
このアルバムから名盤[KARMA]が生まれ、さらに超名盤[EPICA]へと繋がっていきます。
まさに「ホップ・ステップ・ジャンプ」的な躍進。
その序章とも言うべきアルバムです。
ロイ・カーンといえばCONCEPTIONを思い出す人もいるかもしれませんね。
個人的には・・・たしかにCONCEPTION時代から個性的ではあったけど、KAMELOTに加入してバンドとの相乗効果で一気に開花したという感があります。
アメリカ出身でありながら、ヨーロピアンハードの彩りが強く、ドラマティックかつミステリアスなムードを湛えた楽曲は、まさにロイのシットリとセクシーなヴォーカルがフィットしました。
KAMELOTといえば、ジャケットのパターンもあってか「紫」の印象が強い。
そのイメージの通り、美しさ、仄暗さ、妖しさ、激しさ・・・そういったものが混沌としていながらも繊細なメロディーが真骨頂。
ロイ・カーンという唯一無二を個性を手にして、その妖しく艶やかな声をフルに活用した「KAMELOT節」とも呼べるサウンドは、このアルバムで芽吹いています。
このアルバムでは、後々加速していくことになるダークなムードも適度に配しながらも基本的にはヨーロピアンハード独特の哀愁を踏襲。
名作[KARMA][EPICA]よりはコンパクトな印象ですが、昨今のKAMELOTを思えばかなり聴きやすく、直感的に訴えるチカラが強いアルバムだと思います。
ロイのヴォーカルも全盛期を思えばやや深みに欠ける感はありますが、充分に魅力を堪能できます。
なんといってもイントロから導かれるキラーチューン[The Force Legacy]の威力は凄まじいものがあります。
オリエンタルなムードが溢れる[Nights of Arabia]もKAMELOTの魅力の一つ。
バンドの歴史の中での完成度は、圧倒的に[EPICA]を推したいところですが、このアルバムも「今のサウンドが確立された原点」として非常に重要な位置づけではないでしょうか。
[BLACK HALO]以降は徐々にシンフォニックかつ複雑かつ難解かつダークな方向へ向かっていき、最近では「なんだか・・・遠い存在になっちゃったな。KAMELOT」と思っていたのも事実です。
もしかしたら、バンドも同じような袋小路に入り込んでいたのかもしれません。
ロイのコメントを見ると(英語だから翻訳サイトにかけみただけだけど)、「燃え尽き症候群」「家族と過ごしたい」といったニュアンスのようです。
バンドのブレインであるトーマス・ヤングブラッドは新たな道を模索していくと思います。
実際、新ヴォーカリスト候補と接触しているようですし・・・。
が、ロイとのコンビネーションでバンドをここまで成熟させたわけですから、ロイを失ったダメージは小さくはないでしょう。
逆に言えば、何か目に見えなかった足枷が外れることで、また新たな道を見出してくれるかも・・・と、プラスに考えることしか今はできませんね。
そしてメタル界の至宝とも言えるロイ・カーン・・・バンドの方向性とかではなく精神的なものによる脱退だとすると、今後の活動が気になるところです。
New Allegiance(イントロ) & The Fourth Legacy
Kamelot- Nights of Arabia
彼の妖艶な声も、完全にバンドのカラーを決定づけるものだった。
スピード感のある曲を歌おうが、シンフォニックな曲を歌おうが、「彼の色」に染まっていた。
KAMELOTのロイ・カーン。
そのロイがバンドを脱退した。単なる「ヴォーカルの脱退」では片づけられない事態だと思う。
今回は、そのロイが加入したことでバンドが「カラー」を明確に打ち出すことに成功した節目の作品を。
KAMELOT [THE FOURTH LEGACY ]

アメリカ出身(ということに未だに違和感があるわけですが)、4th。
まさに「化けた」という表現がピッタリで、バンドの分岐点になったということについては異論がないところでしょう。
このアルバムから名盤[KARMA]が生まれ、さらに超名盤[EPICA]へと繋がっていきます。
まさに「ホップ・ステップ・ジャンプ」的な躍進。
その序章とも言うべきアルバムです。
ロイ・カーンといえばCONCEPTIONを思い出す人もいるかもしれませんね。
個人的には・・・たしかにCONCEPTION時代から個性的ではあったけど、KAMELOTに加入してバンドとの相乗効果で一気に開花したという感があります。
アメリカ出身でありながら、ヨーロピアンハードの彩りが強く、ドラマティックかつミステリアスなムードを湛えた楽曲は、まさにロイのシットリとセクシーなヴォーカルがフィットしました。
KAMELOTといえば、ジャケットのパターンもあってか「紫」の印象が強い。
そのイメージの通り、美しさ、仄暗さ、妖しさ、激しさ・・・そういったものが混沌としていながらも繊細なメロディーが真骨頂。
ロイ・カーンという唯一無二を個性を手にして、その妖しく艶やかな声をフルに活用した「KAMELOT節」とも呼べるサウンドは、このアルバムで芽吹いています。
このアルバムでは、後々加速していくことになるダークなムードも適度に配しながらも基本的にはヨーロピアンハード独特の哀愁を踏襲。
名作[KARMA][EPICA]よりはコンパクトな印象ですが、昨今のKAMELOTを思えばかなり聴きやすく、直感的に訴えるチカラが強いアルバムだと思います。
ロイのヴォーカルも全盛期を思えばやや深みに欠ける感はありますが、充分に魅力を堪能できます。
なんといってもイントロから導かれるキラーチューン[The Force Legacy]の威力は凄まじいものがあります。
オリエンタルなムードが溢れる[Nights of Arabia]もKAMELOTの魅力の一つ。
バンドの歴史の中での完成度は、圧倒的に[EPICA]を推したいところですが、このアルバムも「今のサウンドが確立された原点」として非常に重要な位置づけではないでしょうか。
[BLACK HALO]以降は徐々にシンフォニックかつ複雑かつ難解かつダークな方向へ向かっていき、最近では「なんだか・・・遠い存在になっちゃったな。KAMELOT」と思っていたのも事実です。
もしかしたら、バンドも同じような袋小路に入り込んでいたのかもしれません。
ロイのコメントを見ると(英語だから翻訳サイトにかけみただけだけど)、「燃え尽き症候群」「家族と過ごしたい」といったニュアンスのようです。
バンドのブレインであるトーマス・ヤングブラッドは新たな道を模索していくと思います。
実際、新ヴォーカリスト候補と接触しているようですし・・・。
が、ロイとのコンビネーションでバンドをここまで成熟させたわけですから、ロイを失ったダメージは小さくはないでしょう。
逆に言えば、何か目に見えなかった足枷が外れることで、また新たな道を見出してくれるかも・・・と、プラスに考えることしか今はできませんね。
そしてメタル界の至宝とも言えるロイ・カーン・・・バンドの方向性とかではなく精神的なものによる脱退だとすると、今後の活動が気になるところです。
New Allegiance(イントロ) & The Fourth Legacy
Kamelot- Nights of Arabia
2011年04月26日
12回目の記念日
先日、我が家の結婚記念日を迎えました。
なんと12年です。12年。
・・・べつに「なんと!」と強調することではありませんが。
今年は何だか感慨深いものがありまして・・・12ってのも十二支とかの関係もあって「一回り」って気がするからでしょうかね。
子供たちも3年生と1年生になって、「結婚記念日」という位置づけは理解できているようだ。
ムスメは「どっちが告白したの?なんで決めたの?」などと具体的なクエスチョンが増えてきた。
ボウズは「おかあさんはオレと結婚するでな。おとうさんはちょっとどっか行っといてな。」などと結婚記念日にふさわしくない不穏なコトを言っている。
とりあえず共通しているのは「結婚記念日っつったらケーキだよね。ケーキ買うよね。自分で好きなの決めてもいいよね。」ということらしい。
ワタシ自身がケーキ好きなこともあって、誕生日だのクリスマスだの結婚記念日だのと毎回の店選びはいろいろ迷うトコなんだが、ここ何度かはシェリールさんが多かった。
個人的には一番好きなのだ。
が、奥様はセーズさんのケーキが好きらしいので、今回はセーズさんでケーキ購入。
子供たちも「自分で結婚記念日のお祝い買う」と言って、200円ほどの焼き菓子を自分のお小遣いで買っていた。
・・・それぞれ一個ね。当然「おかあさんの分だけね」ってことで。はい。
ワタシからは、久しぶりに花を買った。
ここ数年、「花は枯れるし食えないからいらない」と断られていたのだが、他のモノもパターン化してきてたし。久々にね。
この花束を渡したところ、「結婚12年目でバラが12本・・・ちょっとビックリした。すげぇじゃん。」って驚かれた。
・・・残念。
花屋さんがたまたま選んだ本数が12本だっただけで何も考えてなかったです。
花のことなんかサッパリ分からないので、「○○円分。適当に。」って頼んだだけ。
で、「う・・うん。まぁ・・・」と濁したものの、後からムスメが「おとーさん、何も花屋さんに頼んでないよ。全部、花屋さんが決めたんやさ。」と暴露して、終了。
その際の奥様のガッカリ感は言うまでもない。
なんだか竜頭蛇尾とはこのことだ。
花束の価値は急落の底値だ。
で、夜は子供たちのリクエスト&毎年恒例の焼き鳥。
帰りの運転を気にせず二人ともが飲んで、代行を使って帰る・・・ササヤカだけど、我が家にとってはゼイタクなことだ。
ワタシから「12年、どう?」と聞くと、奥様からは一言「・・・綱渡りやな」。
・・・そうでしたか。そうですね。いろいろゴメンナサイ。
ムスメは「カルピスおかわりな。結婚記念日やでな。お祝いやでな。いいよな。」とジョッキのカルピスをオカワリ。
ボウズは「おとーさん、このラムネのな、ビー玉な、取れんのやさ。割ってもいい?」・・・いやいやダメです。
:
:
:
ま、「10年経ってもケンカもせず、毎日仲良しで幸せです。お互い100点満点です!」ってな夫婦は希有だろうと思う。
そう思いたい。
冷戦状態や衝突を繰返し、
日々お互いに妥協と折衝と譲歩を繰返し、
何もない日々に平穏を感じ、
子供のことや将来の不安を吐露しあい、
なんだかんだで「たまたま結婚したけど、元々はアカの他人だった人」が「パートナー」へ変化していく。
まだまだその過程。道半ば。
もともと、何事に対しても「ケッ!」と思う傾向があったワタシだが、なんだかトシを重ねて短気になってきた気がするんだ。我ながら。ヤダヤダ。
揉めてもできるだけ翌朝には繰り越さないように、あとあとまで尾を引かないように・・・そんなことを思いつつ、とりあえず13年目を無事に迎えられるといいなぁ、と願うばかりです。
なんと12年です。12年。
・・・べつに「なんと!」と強調することではありませんが。
今年は何だか感慨深いものがありまして・・・12ってのも十二支とかの関係もあって「一回り」って気がするからでしょうかね。
子供たちも3年生と1年生になって、「結婚記念日」という位置づけは理解できているようだ。
ムスメは「どっちが告白したの?なんで決めたの?」などと具体的なクエスチョンが増えてきた。
ボウズは「おかあさんはオレと結婚するでな。おとうさんはちょっとどっか行っといてな。」などと結婚記念日にふさわしくない不穏なコトを言っている。
とりあえず共通しているのは「結婚記念日っつったらケーキだよね。ケーキ買うよね。自分で好きなの決めてもいいよね。」ということらしい。
ワタシ自身がケーキ好きなこともあって、誕生日だのクリスマスだの結婚記念日だのと毎回の店選びはいろいろ迷うトコなんだが、ここ何度かはシェリールさんが多かった。
個人的には一番好きなのだ。
が、奥様はセーズさんのケーキが好きらしいので、今回はセーズさんでケーキ購入。
子供たちも「自分で結婚記念日のお祝い買う」と言って、200円ほどの焼き菓子を自分のお小遣いで買っていた。
・・・それぞれ一個ね。当然「おかあさんの分だけね」ってことで。はい。
ワタシからは、久しぶりに花を買った。
ここ数年、「花は枯れるし食えないからいらない」と断られていたのだが、他のモノもパターン化してきてたし。久々にね。
この花束を渡したところ、「結婚12年目でバラが12本・・・ちょっとビックリした。すげぇじゃん。」って驚かれた。
・・・残念。
花屋さんがたまたま選んだ本数が12本だっただけで何も考えてなかったです。
花のことなんかサッパリ分からないので、「○○円分。適当に。」って頼んだだけ。
で、「う・・うん。まぁ・・・」と濁したものの、後からムスメが「おとーさん、何も花屋さんに頼んでないよ。全部、花屋さんが決めたんやさ。」と暴露して、終了。
その際の奥様のガッカリ感は言うまでもない。
なんだか竜頭蛇尾とはこのことだ。
花束の価値は急落の底値だ。
で、夜は子供たちのリクエスト&毎年恒例の焼き鳥。
帰りの運転を気にせず二人ともが飲んで、代行を使って帰る・・・ササヤカだけど、我が家にとってはゼイタクなことだ。
ワタシから「12年、どう?」と聞くと、奥様からは一言「・・・綱渡りやな」。
・・・そうでしたか。そうですね。いろいろゴメンナサイ。
ムスメは「カルピスおかわりな。結婚記念日やでな。お祝いやでな。いいよな。」とジョッキのカルピスをオカワリ。
ボウズは「おとーさん、このラムネのな、ビー玉な、取れんのやさ。割ってもいい?」・・・いやいやダメです。
:
:
:
ま、「10年経ってもケンカもせず、毎日仲良しで幸せです。お互い100点満点です!」ってな夫婦は希有だろうと思う。
そう思いたい。
冷戦状態や衝突を繰返し、
日々お互いに妥協と折衝と譲歩を繰返し、
何もない日々に平穏を感じ、
子供のことや将来の不安を吐露しあい、
なんだかんだで「たまたま結婚したけど、元々はアカの他人だった人」が「パートナー」へ変化していく。
まだまだその過程。道半ば。
もともと、何事に対しても「ケッ!」と思う傾向があったワタシだが、なんだかトシを重ねて短気になってきた気がするんだ。我ながら。ヤダヤダ。
揉めてもできるだけ翌朝には繰り越さないように、あとあとまで尾を引かないように・・・そんなことを思いつつ、とりあえず13年目を無事に迎えられるといいなぁ、と願うばかりです。
2011年04月22日
ドリームチーム
さて。脳内で描いてみてください。
サウンドは、キーボードがキラキラと彩る、全盛期のSTRATOVARIUS。
そして、ヴォーカルはティモ・コティペルト・・・ではなく、元ANGRAのアンドレ・マトス。
脳内再生されましたか。
そうそう。
まさにそんなアルバムです。他に言うことはありません。
ってことで、以下余白はトルキ&マトやんに捧げるよ。
:
:
:
と、伊藤政則氏の名(迷)レビューをパクってしまいましたが・・・。
そのスジの方々にとってはドリームチーム!・・・だけど、そのスジの方々は当然現在のトルキ&マトやんの凋落ぶりを知っている方々とイコール。
いろいろと複雑な思いを巡らせつつも期待してしまうのは、双方の黄金期を知っているからですね。
SYMFONIA [In Paradisum]
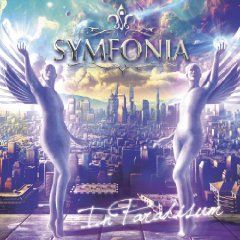
SYMPHONIA・・・ではなく、SYMFONIAです。
メロディックパワーメタル界隈をウロウロしている人たちなら、一度は目にしたことがあるであろうメンバーで構成されていますね。
Vo. アンドレ・マトス!(元 ANGRA)
G. ティモ・トルキ!(元 STRATOVARIUS)
B. ヤリ・カイヌライネン!(元 STRATOVARIUS)
Key.ミッコ・ハルキン!(元 SONATA ARCTICA)
Dr. ウリ・カッシュ!(元 GAMMA RAY/HELLOWEEN)
・・・と、まぁ「!」をイッパイつけてみたものの、このメンツを見て「・・・続かねーな。コレ。」と思ったヒト。
ワタシと感性が近いですね。
とはいえ、一聴して思ったのは「ティモ・トルキ、どん底は抜けたかな。」という感じ。
STRATOVARIUSが彼のバンドだった頃のサウンドが蘇っていますね。
ドコドコドコドコ ダン! ピロピロピロピロ~ というドラム→ブレイク→キーボードへのスイッチもあの当時のSTRATOVARIUSそのまま。
そりゃ全盛期STRATOVARIUSのクオリティを期待しちゃいけない。
だけど、STRATOVARUIS末期(いや、バンドは続いてるから語弊あるかな。ティモ時代の末期ってことね)の頽廃的な状況、Revolution Renaissanceでの中途半端な活動を思えば、ひとまず「表舞台に帰還」という感はありますね。
オープニングを飾る[Fields Of Avalon]は、「ティモ・トルキのSTRATOVARIUS」でイメージされる全てが凝縮しています。
続く[Come By The Hills]は、これまたいかにもSTRATOVARIUSの2曲目といった感じで[Distant Skies]を想起させます・・・こういう単純なスピードチューンではないリズムを持つ曲を作れるのも強みだよね。
アンドレ・マトスも体型はティモに迎合するかのうように巨大化していますが、ヴォーカルは健在。
VIPER~ANGRA初期にはクラシカルなパワーメタルの第一人者として認知されて絶賛されていたにも関わらず、ANGRA脱退後は後任のエドゥ・ファラスキおよびアルバムが素晴らしすぎたこともあって「なんだ、マトやんいらないじゃん」という扱いを受けてしまったツイてない人。
その後のSHAMANやソロでも「らしい」曲を披露しながらも、ANGRA全盛期と比べられてしまい・・・
だけどね。ワタシ個人的にはANGRAのマトス時代、好きです。
細いけど、ピンと筋が通ってて繊細なハイトーン。エドゥとの比較抜きで、いいヴォーカルだなと思います。
いくらマイケル・キスクが上手でも、「やっぱカイのヴォーカルも好きなんだよね。いや、むしろ曲によってはカイじゃないとね」ってヒト、いるよね。(→わたしです)
ま、それと似てると思うよ。
で、トータルでは「今のトルキなら、まぁ・・・盛り上げたところで・・・どうせ・・・ねぇ・・・」という予想は嬉しい方向に裏切られた。
ひとまずファンがメンツを見て期待するであろうサウンドを、期待通り、忠実に表現してくれています。
けど、やはり全盛期を知る人にとっては、あくまで「期待通り」であって「期待以上」ではない。
ストラトサウンドをマトスが歌う。その一言。
だけど、それで充分だと思うんだ。
あの病的だったトルキが(今、その状態を脱しているのか定かではないけど)、期待通りのアルバムを出してくれたってことに意味があると思う。
この二人が新しいことにチャレンジするのではなく、「オレたちのファンが期待してるのは、コレだよね。」と、お互いの輝いていた時代を踏襲してくれたことに意味があると思う。
懐古主義といわれようが、媚びているといわれようが、これで良かったと思う。
聞いた話によると、バンドは4枚の契約をしているという。
今回はティモの意志が強かったのか、STRATOVARIUS色が強くなっているけど、マトスが自分の得意なクラシカル・カラーを織り込んでいけば、また違った魅力が生まれるかもしれない。
そう、アンディ・デリスとマイケル・ヴァイカートという意外な組み合わせがマジカルな相乗効果を生み出したように。
ただ、その期待の反面、やっぱり「4枚ってムチャすぎる!」「オリジナルアルバム2枚、ライブアルバム1枚、あとは・・・まさかベストアルバム!?」という心配も尽きないのだが・・・。
Symfonia - Fields Of Avalon
Symfonia - Come By The Hills
サウンドは、キーボードがキラキラと彩る、全盛期のSTRATOVARIUS。
そして、ヴォーカルはティモ・コティペルト・・・ではなく、元ANGRAのアンドレ・マトス。
脳内再生されましたか。
そうそう。
まさにそんなアルバムです。他に言うことはありません。
ってことで、以下余白はトルキ&マトやんに捧げるよ。
:
:
:
と、伊藤政則氏の名(迷)レビューをパクってしまいましたが・・・。
そのスジの方々にとってはドリームチーム!・・・だけど、そのスジの方々は当然現在のトルキ&マトやんの凋落ぶりを知っている方々とイコール。
いろいろと複雑な思いを巡らせつつも期待してしまうのは、双方の黄金期を知っているからですね。
SYMFONIA [In Paradisum]
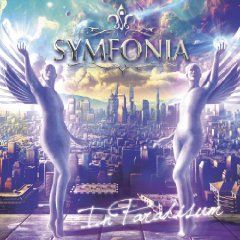
SYMPHONIA・・・ではなく、SYMFONIAです。
メロディックパワーメタル界隈をウロウロしている人たちなら、一度は目にしたことがあるであろうメンバーで構成されていますね。
Vo. アンドレ・マトス!(元 ANGRA)
G. ティモ・トルキ!(元 STRATOVARIUS)
B. ヤリ・カイヌライネン!(元 STRATOVARIUS)
Key.ミッコ・ハルキン!(元 SONATA ARCTICA)
Dr. ウリ・カッシュ!(元 GAMMA RAY/HELLOWEEN)
・・・と、まぁ「!」をイッパイつけてみたものの、このメンツを見て「・・・続かねーな。コレ。」と思ったヒト。
ワタシと感性が近いですね。
とはいえ、一聴して思ったのは「ティモ・トルキ、どん底は抜けたかな。」という感じ。
STRATOVARIUSが彼のバンドだった頃のサウンドが蘇っていますね。
ドコドコドコドコ ダン! ピロピロピロピロ~ というドラム→ブレイク→キーボードへのスイッチもあの当時のSTRATOVARIUSそのまま。
そりゃ全盛期STRATOVARIUSのクオリティを期待しちゃいけない。
だけど、STRATOVARUIS末期(いや、バンドは続いてるから語弊あるかな。ティモ時代の末期ってことね)の頽廃的な状況、Revolution Renaissanceでの中途半端な活動を思えば、ひとまず「表舞台に帰還」という感はありますね。
オープニングを飾る[Fields Of Avalon]は、「ティモ・トルキのSTRATOVARIUS」でイメージされる全てが凝縮しています。
続く[Come By The Hills]は、これまたいかにもSTRATOVARIUSの2曲目といった感じで[Distant Skies]を想起させます・・・こういう単純なスピードチューンではないリズムを持つ曲を作れるのも強みだよね。
アンドレ・マトスも体型はティモに迎合するかのうように巨大化していますが、ヴォーカルは健在。
VIPER~ANGRA初期にはクラシカルなパワーメタルの第一人者として認知されて絶賛されていたにも関わらず、ANGRA脱退後は後任のエドゥ・ファラスキおよびアルバムが素晴らしすぎたこともあって「なんだ、マトやんいらないじゃん」という扱いを受けてしまったツイてない人。
その後のSHAMANやソロでも「らしい」曲を披露しながらも、ANGRA全盛期と比べられてしまい・・・
だけどね。ワタシ個人的にはANGRAのマトス時代、好きです。
細いけど、ピンと筋が通ってて繊細なハイトーン。エドゥとの比較抜きで、いいヴォーカルだなと思います。
いくらマイケル・キスクが上手でも、「やっぱカイのヴォーカルも好きなんだよね。いや、むしろ曲によってはカイじゃないとね」ってヒト、いるよね。(→わたしです)
ま、それと似てると思うよ。
で、トータルでは「今のトルキなら、まぁ・・・盛り上げたところで・・・どうせ・・・ねぇ・・・」という予想は嬉しい方向に裏切られた。
ひとまずファンがメンツを見て期待するであろうサウンドを、期待通り、忠実に表現してくれています。
けど、やはり全盛期を知る人にとっては、あくまで「期待通り」であって「期待以上」ではない。
ストラトサウンドをマトスが歌う。その一言。
だけど、それで充分だと思うんだ。
あの病的だったトルキが(今、その状態を脱しているのか定かではないけど)、期待通りのアルバムを出してくれたってことに意味があると思う。
この二人が新しいことにチャレンジするのではなく、「オレたちのファンが期待してるのは、コレだよね。」と、お互いの輝いていた時代を踏襲してくれたことに意味があると思う。
懐古主義といわれようが、媚びているといわれようが、これで良かったと思う。
聞いた話によると、バンドは4枚の契約をしているという。
今回はティモの意志が強かったのか、STRATOVARIUS色が強くなっているけど、マトスが自分の得意なクラシカル・カラーを織り込んでいけば、また違った魅力が生まれるかもしれない。
そう、アンディ・デリスとマイケル・ヴァイカートという意外な組み合わせがマジカルな相乗効果を生み出したように。
ただ、その期待の反面、やっぱり「4枚ってムチャすぎる!」「オリジナルアルバム2枚、ライブアルバム1枚、あとは・・・まさかベストアルバム!?」という心配も尽きないのだが・・・。
Symfonia - Fields Of Avalon
Symfonia - Come By The Hills
2011年04月20日
カラオケ夢舞台
以前、地域の班での懇親会的イベントがあってですね。
そのイベント(ま、ホテルでの宴会だけどね)は、子供も参加オッケーだったのです。
ホテルでの宴会といえば、カラオケがつきもの。
大人が歌ってるのを見て、たくさんの子供たちがワサワサと「歌いたい歌いたい歌いたい歌いたい」と集まってきた。
で、「ちびまる子ちゃん」とかを歌ったりしてたわけです。
それがあってからというもの、ムスメ&ボウズが「カラオケ行きたいカラオケ行きたいカラオケ行きたい」とウルさくなってきた。
ワタシと奥様は聞く音楽が異なることもあり、二人での娯楽、もしくは家族での娯楽に「カラオケ」という選択肢は無い。
が、せっかくだから・・・いってみる?ということで行ってきましたよ。
子供たち中心だから、基本はアニメソング中心。
・・・ん?
・・・ってことは、何の気兼ねなくアニソンを歌えるってことじゃないか!
子供たちが知っている曲、という足枷はつくものの、これは願ったり叶ったりじゃないか!
まず、子供たちが「ぜったい歌いたい!」と言っていた「ユカイツーカイ怪物くん」からスタート。
そして気付いた。
ムスメは音程を大事にして、慎重に歌うタイプだ。
ボウズは顔を歪めながら声を張り上げシャウトするタイプだ。
このシャウト・・・この歌い方・・・DNAを感じる瞬間でしたよ。
奥様からも「あの叫び方・・・残念ながら似たな。誰かに。」とコチラをチラリ。
あぁ・・・分かってるさ。
その後、二人で歌える「ドラえもん」「ちびまる子ちゃん」といった曲を歌いつつ・・・。
ムスメは「しゅごキャラ」や、最近お気に入りの嵐の曲を。
ボウズは当然、スーパー戦隊、仮面ライダーといった曲を歌いつつ・・・
ついにこの名曲を二人でデュエットするときがきた。
ムスメも「♪キミのそばにいるよ~」と、女性パート担当で参加。
子供たちと「MOTTO! MOTTO!」と叫ぶ。子供たちとJAM PROJECTを競演できるとは・・・まさに親子の夢舞台。
感涙モノですね。
で、コレも盛り上がったよ。
ワタシが歌いたかったスーパーロボット系は、ボウズが3~4歳の頃にハマってたが最近聞いてないようだから、次回カラオケまでに再び思い出してもらおうかと。
そして「パイルダーオン!」「ブイブイブイ!ビクトリー!」「ガッツ!ガッツ!ゲッターガッツ!」と叫ぶのさ。
熱き叫びのDNAを持つ友とね。
そのイベント(ま、ホテルでの宴会だけどね)は、子供も参加オッケーだったのです。
ホテルでの宴会といえば、カラオケがつきもの。
大人が歌ってるのを見て、たくさんの子供たちがワサワサと「歌いたい歌いたい歌いたい歌いたい」と集まってきた。
で、「ちびまる子ちゃん」とかを歌ったりしてたわけです。
それがあってからというもの、ムスメ&ボウズが「カラオケ行きたいカラオケ行きたいカラオケ行きたい」とウルさくなってきた。
ワタシと奥様は聞く音楽が異なることもあり、二人での娯楽、もしくは家族での娯楽に「カラオケ」という選択肢は無い。
が、せっかくだから・・・いってみる?ということで行ってきましたよ。
子供たち中心だから、基本はアニメソング中心。
・・・ん?
・・・ってことは、何の気兼ねなくアニソンを歌えるってことじゃないか!
子供たちが知っている曲、という足枷はつくものの、これは願ったり叶ったりじゃないか!
まず、子供たちが「ぜったい歌いたい!」と言っていた「ユカイツーカイ怪物くん」からスタート。
そして気付いた。
ムスメは音程を大事にして、慎重に歌うタイプだ。
ボウズは顔を歪めながら声を張り上げシャウトするタイプだ。
このシャウト・・・この歌い方・・・DNAを感じる瞬間でしたよ。
奥様からも「あの叫び方・・・残念ながら似たな。誰かに。」とコチラをチラリ。
あぁ・・・分かってるさ。
その後、二人で歌える「ドラえもん」「ちびまる子ちゃん」といった曲を歌いつつ・・・。
ムスメは「しゅごキャラ」や、最近お気に入りの嵐の曲を。
ボウズは当然、スーパー戦隊、仮面ライダーといった曲を歌いつつ・・・
ついにこの名曲を二人でデュエットするときがきた。
ムスメも「♪キミのそばにいるよ~」と、女性パート担当で参加。
子供たちと「MOTTO! MOTTO!」と叫ぶ。子供たちとJAM PROJECTを競演できるとは・・・まさに親子の夢舞台。
感涙モノですね。
で、コレも盛り上がったよ。
ワタシが歌いたかったスーパーロボット系は、ボウズが3~4歳の頃にハマってたが最近聞いてないようだから、次回カラオケまでに再び思い出してもらおうかと。
そして「パイルダーオン!」「ブイブイブイ!ビクトリー!」「ガッツ!ガッツ!ゲッターガッツ!」と叫ぶのさ。
熱き叫びのDNAを持つ友とね。
2011年04月11日
蓼食う虫も好き好き
ちょっと前の東京出張時、新宿のメタルバーGODZで・・・。
(なんか最近、このフリが多いけど気にしないでくださいな。たまたま東京出張が重なっただけなので)
そこで若者数人が高いテンションで盛り上がっていまして。
なんとなく巻き込まれてしまったので話をしていたのです。
その中、紅一点の若いオンナノコと話してたら、そのコは「メタルにハマったキッカケはLORDIでした」って。
LORDIからメタル道へ!しかもハタチソコソコのオンナノコが!
・・・ってのもスゴいが、そもそもLORDIってつい最近じゃねーか!
ってことで、思い出したように引っ張りだしてきました。
LORDI [THE AROCKALYPSE]

フィンランド出身、3rd。2006年リリース・・・最近だよね。
KISS・・・というよりはGWAR(古い・・・)を想起するモンスターちっくなビジュアル。
こういったルックスってのは諸刃の剣で、インパクト強いから記憶には残るものの、そのビジュアル先行で音楽性がついてこれないとただのイロモノになってしまいがち。
LORDIは、そのホラーな見た目とは裏腹に、非常にオーソドックスなハードロックですね。
ヴォーカルスタイルがダミ声で、時にウド・ダークシュナイダーを思わせるとこがあったりするので、直感的にはヒトクセあるように感じるのですが、冷静にメロディラインを紐解いてみると、けっこうキャッチー。
ポップな・・・というと語弊があるかもしれませんが、時にアメリカの産業ロック的メロディを想起します。
そのオーソドックスなハードロックの中でもサビで漂ってくる哀愁は、さすが北欧出身といったところでしょうか。
アルバムで聴いてると「悪くないんだけど、何か一つ抜けたものがない」という気がしなくもないですが、ライブで盛り上がりそうなガッツ溢れるメロディも多いですね。
実際、この音楽性ならこの声じゃなくても・・・と思ったりする場面があるのも事実ですが、こういった曲だと「この声だからこそ盛り上がるんだろな」というところもありますね。
ま、このスタイルで活動していく以上は、どうしたってこの声との共存になるだろうし、難しいとこだろうね。
トータルで言うと、ビジュアルとサウンドのアンバランスさが魅力と言えなくもないですが、もう少し強力なフックが欲しいな、と思います。
ビジュアルでの個性が強すぎるわりには、サウンドが正統派すぎる、マジメすぎる、という感が。
逆に見た目から入るのではなくサウンドから入れば意外と古株のメタルファンから新世代のメタルファンまで分け隔てなく聴ける、良質なハードロック。
見た目で敬遠してしまった人がいるなら、その偏見は捨てて聴いてみてほしいなと思いますよ。
しかしそうやって考えると・・・・あのスタイルで完全にオリジナリティを確立したSlipknotは偉大だな。
Lordi - Hard Rock Hallelujah
Lordi - Bringing Back The Balls To Rock
(なんか最近、このフリが多いけど気にしないでくださいな。たまたま東京出張が重なっただけなので)
そこで若者数人が高いテンションで盛り上がっていまして。
なんとなく巻き込まれてしまったので話をしていたのです。
その中、紅一点の若いオンナノコと話してたら、そのコは「メタルにハマったキッカケはLORDIでした」って。
LORDIからメタル道へ!しかもハタチソコソコのオンナノコが!
・・・ってのもスゴいが、そもそもLORDIってつい最近じゃねーか!
ってことで、思い出したように引っ張りだしてきました。
LORDI [THE AROCKALYPSE]

フィンランド出身、3rd。2006年リリース・・・最近だよね。
KISS・・・というよりはGWAR(古い・・・)を想起するモンスターちっくなビジュアル。
こういったルックスってのは諸刃の剣で、インパクト強いから記憶には残るものの、そのビジュアル先行で音楽性がついてこれないとただのイロモノになってしまいがち。
LORDIは、そのホラーな見た目とは裏腹に、非常にオーソドックスなハードロックですね。
ヴォーカルスタイルがダミ声で、時にウド・ダークシュナイダーを思わせるとこがあったりするので、直感的にはヒトクセあるように感じるのですが、冷静にメロディラインを紐解いてみると、けっこうキャッチー。
ポップな・・・というと語弊があるかもしれませんが、時にアメリカの産業ロック的メロディを想起します。
そのオーソドックスなハードロックの中でもサビで漂ってくる哀愁は、さすが北欧出身といったところでしょうか。
アルバムで聴いてると「悪くないんだけど、何か一つ抜けたものがない」という気がしなくもないですが、ライブで盛り上がりそうなガッツ溢れるメロディも多いですね。
実際、この音楽性ならこの声じゃなくても・・・と思ったりする場面があるのも事実ですが、こういった曲だと「この声だからこそ盛り上がるんだろな」というところもありますね。
ま、このスタイルで活動していく以上は、どうしたってこの声との共存になるだろうし、難しいとこだろうね。
トータルで言うと、ビジュアルとサウンドのアンバランスさが魅力と言えなくもないですが、もう少し強力なフックが欲しいな、と思います。
ビジュアルでの個性が強すぎるわりには、サウンドが正統派すぎる、マジメすぎる、という感が。
逆に見た目から入るのではなくサウンドから入れば意外と古株のメタルファンから新世代のメタルファンまで分け隔てなく聴ける、良質なハードロック。
見た目で敬遠してしまった人がいるなら、その偏見は捨てて聴いてみてほしいなと思いますよ。
しかしそうやって考えると・・・・あのスタイルで完全にオリジナリティを確立したSlipknotは偉大だな。
Lordi - Hard Rock Hallelujah
Lordi - Bringing Back The Balls To Rock
2011年04月08日
それぞれの春
4月だ。春だ。メタTの季節だ。
社会人だと「決算」という大きな節目を迎えるトコも多く、なんだかピリピリだったりドンヨリだったりホクホクだったりと悲喜こもごもかと思うわけですが、子供たちにとっては入学!進学!といった新たな一歩の時。
ご多分に洩れず、我が家でもコドモたちが節目を迎えましたよ。
将来振り返った時に、「そうか・・・この頃は、こんなこと言ってたか」というメモも兼ねて。
完全に「人んちのことなんか興味ねぇ。チラシの裏に書いとけや。」的内容なので、そういった方はスルーでお願いします。
:
:
:
三年生になったムスメ。
最近の口癖は「オトコはカッコよさよりも、優しさと楽しさだよね」だ。
ちなみに今が旬(?)の「嵐」のメンバーの中では、大野クンが№1。松潤が最下位・・・らしい。
弟のボウズが小学生になったこともあり、さすがに「しっかりしないと」と思っているようだ。
ボウズが生まれる前、奥様が長期入院中に2人で生活していた時期があった。
何か不安があったんだろうけど、「怖い夢を見る」ということが多くなっていた。
その頃から、寝る前にワタシからムスメに「怖い夢を見ないおまじない」をしてから寝るようになった。
それはボウズが生まれてからも毎日続いた。
ムスメが奥様と寝る時も、その「おとうさんのおまじない」だけは欠かさなかった。
が。
この春から「おとうさん、わたし何もなしで寝る練習する」ということで、「おまじない」卒業。
・・・なんだか寂しいけど、一歩一歩自立しているんだろうな、と思います。
そして、一年生になったボウズ。
一年生になるということで、最初に気合を入れていたのが、「オレ、目ざましで自分で起きる!」ってことだった。
で、さっそく目ざましを物色に。
以前ムスメ用に買ったデジタルの「ピピピピッ、ピピピピッ」って音なんぞでは子供は起きない。と分かっていたので、かなりウルサい「ジリリリリリリリ!!」と鳴るヤツを選択。
さっそく登校初日に使ったけど、案の定、起きなかったらしい・・・。
早生まれってこともあり、どちらかというと同級生よりも一学年下の子あたりに近いボウズ。
最近は、奥様とモメては
「もういいさ!おとうさんと寝るし、ぜんぶおとうさんに頼むで!おかあさん、イヤ!」(コタツにもぐり込む)
で、ワタシとモメては
「もういいさ!おかあさんと寝るし、(以下同文)」
・・・と、そのときの気分によって半ばキレ気味になる傾向がある。
奥様は「既に反抗期やな。」とゲンナリだが、たぶん「かまってちゃん」なのだ。基本的に。
ま、学校でドンドン揉まれりゃ、「世の中そんなに甘くない」と気付くだろう。
すこしづつステップアップしてくれればいいのだ。
ドラクエのカードゲームにハマってた時代を経て、現在はポケモン/仮面ライダー/バトスピ/デュエルマスターズなど、意味あるのかないのかわからんが数字には慣れ親しんできたから、算数は当面心配いらない感じだ。
で、肝心の「字」は、春からムスメと一緒に習字を始めたから、多少は改善してくれるといいが・・・と、字がヘタクソで人生損しているトーチャンは思うのだ。
:
:
:
ってなことで、ムスメ4歳 & ボウズ1歳のときにスタートしたこのブログも、子供たちの成長と共に着実に老化の一途をたどっておりますよ。はい。
社会人だと「決算」という大きな節目を迎えるトコも多く、なんだかピリピリだったりドンヨリだったりホクホクだったりと悲喜こもごもかと思うわけですが、子供たちにとっては入学!進学!といった新たな一歩の時。
ご多分に洩れず、我が家でもコドモたちが節目を迎えましたよ。
将来振り返った時に、「そうか・・・この頃は、こんなこと言ってたか」というメモも兼ねて。
完全に「人んちのことなんか興味ねぇ。チラシの裏に書いとけや。」的内容なので、そういった方はスルーでお願いします。
:
:
:
三年生になったムスメ。
最近の口癖は「オトコはカッコよさよりも、優しさと楽しさだよね」だ。
ちなみに今が旬(?)の「嵐」のメンバーの中では、大野クンが№1。松潤が最下位・・・らしい。
弟のボウズが小学生になったこともあり、さすがに「しっかりしないと」と思っているようだ。
ボウズが生まれる前、奥様が長期入院中に2人で生活していた時期があった。
何か不安があったんだろうけど、「怖い夢を見る」ということが多くなっていた。
その頃から、寝る前にワタシからムスメに「怖い夢を見ないおまじない」をしてから寝るようになった。
それはボウズが生まれてからも毎日続いた。
ムスメが奥様と寝る時も、その「おとうさんのおまじない」だけは欠かさなかった。
が。
この春から「おとうさん、わたし何もなしで寝る練習する」ということで、「おまじない」卒業。
・・・なんだか寂しいけど、一歩一歩自立しているんだろうな、と思います。
そして、一年生になったボウズ。
一年生になるということで、最初に気合を入れていたのが、「オレ、目ざましで自分で起きる!」ってことだった。
で、さっそく目ざましを物色に。
以前ムスメ用に買ったデジタルの「ピピピピッ、ピピピピッ」って音なんぞでは子供は起きない。と分かっていたので、かなりウルサい「ジリリリリリリリ!!」と鳴るヤツを選択。
さっそく登校初日に使ったけど、案の定、起きなかったらしい・・・。
早生まれってこともあり、どちらかというと同級生よりも一学年下の子あたりに近いボウズ。
最近は、奥様とモメては
「もういいさ!おとうさんと寝るし、ぜんぶおとうさんに頼むで!おかあさん、イヤ!」(コタツにもぐり込む)
で、ワタシとモメては
「もういいさ!おかあさんと寝るし、(以下同文)」
・・・と、そのときの気分によって半ばキレ気味になる傾向がある。
奥様は「既に反抗期やな。」とゲンナリだが、たぶん「かまってちゃん」なのだ。基本的に。
ま、学校でドンドン揉まれりゃ、「世の中そんなに甘くない」と気付くだろう。
すこしづつステップアップしてくれればいいのだ。
ドラクエのカードゲームにハマってた時代を経て、現在はポケモン/仮面ライダー/バトスピ/デュエルマスターズなど、意味あるのかないのかわからんが数字には慣れ親しんできたから、算数は当面心配いらない感じだ。
で、肝心の「字」は、春からムスメと一緒に習字を始めたから、多少は改善してくれるといいが・・・と、字がヘタクソで人生損しているトーチャンは思うのだ。
:
:
:
ってなことで、ムスメ4歳 & ボウズ1歳のときにスタートしたこのブログも、子供たちの成長と共に着実に老化の一途をたどっておりますよ。はい。
2011年04月06日
日出ずる国、ニッポン
先日頂いたコメントを拝見して思い出した。
そう。
今、この曲を取り上げずして、いつ取り上げる。
いや、アルバム自体の出来からして(失礼)一生取り上げないかもしれない。
HEAVENS GATE [HELL FOR SALE!]

名作[LIVIN' IN HYSTERIA]の後を受けてリリースされた、1992年発表の3rdアルバム。
疾風のように現れて、疾風のように去っていった・・・と言うと皮肉が過ぎるでしょうか。
いや、大好きだったからこそ、もっと長く頑張って欲しかったという意味も込めてね。
その[LIVIN' IN HYSTERIA]で一気にブレイク。
メタル専門誌BURRN! の表紙も飾り、来日公演も行い・・・と順風満帆だったわけですが、残念なライブパフォーマンスと、このアルバムのビミョーな出来映え(いや、前作が良すぎた)で一気にトーンダウン。
その後のアルバムは意外と良作だったにも関わらず再加速には至らず。
ま、サシャ・ピートはトビアス・サメットのおかげ(?)で、プロデューサーとして名を売ってたり、一緒に来日しちゃったりしてますが・・・。
このアルバム、印象的な曲があるにも関わらず、全体の散漫な印象が強いです。
JudasPriestあたりを源流とするオールドスタイルなHeavyMetalを軸に、コマーシャルなジャーマン的明朗快活さを盛り込んだスタイルこそが彼らの真骨頂であるわけですが、ブレイクしたバンドによくある
「オレたち、それだけじゃないぜ。もっといろいろなスタイルもこなせるぜ」
という過度な意識がマイナスに働いてしまったのではないかと。
ライブもハイトーンは出てない、フェイクの嵐・・・いやいや、あまりケナすことはやめておこう。それはそれでいい思い出だしね。
そんな彼らだったけど、今でも大好きです。
イヤ、ホントに。
基本的にウチのCDラックは好きなバンドが上位に置かれているのですが、このCDを探してて、ANGRAあたりと並んで2段目に配置されてたのを見て「おぉ、けっこう上位ランク!」と勝手にほくそ笑んでましたから。
ある意味では「ジャーマン・バブル」の飲み込まれていっただけかも・・・。
:
:
:
そんな彼らが、愛する日本のファンに向けて書いてくれた曲がアルバムに収録されている。
RISING SUN・・・まさに「日出ずる国、ニッポン」へ向けてのストレートなメッセージだ。
基本的には「ニッポンのみんなサポートをありがとう!一緒にライブ楽しもうぜ!」的内容で、「チープ」「媚びてる」と言われたらそれまでなのですが・・・
今だからこそ、印象深い歌詞を勝手に抜粋。
♪
We cross the night, we see the light
and our dream comes true
we're gonna bring the power all over you
(夜を駆け、光を見る。
そして夢がかなう。
みんなにパワーを与えよう。)
♪
We cross the land of the rising sun
Hope we'll be all together
(日出ずる国を駆け抜け
団結を誓おう。)
※日本語詩は歌詞カードより抜粋、一部フンイキ勝手に修正アリ
HEAVENS GATE / RISING SUN
そう。
今、この曲を取り上げずして、いつ取り上げる。
いや、アルバム自体の出来からして(失礼)一生取り上げないかもしれない。
HEAVENS GATE [HELL FOR SALE!]

名作[LIVIN' IN HYSTERIA]の後を受けてリリースされた、1992年発表の3rdアルバム。
疾風のように現れて、疾風のように去っていった・・・と言うと皮肉が過ぎるでしょうか。
いや、大好きだったからこそ、もっと長く頑張って欲しかったという意味も込めてね。
その[LIVIN' IN HYSTERIA]で一気にブレイク。
メタル専門誌BURRN! の表紙も飾り、来日公演も行い・・・と順風満帆だったわけですが、残念なライブパフォーマンスと、このアルバムのビミョーな出来映え(いや、前作が良すぎた)で一気にトーンダウン。
その後のアルバムは意外と良作だったにも関わらず再加速には至らず。
ま、サシャ・ピートはトビアス・サメットのおかげ(?)で、プロデューサーとして名を売ってたり、一緒に来日しちゃったりしてますが・・・。
このアルバム、印象的な曲があるにも関わらず、全体の散漫な印象が強いです。
JudasPriestあたりを源流とするオールドスタイルなHeavyMetalを軸に、コマーシャルなジャーマン的明朗快活さを盛り込んだスタイルこそが彼らの真骨頂であるわけですが、ブレイクしたバンドによくある
「オレたち、それだけじゃないぜ。もっといろいろなスタイルもこなせるぜ」
という過度な意識がマイナスに働いてしまったのではないかと。
ライブもハイトーンは出てない、フェイクの嵐・・・いやいや、あまりケナすことはやめておこう。それはそれでいい思い出だしね。
そんな彼らだったけど、今でも大好きです。
イヤ、ホントに。
基本的にウチのCDラックは好きなバンドが上位に置かれているのですが、このCDを探してて、ANGRAあたりと並んで2段目に配置されてたのを見て「おぉ、けっこう上位ランク!」と勝手にほくそ笑んでましたから。
ある意味では「ジャーマン・バブル」の飲み込まれていっただけかも・・・。
:
:
:
そんな彼らが、愛する日本のファンに向けて書いてくれた曲がアルバムに収録されている。
RISING SUN・・・まさに「日出ずる国、ニッポン」へ向けてのストレートなメッセージだ。
基本的には「ニッポンのみんなサポートをありがとう!一緒にライブ楽しもうぜ!」的内容で、「チープ」「媚びてる」と言われたらそれまでなのですが・・・
今だからこそ、印象深い歌詞を勝手に抜粋。
♪
We cross the night, we see the light
and our dream comes true
we're gonna bring the power all over you
(夜を駆け、光を見る。
そして夢がかなう。
みんなにパワーを与えよう。)
♪
We cross the land of the rising sun
Hope we'll be all together
(日出ずる国を駆け抜け
団結を誓おう。)
※日本語詩は歌詞カードより抜粋、一部フンイキ勝手に修正アリ
HEAVENS GATE / RISING SUN