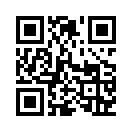ヘビメタパパの書斎 › 2019年07月
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2019年07月31日
ムスメ、17歳になる。
7月某日。
ムスメが17歳になりましたよ。
第一声は「やっとセブンティーン(愛読誌)に追いついた!」と。
いつもこういう節目で思うわけですが、このブログを始めた頃には4歳くらいでしたかね。
そして今や高校二年生。大きくなったものです。
一応大学進学を目指しているらしく、イヤイヤながらも一応勉強を頑張っているようだ。
以前のように「とりあえず東京の大学行ければどこでもいい」といったザックリしたイメージから、多少具現化しているようですが、まだまだ流動的なようだ。
高校一年生の昨夏に、私と二人で東京→千葉→埼玉とオープンキャンパスをハシゴしてきたわけですが、今となっては「ただ観光してきただけだな」という感が強い。
今年は岐阜、富山、新潟‥と、オープンキャンパスにいく予定だ。
いわゆる「行って満足。行っただけで、なんとなく頑張ってる気になる」というヤツですね。
この点については、奥様の「買っただけで満足」「買っただけで健康になったような痩せたような気になる」という血をひいているのでしょう。
新潟と岐阜はまた私と二人旅。
私はそういう時間が作れるだけでそれなりにシアワセだ。成果がなくても。
反抗期とは無縁。
今も相変わらず私にくっついてくるし、お風呂も一緒に入ることもしばしば。
二人で最近読んだ本の話をする時間は、「あぁ‥いいものだな、ムスメというのは」と思うのだ。
ムスメを迎えに行って「おとーさん、なんか買ってこ」と言われると「しゃなーないな(ニコニコ)」だから、奥様に「甘い!甘すぎる!」と叱られる。
けど、いいのだ。
甘えてくれるうちが華なのだ。
勉強と並行して、とある部活に打ち込んでいる。
高校入った直後は全く異なる別の部活に二つ入部してましたが、その二つを早々に退部して今の部活へ。
充実している様子が伝わってきます。
勉強と部活で「ドラマ見る時間がない!」とプリプリしてますが、オン/オフをうまく使い分けてほしいものだ。
誕生日のプレゼントは「掃除機!」。
コードレスで、可愛くて、けどあまり高くなくて‥ということですが、なかなかピンときたものが見つからない。
未だに探しているところで、もしかしたらこのままプレゼントの話は風化するのでは‥と懸念してしまうほどだ。
誕生日の夕食は「肉くいたい!」ってことで、焼きとり屋へ。
私はビール飲めるし、最高のチョイス。
我が家の4人の中では一番の大食漢。よく食べるのだ。とてもシアワセそうに。
「おとーさん、私もダイエットする」
という言葉を定期的に発し、自然消滅していき、また同じセリフを吐き‥を繰り返しているわけですが、
「少しづつでも毎日続けろ」
と話した腹筋は続いているらしく、
「なーなー、おとーさん、このへん(脇腹)触ってみ。ちょっとくびれとるやろ(このとき全裸)」
「おー、すげー!くびれてるやん!(微々たるもの)」
というちょっぴりの満足感に浸っている。
いいのだ。
ムスメはシアワセそうに食べ、シアワセそうに笑うのが魅力なのだ。
それでいいのだ。
ハッピーバースデイ!ムスメ!
ムスメが17歳になりましたよ。
第一声は「やっとセブンティーン(愛読誌)に追いついた!」と。
いつもこういう節目で思うわけですが、このブログを始めた頃には4歳くらいでしたかね。
そして今や高校二年生。大きくなったものです。
一応大学進学を目指しているらしく、イヤイヤながらも一応勉強を頑張っているようだ。
以前のように「とりあえず東京の大学行ければどこでもいい」といったザックリしたイメージから、多少具現化しているようですが、まだまだ流動的なようだ。
高校一年生の昨夏に、私と二人で東京→千葉→埼玉とオープンキャンパスをハシゴしてきたわけですが、今となっては「ただ観光してきただけだな」という感が強い。
今年は岐阜、富山、新潟‥と、オープンキャンパスにいく予定だ。
いわゆる「行って満足。行っただけで、なんとなく頑張ってる気になる」というヤツですね。
この点については、奥様の「買っただけで満足」「買っただけで健康になったような痩せたような気になる」という血をひいているのでしょう。
新潟と岐阜はまた私と二人旅。
私はそういう時間が作れるだけでそれなりにシアワセだ。成果がなくても。
反抗期とは無縁。
今も相変わらず私にくっついてくるし、お風呂も一緒に入ることもしばしば。
二人で最近読んだ本の話をする時間は、「あぁ‥いいものだな、ムスメというのは」と思うのだ。
ムスメを迎えに行って「おとーさん、なんか買ってこ」と言われると「しゃなーないな(ニコニコ)」だから、奥様に「甘い!甘すぎる!」と叱られる。
けど、いいのだ。
甘えてくれるうちが華なのだ。
勉強と並行して、とある部活に打ち込んでいる。
高校入った直後は全く異なる別の部活に二つ入部してましたが、その二つを早々に退部して今の部活へ。
充実している様子が伝わってきます。
勉強と部活で「ドラマ見る時間がない!」とプリプリしてますが、オン/オフをうまく使い分けてほしいものだ。
誕生日のプレゼントは「掃除機!」。
コードレスで、可愛くて、けどあまり高くなくて‥ということですが、なかなかピンときたものが見つからない。
未だに探しているところで、もしかしたらこのままプレゼントの話は風化するのでは‥と懸念してしまうほどだ。
誕生日の夕食は「肉くいたい!」ってことで、焼きとり屋へ。
私はビール飲めるし、最高のチョイス。
我が家の4人の中では一番の大食漢。よく食べるのだ。とてもシアワセそうに。
「おとーさん、私もダイエットする」
という言葉を定期的に発し、自然消滅していき、また同じセリフを吐き‥を繰り返しているわけですが、
「少しづつでも毎日続けろ」
と話した腹筋は続いているらしく、
「なーなー、おとーさん、このへん(脇腹)触ってみ。ちょっとくびれとるやろ(このとき全裸)」
「おー、すげー!くびれてるやん!(微々たるもの)」
というちょっぴりの満足感に浸っている。
いいのだ。
ムスメはシアワセそうに食べ、シアワセそうに笑うのが魅力なのだ。
それでいいのだ。
ハッピーバースデイ!ムスメ!
2019年07月19日
オトナの階段登る
まるでヤンチャぼうずがオトナになっていくような‥そんなフクザツな感慨を抱いている人も多いのではないでしょうか。
すっかり中堅の域に達してきた彼らの「今」は‥。
DRAGONFORCE [REACHING INTO INFINITY]

イギリス出身、圧倒的スピード感がウリでデビューした彼らも7作目ですね。
2017年リリース。
ヴォーカルがZPサートからマーク・ハドソンにチェンジして3作目になるでしょうか。
もう折り返し地点が近いわけですね。
あの衝撃のファーストアルバムのリリースが2003年。
「速いだけ」
「ピロピロ(笑)」
「好きなだけツーバス踏んどけ(笑)」
という嘲笑のマトだった彼らですが、そんな彼らが大好きでした。
そしてその疾走感は基本的にブレることなく、それを機軸に多様なベクトルを身につけてきました。
とくにマーク加入後は、その安定&幅広いヴォーカルスタイルが成長するにつれ、その音楽性も幅広くなった感があります。
その「疾走一辺倒」からの脱却が賛否あるところではないでしょうか。
かくいう私も
「あぁ、なんか彼らもオトナになったなぁ」
「いろんなことを器用にこなすようになったなぁ」
「得意のスピードチューンの中にも安定感が光るなぁ」
という感慨深さと、初期のハッチャケ感が希薄になった寂しさとが同居しているここ数作なのです。
圧倒的疾走感があっても、荒々しさよりも落ち着きを感じてしまうというか。
それこそが「成長」なのだろうとは思うのですが。
穏やかひ爪弾かれるイントロから徐々に勇壮に昂っていく「序曲」と言える[Reacing into Infinity]。
そこから導かれるオープニングチューン[Ashes of the Dawn]。
DragonForceらしい疾走感というよりは、正統派ヘヴィメタルチューンと言えるのではないでしょうか。
ややシリアスに展開していく力強さが印象的です。
このあたりも「オトナになったDragonFoce」の新しい魅力でしょうか。
一転、「んもー!ドラフォ節っ!」と言いたくなっていまう[Judgement Day]。
前任のZPサートが抜ける要因になったとかならないとか言われている、圧倒的スピード感に矢継ぎ早に歌詞を乗せてくるスタイル。
ピロピロピロピロピロギューンギューンギューン!という「らしさ」も全開です。
この「躁」感こそがドラゴンフォースの魅力だ。
続く[Astral Empire]もスピードチューン。
これもいわゆるドラフォ節とは若干異なり、ソリッドなキレで勝負している感がある。
スピード感の中にも変化を織りまぜているのだ。
[Curse of Darkness]は、ここ数作で彼らが得意としているタイプの曲。
彼らにしてみればややミディアムな曲調(とはいえ充分速いですが)の中に、ドラマティックな展開を織りまぜる。
こういった曲で「彼ららしいな」と思えるようになっているのが成長の証でしょう。
[Midnight Madness]での「底抜けに明るいスピード感」も初期から彼らの魅力であるタイプの曲。
サビ手前でテンポを落としてくるあたりがグっとくるのです。
そしてボーナストラックとして収録されている、ZIGGYの[GLORIA]。
この出来が秀逸なのだ。
英語と日本語をミックスし、曲の魅力を損なうことなく、彼らの魅力がアドオンされています。
原曲が大好きだから、DRAGONFORCEが大好きだから、という相乗効果があることは差し引いたとしても、実に素晴らしいのです。
ということで、冒頭で「オトナになった」と言っておきながら今さらなのですが、こうして書いているとやっぱり「速い曲が多い」のだ。
やっぱりDragonForceはDragonForceなのだ。
アルバム全体での印象となると「ちょっと丸くなったな」「落ち着いちゃったな」という印象が残るのですが、初期の幻影に踊らされているだけなのだ。
どれだけ叩かれようが、どれだけバカにされようが、自分の信じたサウンドを追い続けている彼ら。
そしていつしかその信念は彼らの旗印として認知されるようになった。
続けるってことは大切なのだ。
DragonForce - Ashes of the Dawn (Official Music Video)
DragonForce - Gloria
すっかり中堅の域に達してきた彼らの「今」は‥。
DRAGONFORCE [REACHING INTO INFINITY]

イギリス出身、圧倒的スピード感がウリでデビューした彼らも7作目ですね。
2017年リリース。
ヴォーカルがZPサートからマーク・ハドソンにチェンジして3作目になるでしょうか。
もう折り返し地点が近いわけですね。
あの衝撃のファーストアルバムのリリースが2003年。
「速いだけ」
「ピロピロ(笑)」
「好きなだけツーバス踏んどけ(笑)」
という嘲笑のマトだった彼らですが、そんな彼らが大好きでした。
そしてその疾走感は基本的にブレることなく、それを機軸に多様なベクトルを身につけてきました。
とくにマーク加入後は、その安定&幅広いヴォーカルスタイルが成長するにつれ、その音楽性も幅広くなった感があります。
その「疾走一辺倒」からの脱却が賛否あるところではないでしょうか。
かくいう私も
「あぁ、なんか彼らもオトナになったなぁ」
「いろんなことを器用にこなすようになったなぁ」
「得意のスピードチューンの中にも安定感が光るなぁ」
という感慨深さと、初期のハッチャケ感が希薄になった寂しさとが同居しているここ数作なのです。
圧倒的疾走感があっても、荒々しさよりも落ち着きを感じてしまうというか。
それこそが「成長」なのだろうとは思うのですが。
穏やかひ爪弾かれるイントロから徐々に勇壮に昂っていく「序曲」と言える[Reacing into Infinity]。
そこから導かれるオープニングチューン[Ashes of the Dawn]。
DragonForceらしい疾走感というよりは、正統派ヘヴィメタルチューンと言えるのではないでしょうか。
ややシリアスに展開していく力強さが印象的です。
このあたりも「オトナになったDragonFoce」の新しい魅力でしょうか。
一転、「んもー!ドラフォ節っ!」と言いたくなっていまう[Judgement Day]。
前任のZPサートが抜ける要因になったとかならないとか言われている、圧倒的スピード感に矢継ぎ早に歌詞を乗せてくるスタイル。
ピロピロピロピロピロギューンギューンギューン!という「らしさ」も全開です。
この「躁」感こそがドラゴンフォースの魅力だ。
続く[Astral Empire]もスピードチューン。
これもいわゆるドラフォ節とは若干異なり、ソリッドなキレで勝負している感がある。
スピード感の中にも変化を織りまぜているのだ。
[Curse of Darkness]は、ここ数作で彼らが得意としているタイプの曲。
彼らにしてみればややミディアムな曲調(とはいえ充分速いですが)の中に、ドラマティックな展開を織りまぜる。
こういった曲で「彼ららしいな」と思えるようになっているのが成長の証でしょう。
[Midnight Madness]での「底抜けに明るいスピード感」も初期から彼らの魅力であるタイプの曲。
サビ手前でテンポを落としてくるあたりがグっとくるのです。
そしてボーナストラックとして収録されている、ZIGGYの[GLORIA]。
この出来が秀逸なのだ。
英語と日本語をミックスし、曲の魅力を損なうことなく、彼らの魅力がアドオンされています。
原曲が大好きだから、DRAGONFORCEが大好きだから、という相乗効果があることは差し引いたとしても、実に素晴らしいのです。
ということで、冒頭で「オトナになった」と言っておきながら今さらなのですが、こうして書いているとやっぱり「速い曲が多い」のだ。
やっぱりDragonForceはDragonForceなのだ。
アルバム全体での印象となると「ちょっと丸くなったな」「落ち着いちゃったな」という印象が残るのですが、初期の幻影に踊らされているだけなのだ。
どれだけ叩かれようが、どれだけバカにされようが、自分の信じたサウンドを追い続けている彼ら。
そしていつしかその信念は彼らの旗印として認知されるようになった。
続けるってことは大切なのだ。
DragonForce - Ashes of the Dawn (Official Music Video)
DragonForce - Gloria