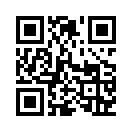ヘビメタパパの書斎 › 2016年11月
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2016年11月30日
不死鳥、舞う
ありがちなタイトルだな‥と思った。
そして、「まぁ、以前のレベルを期待しちゃいけないだろうな」と、自らハードルを下げてたこともあった。
そんな失礼なスタンスでCDをトレイに乗せて‥驚いた。
まさに不死鳥だ。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING

このブログをご覧いただいてる方なら、ときどき目にするバンド名だと思います。
Wikiによると、結成は2007年。もうすぐ10年ですね。
メジャーからリリースされたアルバムは4枚。
そして、このアルバムはミニアルバムとなっています。
私が摩天楼オペラと出会ったのは、2ndアルバムリリース前。
何がキッカケだったか覚えてないのですが、フと聞くことになった[GLORIA]は衝撃だった。
和製RHAPSODYだ。
和製[Emerald Sword]だ。
一気に虜になった。
さらに[Innovational Symphonia]。
そして、「グロリア三部作」(と、勝手に呼んでいる)のラストとなる「喝采と激情のグロリア」。
全てが素晴らしく、全てが劇的だった。
見た目はいかにもヴィジュアル系。
ヴォーカルの歌い回しやビブラートもヴィジュアル系。
耽美的世界観もヴィジュアル系。
だから、洋楽指向のメタルファンにとっては嫌悪感を抱かれるかもしれない。
が、ワタシは元々、X、D'ERLANGER、ZI:KILLといったところを聞いてきた土壌があるからか、全く違和感がない。
だから、ヴィジュアル系に寄っているサウンドでも、メタル的素晴らしさがあればスムーズに咀嚼できる。
摩天楼オペラは、まさにその典型だ。
ヴィジュアル系でありながら、サウンドはメタル指向。
バンド名の由来であり、コンセプトでもある「現代的なものと伝統美の融合」。
それは、メタルとヴィジュアル系の融合でもある。
そんな彼らだが、上述したようた突出した名曲たちがあるのに対して、アルバム全体で見ると曲単位でクオリティの差がある気がしていた。
歌詞も含めて、「もう少し全体的に底上げできればなぁ」という感があった。
そんな中。
ギターのAnziが脱退。
Anziは、国内のメロパワシーンでは伝説とも言えるMasterpieceのメンバーだった。
そのAnziが抜けた影響は大きいだろうな、と思った。
その想いが、冒頭の印象の一部に繋がっていることもあった。
が。
素晴らしいのだ。
ヴィジュアルもシンプルに、黒を基調としたメンバー写真に。
より一層、メタル寄りになってきた感があります。
前作の[BURNING SOUL]でもメタル色を意図的に強めてきた感がありましたが、若干無理してるムードを感じた。
今回はそれを感じない。
まさに不死鳥が羽ばたくかのような、自然かつ力みのない、大きなスケールアップを見せてくれています。
オープニングを飾るイントロダクションとなる[THE RISING]。
Xの名作[BLUE BLOOD]に於ける[PROLOGUE (WORLD ANTHEM)]のような雄大な世界観を魅せてくれます。
そして、シンフォニックかつ強靱な疾走感を伴って[PHOENIX]へ!
以前は「和製RHAPSODYのよう」と表現しましたが、これはまるで和製SONATA ARCTICA。
いや、SONATA ARCTICA的な疾走感に、さらに摩天楼オペラならではの、そしていい意味でのヴィジュアル系的なゴージャスな装飾。
この装飾がさらに荘厳さを印象づけます。
生きる意味。
大地や地球への賛美。
感謝。
希望。
歌詞も実に魅力的。
以前の「グロリア三部作」、そしてその後のアルバムを経て、「あー、やっぱりあの頃がピークだったか」という想いを覆す、まさに起死回生の一曲。
そして後半に配置された[MASK]も魅力的。
リフの刻み方、キーボードの追随は、これまたSONATA ARCTICAの名曲[Abandoned, Pleased, Brainwashed, Exploited]を思い出します。
この曲でも[PHOENIX]でも、サビでの展開、そしてラストに向けてのリズムチェンジ‥このあたりのテクニカルなところも摩天楼オペラの魅力です。
「何十年先も今日みたいに」は、ラストを締めくくるにふさわしい、穏やかで美しく、スケールの大きなパワーバラード。
聞き終えた後の心地よさを演出してくれます。
:
:
:
BABYMETALだけでなく、ヴィジュアル系のバンドも、メタルファンには受け入れられづらいことは分かっている。
どのあたりが、そのハードルになっているかも分かる。
が、これまたBABYMETALのときにも書いたかもしれないけど、メタルかどうかなんて境界線は必要ない。
もし、そういう先入観だけで敬遠しているのであれば、一度は触れてみてほしい。
そして、敬遠するのはそのあとでもいい。
個人的には、毎年LOUDPARKへの参戦を楽しみにしているバンド。
このミニアルバムで、またその扉への距離は縮まったと感じます。
下記に貼るアルバムトレイラーには
「自分の愛した音楽、バンドが愛した音楽、ファンが愛してくれた音楽‥それはきっとこんな音」
という言葉が綴られています。
この言葉が、現在のバンドのモチベーションを物語ってくれています。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING [全曲試聴]
全曲ブツ切りになってるのが勿体ない、全ての魅力は伝えられないのが残念ですが、雰囲気だけでも。
GLORIA/摩天楼オペラ
2012年リリース。サビの高揚感は、まさに和製[Emerald Sword]。
そして、「まぁ、以前のレベルを期待しちゃいけないだろうな」と、自らハードルを下げてたこともあった。
そんな失礼なスタンスでCDをトレイに乗せて‥驚いた。
まさに不死鳥だ。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING

このブログをご覧いただいてる方なら、ときどき目にするバンド名だと思います。
Wikiによると、結成は2007年。もうすぐ10年ですね。
メジャーからリリースされたアルバムは4枚。
そして、このアルバムはミニアルバムとなっています。
私が摩天楼オペラと出会ったのは、2ndアルバムリリース前。
何がキッカケだったか覚えてないのですが、フと聞くことになった[GLORIA]は衝撃だった。
和製RHAPSODYだ。
和製[Emerald Sword]だ。
一気に虜になった。
さらに[Innovational Symphonia]。
そして、「グロリア三部作」(と、勝手に呼んでいる)のラストとなる「喝采と激情のグロリア」。
全てが素晴らしく、全てが劇的だった。
見た目はいかにもヴィジュアル系。
ヴォーカルの歌い回しやビブラートもヴィジュアル系。
耽美的世界観もヴィジュアル系。
だから、洋楽指向のメタルファンにとっては嫌悪感を抱かれるかもしれない。
が、ワタシは元々、X、D'ERLANGER、ZI:KILLといったところを聞いてきた土壌があるからか、全く違和感がない。
だから、ヴィジュアル系に寄っているサウンドでも、メタル的素晴らしさがあればスムーズに咀嚼できる。
摩天楼オペラは、まさにその典型だ。
ヴィジュアル系でありながら、サウンドはメタル指向。
バンド名の由来であり、コンセプトでもある「現代的なものと伝統美の融合」。
それは、メタルとヴィジュアル系の融合でもある。
そんな彼らだが、上述したようた突出した名曲たちがあるのに対して、アルバム全体で見ると曲単位でクオリティの差がある気がしていた。
歌詞も含めて、「もう少し全体的に底上げできればなぁ」という感があった。
そんな中。
ギターのAnziが脱退。
Anziは、国内のメロパワシーンでは伝説とも言えるMasterpieceのメンバーだった。
そのAnziが抜けた影響は大きいだろうな、と思った。
その想いが、冒頭の印象の一部に繋がっていることもあった。
が。
素晴らしいのだ。
ヴィジュアルもシンプルに、黒を基調としたメンバー写真に。
より一層、メタル寄りになってきた感があります。
前作の[BURNING SOUL]でもメタル色を意図的に強めてきた感がありましたが、若干無理してるムードを感じた。
今回はそれを感じない。
まさに不死鳥が羽ばたくかのような、自然かつ力みのない、大きなスケールアップを見せてくれています。
オープニングを飾るイントロダクションとなる[THE RISING]。
Xの名作[BLUE BLOOD]に於ける[PROLOGUE (WORLD ANTHEM)]のような雄大な世界観を魅せてくれます。
そして、シンフォニックかつ強靱な疾走感を伴って[PHOENIX]へ!
以前は「和製RHAPSODYのよう」と表現しましたが、これはまるで和製SONATA ARCTICA。
いや、SONATA ARCTICA的な疾走感に、さらに摩天楼オペラならではの、そしていい意味でのヴィジュアル系的なゴージャスな装飾。
この装飾がさらに荘厳さを印象づけます。
生きる意味。
大地や地球への賛美。
感謝。
希望。
歌詞も実に魅力的。
以前の「グロリア三部作」、そしてその後のアルバムを経て、「あー、やっぱりあの頃がピークだったか」という想いを覆す、まさに起死回生の一曲。
そして後半に配置された[MASK]も魅力的。
リフの刻み方、キーボードの追随は、これまたSONATA ARCTICAの名曲[Abandoned, Pleased, Brainwashed, Exploited]を思い出します。
この曲でも[PHOENIX]でも、サビでの展開、そしてラストに向けてのリズムチェンジ‥このあたりのテクニカルなところも摩天楼オペラの魅力です。
「何十年先も今日みたいに」は、ラストを締めくくるにふさわしい、穏やかで美しく、スケールの大きなパワーバラード。
聞き終えた後の心地よさを演出してくれます。
:
:
:
BABYMETALだけでなく、ヴィジュアル系のバンドも、メタルファンには受け入れられづらいことは分かっている。
どのあたりが、そのハードルになっているかも分かる。
が、これまたBABYMETALのときにも書いたかもしれないけど、メタルかどうかなんて境界線は必要ない。
もし、そういう先入観だけで敬遠しているのであれば、一度は触れてみてほしい。
そして、敬遠するのはそのあとでもいい。
個人的には、毎年LOUDPARKへの参戦を楽しみにしているバンド。
このミニアルバムで、またその扉への距離は縮まったと感じます。
下記に貼るアルバムトレイラーには
「自分の愛した音楽、バンドが愛した音楽、ファンが愛してくれた音楽‥それはきっとこんな音」
という言葉が綴られています。
この言葉が、現在のバンドのモチベーションを物語ってくれています。
摩天楼オペラ / PHOENIX RISING [全曲試聴]
全曲ブツ切りになってるのが勿体ない、全ての魅力は伝えられないのが残念ですが、雰囲気だけでも。
GLORIA/摩天楼オペラ
2012年リリース。サビの高揚感は、まさに和製[Emerald Sword]。
2016年11月17日
奇跡か、必然か。
まさか!でもある。
ついにこの日が‥とも思える。
こういう時期に来ちゃってるのか‥とも思える。
これは書かずにいられない。
ジャーマンメタルの礎を築いたハロウィンに、マイケル・キスクとカイ・ハンセンが期間限定で復帰。
ワールドツアーを行うと発表されました。

ビクターからのリリース(メンバー訳あり)
「カイ・ハンセン&マイケル・キスクが電撃復帰!総勢7人のメンバーでワールド・ツアー!」
http://www.jvcmusic.co.jp/-/Information/A016944.html?article=news30#news30
HELLOWEEN - PUMPKINS UNITED World Tour 2017 / 2018
この動画を見て、血湧き肉躍る人も多いと思う。(私です)
この動画を見て、涙腺が崩壊しちゃう人も多いと思う。(私です)
この動画を見て、今までの紆余曲折を噛みしめる人も多いと思う。(私です)
ボロボロになって離散したメンバーが再び集う。
まさに「再生」の結末を目に焼き付けることのできる場となりそうです。
感情的なわだかまりが消えたわけではないと思う。
それを「オトナの事情」と推測するのは簡単ですが、よく実現を決断してくれたなと思います。
このブログをご覧になっている方ならご存じの方も多いかと思いますが‥
ワタシがメタルに目覚めたキッカケはHELLOWEENとTNTでした。
Xに代表されるジャパニーズメタルを聞いていたときに、フと借りたCD。
それが[Live in the U.K.]でした。
‥鳥肌が立った。一聴しただけで「これがホンモノだったんだ‥」と奈落の底に落ちていくような錯覚を覚えました。
今まで聞いてきたジャパニーズメタルは何だったんだ、と。
(今では、ジャパニーズメタルはジャパニーズメタルとして大好きですが)
そしてHELLOWEENを聴き漁り出した直後にカイ・ハンセンは脱退。
その後、インゴ・シュヴィヒテンバーグの悲劇、マイケル・キスクの脱退‥と、バンドはボロボロになっていきました。
ホント、痛々しいほどだったんだよ‥大好きだったからこそ。
そして、マイケル・キスクの後任は、まさかのPINKCREAM69のアンディ・デリス。
そして、そのアンディを迎えたアルバムが、まさかの奇跡的化学反応。
HELLOWEENは見事に再生の道を歩み、今では「アンディ・デリスこそがハロウィン」というファンも多いでしょう。
‥そりゃ、アンディ加入時に生まれた子供が成人式を越えてますからね。
かたやカイ・ハンセンは、GAMMA RAYを率いて、アンディ・デリスの加入によりワイドに、横へ横へと視野を広げた音楽性となったHELLOWEENに相反するかのように、彼の信じるスタイルで「縦」へと掘り下げていきました。
カイはずっとカイだった。
そして、一時メタル界から離れたマイケル・キスク。
PLACE VENDOMEでの「ややメタルっぽい音」も含んだ穏やかなハードロックへの参加。
このバンドが、アンディ・デリスが在籍していたPINKCREAM69のメンバーが主体だったのも皮肉であり運命的。
さらにAVANTASIAでの「キスケといえば、この音」への帰還。
ハロウィン大好きで、彼らの音で育ったEDGUYのトビアス・サメットが「マイケル・キスクに歌ってもらうために書いた」曲。
そしてまず、UNISONICでカイ・ハンセンとマイケル・キスクが手を組んだ。
この二人は元々仲良しだったから、マイケル・キスクが「ジャーマンメタル」を受け入れさえすれば叶うはずだった「必然」だと思う。
この「必然」を実現したのも、PINKCREAM69のデニス・ワード。
そして、それぞれのメンバー、それぞれのバンドが正常化し、健全なバンド活動を行う中で、精神的な余裕ができたのではないでしょうか。
(オトナの事情は勘繰らないことにしましょう)
:
:
:
と、思い出や思い入れはこのあたりにしておいて。
そんなずっとHELLOWEENが大好きなワタシの率直な感想は
「‥うーん、あんまり意味ない気がするんだけどな」というものでした。
思い入れのある時代を築いてきてくれたカイ・ハンセンとマイケル・キスクの時代は、LOUDPARK11での劇的&感傷的なUNISONICのステージを見て吹っ切れた。
そして、今のアンディ・デリスのHELLOWEENも、過去とは異なる魅力で「今は今で充分に素晴らしい」と思える。
それが今、改めて集い、改めて交わる必要性があるのか。
そう思いました。
が。
冒頭の動画を見て、「‥ズルいな、この動画」とウルウルしたことも事実です。
ワタシがこのHELLOWEENのツアーに期待すること、そして焦点は二つだ。
一つ目は、アンディ・デリスが、アンディの時代の曲だけを歌ってくれること。
これはワタシがずっと望んできて、何度もこのブログに書いているかもしれない。
アンディ・デリス時代のHELLOWEENは素晴らしいのだ。
もちろん、過去のHELLOWEENの魅力が色褪せることがないのですが、もうその時代を引きずる必要はないのだ。
けど、HELLOWEENのライブといえば、[EAGLE FLY FREE]や[I WANT OUT]が外せないということも理解できる。
このツアーだからこそ、もう KEEPER OF THE SEVEN KEYS の幻影を切り離して、アンディの歌が生きるセットリストを見たいのだ。
そして二つ目は、名曲[HOW MANY TEARS]を、カイ・ハンセンのヴォーカルで披露してくれること。
カイの歌声は、元々評価が低い。
そして、昨年のLOUDPARKでは体調不良もあって声が出ず、その後、GAMMA RAYはツインヴォーカル体制となった。
そんな状況だから、「HOW MANY TEARSはもちろん演るよな。もちろん、マイケル・キスクで」という声が多いことも理解できる。
冒頭に触れた[Live In The U.K]での素晴らしさがあっての、今のワタシでもあるのだ。
けど、ワタシはこの曲はオリジナルのカイ・ハンセンのバージョンが好きだ。
あの曲の、荒々しさと美しさのバランスを取るには、やはりカイなのだ。
マイケル・キスクでは美しすぎて、本来の魅力である「ギリギリの危うさ」が半減する。
当時のようにカイが歌えないことは分かっている。
そこはファンがカバーできる。
マイケル・キスク加入前の時代も、今の姿で映し出してほしい。
そのためには、歌えようが歌えまいがカイがフロントマンであってほしい。
個人的には、アンディ・デリスとマイケル・キスクが共演&競演するような場面は必要性を感じない。
カイ時代、キスケ時代、アンディ時代。
ワタシが大好きな全ての時代を、ノスタルジックにステージで表現してくれればいい。
懐古主義と言われても、このツアーはそれが許される、そして、それを期待して集まるファンが多いと思うから。
ツアーは2017年から2018年。
これから一年間、様々な想いでその日を楽しみに待ちたいと思います。
ついにこの日が‥とも思える。
こういう時期に来ちゃってるのか‥とも思える。
これは書かずにいられない。
ジャーマンメタルの礎を築いたハロウィンに、マイケル・キスクとカイ・ハンセンが期間限定で復帰。
ワールドツアーを行うと発表されました。
ビクターからのリリース(メンバー訳あり)
「カイ・ハンセン&マイケル・キスクが電撃復帰!総勢7人のメンバーでワールド・ツアー!」
http://www.jvcmusic.co.jp/-/Information/A016944.html?article=news30#news30
HELLOWEEN - PUMPKINS UNITED World Tour 2017 / 2018
この動画を見て、血湧き肉躍る人も多いと思う。(私です)
この動画を見て、涙腺が崩壊しちゃう人も多いと思う。(私です)
この動画を見て、今までの紆余曲折を噛みしめる人も多いと思う。(私です)
ボロボロになって離散したメンバーが再び集う。
まさに「再生」の結末を目に焼き付けることのできる場となりそうです。
感情的なわだかまりが消えたわけではないと思う。
それを「オトナの事情」と推測するのは簡単ですが、よく実現を決断してくれたなと思います。
このブログをご覧になっている方ならご存じの方も多いかと思いますが‥
ワタシがメタルに目覚めたキッカケはHELLOWEENとTNTでした。
Xに代表されるジャパニーズメタルを聞いていたときに、フと借りたCD。
それが[Live in the U.K.]でした。
‥鳥肌が立った。一聴しただけで「これがホンモノだったんだ‥」と奈落の底に落ちていくような錯覚を覚えました。
今まで聞いてきたジャパニーズメタルは何だったんだ、と。
(今では、ジャパニーズメタルはジャパニーズメタルとして大好きですが)
そしてHELLOWEENを聴き漁り出した直後にカイ・ハンセンは脱退。
その後、インゴ・シュヴィヒテンバーグの悲劇、マイケル・キスクの脱退‥と、バンドはボロボロになっていきました。
ホント、痛々しいほどだったんだよ‥大好きだったからこそ。
そして、マイケル・キスクの後任は、まさかのPINKCREAM69のアンディ・デリス。
そして、そのアンディを迎えたアルバムが、まさかの奇跡的化学反応。
HELLOWEENは見事に再生の道を歩み、今では「アンディ・デリスこそがハロウィン」というファンも多いでしょう。
‥そりゃ、アンディ加入時に生まれた子供が成人式を越えてますからね。
かたやカイ・ハンセンは、GAMMA RAYを率いて、アンディ・デリスの加入によりワイドに、横へ横へと視野を広げた音楽性となったHELLOWEENに相反するかのように、彼の信じるスタイルで「縦」へと掘り下げていきました。
カイはずっとカイだった。
そして、一時メタル界から離れたマイケル・キスク。
PLACE VENDOMEでの「ややメタルっぽい音」も含んだ穏やかなハードロックへの参加。
このバンドが、アンディ・デリスが在籍していたPINKCREAM69のメンバーが主体だったのも皮肉であり運命的。
さらにAVANTASIAでの「キスケといえば、この音」への帰還。
ハロウィン大好きで、彼らの音で育ったEDGUYのトビアス・サメットが「マイケル・キスクに歌ってもらうために書いた」曲。
そしてまず、UNISONICでカイ・ハンセンとマイケル・キスクが手を組んだ。
この二人は元々仲良しだったから、マイケル・キスクが「ジャーマンメタル」を受け入れさえすれば叶うはずだった「必然」だと思う。
この「必然」を実現したのも、PINKCREAM69のデニス・ワード。
そして、それぞれのメンバー、それぞれのバンドが正常化し、健全なバンド活動を行う中で、精神的な余裕ができたのではないでしょうか。
(オトナの事情は勘繰らないことにしましょう)
:
:
:
と、思い出や思い入れはこのあたりにしておいて。
そんなずっとHELLOWEENが大好きなワタシの率直な感想は
「‥うーん、あんまり意味ない気がするんだけどな」というものでした。
思い入れのある時代を築いてきてくれたカイ・ハンセンとマイケル・キスクの時代は、LOUDPARK11での劇的&感傷的なUNISONICのステージを見て吹っ切れた。
そして、今のアンディ・デリスのHELLOWEENも、過去とは異なる魅力で「今は今で充分に素晴らしい」と思える。
それが今、改めて集い、改めて交わる必要性があるのか。
そう思いました。
が。
冒頭の動画を見て、「‥ズルいな、この動画」とウルウルしたことも事実です。
ワタシがこのHELLOWEENのツアーに期待すること、そして焦点は二つだ。
一つ目は、アンディ・デリスが、アンディの時代の曲だけを歌ってくれること。
これはワタシがずっと望んできて、何度もこのブログに書いているかもしれない。
アンディ・デリス時代のHELLOWEENは素晴らしいのだ。
もちろん、過去のHELLOWEENの魅力が色褪せることがないのですが、もうその時代を引きずる必要はないのだ。
けど、HELLOWEENのライブといえば、[EAGLE FLY FREE]や[I WANT OUT]が外せないということも理解できる。
このツアーだからこそ、もう KEEPER OF THE SEVEN KEYS の幻影を切り離して、アンディの歌が生きるセットリストを見たいのだ。
そして二つ目は、名曲[HOW MANY TEARS]を、カイ・ハンセンのヴォーカルで披露してくれること。
カイの歌声は、元々評価が低い。
そして、昨年のLOUDPARKでは体調不良もあって声が出ず、その後、GAMMA RAYはツインヴォーカル体制となった。
そんな状況だから、「HOW MANY TEARSはもちろん演るよな。もちろん、マイケル・キスクで」という声が多いことも理解できる。
冒頭に触れた[Live In The U.K]での素晴らしさがあっての、今のワタシでもあるのだ。
けど、ワタシはこの曲はオリジナルのカイ・ハンセンのバージョンが好きだ。
あの曲の、荒々しさと美しさのバランスを取るには、やはりカイなのだ。
マイケル・キスクでは美しすぎて、本来の魅力である「ギリギリの危うさ」が半減する。
当時のようにカイが歌えないことは分かっている。
そこはファンがカバーできる。
マイケル・キスク加入前の時代も、今の姿で映し出してほしい。
そのためには、歌えようが歌えまいがカイがフロントマンであってほしい。
個人的には、アンディ・デリスとマイケル・キスクが共演&競演するような場面は必要性を感じない。
カイ時代、キスケ時代、アンディ時代。
ワタシが大好きな全ての時代を、ノスタルジックにステージで表現してくれればいい。
懐古主義と言われても、このツアーはそれが許される、そして、それを期待して集まるファンが多いと思うから。
ツアーは2017年から2018年。
これから一年間、様々な想いでその日を楽しみに待ちたいと思います。
2016年11月15日
ワースト、再考
彼らがLOUDPARKの舞台に立ったのは2012年だったでしょうか。
例年、LOUDPARK終了後に「ベストアクト」「ワーストアクト」といった感想が飛び交うわけですが、残念ながら彼らのパフォーマンスは「ワーストアクト」がいつのまにか「ワーストソナタ」に置換されていたほど。
そして、今年になってドン・ドッケンによって「ワーストドン」となり、ようやくその足枷(?)が外れたようです。
ちょうどその頃のアルバムになりますね。
SONATA ARCTICA / STONES GROW HER NAME

リリースは2012年。アルバムとしては7枚目ですね。
このアルバム、正直、あまり聞いてなかった。
けど、「ワーストドン」を目にして、「そういえば、ソナタアークティカもワーストソナタとかってずっとネタにされてたなー」と思い出しました。
そして久しぶりに手にとってみました。
SONATA ARCTICAといえば、1stの衝撃でしょう。
若さゆえの無尽蔵なエナジーで構築された爆発的疾走感と北欧ならでは煌き、そしてその青臭さ。
青臭いだけでなく、洗練されたメロディセンス。
1stにして既に「SONATA ARCITICAとは何か」を強烈に刻み込んだ楽曲たち。
思えば、その後の彼らの方向性に対しての評価は、この時点でこのアルバムと対峙しつづける運命を決められてしまったのかもしれません。
着実にステップアップした2nd。
彼らの個性とチャレンジが絶妙に絡み合った3rd。
ステップアップした4th。
このあたりまでは「らしさ」(日本人が彼らに思い描く「らしさ」)が残っていた。
その後、彼らはその個性を過去の異物として新しい方向性を模索した。
そして問題作といわれる[Unia]。
このアルバムがファンにとっての分水嶺だったでしょうか。
そして、その延長線上にあるといっていいでしょうか、このアルバム、上述のLOUDPARKのステージでも感じたことですが、実に北欧らしく、深みがあるのだ。
そしてトニー・カッコのヴォーカルも、初期の青臭さからは脱皮し、魅力的な声へとステップアップしている。
バッキングの装飾も派手になりすぎず、それでいてアクセントとしては輝きを放つ。
全体的には、繊細な光が絡み合って立体的に構築されているかのような。
危ういバランスのようで、実は綿密に組み立てられていて安心感を抱く。
そんな不可思議な印象のアルバムです。
オープニングはミディアムテンポの[ONLY THE BROKEN HEARTS]。
ザラっとしたリフに続いて爪弾かれるキーボードの音色に彼ららしさを感じながらも、本能的に「一曲目がコレか‥」と思ってしまいます。
SONATA ARCTICA = キラキラとした疾走感、という刷り込まれた記憶は、簡単には覆せない。
が、今改めて聞くと、穏やかで良質なメロディックハードロックだ。
彼らにそれを求めるかどうかは別にして。
[SHITLOAD OF MONEY]のメロディも悪くない。リズム感も独特だ。
美しいキーボードの音色に導かれ、アップテンポに展開していく[LOSING MY INSANITY]は、以前の面影を感じさせつつ、大人になったSONATA ARCTICAの姿を映しだします。
[CINDERBLOX]ではウエスタン調のギターに違和感と不思議な心地よさを感じつつ、朗らかに疾走感していくメロディは、今までとは異なる魅力。
その違和感の中でも、やはりポジティブに疾走していくメロディはSONATA ARCTICAに求めている魅力のひとつ。
そういう意味ではこのアルバムの中では存在感を放ちます。
ラストを飾る組曲形式(?)の2曲は、彼らの懐の深さを感じさせる、複雑でテクニカルな曲。
以前の単調さ(←コレが魅力でもあったわけですが)が若気の至りだったかのような成長を感じさせます。
このアルバムを引っさげてのLOUDPARKでのステージングについては、そのときの感想にも書きましたが‥
成長した彼らの安定したパフォーマンス、幻想的なムードに彩られたステージング‥
思い入れを一切排除すれば、充分に魅力的なものだったと思います。
が、彼らのライブで求めるものではなかった。
今年のSYMPHONY Xで感じましたが、「いくら音楽性を変えようが、ライブで印象深い曲をチョイスしてくれれば盛り上がる」のは当然。
ワーストソナタ、と揶揄されたライブでは、それが圧倒的に足りなかった。
幻想的で落ち着きのあるステージングを、ファンは求めていなかった。
このアルバムも、そのあたりの思い入れによって評価は分かれるでしょう。
と、冷静に書いている私自身がそうだった。
数年経過し、今現在の彼らの姿を受け入れられるようになって(←今でも昔の音のほうが好きだけど)、改めて聞くと魅力は溢れている。
LOUDPARKで「ワーストソナタ」を体感した人にこそ、今、改めて聞いてみてほしい。
「・・ん?悪くないじゃんか。」と思えるのではないでしょうか。
が、「やっぱり、ライブでこのアルバム中心ではダメだな」と再認識するかもしれませんが。
Sonata Arctica Cinderblox Live in Wacken 2013
例年、LOUDPARK終了後に「ベストアクト」「ワーストアクト」といった感想が飛び交うわけですが、残念ながら彼らのパフォーマンスは「ワーストアクト」がいつのまにか「ワーストソナタ」に置換されていたほど。
そして、今年になってドン・ドッケンによって「ワーストドン」となり、ようやくその足枷(?)が外れたようです。
ちょうどその頃のアルバムになりますね。
SONATA ARCTICA / STONES GROW HER NAME

リリースは2012年。アルバムとしては7枚目ですね。
このアルバム、正直、あまり聞いてなかった。
けど、「ワーストドン」を目にして、「そういえば、ソナタアークティカもワーストソナタとかってずっとネタにされてたなー」と思い出しました。
そして久しぶりに手にとってみました。
SONATA ARCTICAといえば、1stの衝撃でしょう。
若さゆえの無尽蔵なエナジーで構築された爆発的疾走感と北欧ならでは煌き、そしてその青臭さ。
青臭いだけでなく、洗練されたメロディセンス。
1stにして既に「SONATA ARCITICAとは何か」を強烈に刻み込んだ楽曲たち。
思えば、その後の彼らの方向性に対しての評価は、この時点でこのアルバムと対峙しつづける運命を決められてしまったのかもしれません。
着実にステップアップした2nd。
彼らの個性とチャレンジが絶妙に絡み合った3rd。
ステップアップした4th。
このあたりまでは「らしさ」(日本人が彼らに思い描く「らしさ」)が残っていた。
その後、彼らはその個性を過去の異物として新しい方向性を模索した。
そして問題作といわれる[Unia]。
このアルバムがファンにとっての分水嶺だったでしょうか。
そして、その延長線上にあるといっていいでしょうか、このアルバム、上述のLOUDPARKのステージでも感じたことですが、実に北欧らしく、深みがあるのだ。
そしてトニー・カッコのヴォーカルも、初期の青臭さからは脱皮し、魅力的な声へとステップアップしている。
バッキングの装飾も派手になりすぎず、それでいてアクセントとしては輝きを放つ。
全体的には、繊細な光が絡み合って立体的に構築されているかのような。
危ういバランスのようで、実は綿密に組み立てられていて安心感を抱く。
そんな不可思議な印象のアルバムです。
オープニングはミディアムテンポの[ONLY THE BROKEN HEARTS]。
ザラっとしたリフに続いて爪弾かれるキーボードの音色に彼ららしさを感じながらも、本能的に「一曲目がコレか‥」と思ってしまいます。
SONATA ARCTICA = キラキラとした疾走感、という刷り込まれた記憶は、簡単には覆せない。
が、今改めて聞くと、穏やかで良質なメロディックハードロックだ。
彼らにそれを求めるかどうかは別にして。
[SHITLOAD OF MONEY]のメロディも悪くない。リズム感も独特だ。
美しいキーボードの音色に導かれ、アップテンポに展開していく[LOSING MY INSANITY]は、以前の面影を感じさせつつ、大人になったSONATA ARCTICAの姿を映しだします。
[CINDERBLOX]ではウエスタン調のギターに違和感と不思議な心地よさを感じつつ、朗らかに疾走感していくメロディは、今までとは異なる魅力。
その違和感の中でも、やはりポジティブに疾走していくメロディはSONATA ARCTICAに求めている魅力のひとつ。
そういう意味ではこのアルバムの中では存在感を放ちます。
ラストを飾る組曲形式(?)の2曲は、彼らの懐の深さを感じさせる、複雑でテクニカルな曲。
以前の単調さ(←コレが魅力でもあったわけですが)が若気の至りだったかのような成長を感じさせます。
このアルバムを引っさげてのLOUDPARKでのステージングについては、そのときの感想にも書きましたが‥
成長した彼らの安定したパフォーマンス、幻想的なムードに彩られたステージング‥
思い入れを一切排除すれば、充分に魅力的なものだったと思います。
が、彼らのライブで求めるものではなかった。
今年のSYMPHONY Xで感じましたが、「いくら音楽性を変えようが、ライブで印象深い曲をチョイスしてくれれば盛り上がる」のは当然。
ワーストソナタ、と揶揄されたライブでは、それが圧倒的に足りなかった。
幻想的で落ち着きのあるステージングを、ファンは求めていなかった。
このアルバムも、そのあたりの思い入れによって評価は分かれるでしょう。
と、冷静に書いている私自身がそうだった。
数年経過し、今現在の彼らの姿を受け入れられるようになって(←今でも昔の音のほうが好きだけど)、改めて聞くと魅力は溢れている。
LOUDPARKで「ワーストソナタ」を体感した人にこそ、今、改めて聞いてみてほしい。
「・・ん?悪くないじゃんか。」と思えるのではないでしょうか。
が、「やっぱり、ライブでこのアルバム中心ではダメだな」と再認識するかもしれませんが。
Sonata Arctica Cinderblox Live in Wacken 2013
2016年11月08日
ようこそ!
今、国内屈指の女性ヴォーカリストだと思います。
が、前バンドは「さぁ、これから」というところで瓦解してしまった。
そして、新たな船出となるアルバムです。
Fuki Commune / Welcome!

元、LIGHT BRINGERのFUKIちゃんとして。
現、Unlucky Morpheusの天外冬黄として。
時にメタルアーティストとして。
時に同人音楽アーティストとして。
時にアニソンヴォーカリストとして。
様々な顔を持つ女性ヴォーカリストである彼女のソロプロジェクトのアルバムです。
ワタシが彼女の存在を知ったのは、Dragon GuardianのDRAGONVARIUSというアルバム。
元々、同人のメロディックスピードメタルプロジェクトだったDragonGuardianは、このアルバムでFUKIちゃんを迎えたことで一気に花開きました。
メジャー感を纏い、大きくステップアップしました。
このアルバムでのFUKIちゃんの力強くキュートな声はインパクト充分でした。
その後、彼女が参加しているLIGHT BRINGERを知り、いまや伝説とも言える、東京キネマ倶楽部でのDragonGuardian / MinstreliX / LightBringerのライブに参戦。
ナマで見る彼女を見て「・・やっぱりすげぇ!」と確信、惚れ込みました。
そしてLightBringerも素晴らしいアルバムをリリース。
FUKIちゃんの魅力が堪能できるキャッチーな曲が粒揃い。まさに「これからだな!」というところでの活動休止。
Unlucky Morpheusも悪くないのですが、やはりLightBringerと比べるとやや魅力に劣る感があり、「FUKIちゃん、どうなるんだよ‥これだけの才能を埋もれさせるなよ‥」と思ってました。
そんな中、リリースされた「FUKI」の名を冠に据えたプロジェクトのアルバムです。
全体的には、上述した彼女の魅力が満遍なく散りばめられている印象です。
LightBringerやDragonGuardianのような、ひとつのコンセプトで統一されているというアルバムとは異なります。
彼女の声は快活であり、実にカラフルだ。
キュートな声色。
パワフルな声色。
キャッチーな声色。
シリアスな声色。
曲によって様々な表情を魅せてくれます。
そして、どの曲でも強い芯を持ち、彼女の周辺に乱反射するようなキラキラとした華やかさを持っています。
この華やかさはFUKIちゃんならでは。
若干、近未来的&ヘヴィな装いのイントロで「・・お?」と身構えてしまいますが‥
LightBringer時代を思い出させるキャッチーなメタルチューン[月が満ちる前に]で「これだよ!」と安堵を覚えます。
挑発すら感じるような余裕。
一曲目にして、彼女の掌の上で踊らされるかのような錯覚。
やっぱりFUKIちゃんにはこういう曲が似合う。
続く[輝く夜へようこそ]は、アニソン的チューン。
まるで声優のようなメリハリと表情が見え隠れする、万華鏡のような煌きとアニソンならではの高揚感がたまりません。
こういう曲にも対応できちゃう、そしてこういう曲でも圧倒的存在感を見せるのです。
[I'll never let you down!]はスピーディーでメタリック、そして彼女のシリアスな一面を見ることができる曲。
タイプとしては、[月が満ちる前に][輝く夜へようこそ]のような歌唱こそFUKIちゃんの魅力であるなぁと思うわけですが、メタルヴォーカリストとしての存在感を見ることができます。
[僕が生きる世界]は、アニソン的な魅力に加え、J-POP的なコマーシャルな一面も見え隠れします。
[狂い咲け雪月華]は陰陽座のようなオリエンタルな世界観。
今までにないタイプの曲ですが、これもまた彼女の色に染められています。
[青い季節に]は、シングルカット向きのキャッチーな曲、でしょうか。
爽やかで透き通るような、ピュアな輝きに満ちています。
ラストを飾る[Sail on my love]では、再びLightBringerを思わせる明朗な疾走感。
新しい一歩にふさわしい歌詞は、今後をポジティブに見据える姿が。
歌詞通り、大海原に漕ぎだすかのようなスケールの大きい、それでいて自然体な彼女の声が際立ちます。
アルバムのタイトル通り、これが初FUKIちゃんとなる方々には「ようこそ!!」という名刺代わり。
既にFUKIちゃんをご存じの方にとっては、今までの集大成でもあり、今の彼女の現在進行形であり、ひとまず表舞台に立ってくれたことに安堵。
ただし、純粋なヘヴィメタルヴォーカリストとして対峙すると、アニソンっぽい快活さが鼻につく可能性があります。
まぁ、既知の方々にとってはそれがFUKIちゃんの魅力でもあるわけですが‥。
冒頭に書いた通り、方向性という意味では若干のバラつきがあり、この後の音楽性という意味では不透明な感もあります。
が、これは2nd、もしくは他のプロジェクトの兼ね合いで柔軟に構えているのではないでしょうか。
今はFUKIちゃんがやりたいことを、なんでもチャレンジしている、そしてその姿勢がアルバムに映し出されている気がします。
FUKIちゃんの魅力が十二分に堪能できるアルバムとなりました。
Fuki Commune - 「輝く夜へようこそ!」(Music Video Short ver.)
が、前バンドは「さぁ、これから」というところで瓦解してしまった。
そして、新たな船出となるアルバムです。
Fuki Commune / Welcome!

元、LIGHT BRINGERのFUKIちゃんとして。
現、Unlucky Morpheusの天外冬黄として。
時にメタルアーティストとして。
時に同人音楽アーティストとして。
時にアニソンヴォーカリストとして。
様々な顔を持つ女性ヴォーカリストである彼女のソロプロジェクトのアルバムです。
ワタシが彼女の存在を知ったのは、Dragon GuardianのDRAGONVARIUSというアルバム。
元々、同人のメロディックスピードメタルプロジェクトだったDragonGuardianは、このアルバムでFUKIちゃんを迎えたことで一気に花開きました。
メジャー感を纏い、大きくステップアップしました。
このアルバムでのFUKIちゃんの力強くキュートな声はインパクト充分でした。
その後、彼女が参加しているLIGHT BRINGERを知り、いまや伝説とも言える、東京キネマ倶楽部でのDragonGuardian / MinstreliX / LightBringerのライブに参戦。
ナマで見る彼女を見て「・・やっぱりすげぇ!」と確信、惚れ込みました。
そしてLightBringerも素晴らしいアルバムをリリース。
FUKIちゃんの魅力が堪能できるキャッチーな曲が粒揃い。まさに「これからだな!」というところでの活動休止。
Unlucky Morpheusも悪くないのですが、やはりLightBringerと比べるとやや魅力に劣る感があり、「FUKIちゃん、どうなるんだよ‥これだけの才能を埋もれさせるなよ‥」と思ってました。
そんな中、リリースされた「FUKI」の名を冠に据えたプロジェクトのアルバムです。
全体的には、上述した彼女の魅力が満遍なく散りばめられている印象です。
LightBringerやDragonGuardianのような、ひとつのコンセプトで統一されているというアルバムとは異なります。
彼女の声は快活であり、実にカラフルだ。
キュートな声色。
パワフルな声色。
キャッチーな声色。
シリアスな声色。
曲によって様々な表情を魅せてくれます。
そして、どの曲でも強い芯を持ち、彼女の周辺に乱反射するようなキラキラとした華やかさを持っています。
この華やかさはFUKIちゃんならでは。
若干、近未来的&ヘヴィな装いのイントロで「・・お?」と身構えてしまいますが‥
LightBringer時代を思い出させるキャッチーなメタルチューン[月が満ちる前に]で「これだよ!」と安堵を覚えます。
挑発すら感じるような余裕。
一曲目にして、彼女の掌の上で踊らされるかのような錯覚。
やっぱりFUKIちゃんにはこういう曲が似合う。
続く[輝く夜へようこそ]は、アニソン的チューン。
まるで声優のようなメリハリと表情が見え隠れする、万華鏡のような煌きとアニソンならではの高揚感がたまりません。
こういう曲にも対応できちゃう、そしてこういう曲でも圧倒的存在感を見せるのです。
[I'll never let you down!]はスピーディーでメタリック、そして彼女のシリアスな一面を見ることができる曲。
タイプとしては、[月が満ちる前に][輝く夜へようこそ]のような歌唱こそFUKIちゃんの魅力であるなぁと思うわけですが、メタルヴォーカリストとしての存在感を見ることができます。
[僕が生きる世界]は、アニソン的な魅力に加え、J-POP的なコマーシャルな一面も見え隠れします。
[狂い咲け雪月華]は陰陽座のようなオリエンタルな世界観。
今までにないタイプの曲ですが、これもまた彼女の色に染められています。
[青い季節に]は、シングルカット向きのキャッチーな曲、でしょうか。
爽やかで透き通るような、ピュアな輝きに満ちています。
ラストを飾る[Sail on my love]では、再びLightBringerを思わせる明朗な疾走感。
新しい一歩にふさわしい歌詞は、今後をポジティブに見据える姿が。
歌詞通り、大海原に漕ぎだすかのようなスケールの大きい、それでいて自然体な彼女の声が際立ちます。
アルバムのタイトル通り、これが初FUKIちゃんとなる方々には「ようこそ!!」という名刺代わり。
既にFUKIちゃんをご存じの方にとっては、今までの集大成でもあり、今の彼女の現在進行形であり、ひとまず表舞台に立ってくれたことに安堵。
ただし、純粋なヘヴィメタルヴォーカリストとして対峙すると、アニソンっぽい快活さが鼻につく可能性があります。
まぁ、既知の方々にとってはそれがFUKIちゃんの魅力でもあるわけですが‥。
冒頭に書いた通り、方向性という意味では若干のバラつきがあり、この後の音楽性という意味では不透明な感もあります。
が、これは2nd、もしくは他のプロジェクトの兼ね合いで柔軟に構えているのではないでしょうか。
今はFUKIちゃんがやりたいことを、なんでもチャレンジしている、そしてその姿勢がアルバムに映し出されている気がします。
FUKIちゃんの魅力が十二分に堪能できるアルバムとなりました。
Fuki Commune - 「輝く夜へようこそ!」(Music Video Short ver.)