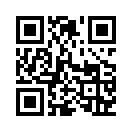ヘビメタパパの書斎 › N
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2017年07月14日
復活の狼煙
もう忘れていた人もいるかもしれない。
「あー、あのダサいPVのバンドね」という程度の人もいるかもしれない。
しばらく音沙汰がなかった彼らが復活の狼煙をあげたようです。
ということで、取り上げてみましたが‥「そういえば‥」と思って検索してみたら、彼らのことを取り上げるのは初めてですね。
なんだか意外です。
NOCTURNAL RITES [Afterlife]

スウェーデン出身。
このアルバムは2000年にリリースされた4thになりますかね。
ワタシのようなオールド世代のファンにとっては、なんといっても3rdの[The Sacred Talisman]が印象的。
いわゆる「ジャーマンメタル」を標榜し、クサく、そしていい意味でイモ臭くB級臭を撒き散らしながら疾走する。
あの玉石混淆百花繚乱のジャーマンメタルブームの中でも強力な個性を放った名盤でした。
1st→2nd→3rdと着実なステップでスケールアップし、さぁこれから!というときにヴォーカルが交代。
そしてリリースされたこの作品。
3rd→4thの頃とか。
2nd→3rdの頃とか。
バンドは「○○みたい」と揶揄される状況を脱却するために方向性を変えようとしてファンからソッポを向かれる、という傾向、よくありますよね。
このバンドの、このアルバムもどちらかというとそういった色合いが強かった。
ワタシも「そうか‥方向性変わっちゃったのか‥」としばらく手つかずだったことを思い出します。
が、このアルバム、素晴らしいのだ。
このアルバム以降にリリースされた作品は、軒並み好評を博していくわけですが、その礎が感じられます。
クサくてジャーマンメタル然としたサウンドから、ストロングな正統派路線へ舵を切り。
それでいつつ、3rdまでの彼ららしいメロディは随所で光る。
リリース当時の評価は厳しかったかもしれませんが、まさに過渡期として必要不可欠だったことが分かります。
そのサウンドを引き立たせるのが、新加入となったヴォーカル、ジョニー・リンドクヴィスト。
力強く、適度にザラついた声質は、新しい世界観の構築に大きく貢献していますl。
幕開けとなる[Afterlife]。
3rdの[Destiny Calls]を思わせるキャッチーな疾走感を内包しつつ、大きくスケールアップした存在感に「おぉ!これは!化けたっ!」とワクワクしてしまいますね。
続く[Wake Up Dead]。
曲名がそうだから‥というわけではありませんが、シリアスかつソリッドなメロディからのキャッチーなサビは、MEGADETHを思い出したりしませんかね。
[The Sinners Cross]での強靱なリフで「お、ちょっとムードが違うな」と感じはじめるかもしれません。
が、こういったリフこそがこのあとの彼らを支えていくことになるんだなぁ‥と感じます。
[Hell And Back]の疾走感は、後に生まれる[AVALON]などの疾走感に通じます。
彼らの生み出す名曲の原点と言えるかもしれませんね。
[Sacrifice] [Temple Of The Dead]といった曲たちのモダンさ(というか、近未来的なイメージ)も印象的。
新しいアルバムから遡れば、全く違和感がないどころか、「このアルバムまではセーフ。これ以前はダサい」と言われるかもしれない。
そして初期から聞いてれば「これはNOCTURNAL RITESじゃない‥」と言われるかもしれない。
そういう意味では、大きな分水嶺になったと思われるアルバムです。
が、結果としてこのアルバムのリリースは正解だった。
そしてこれが今後の彼らの活躍を生んだといえる重要なアルバムと言えるでしょう。
彼らが最後にアルバムをリリースしたのは2007年。
そして、今年ついに復活。
先行リリースされた曲を聞けば、やはりこのアルバムがあったからこそ‥と思えます。
3rdまでで止まってる方がいらっしゃれば、まずこのアルバムを手にとってみてほしい。
そして、その後の路線も楽しんで頂けるのではないかと思います。
祝!復活!
祈!ラウドパーク!
nocturnal rites [Afterlife]
「あー、あのダサいPVのバンドね」という程度の人もいるかもしれない。
しばらく音沙汰がなかった彼らが復活の狼煙をあげたようです。
ということで、取り上げてみましたが‥「そういえば‥」と思って検索してみたら、彼らのことを取り上げるのは初めてですね。
なんだか意外です。
NOCTURNAL RITES [Afterlife]

スウェーデン出身。
このアルバムは2000年にリリースされた4thになりますかね。
ワタシのようなオールド世代のファンにとっては、なんといっても3rdの[The Sacred Talisman]が印象的。
いわゆる「ジャーマンメタル」を標榜し、クサく、そしていい意味でイモ臭くB級臭を撒き散らしながら疾走する。
あの玉石混淆百花繚乱のジャーマンメタルブームの中でも強力な個性を放った名盤でした。
1st→2nd→3rdと着実なステップでスケールアップし、さぁこれから!というときにヴォーカルが交代。
そしてリリースされたこの作品。
3rd→4thの頃とか。
2nd→3rdの頃とか。
バンドは「○○みたい」と揶揄される状況を脱却するために方向性を変えようとしてファンからソッポを向かれる、という傾向、よくありますよね。
このバンドの、このアルバムもどちらかというとそういった色合いが強かった。
ワタシも「そうか‥方向性変わっちゃったのか‥」としばらく手つかずだったことを思い出します。
が、このアルバム、素晴らしいのだ。
このアルバム以降にリリースされた作品は、軒並み好評を博していくわけですが、その礎が感じられます。
クサくてジャーマンメタル然としたサウンドから、ストロングな正統派路線へ舵を切り。
それでいつつ、3rdまでの彼ららしいメロディは随所で光る。
リリース当時の評価は厳しかったかもしれませんが、まさに過渡期として必要不可欠だったことが分かります。
そのサウンドを引き立たせるのが、新加入となったヴォーカル、ジョニー・リンドクヴィスト。
力強く、適度にザラついた声質は、新しい世界観の構築に大きく貢献していますl。
幕開けとなる[Afterlife]。
3rdの[Destiny Calls]を思わせるキャッチーな疾走感を内包しつつ、大きくスケールアップした存在感に「おぉ!これは!化けたっ!」とワクワクしてしまいますね。
続く[Wake Up Dead]。
曲名がそうだから‥というわけではありませんが、シリアスかつソリッドなメロディからのキャッチーなサビは、MEGADETHを思い出したりしませんかね。
[The Sinners Cross]での強靱なリフで「お、ちょっとムードが違うな」と感じはじめるかもしれません。
が、こういったリフこそがこのあとの彼らを支えていくことになるんだなぁ‥と感じます。
[Hell And Back]の疾走感は、後に生まれる[AVALON]などの疾走感に通じます。
彼らの生み出す名曲の原点と言えるかもしれませんね。
[Sacrifice] [Temple Of The Dead]といった曲たちのモダンさ(というか、近未来的なイメージ)も印象的。
新しいアルバムから遡れば、全く違和感がないどころか、「このアルバムまではセーフ。これ以前はダサい」と言われるかもしれない。
そして初期から聞いてれば「これはNOCTURNAL RITESじゃない‥」と言われるかもしれない。
そういう意味では、大きな分水嶺になったと思われるアルバムです。
が、結果としてこのアルバムのリリースは正解だった。
そしてこれが今後の彼らの活躍を生んだといえる重要なアルバムと言えるでしょう。
彼らが最後にアルバムをリリースしたのは2007年。
そして、今年ついに復活。
先行リリースされた曲を聞けば、やはりこのアルバムがあったからこそ‥と思えます。
3rdまでで止まってる方がいらっしゃれば、まずこのアルバムを手にとってみてほしい。
そして、その後の路線も楽しんで頂けるのではないかと思います。
祝!復活!
祈!ラウドパーク!
nocturnal rites [Afterlife]
2017年03月24日
去りぎわの美学
波瀾万丈だったな‥と思う。
一度、ビッグなスポットライトを浴びてしまい、その印象から脱しきれぬまま、このときを迎えてしまった感がある。
これが最後の作品、らしい。
そして皮肉なことに、実に彼ららしいアルバムに仕上がっているのだ。
NELSON [Peace Out]

2015年リリース。
マシュー・ネルソン&ガナー・ネルソンという美男子兄弟によるアメリカンハードロックバンド。
この作品が9枚目でしょうか。
デビューで脚光を浴びたアルバムがリリースされたのが1990年。
‥いつまでも若々しい印象がありますが、もう四半世紀でしたか‥。
彼らが登場したCM「宝酒造 純」を記憶してらっしゃる方はワタシと同年代でしょうかね。
そして、その頃の彼らを知っている人は意外と(というと失礼ですが)多い気がします。
瑞々しく、甘く、キャッチー。
彼らのルックスもその音楽性を後押しし、一気にスターダームの座へ。
‥と言っても、その甘さゆえ、ガチガチのメタラーからは叩かれた印象もありますが。
そういった外見的な要素や先入観もあってか、逆に足を引っ張られた感もありますが、初期のアルバムは充実していました。
が。
その強すぎる印象から、少しヘヴィな曲を書いただけで「違う。あの彼らじゃない」とソッポを向かれ‥。
いや、その頃のアルバムも良かったんですがね。
最初の印象が強すぎて、メタラーからはもともと目の敵にされ、初期のファンは少し離れていき‥という負のスパイラルに陥っていた気がします。
その後は一気にカントリー方面へ舵を切り、「あー、そっち方面へ行っちゃったか」という落胆もありつつ、それでもやはり彼ら流の輝きは見え隠れしていました。
が、さすがに初期のメロディックハーロドック路線は期待できないな‥と踏ん切りをつけたファンも多いことでしょう(←ワタシです)
そして、「NELSONのアルバムとしては最後になる」とアナウンスされてリリースされたこのアルバム。
これが実に素晴らしいのだ。
初期の煌き。透明感。
四半世紀を経て自然と滲み出る貫祿。
紆余曲折を経た余裕から生まれるスケール感。
初期の瑞々しさを残しつつも、燻銀の落ち着きを感じさせる、という、奇跡的なバランスが構築されています。
もちろん、その芯であり核となるのは、彼らが持ち合わせたメロディセンスと美しいハーモニー。
「おいおい、最後の最後にコレかよ‥」という、驚きや、喜びや、これで最後だという落胆と心残りがフクザツに絡み合います。
オープニングを飾る[Hello Everybody]。
まるでバンドのデビューアルバムのオープニングトラックであるかのような歌詞と躍動感。
彼らの真骨頂である美しいコーラスも満載。
とてもラストアルバムとは思えないポジティブさを撒き散らしながらアルバムはスタートします。
ダイナミズムに満ちた[Back in the Day]。
アメリカンハードロックの王道とも言える曲調。とろけそうな甘さを醸しだしていた初期とは異なり、スケールアップした彼らの「今」を聞くことができます。
ややトンガった印象を伴いつつも、やはりサビの美しさが際立つ[Rockstar]。
心地よいカラっとした疾走感が心地いい[Autograph]。
こういう路線は今までありそうで無かったのではないでしょうか。
まだまだ彼らの可能性は広がっている。
このままフェードアウトしていくのは惜しい。残念すぎる。
そう思わせてくれる曲です。
まるでFIREHOUSEを思わせるようなエッジを感じさせる[Bad for You]。
いい意味で、吹っ切れてるなと感じます。
穏やかにラストを飾る[Leave the Light on for Me]。
肩の力が抜けた、自然体の彼らの姿が見えてきます。
適度に感傷的に、適度にハッピーエンド。
そう。
このアルバムに漲るのは「ハッピーエンド」感だなと感じます。
冒頭に触れたように、波瀾万丈だったと思う。
音楽性、方向性もいろいろ模索してきた。
が、最後の最後に、最も彼ららしいと思えるアルバムを造り上げた。
アルバムのタイトル。
アルバムのジャケット。
アルバムの音楽の素晴らしさ。
勿体ないと思う。
まだまだ才能は枯渇していないと思う。
けど、なんだか「あー、これで良かったのかもしれない」と思わせてくれるアルバムだ。
「多幸感」が溢れているのだ。
これだけのハッピーエンド感をもってバンドに幕を下ろすバンド、幕を下ろせるバンドは、あまりない。
華やかに登場し、美しくさりげなく表舞台を去る。
寂しいけど、素晴らしいラストアルバムとなりました。
Nelson - Autograph
一度、ビッグなスポットライトを浴びてしまい、その印象から脱しきれぬまま、このときを迎えてしまった感がある。
これが最後の作品、らしい。
そして皮肉なことに、実に彼ららしいアルバムに仕上がっているのだ。
NELSON [Peace Out]

2015年リリース。
マシュー・ネルソン&ガナー・ネルソンという美男子兄弟によるアメリカンハードロックバンド。
この作品が9枚目でしょうか。
デビューで脚光を浴びたアルバムがリリースされたのが1990年。
‥いつまでも若々しい印象がありますが、もう四半世紀でしたか‥。
彼らが登場したCM「宝酒造 純」を記憶してらっしゃる方はワタシと同年代でしょうかね。
そして、その頃の彼らを知っている人は意外と(というと失礼ですが)多い気がします。
瑞々しく、甘く、キャッチー。
彼らのルックスもその音楽性を後押しし、一気にスターダームの座へ。
‥と言っても、その甘さゆえ、ガチガチのメタラーからは叩かれた印象もありますが。
そういった外見的な要素や先入観もあってか、逆に足を引っ張られた感もありますが、初期のアルバムは充実していました。
が。
その強すぎる印象から、少しヘヴィな曲を書いただけで「違う。あの彼らじゃない」とソッポを向かれ‥。
いや、その頃のアルバムも良かったんですがね。
最初の印象が強すぎて、メタラーからはもともと目の敵にされ、初期のファンは少し離れていき‥という負のスパイラルに陥っていた気がします。
その後は一気にカントリー方面へ舵を切り、「あー、そっち方面へ行っちゃったか」という落胆もありつつ、それでもやはり彼ら流の輝きは見え隠れしていました。
が、さすがに初期のメロディックハーロドック路線は期待できないな‥と踏ん切りをつけたファンも多いことでしょう(←ワタシです)
そして、「NELSONのアルバムとしては最後になる」とアナウンスされてリリースされたこのアルバム。
これが実に素晴らしいのだ。
初期の煌き。透明感。
四半世紀を経て自然と滲み出る貫祿。
紆余曲折を経た余裕から生まれるスケール感。
初期の瑞々しさを残しつつも、燻銀の落ち着きを感じさせる、という、奇跡的なバランスが構築されています。
もちろん、その芯であり核となるのは、彼らが持ち合わせたメロディセンスと美しいハーモニー。
「おいおい、最後の最後にコレかよ‥」という、驚きや、喜びや、これで最後だという落胆と心残りがフクザツに絡み合います。
オープニングを飾る[Hello Everybody]。
まるでバンドのデビューアルバムのオープニングトラックであるかのような歌詞と躍動感。
彼らの真骨頂である美しいコーラスも満載。
とてもラストアルバムとは思えないポジティブさを撒き散らしながらアルバムはスタートします。
ダイナミズムに満ちた[Back in the Day]。
アメリカンハードロックの王道とも言える曲調。とろけそうな甘さを醸しだしていた初期とは異なり、スケールアップした彼らの「今」を聞くことができます。
ややトンガった印象を伴いつつも、やはりサビの美しさが際立つ[Rockstar]。
心地よいカラっとした疾走感が心地いい[Autograph]。
こういう路線は今までありそうで無かったのではないでしょうか。
まだまだ彼らの可能性は広がっている。
このままフェードアウトしていくのは惜しい。残念すぎる。
そう思わせてくれる曲です。
まるでFIREHOUSEを思わせるようなエッジを感じさせる[Bad for You]。
いい意味で、吹っ切れてるなと感じます。
穏やかにラストを飾る[Leave the Light on for Me]。
肩の力が抜けた、自然体の彼らの姿が見えてきます。
適度に感傷的に、適度にハッピーエンド。
そう。
このアルバムに漲るのは「ハッピーエンド」感だなと感じます。
冒頭に触れたように、波瀾万丈だったと思う。
音楽性、方向性もいろいろ模索してきた。
が、最後の最後に、最も彼ららしいと思えるアルバムを造り上げた。
アルバムのタイトル。
アルバムのジャケット。
アルバムの音楽の素晴らしさ。
勿体ないと思う。
まだまだ才能は枯渇していないと思う。
けど、なんだか「あー、これで良かったのかもしれない」と思わせてくれるアルバムだ。
「多幸感」が溢れているのだ。
これだけのハッピーエンド感をもってバンドに幕を下ろすバンド、幕を下ろせるバンドは、あまりない。
華やかに登場し、美しくさりげなく表舞台を去る。
寂しいけど、素晴らしいラストアルバムとなりました。
Nelson - Autograph
2016年07月06日
栄華の幻影
鮮烈に焼きついたイメージを払拭するのは大変なことだ。
彼らもデビュー当時の印象が拭われるまま、不当な評価をされていた感がある。
NELSON [THE SILENCE IS BROKEN]

アメリカ出身。
マシュー&ガナー、二人のイケメンブラザーズ。
この作品は4th。リリースは1997年‥もう20年かぁ。
当時のメタルファン、いや、洋楽ファンでも「ネルソン」といえば美形の二人の表情が思い浮かぶのではないでしょうか。
キャッチー。
メロディアス。
美形。
爽やか。
その印象をそのままに、日本でも焼酎「純」のCMに出演するなど、デビュー当時にして栄華の頂点、という華やかさがありました。
が。
この印象が良くも悪くも彼らの足枷となった気がします。
1stアルバムに続いて準備していた[IMAGINATOR]が「イメージと違う」ということでお蔵入り。
改めて、2ndとしてイメージを尊重した[BECAUSE THEY CAN]をリリースするも、漂う「二番煎じ」感。
その後、お蔵入りとなっていた[IMAGINATOR]を3rdアルバムとしてリリースするも、やはり1stとのギャップで印象は良くなかったようで‥
この頃から「なんだかかわいそうな、不運な人たち」という印象が浮き彫りに。
そして、続いてリリースされたのが、このアルバム。
なんだか2nd以降は残念な印象のように書いてしまいましたが、それぞれ良質なのだ。
2ndの甘さ。
3rdのヘヴィながらも充実のメロディ。
あくまでも「AFTER THA RAINのNELSON」という印象と比較しての「‥うーん」感なのだが、これが思った以上に重かった。
が、この4thでは吹っ切れたかのような素晴らしさが戻ってきています。
いや、戻ってきているというのは適切ではないかもしれません。
自然体で、1stの華やかさ、2ndの甘さ、3rdのソリッド感をうまく継承し、NELSONらしさを保ちつつ、新しい一歩を踏み出したかのような信念を感じます。
アメリカンハードテイストに満ちたリフに導かれて、アダルティなムードのドライヴ感が心地よい[GHOSTDANCE]。
オープニングから「これは今までと違う!」という期待感。
かと思えば一転、キャッチーで華やかな[SAY IT ISN'T SO]へ。まさにNELSONに期待するメロディです。
[YOU TALK TOO MUCH]もその路線。実に爽やか。
穏やかに始まり、ダイナミックなサビを迎えるタイトル曲[THE SILENCE IS BROKEN]。
このスケールと組み立ては今までに無かったタイプ。
この曲を評価できるかどうかで、このアルバムの評価は分かれるでしょうか。
私にとっては「この曲こそが、このアルバムのハイライト」というくらいインパクトが強い。
[L.O.V.E ME NOT]もザクザクとしたリフ、コーラスの入り方など、若干硬派路線。
[RUNNING OUT OF TIME][TEARS OF PAIN]は欧州風味が漂うと言えるような哀愁路線。
このアルバム、前半と後半でずいぶん印象が異なります。
そしてラストを飾る美しい[LOVE ME TODAY PART 2]。
終わり良ければ全てよし‥という言葉が脳裏をよぎる、完璧すぎるラストです。
そしてこの劇的なラストの最後に隠されたシークレットチューン‥楽しげな子供たちの歌声。
なんと、マシュー&ガナーが10歳のときに録音したという曲。
これがまたいいムード!そして上手い!
冒頭に書いた通り、NELSONといえば1stの印象が強く、最後の最後までその幻影につきまとわれた感がある。
いろいろな思惑、戦略などでゴタゴタした2nd、3rd(この二枚も悪くないのだ)。
そしてこの4th。
もし1stアルバムだけは聞いたことがあって、「あー、ネルソン、懐かしいねー」と思った方がいらっしゃったら、まずこの4thを手にとってみてはどうでしょうか。
期待通りの姿。
意外な姿。
そしてやはり(見た目も音も)美しいなー‥と思って頂けると思います。
Nelson / Ghostdance 他にもっと聞いてほしい曲があるのに、コレしか無かった‥。
彼らもデビュー当時の印象が拭われるまま、不当な評価をされていた感がある。
NELSON [THE SILENCE IS BROKEN]

アメリカ出身。
マシュー&ガナー、二人のイケメンブラザーズ。
この作品は4th。リリースは1997年‥もう20年かぁ。
当時のメタルファン、いや、洋楽ファンでも「ネルソン」といえば美形の二人の表情が思い浮かぶのではないでしょうか。
キャッチー。
メロディアス。
美形。
爽やか。
その印象をそのままに、日本でも焼酎「純」のCMに出演するなど、デビュー当時にして栄華の頂点、という華やかさがありました。
が。
この印象が良くも悪くも彼らの足枷となった気がします。
1stアルバムに続いて準備していた[IMAGINATOR]が「イメージと違う」ということでお蔵入り。
改めて、2ndとしてイメージを尊重した[BECAUSE THEY CAN]をリリースするも、漂う「二番煎じ」感。
その後、お蔵入りとなっていた[IMAGINATOR]を3rdアルバムとしてリリースするも、やはり1stとのギャップで印象は良くなかったようで‥
この頃から「なんだかかわいそうな、不運な人たち」という印象が浮き彫りに。
そして、続いてリリースされたのが、このアルバム。
なんだか2nd以降は残念な印象のように書いてしまいましたが、それぞれ良質なのだ。
2ndの甘さ。
3rdのヘヴィながらも充実のメロディ。
あくまでも「AFTER THA RAINのNELSON」という印象と比較しての「‥うーん」感なのだが、これが思った以上に重かった。
が、この4thでは吹っ切れたかのような素晴らしさが戻ってきています。
いや、戻ってきているというのは適切ではないかもしれません。
自然体で、1stの華やかさ、2ndの甘さ、3rdのソリッド感をうまく継承し、NELSONらしさを保ちつつ、新しい一歩を踏み出したかのような信念を感じます。
アメリカンハードテイストに満ちたリフに導かれて、アダルティなムードのドライヴ感が心地よい[GHOSTDANCE]。
オープニングから「これは今までと違う!」という期待感。
かと思えば一転、キャッチーで華やかな[SAY IT ISN'T SO]へ。まさにNELSONに期待するメロディです。
[YOU TALK TOO MUCH]もその路線。実に爽やか。
穏やかに始まり、ダイナミックなサビを迎えるタイトル曲[THE SILENCE IS BROKEN]。
このスケールと組み立ては今までに無かったタイプ。
この曲を評価できるかどうかで、このアルバムの評価は分かれるでしょうか。
私にとっては「この曲こそが、このアルバムのハイライト」というくらいインパクトが強い。
[L.O.V.E ME NOT]もザクザクとしたリフ、コーラスの入り方など、若干硬派路線。
[RUNNING OUT OF TIME][TEARS OF PAIN]は欧州風味が漂うと言えるような哀愁路線。
このアルバム、前半と後半でずいぶん印象が異なります。
そしてラストを飾る美しい[LOVE ME TODAY PART 2]。
終わり良ければ全てよし‥という言葉が脳裏をよぎる、完璧すぎるラストです。
そしてこの劇的なラストの最後に隠されたシークレットチューン‥楽しげな子供たちの歌声。
なんと、マシュー&ガナーが10歳のときに録音したという曲。
これがまたいいムード!そして上手い!
冒頭に書いた通り、NELSONといえば1stの印象が強く、最後の最後までその幻影につきまとわれた感がある。
いろいろな思惑、戦略などでゴタゴタした2nd、3rd(この二枚も悪くないのだ)。
そしてこの4th。
もし1stアルバムだけは聞いたことがあって、「あー、ネルソン、懐かしいねー」と思った方がいらっしゃったら、まずこの4thを手にとってみてはどうでしょうか。
期待通りの姿。
意外な姿。
そしてやはり(見た目も音も)美しいなー‥と思って頂けると思います。
Nelson / Ghostdance 他にもっと聞いてほしい曲があるのに、コレしか無かった‥。
2015年03月18日
意外な国からの刺客
このブログを定期的orときどきでも覗いてくださる方なら御存じのことと思いますが・・。
メロスピが好きです。(キッパリ)
同じメロディックスピードメタルを愛する人なら、脳裏に「メロスピの基本的フォーマット」ってのがあると思います。
イメージしてみてください。
・・
・・・・
・・・・・・ そうそう、そのイメージです。
そのイメージをそのまま具現してくれるバンドが、意外な国から現れましたよ。
NAUTILUZ / Leaving All Behind

2013年リリース。なんと南米ペルー出身ですよ。
とはいえ、ANGRAを産んだブラジルあたりではこういった音楽性が人気があるわけで、そういう意味では違和感ないのかもしれません。
が、ペルーですよ。ペルー。
ちなみにバンド名は「ノーチラス」と読むそうです。(←読めなかった)
ワタシはこのバンド、名前は見たことがある程度で実際に触れる機会がありませんでした。
が、とあるご縁でこのバンドを知り、「!」という驚きに包まれました。
メロスピ/メロパワの定番、大仰かつシンフォニックなオープニング→疾走チューン。あります。
HEAVENLYを思わせる鐘の音。あります。
ANGRAの[CARRY ON]を思わせる曲間のブレイクでの「GO!!」の叫び。あります。
EDGUYの[BABYLON]を思わせるシャウトからの疾走。あります。
FREEDOM CALLを思わせる「♪ドコドコドコドコチンチンチンチン」なドラミング(←褒めてます)、あります。
SONATA ARCTICAを思わせるキラキラキーボードソロ、あります。
とにかくメロディックスピードメタルに期待するものが如実にアピールされています。
これがデビューアルバムってんだから驚きです。
国内盤リリースのSPIRITUAL BEASTのバンド紹介ページによると
「IRON MAIDEN, Yngwie Malmsteen, ANGRA, DREAM THEATER, HELLOWEEN, STRATOVARIUS, NOCTURNAL RITES, ADAGIO, HANGARなどからの影響を公言」
とのこと。
バンド名を見ただけでニヤニヤしてしまうラインナップだ。
「ですよねー」と言いたくなるラインナップだ。
「仲良くしましょう」と言いたくなるラインナップだ。
個人的にはADAGIOが入ってるところがウレシイ。そのクラシカルなエッセンスはギターソロ、キーボードソロの随所で光ります。
ANGRAのようなトライバルな印象は薄いですが、逆に欧州的ウェットな疾走感が好感触。
少なくとも一聴して南米的印象は受けません(まぁ、これが良いか悪いかは置いといて)
曲名も「MOONLIGHT」「MIRROR」「SERENADE」「BARD」「CHASING」などといった、このジャンルが好きな人ならなぜか「これは名曲の予感!」というキーワードが並びます。(あくまで個人的感想ですが、共感してくださる方もいらっしゃると思いたい)
シンフォニックメタルの幕開けを思わせるイントロ[Somniac Lifeline]から典型的スピードチューン[Under The Moonlight]へ。
この曲はまだまだ序の口。名刺代わりみたいなものだと思ってください。
続く[Burning Hearts]。「そうそう、メロスピの2曲目(実質3曲目)は、こういうミディアムチューンなんだよなー。」と嬉しくなります。
STRATOVARIUSのアルバム構成を思い出しますね。
[The Mirror]ではSymphony Xのようなクラシカルな旋律で幕を開け、サビに導くメロディはZONATAを思わせるシリアスなパワーメタルチューン。
中盤のハイライト[Chasing The Light]はSTRATOVARIUS+ANGRAといった印象のキラーチューン。
疾走→ブレイクからの「GO!!」という叫び→キーボードとギターのクラシカルなソロの競演という流れは鳥肌モノ!
ラストを飾る[Leaving All Behind]はHEAVENLY的。(HEAVENLY的でありながらGAMMA RAY的じゃない、ってのがキモ)
サビの歌メロはKAMELOTを思い出したりしますね。
:
:
といった具合に「○○的」というキーワードが並んでしまうわけですが、これが全くあざとさを感じないのです。
・・まぁ、ワタシがこういう音が好きだからという補正値は入ってしまいますが。
ホントに「こういうスピードメタルが好き!」ということが伝わってくる、実に美味しいアルバムです。
逆に言うと、「NAUTILUZならではの個性」という意味ではまだ突出していない気がします。
ヴォーカルも悪くないけど「一聴してNAUTILUZと分かる」という点では弱い。
これだけ「全部詰め込んでみました」の後は「俺たちはこういう曲ばかりじゃないんだぜ」とばかりに方向転換するバンドも多い。(特に3rdあたりで)
次のアルバムでこの路線をスケールアップして、さらに個性を輝かせることができるかが勝負になりそうな気がします。
とはいえ、とりあえず「メロスピ好きなら聞いてみて損はない」と断言できますよ。
Chasing the Light - Nautiluz
(この曲が合わなければ、メロスピというジャンルは合わないでしょうね。というレベルの曲だと思うのです)
メロスピが好きです。(キッパリ)
同じメロディックスピードメタルを愛する人なら、脳裏に「メロスピの基本的フォーマット」ってのがあると思います。
イメージしてみてください。
・・
・・・・
・・・・・・ そうそう、そのイメージです。
そのイメージをそのまま具現してくれるバンドが、意外な国から現れましたよ。
NAUTILUZ / Leaving All Behind

2013年リリース。なんと南米ペルー出身ですよ。
とはいえ、ANGRAを産んだブラジルあたりではこういった音楽性が人気があるわけで、そういう意味では違和感ないのかもしれません。
が、ペルーですよ。ペルー。
ちなみにバンド名は「ノーチラス」と読むそうです。(←読めなかった)
ワタシはこのバンド、名前は見たことがある程度で実際に触れる機会がありませんでした。
が、とあるご縁でこのバンドを知り、「!」という驚きに包まれました。
メロスピ/メロパワの定番、大仰かつシンフォニックなオープニング→疾走チューン。あります。
HEAVENLYを思わせる鐘の音。あります。
ANGRAの[CARRY ON]を思わせる曲間のブレイクでの「GO!!」の叫び。あります。
EDGUYの[BABYLON]を思わせるシャウトからの疾走。あります。
FREEDOM CALLを思わせる「♪ドコドコドコドコチンチンチンチン」なドラミング(←褒めてます)、あります。
SONATA ARCTICAを思わせるキラキラキーボードソロ、あります。
とにかくメロディックスピードメタルに期待するものが如実にアピールされています。
これがデビューアルバムってんだから驚きです。
国内盤リリースのSPIRITUAL BEASTのバンド紹介ページによると
「IRON MAIDEN, Yngwie Malmsteen, ANGRA, DREAM THEATER, HELLOWEEN, STRATOVARIUS, NOCTURNAL RITES, ADAGIO, HANGARなどからの影響を公言」
とのこと。
バンド名を見ただけでニヤニヤしてしまうラインナップだ。
「ですよねー」と言いたくなるラインナップだ。
「仲良くしましょう」と言いたくなるラインナップだ。
個人的にはADAGIOが入ってるところがウレシイ。そのクラシカルなエッセンスはギターソロ、キーボードソロの随所で光ります。
ANGRAのようなトライバルな印象は薄いですが、逆に欧州的ウェットな疾走感が好感触。
少なくとも一聴して南米的印象は受けません(まぁ、これが良いか悪いかは置いといて)
曲名も「MOONLIGHT」「MIRROR」「SERENADE」「BARD」「CHASING」などといった、このジャンルが好きな人ならなぜか「これは名曲の予感!」というキーワードが並びます。(あくまで個人的感想ですが、共感してくださる方もいらっしゃると思いたい)
シンフォニックメタルの幕開けを思わせるイントロ[Somniac Lifeline]から典型的スピードチューン[Under The Moonlight]へ。
この曲はまだまだ序の口。名刺代わりみたいなものだと思ってください。
続く[Burning Hearts]。「そうそう、メロスピの2曲目(実質3曲目)は、こういうミディアムチューンなんだよなー。」と嬉しくなります。
STRATOVARIUSのアルバム構成を思い出しますね。
[The Mirror]ではSymphony Xのようなクラシカルな旋律で幕を開け、サビに導くメロディはZONATAを思わせるシリアスなパワーメタルチューン。
中盤のハイライト[Chasing The Light]はSTRATOVARIUS+ANGRAといった印象のキラーチューン。
疾走→ブレイクからの「GO!!」という叫び→キーボードとギターのクラシカルなソロの競演という流れは鳥肌モノ!
ラストを飾る[Leaving All Behind]はHEAVENLY的。(HEAVENLY的でありながらGAMMA RAY的じゃない、ってのがキモ)
サビの歌メロはKAMELOTを思い出したりしますね。
:
:
といった具合に「○○的」というキーワードが並んでしまうわけですが、これが全くあざとさを感じないのです。
・・まぁ、ワタシがこういう音が好きだからという補正値は入ってしまいますが。
ホントに「こういうスピードメタルが好き!」ということが伝わってくる、実に美味しいアルバムです。
逆に言うと、「NAUTILUZならではの個性」という意味ではまだ突出していない気がします。
ヴォーカルも悪くないけど「一聴してNAUTILUZと分かる」という点では弱い。
これだけ「全部詰め込んでみました」の後は「俺たちはこういう曲ばかりじゃないんだぜ」とばかりに方向転換するバンドも多い。(特に3rdあたりで)
次のアルバムでこの路線をスケールアップして、さらに個性を輝かせることができるかが勝負になりそうな気がします。
とはいえ、とりあえず「メロスピ好きなら聞いてみて損はない」と断言できますよ。
Chasing the Light - Nautiluz
(この曲が合わなければ、メロスピというジャンルは合わないでしょうね。というレベルの曲だと思うのです)
2011年02月02日
見た目で決めないで
「人は見た目が9割」ってな本が売れたことがありましたねぇ。
この人たちは、メタル的視点でいうと、見た目で損してんなぁ・・・と思ってるのです。
見た目で「ケッ!」って思うメタラーは多いと思うんだよね。
だけど、その音楽性は侮れないのですよ。
NELSON [After The Rain]

このアルバムが1stですね。wikiによると、発表は1990年。
マシュー・ネルソンとガナー・ネルソンという双子の兄弟を中心としたアメリカン・ハードロックバンド。
もうね、見た目の美しさだけで得してる部分もあるとは思うのですが、大半のメタラーは「ポップアイドルだろ」って先入観を持ってしまうと思います。
ところが、その音楽性は穏やかでキャッチーな楽曲、キラキラとした瑞々しさ、そして全編に渡って印象的なコーラスは双子ならではでしょうか。
確かにポップな路線ではあると思います。
例えるなら、FIREHOUSEからハードなドライヴ感を控えめにして、HAREM SCAREM的なハーモニーを加えたような。
そしてその爽やかなメロディはTERRA NOVAのような美しさを湛えています。
こういったバンドはメロディアスハード界隈ではそれなりに評価されているわけですから、NELSONも充分にそのテリトリーに入ってると思うのです。
だからこそ、見た目で引いちゃう方がいると、惜しいなぁ・・・と。
とはいえ、当時はCM等で使われたりもして、一般的認知度はソコソコあった・・・んじゃないかな。
メタル側からしか見てなかったからワカンナイんだけどね。
基本的にはキャッチーなハードロック・・・いや、ハードポップってとこかな。
その中で、アコースティックな面ではカントリーっぽいムードも醸しだしていますね。
「カントリー」というとメタル的視点ではいい表現ではないかもしれませんが・・・・このカラリとしたムードはアメリカンハードの一つの魅力かな、と思うんだ。
・・・と、音楽性だけ見れば魅力タップリなんですが・・・。
あれだけの美貌、そして甘いメロディ・・・・そりゃレコード会社もその路線でプッシュしたいわけですよ。
2ndでは、その路線を強調したアルバムだったわけですが、インパクトはやや薄く・・・。
そして世の中はグランジブームに沸き上がり、その時流に飲み込まれ・・・
忘れた頃にリリースした3rd~4thは、ややヘヴィな路線で話題に登らず・・・良作なんだけど、その印象とのギャップとか世間とのタイミングとかね。
なんだかその見た目が故に振り回された不幸な兄弟・・・という印象が強いのです。
だからこそ、この1stはメロディアスハードが好きな方には是非聞いてほしい。名作ですよ。
Nelson - After the Rain (「らしさ」全開の名曲)
Nelson - Only Time Will Tell (感動の名バラード)
Too Many Dreams (たしか焼酎のCM曲)
type=
この人たちは、メタル的視点でいうと、見た目で損してんなぁ・・・と思ってるのです。
見た目で「ケッ!」って思うメタラーは多いと思うんだよね。
だけど、その音楽性は侮れないのですよ。
NELSON [After The Rain]

このアルバムが1stですね。wikiによると、発表は1990年。
マシュー・ネルソンとガナー・ネルソンという双子の兄弟を中心としたアメリカン・ハードロックバンド。
もうね、見た目の美しさだけで得してる部分もあるとは思うのですが、大半のメタラーは「ポップアイドルだろ」って先入観を持ってしまうと思います。
ところが、その音楽性は穏やかでキャッチーな楽曲、キラキラとした瑞々しさ、そして全編に渡って印象的なコーラスは双子ならではでしょうか。
確かにポップな路線ではあると思います。
例えるなら、FIREHOUSEからハードなドライヴ感を控えめにして、HAREM SCAREM的なハーモニーを加えたような。
そしてその爽やかなメロディはTERRA NOVAのような美しさを湛えています。
こういったバンドはメロディアスハード界隈ではそれなりに評価されているわけですから、NELSONも充分にそのテリトリーに入ってると思うのです。
だからこそ、見た目で引いちゃう方がいると、惜しいなぁ・・・と。
とはいえ、当時はCM等で使われたりもして、一般的認知度はソコソコあった・・・んじゃないかな。
メタル側からしか見てなかったからワカンナイんだけどね。
基本的にはキャッチーなハードロック・・・いや、ハードポップってとこかな。
その中で、アコースティックな面ではカントリーっぽいムードも醸しだしていますね。
「カントリー」というとメタル的視点ではいい表現ではないかもしれませんが・・・・このカラリとしたムードはアメリカンハードの一つの魅力かな、と思うんだ。
・・・と、音楽性だけ見れば魅力タップリなんですが・・・。
あれだけの美貌、そして甘いメロディ・・・・そりゃレコード会社もその路線でプッシュしたいわけですよ。
2ndでは、その路線を強調したアルバムだったわけですが、インパクトはやや薄く・・・。
そして世の中はグランジブームに沸き上がり、その時流に飲み込まれ・・・
忘れた頃にリリースした3rd~4thは、ややヘヴィな路線で話題に登らず・・・良作なんだけど、その印象とのギャップとか世間とのタイミングとかね。
なんだかその見た目が故に振り回された不幸な兄弟・・・という印象が強いのです。
だからこそ、この1stはメロディアスハードが好きな方には是非聞いてほしい。名作ですよ。
Nelson - After the Rain (「らしさ」全開の名曲)
Nelson - Only Time Will Tell (感動の名バラード)
Too Many Dreams (たしか焼酎のCM曲)
type=
2010年02月03日
白銀を背に
2月になった。
2月って、1月の「お正月から一気に駆け抜ける感」も落ち着いて、一番冷たい印象のある月だ。
「白銀」ってコトバが似合う月だと思うのだ。
そんな季節には、やっぱり北欧だ。
ジャケットのムードもピッタリなこのバンドで2月のスタートを切ってみたらどうでしょうかね。
NORTHER [MIRROR OF MADNESS]

フィンランド出身のメロディックデスメタルバンド。
メロディック「デスメタル」といっても、これはデスメタルではないな。ワタシの位置づけでは。
キラキラとした疾走感にデスヴォイスが乗るスタイルは、否応にも初期CHILDREN OF BODOMを想起します。
しかし、ヘタすりゃ SONATA ARCTICA にも通じるメロディックなサウンドは CHILDREN OF BODOM が備え持つ慟哭や残虐性とは一線を画します。
このあたりを「メロデスにしては軽い」と見るか、「メロディックメタルファンにもアピールするサウンド」と見るかで評価が分かれるところでしょうか。
ワタシはですね。
最近のストロングスタイルなチルボドもいいけど、初期のメロディックで適度に明朗軽快なチルボドも好きなヒトなので、結構好意的に受け止めてますよ。
っつーか、ココまでメロディックだとデス声じゃなくていいじゃん! という葛藤はあるわけですが・・・。
全編を覆うクリアでありながら凛々しく張りつめた空気は、まさに白銀の世界。
ストレートながらも物悲しく紡がれるリフは、北欧メロデス直系。
ヴォーカルは・・・いまひとつコレ!という個性に乏しい気がしますが、クセのないデス声とでもいいましょうか。悪くありません。
もう一つ、何か突き抜けるモノが欲しい気がしなくもないですが、メロデスとメロパワの最大公約数的サウンドと考えれば充分でしょうかね。
Norther- Mirror of Madness
2月って、1月の「お正月から一気に駆け抜ける感」も落ち着いて、一番冷たい印象のある月だ。
「白銀」ってコトバが似合う月だと思うのだ。
そんな季節には、やっぱり北欧だ。
ジャケットのムードもピッタリなこのバンドで2月のスタートを切ってみたらどうでしょうかね。
NORTHER [MIRROR OF MADNESS]

フィンランド出身のメロディックデスメタルバンド。
メロディック「デスメタル」といっても、これはデスメタルではないな。ワタシの位置づけでは。
キラキラとした疾走感にデスヴォイスが乗るスタイルは、否応にも初期CHILDREN OF BODOMを想起します。
しかし、ヘタすりゃ SONATA ARCTICA にも通じるメロディックなサウンドは CHILDREN OF BODOM が備え持つ慟哭や残虐性とは一線を画します。
このあたりを「メロデスにしては軽い」と見るか、「メロディックメタルファンにもアピールするサウンド」と見るかで評価が分かれるところでしょうか。
ワタシはですね。
最近のストロングスタイルなチルボドもいいけど、初期のメロディックで適度に明朗軽快なチルボドも好きなヒトなので、結構好意的に受け止めてますよ。
っつーか、ココまでメロディックだとデス声じゃなくていいじゃん! という葛藤はあるわけですが・・・。
全編を覆うクリアでありながら凛々しく張りつめた空気は、まさに白銀の世界。
ストレートながらも物悲しく紡がれるリフは、北欧メロデス直系。
ヴォーカルは・・・いまひとつコレ!という個性に乏しい気がしますが、クセのないデス声とでもいいましょうか。悪くありません。
もう一つ、何か突き抜けるモノが欲しい気がしなくもないですが、メロデスとメロパワの最大公約数的サウンドと考えれば充分でしょうかね。
Norther- Mirror of Madness
2008年11月20日
狂気の構造
狸於さんオススメのバンドらしい。
恥ずかしながら、名前は知ってたけど聴いたことがなかった。
イザ聴いてみたら、ワタシは数々誤解していたことが分かった。
NEVERMORE [This Godless Endeavor]

一聴して「狂気」という言葉が脳裏をよぎった。
全くジャンルは違うんだけど、初期のDestructionが思い浮かんだ。
時に混沌、時に繊細な世界。
暗黒的重苦しさと同居する鋭利で危険なニオイ。
時にスラッシーであり、デスメタル的でもあり、テクニカルでもある。
「●●っぽい」っていう表現が難しいサウンドは、NEVERMOREのオリジナリティとして確立しているようです。
ハマれば中毒性が高いですが、ちょっと聞き手を選ぶんじゃないかなと思います。
割と単純なメロディックスピードメタルや哀愁のメロディックハード、直球勝負のスラッシュ/メロデスが人気のある日本よりも、欧州で人気があるってのは納得です。
で、勝手に「欧州産のベテラン、ドイツ出身」ってなイメージを持っていたワタシ。
wikiで見てみたら。
「アメリカ、シアトル出身」(!)
「元SANCTUARYのメンバーが中心となった」(!!)
「ARCH ENEMYのマイケルアモットが影響された」(!!!)
元メンバーには
脱退後にCANNIBAL CORPSEに加入した人(!)
元FORBIDDENの人(!!)
元TESTAMENTの人(!!!)
おいおい、アメリカ出身で、しかも元SANCTUARY。
で、関係したヒトたちはツワモノ揃い。
狂気の世界を支える屋台骨はガッシリドッシリとしたスキルにシッカリと支えられているのだ。
恥ずかしながら、名前は知ってたけど聴いたことがなかった。
イザ聴いてみたら、ワタシは数々誤解していたことが分かった。
NEVERMORE [This Godless Endeavor]

一聴して「狂気」という言葉が脳裏をよぎった。
全くジャンルは違うんだけど、初期のDestructionが思い浮かんだ。
時に混沌、時に繊細な世界。
暗黒的重苦しさと同居する鋭利で危険なニオイ。
時にスラッシーであり、デスメタル的でもあり、テクニカルでもある。
「●●っぽい」っていう表現が難しいサウンドは、NEVERMOREのオリジナリティとして確立しているようです。
ハマれば中毒性が高いですが、ちょっと聞き手を選ぶんじゃないかなと思います。
割と単純なメロディックスピードメタルや哀愁のメロディックハード、直球勝負のスラッシュ/メロデスが人気のある日本よりも、欧州で人気があるってのは納得です。
で、勝手に「欧州産のベテラン、ドイツ出身」ってなイメージを持っていたワタシ。
wikiで見てみたら。
「アメリカ、シアトル出身」(!)
「元SANCTUARYのメンバーが中心となった」(!!)
「ARCH ENEMYのマイケルアモットが影響された」(!!!)
元メンバーには
脱退後にCANNIBAL CORPSEに加入した人(!)
元FORBIDDENの人(!!)
元TESTAMENTの人(!!!)
おいおい、アメリカ出身で、しかも元SANCTUARY。
で、関係したヒトたちはツワモノ揃い。
狂気の世界を支える屋台骨はガッシリドッシリとしたスキルにシッカリと支えられているのだ。
2008年06月05日
ラテンの血
梅雨入りしました。
この季節になると、いつも思い出すアルバムがあります。
いつも思い出してもなかなか引っ張りださないんだけど、たまたま事故ってクルマと一緒にCDケースも「入院中」なので、ラックを覗いていて引っ張りだした。
Nuclear Valdez [ I AM I ]

なんというか、不思議なアルバムなのです。
改めてライナーノーツを見てたら、メンバーはドミニカとかキューバの移民の血統なんだって。
どうりで…。
基本的には哀愁溢れるハードロックなのですが、メンバーの血統もあってかラテンの空気を孕んでいます。
だからでしょうか。
ブルージーでありながら情熱的。
カラッとしていつつウェットで憂いを持ったメロディ。
土着的でありながらアメリカンハードロックのそれとは一線を画した、ネイティブアメリカンな空気。
梅雨の雨上がりの日差しとか。
夏の夕立の後の熱気を帯びたアスファルトの匂いとか。
そんなときに脳裏をよぎるのが、一曲目に収録の [Summer] です。
音楽性が個性的なのもありますが、なによりも曲のフックがスゴい。
この情熱的なサウンドが耳をとらえて離さないのです。
しかも、後を引くんです。
数年、いや、十数年経っても全く色褪せることなく訴え掛けてくるチカラがあるんです。
自分の中で「名盤○選」って選んでもなかなか浮かんで来ないアルバムなんだけど、鮮烈な印象を残した「裏名盤」なのです。
この季節になると、いつも思い出すアルバムがあります。
いつも思い出してもなかなか引っ張りださないんだけど、たまたま事故ってクルマと一緒にCDケースも「入院中」なので、ラックを覗いていて引っ張りだした。
Nuclear Valdez [ I AM I ]
なんというか、不思議なアルバムなのです。
改めてライナーノーツを見てたら、メンバーはドミニカとかキューバの移民の血統なんだって。
どうりで…。
基本的には哀愁溢れるハードロックなのですが、メンバーの血統もあってかラテンの空気を孕んでいます。
だからでしょうか。
ブルージーでありながら情熱的。
カラッとしていつつウェットで憂いを持ったメロディ。
土着的でありながらアメリカンハードロックのそれとは一線を画した、ネイティブアメリカンな空気。
梅雨の雨上がりの日差しとか。
夏の夕立の後の熱気を帯びたアスファルトの匂いとか。
そんなときに脳裏をよぎるのが、一曲目に収録の [Summer] です。
音楽性が個性的なのもありますが、なによりも曲のフックがスゴい。
この情熱的なサウンドが耳をとらえて離さないのです。
しかも、後を引くんです。
数年、いや、十数年経っても全く色褪せることなく訴え掛けてくるチカラがあるんです。
自分の中で「名盤○選」って選んでもなかなか浮かんで来ないアルバムなんだけど、鮮烈な印象を残した「裏名盤」なのです。
2006年12月18日
雪→北欧?
雪が積もりましたね。
仕事の都合で既に11月下旬にはタイヤ交換を済ませていたため、それほどあわてることはないものの
これから先、積雪~圧雪~チェーンでガタガタの国道(酷道?)の状況を思うと憂鬱です。
雪が積もり白銀の世界になると、雪→極寒→北極→北欧。(短絡的ですが…)
「北欧メタル」というジャンルは以前から確立されており、EUROPE、TNT、PRETTYMAIDS等が思い出されますが、このキンと冷えた空気と静けさで思い出すアルバムといえば…。
フィンランドで国民的人気を誇る
[ NIGHTWISH / Oceanborn ]

もともと、北欧というと白夜やオーロラ等で神秘的、ミステリアスなイメージがあります。
それを地でいくかのような美しくクラシカルな楽曲達は、フィンランドの空気を伝えてくれるかのようです。
それに絡むターヤ嬢のオペラティックな声、キーボードのキラキラした旋律。
特にターヤ嬢の声は、唯一無二の存在感を示しています。この声を受け入れられるかは個人差がありそうですが。
(残念ながら、最近脱退しましたが…)
このアルバム以降のフィンランド内での人気は凄まじいらしく…。
次のアルバムでは初登場1位(3週連続)→ゴールドディスク
さらに次では、初日2時間でゴールドディスク
他では、THE RASMUS/CHILDREN OF BODOM/KORPIKLAANIといった個性的なバンドもフィンランド。
やっぱりミステリアスな国だ。
仕事の都合で既に11月下旬にはタイヤ交換を済ませていたため、それほどあわてることはないものの
これから先、積雪~圧雪~チェーンでガタガタの国道(酷道?)の状況を思うと憂鬱です。
雪が積もり白銀の世界になると、雪→極寒→北極→北欧。(短絡的ですが…)
「北欧メタル」というジャンルは以前から確立されており、EUROPE、TNT、PRETTYMAIDS等が思い出されますが、このキンと冷えた空気と静けさで思い出すアルバムといえば…。
フィンランドで国民的人気を誇る
[ NIGHTWISH / Oceanborn ]

もともと、北欧というと白夜やオーロラ等で神秘的、ミステリアスなイメージがあります。
それを地でいくかのような美しくクラシカルな楽曲達は、フィンランドの空気を伝えてくれるかのようです。
それに絡むターヤ嬢のオペラティックな声、キーボードのキラキラした旋律。
特にターヤ嬢の声は、唯一無二の存在感を示しています。この声を受け入れられるかは個人差がありそうですが。
(残念ながら、最近脱退しましたが…)
このアルバム以降のフィンランド内での人気は凄まじいらしく…。
次のアルバムでは初登場1位(3週連続)→ゴールドディスク
さらに次では、初日2時間でゴールドディスク
他では、THE RASMUS/CHILDREN OF BODOM/KORPIKLAANIといった個性的なバンドもフィンランド。
やっぱりミステリアスな国だ。