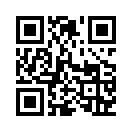ヘビメタパパの書斎 › 2016年03月
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2016年03月29日
映し出された「今」
名作に「続編」のようなナンバリングをすることはリスキーだなと思う。
その作品に思い入れがあるファンにとっては尚更。
最低でもそのライン、できればその上、その作品を下回るようだとその名作への侮辱にすら感じることもあるくらいだ。
(個人的思い入れにもよるかと思いますが)
SONATA ARCTICA / ECLIPTICA (REVISITED)

フィンランド出身、今となっては中堅どころとなったメロディックパワーメタルバンドですね。
‥といっても、彼ら自身は他のバンドとの十把一絡げを嫌ってか「メロスピじゃないから」と路線変更していますが。
彼らの1stアルバムは衝撃だった。
リリースは1999年。‥もう15年以上経ったのか。
いい意味での青臭さ。
トニー・カッコの適度に不安定なハイトーン。
まさに美旋律を「撒き散らす」といった勢いで走り抜ける疾走感。
B級メロディックスピードメタルの超新星現る、という驚きがあった。
そう、まさに「超新星」という言葉がピッタリだった。
その衝撃は、STRATOVARIUSの登場時を凌駕していた。
キラキラとした煌きは、その青臭さとの相乗効果で更なる儚さを生み出していた。
その儚さ、そして叩けば壊れるような繊細さ。
未熟が故に生まれたそのギリギリの美しさが緊張感を生み出していた。
今でも「SONATA ARCTICAといえば1st」という人は多いんじゃないかと思う。
その魅力がデビューアルバム[ECLIPTICA]には最初から最後まで貫かれていた。
時は流れ‥
アルバムとしては8枚。
年数としては15年。
その時を経て、その名作をリレコーディングするという。
冒頭にも触れた通り、非常にリスキーな選択だと思う。その「象徴」とも言えるアルバムを自ら焼き直すというのは。
個人的には、メロディックスピードメタルから離れていた彼らなりの「また戻ってくるからね」というメッセージとして受け取りたい。
が、このアルバムの完全再現ツアーをしたりすると「集金目的」というキーワードが脳裏をよぎらなくもない。
当然、彼ら自身は大きな存在になった。
ライブでも「貫祿が出てきたなー」と思わせてくれている。(セットリストはイマイチだが)
その成長した彼らが見せてくれた、自らの原点の再提示は‥
オープニングの[BLANK FILE]。
♪ダカダカダカダカダカダカダッ ジャージャッ
という力強いドラミングからのリフ。
このリフ1音だけでガッカリするファン、多いのではないでしょうか。
リフの音が下げられているのだ。
この1音、時間にして1秒ほどで「あー、もうこのアルバムの全貌が見えたよ‥」と思わせます。
実際、このリフから導かれて歌い始めるトニー・カッコは当時の青臭い姿ではなく、落ち着きと貫祿の声。
が、「‥違うんだよ」と切なさが漂います。
名曲[8TH COMMANDMENT]の強靱なリフと美しいキーボードの競演は当時の面影のままスケールアップした感があります。
この曲ではキーも原曲に近いこともあり、素直に「やっぱりカッコイイなー」と思わせてくれます。
「ラナウェイラナウェイラナウェイ」というコーラスがこのアルバムの象徴とも言える[FULLMOON]。
やはりサビでの「落ち着いてる感」が気になるところ。
これも名曲[UNOPENED]ですが、これまたやや違和感のあるキー加減。
そして個人的至高の名曲[DESTRUCTION PREVENTER]。
(やけに「名曲」いう言葉が乱舞してますが、ホントにそれだけの名曲揃いなのだ)
これも[BLANKFILE]と同様の違和感のあるスタート、その違和感を孕んだまま駆け抜けていきます。
一つの見せ場である「♪In The Center Of All Mankind~(オーマンカーーーーーイイン!!)」の叫びも控えめ。
「♪Your End Is At Hand, If They Blow~」 ジャジャジャジャージャジャジャッジャッジャッ 「フッッ!!!」の叫びもナシ。
さらには「♪オーオオオー」のシンガロングの元気のなさ。
‥と、こういった書き方をするといいところが無いように見えてしまいますが‥
改めて曲のクオリティの高さを再認識することはできます。
もし、SONATA ARCTICAを聞いたことがない方が聞くなら、こちらのほうがクセは少ないかもしれません。
そういう意味ではかなりマイルドな仕上がりとなっている、と言えるのではないでしょうか。
そして、悪い意味では「まるでカバーアルバムのよう」という現実離れした感触です。
が、逆に捉えれば現地味がなさすぎて「あの名作とは別物」と割り切ることができます。
酸味と爽やかさのスパークリングワインが、酸味も落ち着き、味もまろやかになったような。
(悪く言えば、「気が抜けた」ような)
ヤンチャしてた学生が留年しちゃって落ち着いちゃって居場所がなくなったような。
そんなアルバムです。
彼らの「今」を映し出すという意味では、一度触れておいてもいいかもしれません。
‥が、やっぱり1stは素晴らしかった。改めてそう思います。
Sonata Arctica - Destruction Preventer (もちろんオリジナルバージョン)
その作品に思い入れがあるファンにとっては尚更。
最低でもそのライン、できればその上、その作品を下回るようだとその名作への侮辱にすら感じることもあるくらいだ。
(個人的思い入れにもよるかと思いますが)
SONATA ARCTICA / ECLIPTICA (REVISITED)

フィンランド出身、今となっては中堅どころとなったメロディックパワーメタルバンドですね。
‥といっても、彼ら自身は他のバンドとの十把一絡げを嫌ってか「メロスピじゃないから」と路線変更していますが。
彼らの1stアルバムは衝撃だった。
リリースは1999年。‥もう15年以上経ったのか。
いい意味での青臭さ。
トニー・カッコの適度に不安定なハイトーン。
まさに美旋律を「撒き散らす」といった勢いで走り抜ける疾走感。
B級メロディックスピードメタルの超新星現る、という驚きがあった。
そう、まさに「超新星」という言葉がピッタリだった。
その衝撃は、STRATOVARIUSの登場時を凌駕していた。
キラキラとした煌きは、その青臭さとの相乗効果で更なる儚さを生み出していた。
その儚さ、そして叩けば壊れるような繊細さ。
未熟が故に生まれたそのギリギリの美しさが緊張感を生み出していた。
今でも「SONATA ARCTICAといえば1st」という人は多いんじゃないかと思う。
その魅力がデビューアルバム[ECLIPTICA]には最初から最後まで貫かれていた。
時は流れ‥
アルバムとしては8枚。
年数としては15年。
その時を経て、その名作をリレコーディングするという。
冒頭にも触れた通り、非常にリスキーな選択だと思う。その「象徴」とも言えるアルバムを自ら焼き直すというのは。
個人的には、メロディックスピードメタルから離れていた彼らなりの「また戻ってくるからね」というメッセージとして受け取りたい。
が、このアルバムの完全再現ツアーをしたりすると「集金目的」というキーワードが脳裏をよぎらなくもない。
当然、彼ら自身は大きな存在になった。
ライブでも「貫祿が出てきたなー」と思わせてくれている。(セットリストはイマイチだが)
その成長した彼らが見せてくれた、自らの原点の再提示は‥
オープニングの[BLANK FILE]。
♪ダカダカダカダカダカダカダッ ジャージャッ
という力強いドラミングからのリフ。
このリフ1音だけでガッカリするファン、多いのではないでしょうか。
リフの音が下げられているのだ。
この1音、時間にして1秒ほどで「あー、もうこのアルバムの全貌が見えたよ‥」と思わせます。
実際、このリフから導かれて歌い始めるトニー・カッコは当時の青臭い姿ではなく、落ち着きと貫祿の声。
が、「‥違うんだよ」と切なさが漂います。
名曲[8TH COMMANDMENT]の強靱なリフと美しいキーボードの競演は当時の面影のままスケールアップした感があります。
この曲ではキーも原曲に近いこともあり、素直に「やっぱりカッコイイなー」と思わせてくれます。
「ラナウェイラナウェイラナウェイ」というコーラスがこのアルバムの象徴とも言える[FULLMOON]。
やはりサビでの「落ち着いてる感」が気になるところ。
これも名曲[UNOPENED]ですが、これまたやや違和感のあるキー加減。
そして個人的至高の名曲[DESTRUCTION PREVENTER]。
(やけに「名曲」いう言葉が乱舞してますが、ホントにそれだけの名曲揃いなのだ)
これも[BLANKFILE]と同様の違和感のあるスタート、その違和感を孕んだまま駆け抜けていきます。
一つの見せ場である「♪In The Center Of All Mankind~(オーマンカーーーーーイイン!!)」の叫びも控えめ。
「♪Your End Is At Hand, If They Blow~」 ジャジャジャジャージャジャジャッジャッジャッ 「フッッ!!!」の叫びもナシ。
さらには「♪オーオオオー」のシンガロングの元気のなさ。
‥と、こういった書き方をするといいところが無いように見えてしまいますが‥
改めて曲のクオリティの高さを再認識することはできます。
もし、SONATA ARCTICAを聞いたことがない方が聞くなら、こちらのほうがクセは少ないかもしれません。
そういう意味ではかなりマイルドな仕上がりとなっている、と言えるのではないでしょうか。
そして、悪い意味では「まるでカバーアルバムのよう」という現実離れした感触です。
が、逆に捉えれば現地味がなさすぎて「あの名作とは別物」と割り切ることができます。
酸味と爽やかさのスパークリングワインが、酸味も落ち着き、味もまろやかになったような。
(悪く言えば、「気が抜けた」ような)
ヤンチャしてた学生が留年しちゃって落ち着いちゃって居場所がなくなったような。
そんなアルバムです。
彼らの「今」を映し出すという意味では、一度触れておいてもいいかもしれません。
‥が、やっぱり1stは素晴らしかった。改めてそう思います。
Sonata Arctica - Destruction Preventer (もちろんオリジナルバージョン)
2016年03月11日
新たな一歩
ホント、北欧という地域は懐が深い。
メロデスからキラキラ北欧メタルから、こういったキャッチーなバンドまで。
このバンドも、その北欧の若手の旗手と言ってもいいでしょう。
DYNAZTY [RENATUS]

スウェーデン出身。これが4thになるようですね。
もともとはキャッチー&ややグラマラス、そして北欧独特の憂いを帯びた‥という、THE POODLESやRECKLESS LOVEあたりに通じるムードを持っていた彼ら。
3rdまではその路線が中心でしたね。
この3rdまでのアルバムも素晴らしいので、またそのうち触れるとして‥
この4thアルバムで大きく化けました。
ポジティブに捉えればスケールアップしたとも言える。
ネガティブに捉えれば今までの魅力を消したとも言える。
捉え方によって賛否は分かれるところでしょう。
ワタシ個人としては音楽的路線でいえば3rdまでの方が好みだと思う。
が、この4th、そのスタイルチェンジについても有無を言わさす説き伏せるだけの説得力がある。
モダンかつヘヴィなリフ。
デジタルな装飾。
今までのファンにとってネガティブに受け取られるであろう要素を中心に組み立てていながら、しかし、そのメロディの質が素晴らしい。
骨太かつストロングに彩られた剛直なヘヴィメタルに、AMARANTHEあたりを思わせるキーボードの浮遊感。
そしてもともと持ち合わせたメロディセンスのバランスが絶妙なのだ。
一気に正統派ヘヴィメタル路線に舵を切りつつ、彼らの魅力は失っていない。
オープニングに配置された[CROSS THE LINE]。
3rdまでの彼らを知る人、そしてそのサウンドが好きだった人にとっては衝撃的であることが想像に難くありません。
淡々とザクザクと刻まれるモダンなリフ。ややダークなムード。
が、サビでは力強さとキャッチーさが顔を覗かせ、多少の安堵を覚えることになるでしょう。
続く[STARLIGHT]。このアルバムの象徴ともいえる曲でしょうか。
ヘヴィなリフは今までの彼らとは異なる個性を放っていますが、サビで一気に空間を開放し、その空間を彩り、飛翔していくかのようなスケールの大きさ。
「こんなことができたのか!」という驚きと、強烈なフックを伴うメロディが新しい彼らを印象づけていきます。
[DAWN OF YOUR CREATION]は、冒頭に例えたAMARANTHEに近いメロディでしょうか。
それでもサビでのドライヴ感はやはり彼らならでは。
[RUN AMOK]は、[STARLIGHT]と並んでこのアルバムのキラーチューン。
[STARLIGHT]と同系統、鮮やかに煌びやかな彩りの中を突き抜けていくような爽快感が漲ります。
このあたりのスペーシーな空間の構築は、このアルバムの特徴と言えるでしょう。
[SALVATION]はパワーメタルのような力強さを纏っています。
こういった曲も新しい顔といえるでしょうか。
といった具合に、今までの路線とは異なり、新たなスタートと言っても過言ではないかもしれません。
3rdまでの路線も素晴らしかったのですが、同郷および周辺国ではその路線のバンドは多く、そこに居すわるよりも新しい一歩を踏み出した、ということでしょうか。
が、その劇的な変化に失望したファンも多いかもしれません。
個人的にはどちらの路線も素晴らしいと思います。
そして、この新しい一歩から次の一歩へ進んでくれることを期待しています。
Dynazty - Starlight
メロデスからキラキラ北欧メタルから、こういったキャッチーなバンドまで。
このバンドも、その北欧の若手の旗手と言ってもいいでしょう。
DYNAZTY [RENATUS]

スウェーデン出身。これが4thになるようですね。
もともとはキャッチー&ややグラマラス、そして北欧独特の憂いを帯びた‥という、THE POODLESやRECKLESS LOVEあたりに通じるムードを持っていた彼ら。
3rdまではその路線が中心でしたね。
この3rdまでのアルバムも素晴らしいので、またそのうち触れるとして‥
この4thアルバムで大きく化けました。
ポジティブに捉えればスケールアップしたとも言える。
ネガティブに捉えれば今までの魅力を消したとも言える。
捉え方によって賛否は分かれるところでしょう。
ワタシ個人としては音楽的路線でいえば3rdまでの方が好みだと思う。
が、この4th、そのスタイルチェンジについても有無を言わさす説き伏せるだけの説得力がある。
モダンかつヘヴィなリフ。
デジタルな装飾。
今までのファンにとってネガティブに受け取られるであろう要素を中心に組み立てていながら、しかし、そのメロディの質が素晴らしい。
骨太かつストロングに彩られた剛直なヘヴィメタルに、AMARANTHEあたりを思わせるキーボードの浮遊感。
そしてもともと持ち合わせたメロディセンスのバランスが絶妙なのだ。
一気に正統派ヘヴィメタル路線に舵を切りつつ、彼らの魅力は失っていない。
オープニングに配置された[CROSS THE LINE]。
3rdまでの彼らを知る人、そしてそのサウンドが好きだった人にとっては衝撃的であることが想像に難くありません。
淡々とザクザクと刻まれるモダンなリフ。ややダークなムード。
が、サビでは力強さとキャッチーさが顔を覗かせ、多少の安堵を覚えることになるでしょう。
続く[STARLIGHT]。このアルバムの象徴ともいえる曲でしょうか。
ヘヴィなリフは今までの彼らとは異なる個性を放っていますが、サビで一気に空間を開放し、その空間を彩り、飛翔していくかのようなスケールの大きさ。
「こんなことができたのか!」という驚きと、強烈なフックを伴うメロディが新しい彼らを印象づけていきます。
[DAWN OF YOUR CREATION]は、冒頭に例えたAMARANTHEに近いメロディでしょうか。
それでもサビでのドライヴ感はやはり彼らならでは。
[RUN AMOK]は、[STARLIGHT]と並んでこのアルバムのキラーチューン。
[STARLIGHT]と同系統、鮮やかに煌びやかな彩りの中を突き抜けていくような爽快感が漲ります。
このあたりのスペーシーな空間の構築は、このアルバムの特徴と言えるでしょう。
[SALVATION]はパワーメタルのような力強さを纏っています。
こういった曲も新しい顔といえるでしょうか。
といった具合に、今までの路線とは異なり、新たなスタートと言っても過言ではないかもしれません。
3rdまでの路線も素晴らしかったのですが、同郷および周辺国ではその路線のバンドは多く、そこに居すわるよりも新しい一歩を踏み出した、ということでしょうか。
が、その劇的な変化に失望したファンも多いかもしれません。
個人的にはどちらの路線も素晴らしいと思います。
そして、この新しい一歩から次の一歩へ進んでくれることを期待しています。
Dynazty - Starlight