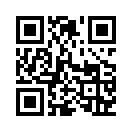ヘビメタパパの書斎 › H
スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2021年04月19日
一夜の夢の続き
私はこのバンドと共にハードロック・ヘヴィメタルを聞き続けてきました。
このバンドがいなければ、私の今はない。
そんな大切なバンドだからこそ、この大きな転換期には大きな思いがある。
HELLOWEEN [ SKYFALL ]

「ジャーマンメタル」の原点と言ってもいいでしょう。
いまさらながらWikiでアルバムを眺めてみると15枚もリリースしてますね。
そしてこの作品は歴代メンバーが集ってのシングルとなります。
いろいろな障壁を乗り越えて、たくさんのメンバーチェンジを乗り越えて、メンバーの死を乗り越えて。
音楽性が変わってもメンバーが変わっても、「どの時代の、どのアルバムも、どのメンバーも、それぞれに魅力的」と思えるのは決して私が盲目的なのではない。
それだけ私に浸透するサウンドをリリースし続けてくれているのだ。
私が最も敬愛するミュージシャンであるカイ・ハンセンがヴォーカルだった時代。
ハロウィンがハロウィンたる所以である「キーパーサウンド」を生み出したマイケル・キスク時代。
まさかの奇跡的科学融合を生み出したアンディ・デリス時代。
どの時代も大好きだ。
そして、(ここではオカネの話はしないことにして)若かりし頃のわだかまりをリセットし、奇跡の再集結となったPUMPKINS UNITED TOUR。
2018年4月。もう3年になりますね。
その夢の夜のあと、様々な憶測が飛び交った。
・もう一度ツアーをするらしい (コロナで吹っ飛びましたが‥)
・このメンバーでアルバムを作るらしい
まぁ、このツアーでずいぶん強烈な感触を得ただろうし、お祭りの続きでアルバムを作ることもあるだろうな‥と思ってはいました。
が、まさか‥このメンバーでPUMPKINS UNITED名義ではなくHELLOWEEN名義でのリリースとなるとは‥
現在の盛り上がりっぷりは、メタルファンみんなが諸手を挙げて歓喜に沸いている。
が、私は強い違和感を感じるのです。
大好きだからこそ、その思いは強いのです。
カイもキスケも大好きだけど、いまさらそんな思い出を掘り返すようなアルバム作らなくてもいい。
このメンバーならあくまでもハロウィンではなくPUMPKINS UNITEDで作ってほしかった。
充分に充実していたアンディのハロウィンの歩みを止めてしまうかのよう。
そんな違和感が拭いきれないのです。
その思いがモヤモヤする中リリースされたこの先行シングル。
カイ作曲。
10分越え。
もうね、この二点だけでワクワクとウキウキは頂点ですよ。
結局、ファンなんてチョロいもんですよ。
最初に通して聞いた感想としては、「カイがハロウィン向けに作ろうとすれば、このくらい朝飯前だな」という感じ。
このいかにも「ジャーマンメタル然」としたサウンドは、彼のGAMMA RAYでは敢えて封印していたと思える路線。
GAMMA RAYでは、カイの才能が枯渇したのではなく常にチャレンジしていたのだと改めて感じさせてくれます。
そして興味深いのはバンドとしての大きな過渡期であり賛否両論だった[Pink Bubbles Go Ape]~[Chameleon]期。
そしてオリジナルメンバーでありずっとバンドを支えたヴァイキーが「好きではない」と語る[The Dark Ride]。
このあたりの風味が強いこと。
その風味の中にカイはいなかったこと。
カイが、自身が脱退したあとのバンドへのリスペクト、今改めてその時代を俯瞰して作り上げた‥と考えるのは考えすぎでしょうか。
王道ジャーマンメタルであり、サビ前のポジティブさ、サビでの高揚感。
ソリッドなパワーメタルサウンドの中に内包された暖かさと自由。
そして、長い時代を駆け抜けてきたツワモノならではの余裕と風格。
これだけの曲であっても「まだまだ。全然」と笑っている彼らの顔が浮かぶのです。
決して単なる「原点回帰」ではない。
どの時代の薫りも漂わせつつ、どの時代とも異なる。
今の彼らを象徴する素晴らしい曲になっています。
そして意外と(というと失礼ですが)カイのヴォーカルパートが多いのも嬉しい。
三者三様。
カイの声で「あぁ、カイだなぁ(歓喜)」
キスケの声で「あぁ、キスケだなぁ(恍惚)」
アンディの声で「あぁ、アンディだなぁ(安堵)」
どの時代も、どの声も大好きだから、そりゃどのパートも魅力的だ。
:
:
:
と、結局は私も諸手を挙げて喜んでいるかのようですが(喜んでいるのですが)・・。
やはり私は今回の「HELLOWEEN」としてのリリースにはモヤモヤしたものは残る。
このメンバーで続けるつもりなのか。
一作限りなのか。
このアルバムのツアーはUNITEDではなくHELLOWEEN名義なのか。
一夜の夢の続き。
南瓜の未来は何を映し出すのか。
その違和感を抱えたまま、アルバムリリースと対峙します。
HELLOWEEN - Skyfall (Single Edit) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
※シングルエディットだから短めです。
このバンドがいなければ、私の今はない。
そんな大切なバンドだからこそ、この大きな転換期には大きな思いがある。
HELLOWEEN [ SKYFALL ]

「ジャーマンメタル」の原点と言ってもいいでしょう。
いまさらながらWikiでアルバムを眺めてみると15枚もリリースしてますね。
そしてこの作品は歴代メンバーが集ってのシングルとなります。
いろいろな障壁を乗り越えて、たくさんのメンバーチェンジを乗り越えて、メンバーの死を乗り越えて。
音楽性が変わってもメンバーが変わっても、「どの時代の、どのアルバムも、どのメンバーも、それぞれに魅力的」と思えるのは決して私が盲目的なのではない。
それだけ私に浸透するサウンドをリリースし続けてくれているのだ。
私が最も敬愛するミュージシャンであるカイ・ハンセンがヴォーカルだった時代。
ハロウィンがハロウィンたる所以である「キーパーサウンド」を生み出したマイケル・キスク時代。
まさかの奇跡的科学融合を生み出したアンディ・デリス時代。
どの時代も大好きだ。
そして、(ここではオカネの話はしないことにして)若かりし頃のわだかまりをリセットし、奇跡の再集結となったPUMPKINS UNITED TOUR。
2018年4月。もう3年になりますね。
その夢の夜のあと、様々な憶測が飛び交った。
・もう一度ツアーをするらしい (コロナで吹っ飛びましたが‥)
・このメンバーでアルバムを作るらしい
まぁ、このツアーでずいぶん強烈な感触を得ただろうし、お祭りの続きでアルバムを作ることもあるだろうな‥と思ってはいました。
が、まさか‥このメンバーでPUMPKINS UNITED名義ではなくHELLOWEEN名義でのリリースとなるとは‥
現在の盛り上がりっぷりは、メタルファンみんなが諸手を挙げて歓喜に沸いている。
が、私は強い違和感を感じるのです。
大好きだからこそ、その思いは強いのです。
カイもキスケも大好きだけど、いまさらそんな思い出を掘り返すようなアルバム作らなくてもいい。
このメンバーならあくまでもハロウィンではなくPUMPKINS UNITEDで作ってほしかった。
充分に充実していたアンディのハロウィンの歩みを止めてしまうかのよう。
そんな違和感が拭いきれないのです。
その思いがモヤモヤする中リリースされたこの先行シングル。
カイ作曲。
10分越え。
もうね、この二点だけでワクワクとウキウキは頂点ですよ。
結局、ファンなんてチョロいもんですよ。
最初に通して聞いた感想としては、「カイがハロウィン向けに作ろうとすれば、このくらい朝飯前だな」という感じ。
このいかにも「ジャーマンメタル然」としたサウンドは、彼のGAMMA RAYでは敢えて封印していたと思える路線。
GAMMA RAYでは、カイの才能が枯渇したのではなく常にチャレンジしていたのだと改めて感じさせてくれます。
そして興味深いのはバンドとしての大きな過渡期であり賛否両論だった[Pink Bubbles Go Ape]~[Chameleon]期。
そしてオリジナルメンバーでありずっとバンドを支えたヴァイキーが「好きではない」と語る[The Dark Ride]。
このあたりの風味が強いこと。
その風味の中にカイはいなかったこと。
カイが、自身が脱退したあとのバンドへのリスペクト、今改めてその時代を俯瞰して作り上げた‥と考えるのは考えすぎでしょうか。
王道ジャーマンメタルであり、サビ前のポジティブさ、サビでの高揚感。
ソリッドなパワーメタルサウンドの中に内包された暖かさと自由。
そして、長い時代を駆け抜けてきたツワモノならではの余裕と風格。
これだけの曲であっても「まだまだ。全然」と笑っている彼らの顔が浮かぶのです。
決して単なる「原点回帰」ではない。
どの時代の薫りも漂わせつつ、どの時代とも異なる。
今の彼らを象徴する素晴らしい曲になっています。
そして意外と(というと失礼ですが)カイのヴォーカルパートが多いのも嬉しい。
三者三様。
カイの声で「あぁ、カイだなぁ(歓喜)」
キスケの声で「あぁ、キスケだなぁ(恍惚)」
アンディの声で「あぁ、アンディだなぁ(安堵)」
どの時代も、どの声も大好きだから、そりゃどのパートも魅力的だ。
:
:
:
と、結局は私も諸手を挙げて喜んでいるかのようですが(喜んでいるのですが)・・。
やはり私は今回の「HELLOWEEN」としてのリリースにはモヤモヤしたものは残る。
このメンバーで続けるつもりなのか。
一作限りなのか。
このアルバムのツアーはUNITEDではなくHELLOWEEN名義なのか。
一夜の夢の続き。
南瓜の未来は何を映し出すのか。
その違和感を抱えたまま、アルバムリリースと対峙します。
HELLOWEEN - Skyfall (Single Edit) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
※シングルエディットだから短めです。
2018年01月11日
始祖の集大成
ずっと敬愛しているアーティスト‥とはいっても、方向性の変化によって違和感を抱くようになるのは仕方ないこと。
その違和感と不安、払拭してくれるでしょうか。
敬愛するカイ・ハンセンのソロアルバムがリリースされました。
Hansen & Friends [Three Decades In Metal]

[Three Decades]の言葉が表す通り、ハロウィンのメンバーとしてデビューしてから30周年の節目にリリースされたソロアルバム。
Helloween、Gamma Ray、Unisonic、そして現在は奇跡のPumpkins United‥と、バンドの遍歴を書くだけなら「へー」で終わってしまう。
が、Helloween脱退以降の紆余曲折、波瀾万丈、そして今。
思い入れのあるファンにとっては「よくここまできてくれたなぁ」と感慨深くなることでしょう。
以前にも書いたことがあるかもしれませんが、私がメタルにのめりこむキッカケになったのは、HELLOWEENの[Live in UK]との出会いが大きかった。
必然的に[Keeper of the Seven Keys]も聞き、一気に虜になった。
その頃のHelloweenは、私にとっては「カイ・ハンセンとマイケル・キスクのバンド」という認識だった。
ヴァイキーはむしろ「ハロウィンの分裂を招いた張本人」と大変失礼な思い込みをしていた。
そして「私をメタル界へ導いてくれたのはカイ」と強く思った気持ちはずっと変わらず、今でも大好きなアーティストだ。
Helloween脱退後、初期GammaRayではジャーマンメタルの理想の姿、カイが紡ぐメロディの理想の姿を提示してくれました。
が。
最近のGammaRayではそのジャーマンメタルスタイルが若干希薄に。
本人も言うように、シンプルにソリッドに、まるで彼の音楽的原点に回帰しようとしているかのようなシンプルなHMが多くなってきた。
それはそれでいいのだろう、とは思う。
が、やはり私は彼には「カイにしか書けない、いわゆるジャーマンメタル」を求めてしまう。
バンドという束縛から解き放たれた彼が見せるスタイル、どうなることでしょうか。
結論から言うと、やはり現在のGammaRay路線が基本軸になっているようです。
Helloween、初期GammaRayの「ジャーマンメタル」的要素は薄い。
が、多彩なゲストを招いていることもあって、Gamma Rayよりもサウンドも多彩な印象。
30周年という節目もあって、全体的に「お祭り」「仲良しが集まった同窓会」のような和気あいあいのムードが漂います。
ヴォーカルのカイの声は、相変わらず賛否両論(というか、圧倒的に「非」)でしょう。
いいのです。
私はカイの声が大好きだから。
以前と比べるとキレやパワーに衰えは隠せませんが、それでもいいのです。
唯一無二の個性を放つヴォーカルは、このアルバムでも健在です。
ラルフ・シーパース。
ピート・シールク。
トビアス・サメット。
ローランド・グラポウ。
マイケル・ヴァイカート。
ハンズィ・キアシュ。
まさに「盟友」たちの集い。
それぞれのメンバーと、それぞれの事情で袂を分けた経緯があったにも関わらず、これだけのメンバーが集ってアルバムが作られた。
その意味は大きいのではないでしょうか。
:
:
:
と、30周年記念のアルバムとして見たときには価値があると思うわけですが‥
単純に一枚のメタルアルバムとして見た場合。
Helloweenから始まった「ジャーマンメタル(いわゆる音楽的な意味で)」の始祖の一人として見た場合。
彼が書くメロディの虜になった身として見た場合。
ちょっと寂しいと言わざるを得ません。
そしてGamma Rayの今後についても「やっぱりこの路線なのかな‥」と思ってしまいます。
いや。
逆にソロアルバムという形で自分の思いを吐き出してくれれば、ファンがガンマレイ&カイに求める姿に立ち返ってくれる‥かも‥しれない。
自らのヴォーカルの負担を減らすために、ツインヴォーカルというスタイルでリスタートを切っているガンマレイ。
ソロアルバム、PumpkinsUnitedという「原点・過去」を見つめなおした機会を一つのステップに、次はどういった方向へ舵を切ってくれるでしょうか。
とりあえず私は春のPumpkinsUnitedでカイの姿、カイの声を目に焼き付けてきます。
私が愛した「カイ・ハンセンのHelloween」「カイ・ハンセンのジャーマンメタル」のために。
Hansen & Friends "Born Free" Official Music Video
その違和感と不安、払拭してくれるでしょうか。
敬愛するカイ・ハンセンのソロアルバムがリリースされました。
Hansen & Friends [Three Decades In Metal]

[Three Decades]の言葉が表す通り、ハロウィンのメンバーとしてデビューしてから30周年の節目にリリースされたソロアルバム。
Helloween、Gamma Ray、Unisonic、そして現在は奇跡のPumpkins United‥と、バンドの遍歴を書くだけなら「へー」で終わってしまう。
が、Helloween脱退以降の紆余曲折、波瀾万丈、そして今。
思い入れのあるファンにとっては「よくここまできてくれたなぁ」と感慨深くなることでしょう。
以前にも書いたことがあるかもしれませんが、私がメタルにのめりこむキッカケになったのは、HELLOWEENの[Live in UK]との出会いが大きかった。
必然的に[Keeper of the Seven Keys]も聞き、一気に虜になった。
その頃のHelloweenは、私にとっては「カイ・ハンセンとマイケル・キスクのバンド」という認識だった。
ヴァイキーはむしろ「ハロウィンの分裂を招いた張本人」と大変失礼な思い込みをしていた。
そして「私をメタル界へ導いてくれたのはカイ」と強く思った気持ちはずっと変わらず、今でも大好きなアーティストだ。
Helloween脱退後、初期GammaRayではジャーマンメタルの理想の姿、カイが紡ぐメロディの理想の姿を提示してくれました。
が。
最近のGammaRayではそのジャーマンメタルスタイルが若干希薄に。
本人も言うように、シンプルにソリッドに、まるで彼の音楽的原点に回帰しようとしているかのようなシンプルなHMが多くなってきた。
それはそれでいいのだろう、とは思う。
が、やはり私は彼には「カイにしか書けない、いわゆるジャーマンメタル」を求めてしまう。
バンドという束縛から解き放たれた彼が見せるスタイル、どうなることでしょうか。
結論から言うと、やはり現在のGammaRay路線が基本軸になっているようです。
Helloween、初期GammaRayの「ジャーマンメタル」的要素は薄い。
が、多彩なゲストを招いていることもあって、Gamma Rayよりもサウンドも多彩な印象。
30周年という節目もあって、全体的に「お祭り」「仲良しが集まった同窓会」のような和気あいあいのムードが漂います。
ヴォーカルのカイの声は、相変わらず賛否両論(というか、圧倒的に「非」)でしょう。
いいのです。
私はカイの声が大好きだから。
以前と比べるとキレやパワーに衰えは隠せませんが、それでもいいのです。
唯一無二の個性を放つヴォーカルは、このアルバムでも健在です。
ラルフ・シーパース。
ピート・シールク。
トビアス・サメット。
ローランド・グラポウ。
マイケル・ヴァイカート。
ハンズィ・キアシュ。
まさに「盟友」たちの集い。
それぞれのメンバーと、それぞれの事情で袂を分けた経緯があったにも関わらず、これだけのメンバーが集ってアルバムが作られた。
その意味は大きいのではないでしょうか。
:
:
:
と、30周年記念のアルバムとして見たときには価値があると思うわけですが‥
単純に一枚のメタルアルバムとして見た場合。
Helloweenから始まった「ジャーマンメタル(いわゆる音楽的な意味で)」の始祖の一人として見た場合。
彼が書くメロディの虜になった身として見た場合。
ちょっと寂しいと言わざるを得ません。
そしてGamma Rayの今後についても「やっぱりこの路線なのかな‥」と思ってしまいます。
いや。
逆にソロアルバムという形で自分の思いを吐き出してくれれば、ファンがガンマレイ&カイに求める姿に立ち返ってくれる‥かも‥しれない。
自らのヴォーカルの負担を減らすために、ツインヴォーカルというスタイルでリスタートを切っているガンマレイ。
ソロアルバム、PumpkinsUnitedという「原点・過去」を見つめなおした機会を一つのステップに、次はどういった方向へ舵を切ってくれるでしょうか。
とりあえず私は春のPumpkinsUnitedでカイの姿、カイの声を目に焼き付けてきます。
私が愛した「カイ・ハンセンのHelloween」「カイ・ハンセンのジャーマンメタル」のために。
Hansen & Friends "Born Free" Official Music Video
2016年01月08日
スタートダッシュ!
さて、2016年が始まりましたね。
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
今年もユルく続けていけたらいいなーと思ってますので、よろしくおつきあいいただけると嬉しく思いますよ。
ということで、新年一つ目になりますね。
こういった節目というか新しい何かが始まるとき、これからだぞ、ってとき、聞きたくなる曲ってありますよね。
スタートダッシュにふさわしい曲。
私にとって、そういう節目に外せない曲が収録されているアルバムを。
HELLOWEEN / The Time of the Oath

ハロウィンについては、このブログを訪れてくださる方々には説明不要かと思いますが‥
ドイツ出身、メロディックパワーメタルの礎を築いたバンドであり、ジャーマンメタルの始祖とも言えるバンドですね。
バンドとしては7枚目になりますか。
そして大きな節目となったアンディ・デリス加入後としては2枚目。
リリースは1996年。ちょうど20年ですか‥このアルバムと一緒に産声を上げた子供たちは成人式ですよ。感慨深いですね。
死に体と化していたバンドが、その音楽性の象徴ともいえた声のマイケル・キスクを袂を分かち、まさかの全く違うタイプの、しかも別のバンドで活躍していたフロントマンであるアンディ・デリスを迎え入れた前作。
多くのファンが「もうダメかな」と思い、そのメンバーチェンジに言葉を失い‥
しかし、まさかの起死回生となったのが前作[MASTER OF THE RINGS]。
[MASTER OF THE RINGS]は、マイケル・ヴァイカートが過去のしがらみを振り切り、そこにアンディ・デリスという希有なメロディメーカーが新風を吹き込んだ奇跡だった。
全く音楽性が異なる二人がここまでミラクルな相乗効果を見せてくれるとは誰が想像したでしょうか。
とはいえ、初期カイ・ハンセン時代~その後のマイケル・キスク時代のザラザラした鋭利なスピード感こそがHELLOWEENだった。という人にとってはもう別のバンドになってしまったかもしれません。
私はアンディが在籍していたPINKCREAM69も大好きだったから、その魅力が存分に生かされたことに震えるような興奮を覚えました。
そして‥
その奇跡からの真価が問われるアルバムでしょうか。
全体像としては、アンディ色が強かった[MASTER OF THE RINGS]から、ややシリアスなムードを取り戻し、現在のパワーバランスが構築されたという意味では、現在のHELLOWEENを形成したアルバムと言えるでしょうか。
[MASTER OF THE RINGS]と[THE TIME OF THE OATH]、兄弟のようでもあり、写し鏡のようであり、一つの対になっているようでありながら、それぞれ映し出す姿は微妙に異なる。
だからといってアンディとヴァイキーのバランスが崩れることはない。
この二人の異なるメロディメーカーのバランスが保たれていることが、この後のHELLOWEENの基本であり、強固な安心感に結びついています。
PINKCREAM69時代からのファンにとっては違和感があったであろう、まさに熱く燃えるようなパワーチューン[WE BURN]。
このヘヴィメタリックな質感はアンディ・デリスにとっては新しい挑戦ですが、この後のアルバムではこういったメタリックなチューンも多く産まれました。
これがアンディのペンによるもの、ということも驚きであり、その懐の深さを感じます。
ヴァイキーがアンディの声をイメージして曲を書くと、こんな感じになるんだろな、という[STEEL TORMENTOR]。
心地よい疾走感はHELLOWEENそのものでありながら、やはりアンディが歌うことで「今」の姿を映し出しています。
キャッチーな[WAKE UP THE MOUNTAIN]。こういった曲が違和感なく溶け込むのもアンディ加入後ならではでしょうか。
が、間奏でのギターソロは実に強靱で、初期HELLOWEENの息吹を最も感じる瞬間と言えるかもしれません。
スピード感と繊細さが同居する[BEFORE THE WAR]。これもアンディ作ですね。美しいギターハーモニーも聞きどころ。
いかにもヴァイキー、な[KING WILL BE KINGS]。
以前のHELLOWEENでは考えられなかったようなポップなチューン[ANYTHING MAMA DON'T LIKE]はPINKCREAM69時代からの流れを汲んでおり‥というか、PC69のアルバムに入っていても違和感がない曲ですね。
そしてなんといっても、このアルバムの象徴であり、アンディ期のHELLOWEENの象徴であり、私の元気の源でもある[POWER]。
冒頭に書いた通り、「これからだな」というときに聞きたくなる曲、スタートダッシュにふさわしい曲。
ポジティブなメロディ、漲ってくるガッツ、ライブでのコーラス。
この名曲はヴァイキー作。
[MASTER OF THE RINGS]と[THE TIME OF THE OATH]では、実にヴァイキーは器用だな、と痛感します。
そして、どんな方向性でも「やっぱりHELLOWEEN」という刻印を刻み続けているのはすごいことだなと感じます。
正直に言うと、私はカイ・ハンセンが大好きだったし、今も大好きだ。
そしてマイケル・キスクも当然大好きだった。
HELLOWEENの音楽はこの二人によって支えられていたと思っていたし、この二人が脱退したのはヴァイキーのせいだと思っていた。
だから、どちらかというと「カイがいなくなって何ができるんだよ」って思っていた。
が、この2枚のアルバムでその考えは完全に消えた。
「ヴァイキーこそがHELLOWEEN!!」などと声高に叫ぶつもりもないが、ヴァイキーの柔軟なセンス(アンディを選んだことも含めて)がHELLOWEENを蘇らせた。
この後、さらにバラエティに富んだ作品を生み出し、それでもHELLOWEENであり続けている。
どんどん横方向の視野を拡げていったマイケル・ヴァイカート。
逆に、どんどん自分の信じる音楽を掘り下げて縦方向へ突進していったカイ・ハンセン。
どちらもそれぞれの魅力で新しい音楽を生み出してくれた。
そして、アンディ・デリスが抜けてしまったPINKCREAM69も生まれ変わって素晴らしい音楽を生み出してくれている。
さらには、一度メタル界から離れたマイケル・キスクもリフレッシュして表舞台に帰って来た。
サビついていた歯車は、この英断によって少しづつ動き始め、そして大きな歯車になってドイツの音楽シーンを支えてくれている。
まさに奇跡であり、今に至る道しるべが明確に示され、大きな未来を確信することとなったアルバムです。
HELLOWEEN - Power
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
今年もユルく続けていけたらいいなーと思ってますので、よろしくおつきあいいただけると嬉しく思いますよ。
ということで、新年一つ目になりますね。
こういった節目というか新しい何かが始まるとき、これからだぞ、ってとき、聞きたくなる曲ってありますよね。
スタートダッシュにふさわしい曲。
私にとって、そういう節目に外せない曲が収録されているアルバムを。
HELLOWEEN / The Time of the Oath

ハロウィンについては、このブログを訪れてくださる方々には説明不要かと思いますが‥
ドイツ出身、メロディックパワーメタルの礎を築いたバンドであり、ジャーマンメタルの始祖とも言えるバンドですね。
バンドとしては7枚目になりますか。
そして大きな節目となったアンディ・デリス加入後としては2枚目。
リリースは1996年。ちょうど20年ですか‥このアルバムと一緒に産声を上げた子供たちは成人式ですよ。感慨深いですね。
死に体と化していたバンドが、その音楽性の象徴ともいえた声のマイケル・キスクを袂を分かち、まさかの全く違うタイプの、しかも別のバンドで活躍していたフロントマンであるアンディ・デリスを迎え入れた前作。
多くのファンが「もうダメかな」と思い、そのメンバーチェンジに言葉を失い‥
しかし、まさかの起死回生となったのが前作[MASTER OF THE RINGS]。
[MASTER OF THE RINGS]は、マイケル・ヴァイカートが過去のしがらみを振り切り、そこにアンディ・デリスという希有なメロディメーカーが新風を吹き込んだ奇跡だった。
全く音楽性が異なる二人がここまでミラクルな相乗効果を見せてくれるとは誰が想像したでしょうか。
とはいえ、初期カイ・ハンセン時代~その後のマイケル・キスク時代のザラザラした鋭利なスピード感こそがHELLOWEENだった。という人にとってはもう別のバンドになってしまったかもしれません。
私はアンディが在籍していたPINKCREAM69も大好きだったから、その魅力が存分に生かされたことに震えるような興奮を覚えました。
そして‥
その奇跡からの真価が問われるアルバムでしょうか。
全体像としては、アンディ色が強かった[MASTER OF THE RINGS]から、ややシリアスなムードを取り戻し、現在のパワーバランスが構築されたという意味では、現在のHELLOWEENを形成したアルバムと言えるでしょうか。
[MASTER OF THE RINGS]と[THE TIME OF THE OATH]、兄弟のようでもあり、写し鏡のようであり、一つの対になっているようでありながら、それぞれ映し出す姿は微妙に異なる。
だからといってアンディとヴァイキーのバランスが崩れることはない。
この二人の異なるメロディメーカーのバランスが保たれていることが、この後のHELLOWEENの基本であり、強固な安心感に結びついています。
PINKCREAM69時代からのファンにとっては違和感があったであろう、まさに熱く燃えるようなパワーチューン[WE BURN]。
このヘヴィメタリックな質感はアンディ・デリスにとっては新しい挑戦ですが、この後のアルバムではこういったメタリックなチューンも多く産まれました。
これがアンディのペンによるもの、ということも驚きであり、その懐の深さを感じます。
ヴァイキーがアンディの声をイメージして曲を書くと、こんな感じになるんだろな、という[STEEL TORMENTOR]。
心地よい疾走感はHELLOWEENそのものでありながら、やはりアンディが歌うことで「今」の姿を映し出しています。
キャッチーな[WAKE UP THE MOUNTAIN]。こういった曲が違和感なく溶け込むのもアンディ加入後ならではでしょうか。
が、間奏でのギターソロは実に強靱で、初期HELLOWEENの息吹を最も感じる瞬間と言えるかもしれません。
スピード感と繊細さが同居する[BEFORE THE WAR]。これもアンディ作ですね。美しいギターハーモニーも聞きどころ。
いかにもヴァイキー、な[KING WILL BE KINGS]。
以前のHELLOWEENでは考えられなかったようなポップなチューン[ANYTHING MAMA DON'T LIKE]はPINKCREAM69時代からの流れを汲んでおり‥というか、PC69のアルバムに入っていても違和感がない曲ですね。
そしてなんといっても、このアルバムの象徴であり、アンディ期のHELLOWEENの象徴であり、私の元気の源でもある[POWER]。
冒頭に書いた通り、「これからだな」というときに聞きたくなる曲、スタートダッシュにふさわしい曲。
ポジティブなメロディ、漲ってくるガッツ、ライブでのコーラス。
この名曲はヴァイキー作。
[MASTER OF THE RINGS]と[THE TIME OF THE OATH]では、実にヴァイキーは器用だな、と痛感します。
そして、どんな方向性でも「やっぱりHELLOWEEN」という刻印を刻み続けているのはすごいことだなと感じます。
正直に言うと、私はカイ・ハンセンが大好きだったし、今も大好きだ。
そしてマイケル・キスクも当然大好きだった。
HELLOWEENの音楽はこの二人によって支えられていたと思っていたし、この二人が脱退したのはヴァイキーのせいだと思っていた。
だから、どちらかというと「カイがいなくなって何ができるんだよ」って思っていた。
が、この2枚のアルバムでその考えは完全に消えた。
「ヴァイキーこそがHELLOWEEN!!」などと声高に叫ぶつもりもないが、ヴァイキーの柔軟なセンス(アンディを選んだことも含めて)がHELLOWEENを蘇らせた。
この後、さらにバラエティに富んだ作品を生み出し、それでもHELLOWEENであり続けている。
どんどん横方向の視野を拡げていったマイケル・ヴァイカート。
逆に、どんどん自分の信じる音楽を掘り下げて縦方向へ突進していったカイ・ハンセン。
どちらもそれぞれの魅力で新しい音楽を生み出してくれた。
そして、アンディ・デリスが抜けてしまったPINKCREAM69も生まれ変わって素晴らしい音楽を生み出してくれている。
さらには、一度メタル界から離れたマイケル・キスクもリフレッシュして表舞台に帰って来た。
サビついていた歯車は、この英断によって少しづつ動き始め、そして大きな歯車になってドイツの音楽シーンを支えてくれている。
まさに奇跡であり、今に至る道しるべが明確に示され、大きな未来を確信することとなったアルバムです。
HELLOWEEN - Power
2015年07月22日
南瓜品質
「ジャーマンメタルの始祖」と言ってもいいでしょうね。
そして紆余曲折あったものの、今も「伝統」を守っている。
すっかりベテランの域に入った彼らの新作は…
HELLOWEEN [My God-Given Right]

ドイツの大御所。wikiによるとこれが15枚目。
一大革命を起こした守護神伝シリーズから数えて28年。
そしてアンディ・デリスが加入して21年。(←ココに驚きますね)
最近成人式を迎えたコたちが産声を上げたときには、すでにアンディ・デリスだったわけですよ。
まぁ、彼らの音楽性については今更触れる必要もない。(←といいつつ、触れますが)
カイ・ハンセン & マイケル・ヴァイカートという稀代なメロディーメーカーによる、疾走感+ハイトーン+ツーバス+おおらかなサビ、アニソンにも通じる親しみやすいメロディ。
一つの「ジャーマンメタル」のフォーマットと言えますね。
その屋台骨だったカイ・ハンセンが脱退。
さらにそのメロディーを彩ったマイケル・キスクも脱退。
そして加入したのがPINKCREAM69のアンディ・デリス。
PINKCREAM69は大好きだったけど、それはないだろ…と落胆した人も多いはず(ワタシです)
彼の歌は大好きだけど、あくまでPC69だから素晴らしいのであってマイケル・キスクと比べると酷だろ…と落胆した人も多いはず(ワタシです)
しかし、まさかの相乗効果で名作[Master of the Rings]を生み出したのは記憶に新しいところ(といっても、21年経ちますが)
今となっては「HELLOWEEN = アンディ・デリス」という人も多いことでしょう。
ところどころで「問題作」と呼ばれる作品を挟みながらも、前作で実に「らしい」アルバムをリリースしてくれた彼ら。
今作品もその延長線にあるように感じます。
延長線上にありながらも、今作では各メンバーが作曲をバランスよく分散。
その各メンバーの個性が如実に表れている印象です。
特にアンディ・デリス作曲の存在感が際立っていますね。これは個人的嗜好もあって耳に馴染むから、という点はあるかと思いますが。
そう。ワタシはアンディ・デリスの曲が大好きだ。
PINKCREAM69時代からずっと大好きだ。
上述の奇跡の一枚[Master of the Rings]は、アンディ・デリスがいたから生まれた、そしてヴァイキー過去のHELLOWEENに拘ることなくアンディのメロディを受け入れたからこそ生まれた奇跡だと思う。
[Master of the Rings]は「これはアンディ・デリス with HELLOEENだな」と思ったくらいだ。
その「アンディ節」を満喫できるという意味では、その[Master of the Rings]に通じるのではないでしょうか。
(本編13曲中、共作も含めて7曲)
そして当然ですが、マイケル・ヴァイカートは「HELLOWEENとはこういう音楽」という信念と筋の通った楽曲で「らしさ」をアピールしてくれています。
やっぱりヴァイキーの「HELLOWEEN印」の曲がないと寂しいからね。
まさに安定の「金太郎飴」的メロディです。
そんな二人の存在感が際立つ中ですが、意外にもややヘヴィなリフで幕を開ける、サシャ・ゲルストナーによる[Heroes]。
サビはライブで盛り上がりそうなシンガロング系ですね。
こういったヘヴィな曲も、[THE DARK RIDE] や [7SINNERS]などを経て、それほど違和感がなくなってきましたね。
続いてヴァイキーによる[Battle’s Won]。まさにHELLOWEEN。まさにヴァイキー。
…といっても、マイケル・キスク時代のHELLOWEENのテイストとは微妙に異なる。アンディの歌うHELLOWEENの典型的、という曲だ。
そしてアンディによる[My God-Given Right]。Aメロ~Bメロの流れが涙が出るほどアンディだ。
彼のソロアルバムにあっても違和感ないようなメロディだ。
こういう曲がフィットしちゃうところにアンディが加入してすっかり地が固まってきてることを強く感じますね。
アンディの曲といえば、[If God Loves Rock'n'Roll]も素晴らしい。この曲のサビも「あー、アンディだよ!!」とニヤニヤしてしまいますね。
ヴァイキーも[Creatures In Heaven][Claws]あたりでもそのメロディセンスを十分に発揮。
これも一度聞くだけで「うん、ヴァイキーだな」と確信できる安定のクオリティです。
どうしてもアンディとヴァイキーの曲が際立つ&彼らの音楽が好きなので、サシャやマーカスの曲は「中休み」的印象になってしまいますね。
今作を聞いて、「実にチームバランスがとれている」「バンドの状態が良好なんだろうな」ということを感じました。
それぞれがそれぞれの個性を受け入れ、バンドの音して昇華させている感じがします。
これだけの個性がバラバラに存在しているにも関わらず、アルバムとしての一体感を感じるのです。
そしてその中心はやはりヴァイキーなんだろうな、と。
「HELLOWEENというブランド」はしっかり維持しつつ、アンディの曲や他メンバーの曲をバンドの音として吸収する。
そして自らもHELLOWEENらしさは守りつつ、カイ・ハンセン時代ともマイケル・キスク時代とも異なる音でそれを体現してくれる。
これって実はスゴいことだと思うのだ。
逆に言うと、初期HELLOWEENこそが至高であり、アンディ・デリスに今も馴染めない人にとっては今作は(今作も)「何か違うなー」と感じるかもしれない。
そしてアンディ・デリスは好きだけど、HELLOWEENで無理してハイトーンで歌ってる姿が痛々しい…と思っている方がいれば、今作は聞いてみてほしい。
実にアンディらしいメロディを堪能できるはずだから。
前作~今作ですっかり「安定」した感のあるHELLOWEEN。全く心配することない、安定のブランドです。
HELLOWEEN - My God-Given Right (OFFICIAL VIDEO)
・・アンディのアゴのタプタプ感が気になりますね。
そして紆余曲折あったものの、今も「伝統」を守っている。
すっかりベテランの域に入った彼らの新作は…
HELLOWEEN [My God-Given Right]

ドイツの大御所。wikiによるとこれが15枚目。
一大革命を起こした守護神伝シリーズから数えて28年。
そしてアンディ・デリスが加入して21年。(←ココに驚きますね)
最近成人式を迎えたコたちが産声を上げたときには、すでにアンディ・デリスだったわけですよ。
まぁ、彼らの音楽性については今更触れる必要もない。(←といいつつ、触れますが)
カイ・ハンセン & マイケル・ヴァイカートという稀代なメロディーメーカーによる、疾走感+ハイトーン+ツーバス+おおらかなサビ、アニソンにも通じる親しみやすいメロディ。
一つの「ジャーマンメタル」のフォーマットと言えますね。
その屋台骨だったカイ・ハンセンが脱退。
さらにそのメロディーを彩ったマイケル・キスクも脱退。
そして加入したのがPINKCREAM69のアンディ・デリス。
PINKCREAM69は大好きだったけど、それはないだろ…と落胆した人も多いはず(ワタシです)
彼の歌は大好きだけど、あくまでPC69だから素晴らしいのであってマイケル・キスクと比べると酷だろ…と落胆した人も多いはず(ワタシです)
しかし、まさかの相乗効果で名作[Master of the Rings]を生み出したのは記憶に新しいところ(といっても、21年経ちますが)
今となっては「HELLOWEEN = アンディ・デリス」という人も多いことでしょう。
ところどころで「問題作」と呼ばれる作品を挟みながらも、前作で実に「らしい」アルバムをリリースしてくれた彼ら。
今作品もその延長線にあるように感じます。
延長線上にありながらも、今作では各メンバーが作曲をバランスよく分散。
その各メンバーの個性が如実に表れている印象です。
特にアンディ・デリス作曲の存在感が際立っていますね。これは個人的嗜好もあって耳に馴染むから、という点はあるかと思いますが。
そう。ワタシはアンディ・デリスの曲が大好きだ。
PINKCREAM69時代からずっと大好きだ。
上述の奇跡の一枚[Master of the Rings]は、アンディ・デリスがいたから生まれた、そしてヴァイキー過去のHELLOWEENに拘ることなくアンディのメロディを受け入れたからこそ生まれた奇跡だと思う。
[Master of the Rings]は「これはアンディ・デリス with HELLOEENだな」と思ったくらいだ。
その「アンディ節」を満喫できるという意味では、その[Master of the Rings]に通じるのではないでしょうか。
(本編13曲中、共作も含めて7曲)
そして当然ですが、マイケル・ヴァイカートは「HELLOWEENとはこういう音楽」という信念と筋の通った楽曲で「らしさ」をアピールしてくれています。
やっぱりヴァイキーの「HELLOWEEN印」の曲がないと寂しいからね。
まさに安定の「金太郎飴」的メロディです。
そんな二人の存在感が際立つ中ですが、意外にもややヘヴィなリフで幕を開ける、サシャ・ゲルストナーによる[Heroes]。
サビはライブで盛り上がりそうなシンガロング系ですね。
こういったヘヴィな曲も、[THE DARK RIDE] や [7SINNERS]などを経て、それほど違和感がなくなってきましたね。
続いてヴァイキーによる[Battle’s Won]。まさにHELLOWEEN。まさにヴァイキー。
…といっても、マイケル・キスク時代のHELLOWEENのテイストとは微妙に異なる。アンディの歌うHELLOWEENの典型的、という曲だ。
そしてアンディによる[My God-Given Right]。Aメロ~Bメロの流れが涙が出るほどアンディだ。
彼のソロアルバムにあっても違和感ないようなメロディだ。
こういう曲がフィットしちゃうところにアンディが加入してすっかり地が固まってきてることを強く感じますね。
アンディの曲といえば、[If God Loves Rock'n'Roll]も素晴らしい。この曲のサビも「あー、アンディだよ!!」とニヤニヤしてしまいますね。
ヴァイキーも[Creatures In Heaven][Claws]あたりでもそのメロディセンスを十分に発揮。
これも一度聞くだけで「うん、ヴァイキーだな」と確信できる安定のクオリティです。
どうしてもアンディとヴァイキーの曲が際立つ&彼らの音楽が好きなので、サシャやマーカスの曲は「中休み」的印象になってしまいますね。
今作を聞いて、「実にチームバランスがとれている」「バンドの状態が良好なんだろうな」ということを感じました。
それぞれがそれぞれの個性を受け入れ、バンドの音して昇華させている感じがします。
これだけの個性がバラバラに存在しているにも関わらず、アルバムとしての一体感を感じるのです。
そしてその中心はやはりヴァイキーなんだろうな、と。
「HELLOWEENというブランド」はしっかり維持しつつ、アンディの曲や他メンバーの曲をバンドの音として吸収する。
そして自らもHELLOWEENらしさは守りつつ、カイ・ハンセン時代ともマイケル・キスク時代とも異なる音でそれを体現してくれる。
これって実はスゴいことだと思うのだ。
逆に言うと、初期HELLOWEENこそが至高であり、アンディ・デリスに今も馴染めない人にとっては今作は(今作も)「何か違うなー」と感じるかもしれない。
そしてアンディ・デリスは好きだけど、HELLOWEENで無理してハイトーンで歌ってる姿が痛々しい…と思っている方がいれば、今作は聞いてみてほしい。
実にアンディらしいメロディを堪能できるはずだから。
前作~今作ですっかり「安定」した感のあるHELLOWEEN。全く心配することない、安定のブランドです。
HELLOWEEN - My God-Given Right (OFFICIAL VIDEO)
・・アンディのアゴのタプタプ感が気になりますね。
2015年06月09日
褪せない輝き
ハードロック史に残る名作だった。
その名作をリレコーディングすると聞いて、「余計なことすんなよ」「集金ですかね」「オリジナルは越えられねぇよ」というネガティブな印象だったのはワタシだけはないはず。
‥いや、「あの名作が、素晴らしい音で蘇るなんて素晴らしい!」と思った人もいるでしょうけどね。
そんな複雑な思いの中でリリースされた今作。
HAREM SCAREM [MOOD SWINGSⅡ]

カナダ出身、メロディアスハードロック界の雄。
wikiによると、HAREM SCAREM名義では12枚目らしいですね。あのRUBBERも含めると13枚目ですか。
デビューアルバムは1991年なので、もう25年近いわけですね。
[MOOD SWINGS]については過去のブログで書いてたかもしれないけど、敢えて過去の記事は見ないようにしてるから(読むとその印象が蘇っちゃうから)、似たような話になっても気にしないでね。
:
:
:
冒頭に書いた通り、メロディアスハードロックファンなら間違いなくこの作品を通過していると思う。
むしろ、このアルバムからメロハーの魅力を知ったという人も多いと思う。
「メロディアスハード」の代名詞とも言える道標だと思う。
それほどまでに印象的かつ象徴的なアルバムを再録するというのは、ある意味チャレンジだと思う。
正直なところ、このアルバムは聞かないつもりだった。
思い入れが強いアルバムだから、その記憶を薄めたくないから。
が。
やはり名作は名作。
多少の違和感を抱きつつも、聞き進むにつれてそのメロディセンスの素晴らしさに有無を言わせず口を塞がれる感じだ。
ハーレムスキャーレムの個性はなんだろうか‥と考えてみると‥
キャッチーでポップ感すら漂う1st。
適度にヘヴィでありながらメロディの質がズバ抜けている2nd。
一気にモダン路線へ傾倒した問題作3rd。
再びキャッチーな路線へシフトした4th。
‥と、「なんとなくHAREM SCAREM」という音像はイメージできるものの、けっこうアルバムごとにカラーが異なるのだ。
それなのに「HAREM SCAREMってこういう音なんだよね」と印象を植えつけてるのはすごいことだと思う。
その印象を決定づけているのは、このアルバムであることは間違いないと思う。
メロハーと言っても、キラキラとした爽快感が中心じゃない。
コマーシャルなメロディかというと、そうでもない。
リフやグルーヴはけっこうモダン&ヘヴィな一面を見せる。メロハーファンがわりと敬遠したくなる音だろうと思う。
それでありながら、そのヘヴィさを上塗りするかのように美しく重厚なコーラスワークが姿を表す。
ヴォーカルの声はウェットでエモーショナル。
その声質が、さらにその不可思議で美しいメロディを彩っていく。
ポップすぎてもヘヴィすぎても「なんだか違うんだよなー」と思ってしまう、この絶妙なバランス。そしてそのバランスを支えるメロディセンスこそが彼らの命綱であり魅力だと思います。
分厚い雲の隙間から光が差すような。
夕暮れの遊園地の切なさのような。
雨上がりの散歩道のような。
彼らの音楽を聞くと、そんな風景が脳裏をよぎるのです。
おっと、思い入れが強すぎて肝心の内容に触れないままでしたね。
「MOOD SWINGS」から「MOOD SWINGSⅡ」への変化。
上述した通り、メロディの素晴らしさは変わらないんだから、当然作品としての素晴らしさは説明不要ですね。
ちょっと「ん?」と思った点は‥
・各パートの音が明確になった(気がする)
・音がダイなミックになった(気がする)
・音の「境界線」がクッキリした(気がする)
といったところでしょうかね。
ちょっと迫力が増した感があります。
一番大きな違いといえば、名曲[JUST LIKE I PLANED]がアカペラじゃなくなったことでしょうか。
終盤にこの曲が出てきたインパクトを思えば、ここはマイナスかなと思います。
‥まぁ、これもオリジナルを聞いてるからこその苦言であり、曲としては素晴らしいですが。
そんなわけで、「名作はやはり名作」との思いを強く抱いた一枚となりました。
:
:
:
だいたいにおいて、名作に「Ⅱ」の冠がついたアルバムは、その名作を越えられないことが多い。
その名作の幻影を引きずっちゃうし、そのクオリティを期待しちゃうから。
「名作」ってのはアルバムの質だけじゃなくて思い入れ補正も付加されるから、ハードルの高さがハンパない。
当然、そのハードルを越えるのは困難で、越えられないことが多いのも当然だと思う。
(もう「Ⅱ」という作品には慣れたけど)
が、このアルバムは「続編」ではなくリレコーディングだったことに救われた感がある。
全く違う曲でこのタイトルをつけてたら、きっとガッカリしたことだろうなと思う。
とはいえ、こういう作品には賛否両論あることだろうと思う。
ワタシ自身も圧倒的「否」の思いだったけど、聞いてみたら「やっぱりいいバンドだなー」と再認識できました。
思い入れがある方こそ、改めてその素晴らしさに触れてほしいと思いますよ。
Harem Scarem - Mood Swings Ⅱ - Change Comes Around
その名作をリレコーディングすると聞いて、「余計なことすんなよ」「集金ですかね」「オリジナルは越えられねぇよ」というネガティブな印象だったのはワタシだけはないはず。
‥いや、「あの名作が、素晴らしい音で蘇るなんて素晴らしい!」と思った人もいるでしょうけどね。
そんな複雑な思いの中でリリースされた今作。
HAREM SCAREM [MOOD SWINGSⅡ]

カナダ出身、メロディアスハードロック界の雄。
wikiによると、HAREM SCAREM名義では12枚目らしいですね。あのRUBBERも含めると13枚目ですか。
デビューアルバムは1991年なので、もう25年近いわけですね。
[MOOD SWINGS]については過去のブログで書いてたかもしれないけど、敢えて過去の記事は見ないようにしてるから(読むとその印象が蘇っちゃうから)、似たような話になっても気にしないでね。
:
:
:
冒頭に書いた通り、メロディアスハードロックファンなら間違いなくこの作品を通過していると思う。
むしろ、このアルバムからメロハーの魅力を知ったという人も多いと思う。
「メロディアスハード」の代名詞とも言える道標だと思う。
それほどまでに印象的かつ象徴的なアルバムを再録するというのは、ある意味チャレンジだと思う。
正直なところ、このアルバムは聞かないつもりだった。
思い入れが強いアルバムだから、その記憶を薄めたくないから。
が。
やはり名作は名作。
多少の違和感を抱きつつも、聞き進むにつれてそのメロディセンスの素晴らしさに有無を言わせず口を塞がれる感じだ。
ハーレムスキャーレムの個性はなんだろうか‥と考えてみると‥
キャッチーでポップ感すら漂う1st。
適度にヘヴィでありながらメロディの質がズバ抜けている2nd。
一気にモダン路線へ傾倒した問題作3rd。
再びキャッチーな路線へシフトした4th。
‥と、「なんとなくHAREM SCAREM」という音像はイメージできるものの、けっこうアルバムごとにカラーが異なるのだ。
それなのに「HAREM SCAREMってこういう音なんだよね」と印象を植えつけてるのはすごいことだと思う。
その印象を決定づけているのは、このアルバムであることは間違いないと思う。
メロハーと言っても、キラキラとした爽快感が中心じゃない。
コマーシャルなメロディかというと、そうでもない。
リフやグルーヴはけっこうモダン&ヘヴィな一面を見せる。メロハーファンがわりと敬遠したくなる音だろうと思う。
それでありながら、そのヘヴィさを上塗りするかのように美しく重厚なコーラスワークが姿を表す。
ヴォーカルの声はウェットでエモーショナル。
その声質が、さらにその不可思議で美しいメロディを彩っていく。
ポップすぎてもヘヴィすぎても「なんだか違うんだよなー」と思ってしまう、この絶妙なバランス。そしてそのバランスを支えるメロディセンスこそが彼らの命綱であり魅力だと思います。
分厚い雲の隙間から光が差すような。
夕暮れの遊園地の切なさのような。
雨上がりの散歩道のような。
彼らの音楽を聞くと、そんな風景が脳裏をよぎるのです。
おっと、思い入れが強すぎて肝心の内容に触れないままでしたね。
「MOOD SWINGS」から「MOOD SWINGSⅡ」への変化。
上述した通り、メロディの素晴らしさは変わらないんだから、当然作品としての素晴らしさは説明不要ですね。
ちょっと「ん?」と思った点は‥
・各パートの音が明確になった(気がする)
・音がダイなミックになった(気がする)
・音の「境界線」がクッキリした(気がする)
といったところでしょうかね。
ちょっと迫力が増した感があります。
一番大きな違いといえば、名曲[JUST LIKE I PLANED]がアカペラじゃなくなったことでしょうか。
終盤にこの曲が出てきたインパクトを思えば、ここはマイナスかなと思います。
‥まぁ、これもオリジナルを聞いてるからこその苦言であり、曲としては素晴らしいですが。
そんなわけで、「名作はやはり名作」との思いを強く抱いた一枚となりました。
:
:
:
だいたいにおいて、名作に「Ⅱ」の冠がついたアルバムは、その名作を越えられないことが多い。
その名作の幻影を引きずっちゃうし、そのクオリティを期待しちゃうから。
「名作」ってのはアルバムの質だけじゃなくて思い入れ補正も付加されるから、ハードルの高さがハンパない。
当然、そのハードルを越えるのは困難で、越えられないことが多いのも当然だと思う。
(もう「Ⅱ」という作品には慣れたけど)
が、このアルバムは「続編」ではなくリレコーディングだったことに救われた感がある。
全く違う曲でこのタイトルをつけてたら、きっとガッカリしたことだろうなと思う。
とはいえ、こういう作品には賛否両論あることだろうと思う。
ワタシ自身も圧倒的「否」の思いだったけど、聞いてみたら「やっぱりいいバンドだなー」と再認識できました。
思い入れがある方こそ、改めてその素晴らしさに触れてほしいと思いますよ。
Harem Scarem - Mood Swings Ⅱ - Change Comes Around
2013年01月28日
南瓜の本懐
LOUDPARK12でのパフォーマンスの記憶も褪せぬ中、伝わってきた新譜の情報。
各種メディアの評価、ライターのツイート、全てが「ちょい今までと違うな、コレは・・」というフシギな高揚感の中、リリースされました。
HELLOWEEN [ Straight Out of Hell ]

説明不要ですね。
ドイツ(いや、ここはあえて「ジャーマン」と呼ぼう)の重鎮。
Wikiによると、アルバムとしては14枚目ですね。
マイケル・キスクからアンディ・デリスに交代してから数えても既に9枚目ですか・・。
さて、今回のアルバム。
事前にfacebookのオフィシャルページで思わせぶりにチョイ出し→チョイ出し→チョイ出しを繰り返して姿を見せたジャケットを見て「・・・ダメだこりゃ。」と確信したのと逆行するかのように・・。
Burrn!誌での前評判、twitterでの事前情報、ともに「最高傑作」を思わせるものでした。
とはいえ、あまりハードルを上げすぎるとガッカリすることも多いので冷静沈着(のつもり)にその日を待ってましたよ。
トータルで見ると、とにかくアンディ・デリス期の魅力が全て詰まっているアルバムだなと思います。
一聴したときのポジティブな高揚感と明朗な疾走感は、Helloweenの代名詞と呼べるものでしょう。
そして、ヘヴィ&モダンな音像やリフはここ数作の彼らの作品でクローズアップされてきたもの。
それらが高いレベルで一体化していますね。
アンディ・デリスが加入して20年弱。
当然、最近の若いファンはHelloweenといえばアンディ・デリスでしょうね。
そのアンディ期にファンになった人や最近Helloweenに出会った人からすれば、おそらく最もHelloweenらしいアルバムであり、最も分かりやすいアルバムになることでしょう。
そしてココからは四十路を超えた、「Helloweenといえばカイ&キスケだよね。けど、Pinkcream69も大好きだから、アンディ時代のHelloweenも大好きだよ」というオッサンの独り言になりますが・・。
このアルバム、間違いなく名盤だと思います。
上述の通り、「らしさ」という意味では秀逸の出来。
では、その「らしさ」を紐解いていくと・・・
劇的疾走感を見せる[World of War]では「[Silent Rain]っぽいなー」と思ったり。
アンディ節が炸裂する[Waiting For The Thunder]では、「たしかにアンディだけど、あの曲やあの曲のほうが・・・」と思ったり。
真骨頂だなと思わせる[Years]でも[All Over The Nations]や[Salvation]を思い出したり。
それぞれの曲が高いレベルで「らしさ」を見せつつも、歴代の「その系統」の曲を越えられていないなというのが正直なところ。
結局、先行リリースされた[Burning Sun]と、同じく先行でリリースされて「サビが惜しいなー」と思っていた[Nabataea]が印象に残るんだよね。
とはいえ、「らしさ」を発揮した上述の曲だけでなく
ライブで大合唱必至の[Live Now!]。
キラキラとした疾走感が美しい[Far From The Stars]。
アンディの魅力を十二分に引き出すバラード[Hold Me In Your Arms]。
タイトル曲[Straight Out Of Hell]では、Helloweenらしいメロディと、これまたライブで盛り上がりそうなサビ。
感動的な[Years]の後にも心地よい疾走感の[Make Fire Catch The Fly]→[Church Breaks Down]で本編を締める。
と、改めて羅列してみると「こりゃ、隙がないわ」と思わせるクオリティ。
そんなわけで、なんだか支離滅裂な流れになってしまいましたが・・・。
ずっっっっっと昔からHelloweenが大好き。
もちろんPinkcream69も大好き。
カイ&キスケの時代も大好き。
アンディ加入後のHelloweenも大好き。
キスケ時代とアンディ時代は別物だけど、どっちも素晴らしいよね!
・・という、ワタシと境遇が近い人に、このアルバムの率直な意見を聞いてみたいなー、と。
このフクザツかつ葛藤に満ちた思いを共有できる人もいるんじゃないかなー、と。
90点前後の曲がザクザクと埋もれてるんだけど、過去にリアルタイムで95点を越える曲を聞いてきた衝撃を越えられないんだよね。
ゼイタクな話ではあるのですが。
やっぱりアンディ・デリスとマイケル・ヴァイカートが迎合して不安の中で叩きつけられた[Master of the Rings]での奇跡的相乗効果は、その時代を生きてきた年寄りには衝撃的だったからなー。
その反面・・
とにかくファンなら聞いて損はない。
アンディ期からのファンなら、最高傑作に挙げる人も多いことでしょう。
そして、アンディ期を敬遠してた昔のファンにも聞いてほしい。
最近のHelloweenの全ての魅力が高いレベルで凝縮されていると思うから。
そして、このあと紡がれていくであろうHelloweenの歴史の中でも重要な一枚になると思うから。
Helloween - Years
良曲揃いで、Youtubeから貼る曲を迷ってしまうのですが・・・ドラマティックな疾走感は感涙ものでしょう。
シンフォニックなアレンジに加えて、ワタシが弱い「鐘の音」を加えられたらもう・・・!
各種メディアの評価、ライターのツイート、全てが「ちょい今までと違うな、コレは・・」というフシギな高揚感の中、リリースされました。
HELLOWEEN [ Straight Out of Hell ]

説明不要ですね。
ドイツ(いや、ここはあえて「ジャーマン」と呼ぼう)の重鎮。
Wikiによると、アルバムとしては14枚目ですね。
マイケル・キスクからアンディ・デリスに交代してから数えても既に9枚目ですか・・。
さて、今回のアルバム。
事前にfacebookのオフィシャルページで思わせぶりにチョイ出し→チョイ出し→チョイ出しを繰り返して姿を見せたジャケットを見て「・・・ダメだこりゃ。」と確信したのと逆行するかのように・・。
Burrn!誌での前評判、twitterでの事前情報、ともに「最高傑作」を思わせるものでした。
とはいえ、あまりハードルを上げすぎるとガッカリすることも多いので冷静沈着(のつもり)にその日を待ってましたよ。
トータルで見ると、とにかくアンディ・デリス期の魅力が全て詰まっているアルバムだなと思います。
一聴したときのポジティブな高揚感と明朗な疾走感は、Helloweenの代名詞と呼べるものでしょう。
そして、ヘヴィ&モダンな音像やリフはここ数作の彼らの作品でクローズアップされてきたもの。
それらが高いレベルで一体化していますね。
アンディ・デリスが加入して20年弱。
当然、最近の若いファンはHelloweenといえばアンディ・デリスでしょうね。
そのアンディ期にファンになった人や最近Helloweenに出会った人からすれば、おそらく最もHelloweenらしいアルバムであり、最も分かりやすいアルバムになることでしょう。
そしてココからは四十路を超えた、「Helloweenといえばカイ&キスケだよね。けど、Pinkcream69も大好きだから、アンディ時代のHelloweenも大好きだよ」というオッサンの独り言になりますが・・。
このアルバム、間違いなく名盤だと思います。
上述の通り、「らしさ」という意味では秀逸の出来。
では、その「らしさ」を紐解いていくと・・・
劇的疾走感を見せる[World of War]では「[Silent Rain]っぽいなー」と思ったり。
アンディ節が炸裂する[Waiting For The Thunder]では、「たしかにアンディだけど、あの曲やあの曲のほうが・・・」と思ったり。
真骨頂だなと思わせる[Years]でも[All Over The Nations]や[Salvation]を思い出したり。
それぞれの曲が高いレベルで「らしさ」を見せつつも、歴代の「その系統」の曲を越えられていないなというのが正直なところ。
結局、先行リリースされた[Burning Sun]と、同じく先行でリリースされて「サビが惜しいなー」と思っていた[Nabataea]が印象に残るんだよね。
とはいえ、「らしさ」を発揮した上述の曲だけでなく
ライブで大合唱必至の[Live Now!]。
キラキラとした疾走感が美しい[Far From The Stars]。
アンディの魅力を十二分に引き出すバラード[Hold Me In Your Arms]。
タイトル曲[Straight Out Of Hell]では、Helloweenらしいメロディと、これまたライブで盛り上がりそうなサビ。
感動的な[Years]の後にも心地よい疾走感の[Make Fire Catch The Fly]→[Church Breaks Down]で本編を締める。
と、改めて羅列してみると「こりゃ、隙がないわ」と思わせるクオリティ。
そんなわけで、なんだか支離滅裂な流れになってしまいましたが・・・。
ずっっっっっと昔からHelloweenが大好き。
もちろんPinkcream69も大好き。
カイ&キスケの時代も大好き。
アンディ加入後のHelloweenも大好き。
キスケ時代とアンディ時代は別物だけど、どっちも素晴らしいよね!
・・という、ワタシと境遇が近い人に、このアルバムの率直な意見を聞いてみたいなー、と。
このフクザツかつ葛藤に満ちた思いを共有できる人もいるんじゃないかなー、と。
90点前後の曲がザクザクと埋もれてるんだけど、過去にリアルタイムで95点を越える曲を聞いてきた衝撃を越えられないんだよね。
ゼイタクな話ではあるのですが。
やっぱりアンディ・デリスとマイケル・ヴァイカートが迎合して不安の中で叩きつけられた[Master of the Rings]での奇跡的相乗効果は、その時代を生きてきた年寄りには衝撃的だったからなー。
その反面・・
とにかくファンなら聞いて損はない。
アンディ期からのファンなら、最高傑作に挙げる人も多いことでしょう。
そして、アンディ期を敬遠してた昔のファンにも聞いてほしい。
最近のHelloweenの全ての魅力が高いレベルで凝縮されていると思うから。
そして、このあと紡がれていくであろうHelloweenの歴史の中でも重要な一枚になると思うから。
Helloween - Years
良曲揃いで、Youtubeから貼る曲を迷ってしまうのですが・・・ドラマティックな疾走感は感涙ものでしょう。
シンフォニックなアレンジに加えて、ワタシが弱い「鐘の音」を加えられたらもう・・・!
2011年06月21日
進化系南瓜
バンドってのは「同じこと」を続けるってことに抵抗があるんだろうか。
ある程度売れた後に「意欲的な」「新たな魅力」「新境地」的なタタキを見ると「またか・・・」と思ってしまいます。
さて。大御所と言っていい彼らも、その欲求は尽きないらしい。
HELLOWEEN [7 SINNERS]

もう何枚目か記憶だけじゃ追えないのでWikiによると・・・デビュー24年、13枚目のアルバム。四半世紀だね。
このアルバムの前に往年の曲をアコースティックアレンジしたアルバムをリリースする、という暴挙を成し遂げたHELLOWEEN。
そもそも、そのアルバム自体が「意欲的」「新鮮」っつーレベルを凌駕した「ま、コレはコレで置いといて・・・」「これは見なかったことに・・・」というモノだったわけで。
そしてその反動でしょうか。事前から「とにかくヘヴィ」というアナウンスが大々的に聞こえてきた。
(ま、「とにかくヘヴィ」なんてフレーズは、どのアーティストも使う常套句ですけどね)
実際リリースされたアルバムは、たしかに「ヘヴィ」であることに拘った仕上がりとなりました。
古くからのHELLOWEENファンにとって彼らの魅力といえば、いわゆる「ジャーマンメタル」と礎となったサウンド、そして時折みせるコミカルでポップなフレーズ。
そのあたりを真っ向から否定するかのような「トンガってる」という印象のアルバムです。
重くシリアスなムードで進行していく様は「DARK RIDE」アルバムで得た第一印象に通じるものがあります。
特に印象的なのは [Are You Metal?]でのアンディ・デリスの「Meeeeeeetaaaaaalllllll!!!!」という叫び。
アンディ・デリスのアルバムの話の時にも書いたけど、なんだか「ヘヴィであることに傾倒しすぎて、無理している」感が漂います。
その重い空気の中でも、HELLOWEENらしいメロディラインが顔をだすのでホッとするわけですが、一番「これこそHELLOWEEN」と思えるのが終盤を飾る[Far In The Future]でのギターソロというのがやや寂しいところ。
そうそう、こういうフレーズこそがヴァイキーの魅力なんだよね。
そして名曲[Perfect Gentleman]のメロディーが導入された[Who Is Mr. Madman?]は、最近のHELLOWEENらしさが見られる佳曲。
・・・と、まぁなんだかんだ言ってもいくつかの大きな印象を刻んでいくのは、さすがといったところでしょうかね。
[Are You Metal?]なんかは、好き嫌いは別にして結局リピートしてたりしたし。
そもそも、昨今のHELLOWEENファンってのはアンディ・デリス加入後のファンが多いと思う。
なんつったって、25周年を迎えたバンドだ。四半世紀だ。
そんなファンにとっては、過去のメロディを踏襲しつつモダンにヘヴィになっていく彼らの姿を見て、着実に「進化」しているように映ると思う。
それは否定しません。
が、HELLOWEENが一番HELLOWEENらしかった時代、そしてアンディ・デリスのメロディセンスを知る者としては、一抹の寂しさを覚えるのも事実。
HELLOWEENなりの「ヘヴィ」を追求した後、ヴァイキーとアンディはどんな「次」を見据えているんでしょうか。
Helloween - "Are You Metal?"
Helloween- Who Is Mr. Madman?
Helloween Far in The Future
//img01.hida-ch.com/usr/ten/helloween_7sinner.jpg
ある程度売れた後に「意欲的な」「新たな魅力」「新境地」的なタタキを見ると「またか・・・」と思ってしまいます。
さて。大御所と言っていい彼らも、その欲求は尽きないらしい。
HELLOWEEN [7 SINNERS]

もう何枚目か記憶だけじゃ追えないのでWikiによると・・・デビュー24年、13枚目のアルバム。四半世紀だね。
このアルバムの前に往年の曲をアコースティックアレンジしたアルバムをリリースする、という暴挙を成し遂げたHELLOWEEN。
そもそも、そのアルバム自体が「意欲的」「新鮮」っつーレベルを凌駕した「ま、コレはコレで置いといて・・・」「これは見なかったことに・・・」というモノだったわけで。
そしてその反動でしょうか。事前から「とにかくヘヴィ」というアナウンスが大々的に聞こえてきた。
(ま、「とにかくヘヴィ」なんてフレーズは、どのアーティストも使う常套句ですけどね)
実際リリースされたアルバムは、たしかに「ヘヴィ」であることに拘った仕上がりとなりました。
古くからのHELLOWEENファンにとって彼らの魅力といえば、いわゆる「ジャーマンメタル」と礎となったサウンド、そして時折みせるコミカルでポップなフレーズ。
そのあたりを真っ向から否定するかのような「トンガってる」という印象のアルバムです。
重くシリアスなムードで進行していく様は「DARK RIDE」アルバムで得た第一印象に通じるものがあります。
特に印象的なのは [Are You Metal?]でのアンディ・デリスの「Meeeeeeetaaaaaalllllll!!!!」という叫び。
アンディ・デリスのアルバムの話の時にも書いたけど、なんだか「ヘヴィであることに傾倒しすぎて、無理している」感が漂います。
その重い空気の中でも、HELLOWEENらしいメロディラインが顔をだすのでホッとするわけですが、一番「これこそHELLOWEEN」と思えるのが終盤を飾る[Far In The Future]でのギターソロというのがやや寂しいところ。
そうそう、こういうフレーズこそがヴァイキーの魅力なんだよね。
そして名曲[Perfect Gentleman]のメロディーが導入された[Who Is Mr. Madman?]は、最近のHELLOWEENらしさが見られる佳曲。
・・・と、まぁなんだかんだ言ってもいくつかの大きな印象を刻んでいくのは、さすがといったところでしょうかね。
[Are You Metal?]なんかは、好き嫌いは別にして結局リピートしてたりしたし。
そもそも、昨今のHELLOWEENファンってのはアンディ・デリス加入後のファンが多いと思う。
なんつったって、25周年を迎えたバンドだ。四半世紀だ。
そんなファンにとっては、過去のメロディを踏襲しつつモダンにヘヴィになっていく彼らの姿を見て、着実に「進化」しているように映ると思う。
それは否定しません。
が、HELLOWEENが一番HELLOWEENらしかった時代、そしてアンディ・デリスのメロディセンスを知る者としては、一抹の寂しさを覚えるのも事実。
HELLOWEENなりの「ヘヴィ」を追求した後、ヴァイキーとアンディはどんな「次」を見据えているんでしょうか。
Helloween - "Are You Metal?"
Helloween- Who Is Mr. Madman?
Helloween Far in The Future
//img01.hida-ch.com/usr/ten/helloween_7sinner.jpg
2011年04月06日
日出ずる国、ニッポン
先日頂いたコメントを拝見して思い出した。
そう。
今、この曲を取り上げずして、いつ取り上げる。
いや、アルバム自体の出来からして(失礼)一生取り上げないかもしれない。
HEAVENS GATE [HELL FOR SALE!]

名作[LIVIN' IN HYSTERIA]の後を受けてリリースされた、1992年発表の3rdアルバム。
疾風のように現れて、疾風のように去っていった・・・と言うと皮肉が過ぎるでしょうか。
いや、大好きだったからこそ、もっと長く頑張って欲しかったという意味も込めてね。
その[LIVIN' IN HYSTERIA]で一気にブレイク。
メタル専門誌BURRN! の表紙も飾り、来日公演も行い・・・と順風満帆だったわけですが、残念なライブパフォーマンスと、このアルバムのビミョーな出来映え(いや、前作が良すぎた)で一気にトーンダウン。
その後のアルバムは意外と良作だったにも関わらず再加速には至らず。
ま、サシャ・ピートはトビアス・サメットのおかげ(?)で、プロデューサーとして名を売ってたり、一緒に来日しちゃったりしてますが・・・。
このアルバム、印象的な曲があるにも関わらず、全体の散漫な印象が強いです。
JudasPriestあたりを源流とするオールドスタイルなHeavyMetalを軸に、コマーシャルなジャーマン的明朗快活さを盛り込んだスタイルこそが彼らの真骨頂であるわけですが、ブレイクしたバンドによくある
「オレたち、それだけじゃないぜ。もっといろいろなスタイルもこなせるぜ」
という過度な意識がマイナスに働いてしまったのではないかと。
ライブもハイトーンは出てない、フェイクの嵐・・・いやいや、あまりケナすことはやめておこう。それはそれでいい思い出だしね。
そんな彼らだったけど、今でも大好きです。
イヤ、ホントに。
基本的にウチのCDラックは好きなバンドが上位に置かれているのですが、このCDを探してて、ANGRAあたりと並んで2段目に配置されてたのを見て「おぉ、けっこう上位ランク!」と勝手にほくそ笑んでましたから。
ある意味では「ジャーマン・バブル」の飲み込まれていっただけかも・・・。
:
:
:
そんな彼らが、愛する日本のファンに向けて書いてくれた曲がアルバムに収録されている。
RISING SUN・・・まさに「日出ずる国、ニッポン」へ向けてのストレートなメッセージだ。
基本的には「ニッポンのみんなサポートをありがとう!一緒にライブ楽しもうぜ!」的内容で、「チープ」「媚びてる」と言われたらそれまでなのですが・・・
今だからこそ、印象深い歌詞を勝手に抜粋。
♪
We cross the night, we see the light
and our dream comes true
we're gonna bring the power all over you
(夜を駆け、光を見る。
そして夢がかなう。
みんなにパワーを与えよう。)
♪
We cross the land of the rising sun
Hope we'll be all together
(日出ずる国を駆け抜け
団結を誓おう。)
※日本語詩は歌詞カードより抜粋、一部フンイキ勝手に修正アリ
HEAVENS GATE / RISING SUN
そう。
今、この曲を取り上げずして、いつ取り上げる。
いや、アルバム自体の出来からして(失礼)一生取り上げないかもしれない。
HEAVENS GATE [HELL FOR SALE!]

名作[LIVIN' IN HYSTERIA]の後を受けてリリースされた、1992年発表の3rdアルバム。
疾風のように現れて、疾風のように去っていった・・・と言うと皮肉が過ぎるでしょうか。
いや、大好きだったからこそ、もっと長く頑張って欲しかったという意味も込めてね。
その[LIVIN' IN HYSTERIA]で一気にブレイク。
メタル専門誌BURRN! の表紙も飾り、来日公演も行い・・・と順風満帆だったわけですが、残念なライブパフォーマンスと、このアルバムのビミョーな出来映え(いや、前作が良すぎた)で一気にトーンダウン。
その後のアルバムは意外と良作だったにも関わらず再加速には至らず。
ま、サシャ・ピートはトビアス・サメットのおかげ(?)で、プロデューサーとして名を売ってたり、一緒に来日しちゃったりしてますが・・・。
このアルバム、印象的な曲があるにも関わらず、全体の散漫な印象が強いです。
JudasPriestあたりを源流とするオールドスタイルなHeavyMetalを軸に、コマーシャルなジャーマン的明朗快活さを盛り込んだスタイルこそが彼らの真骨頂であるわけですが、ブレイクしたバンドによくある
「オレたち、それだけじゃないぜ。もっといろいろなスタイルもこなせるぜ」
という過度な意識がマイナスに働いてしまったのではないかと。
ライブもハイトーンは出てない、フェイクの嵐・・・いやいや、あまりケナすことはやめておこう。それはそれでいい思い出だしね。
そんな彼らだったけど、今でも大好きです。
イヤ、ホントに。
基本的にウチのCDラックは好きなバンドが上位に置かれているのですが、このCDを探してて、ANGRAあたりと並んで2段目に配置されてたのを見て「おぉ、けっこう上位ランク!」と勝手にほくそ笑んでましたから。
ある意味では「ジャーマン・バブル」の飲み込まれていっただけかも・・・。
:
:
:
そんな彼らが、愛する日本のファンに向けて書いてくれた曲がアルバムに収録されている。
RISING SUN・・・まさに「日出ずる国、ニッポン」へ向けてのストレートなメッセージだ。
基本的には「ニッポンのみんなサポートをありがとう!一緒にライブ楽しもうぜ!」的内容で、「チープ」「媚びてる」と言われたらそれまでなのですが・・・
今だからこそ、印象深い歌詞を勝手に抜粋。
♪
We cross the night, we see the light
and our dream comes true
we're gonna bring the power all over you
(夜を駆け、光を見る。
そして夢がかなう。
みんなにパワーを与えよう。)
♪
We cross the land of the rising sun
Hope we'll be all together
(日出ずる国を駆け抜け
団結を誓おう。)
※日本語詩は歌詞カードより抜粋、一部フンイキ勝手に修正アリ
HEAVENS GATE / RISING SUN
2010年11月04日
ハロウィン過ぎて・・・
「ハロウィンの日にはハロウィンのことを書いとこう。安直だけど分かりやすいし。べ・・・べつにネタに困ってるわけじゃないんだからね!」
そう思いつつ、一昨年と昨年もハロウィンのことを書いてたわけですが・・・。
知らぬ間に終わってたよ。ハロウィン。
だって、ワタシのまわりでは「はろうぃん! はろうぃん!」って喧騒は皆無なんだもん。
だって、ニッポン人にはあんまり関係ないんじゃね?
各方面のギョーカイの人たちが盛り上げようとしてるだけじゃね?
そういったヒネクレ思想は置いといて、今年も遅ればせながらハロウィンのことを書いちゃうわけです。
結局便乗しちゃうのです。
タイミング逸してる感満載だけどカンベンしてくださいませ。
振り返ってみると、結構ハロウィンのアルバムはいくつか取り上げてるんだな。覚えてなかったけど。
そんなわけで、今年はこのアルバムを。
HELLOWEEN [THE DARK RIDE]

通算で9枚目、アンディ・デリス加入後では4枚目・・・だったと思う。
アンディ加入後の新生HELLOWEENは、どうしてもマイケル・キスクの幻影、そして少し間が開いてるとはいえ、カイ・ハンセンの幻影との戦いだったと思う。
全く毛色の違うPINKCREAM69というバンドで、ポップな色彩が魅力だったアンディが加入して、ファンは大きな不安をもって船出を見つめていたと思う。
当然、アンディ加入後のHELLOWEENは、その「HELLOWEENらしさとアンディのメロディセンスの融和」がキーポイント。
結果、それを見事に成立させてくれた。
カイ信者だったワタシも「これはこれでイイ!」と思えた。(ま、ワタシがPINKCREAM69も好きだった、ってのもあるけどね)
そして、その段階を越えて「アンディのHELLOWEEN」としての存在が確立できたところで、ようやくその足枷が外れて自由にアルバムを作ってみた・・・そんな印象です。
タイトルの通り、全体を覆うダークな印象。
正統派メタルファンが嫌悪する「モダン」という言葉。
賛否両論のアルバムだと思います。
(いつも書くけど、「賛否両論」ってときは概して「否」が多いときの表現だよね)
確かに、モダンでフックのない曲も多い。
アルバム全体の印象も暗い。
だけど、キラーチューンの破壊力という点では、アンディ加入後のアルバムの中でも珠玉だと思うのだ。
だから個人的にはそれほど否定的な印象はないんだな。
[All Over The Nations]でのHELLOWEEN節満載の典型的「ジャーマンメタル」。そしてこの飛翔感。この曲をアンディが歌って違和感がないってのは大きいと思うんだ。
ヘヴィながらもキャッチーな[Mr.Torutre]は、アンディ加入後のHELLOWEENの一つの新しい「王道」とも取れる曲だ。
[Salvation]もヴァイキーらしさ満点、スピーディーなリフにゆったりとしたアンディの声が心地よく、イントロのリフだけで「よしよし、その筋の曲だな。ちゃんとちゃんとだな。」と直感できる名曲。
そしてなんといっても得意の大曲[The Dark Ride]。アルバムのダークな印象と、得意のドラマティックな世界観が一体になったハイライト。
・・・と、HELLOWEENの歴史に残る名曲群を収録していながら、駄曲との差が激しい印象が強いこのアルバム。
個人的には「75点~85点の曲が満載の、トータル80点のアルバム」よりは「トータル70点だけど、90点以上の曲が数曲ある」というアルバムのほうが印象に残ったりする。
だから、「THE DARK RIDEの前後のアルバムってなんだっけ・・・」と思うほど、この時期はこのアルバムの印象が強い。
古くからのHELLOWEENファンは、カイのリフじゃないHELLOWEEN、キスケのハイトーンが聞けないHELLOWEENを追いかける気にならない人もいるかもしれない。
そんな人には、敢えてこのアルバムから入るってのも手だと思うんだ。
アンディ加入直後のアルバムは良くも悪くもアンディの魅力が詰まってるからそのギャップに苦しむかもしれないけど、このアルバムは新生HELLOWEENの新しい魅力が見えると思うから。
Helloween - Mr. Torture
Helloween - Salvation
Helloween - The dark ride
そう思いつつ、一昨年と昨年もハロウィンのことを書いてたわけですが・・・。
知らぬ間に終わってたよ。ハロウィン。
だって、ワタシのまわりでは「はろうぃん! はろうぃん!」って喧騒は皆無なんだもん。
だって、ニッポン人にはあんまり関係ないんじゃね?
各方面のギョーカイの人たちが盛り上げようとしてるだけじゃね?
そういったヒネクレ思想は置いといて、今年も遅ればせながらハロウィンのことを書いちゃうわけです。
結局便乗しちゃうのです。
タイミング逸してる感満載だけどカンベンしてくださいませ。
振り返ってみると、結構ハロウィンのアルバムはいくつか取り上げてるんだな。覚えてなかったけど。
そんなわけで、今年はこのアルバムを。
HELLOWEEN [THE DARK RIDE]

通算で9枚目、アンディ・デリス加入後では4枚目・・・だったと思う。
アンディ加入後の新生HELLOWEENは、どうしてもマイケル・キスクの幻影、そして少し間が開いてるとはいえ、カイ・ハンセンの幻影との戦いだったと思う。
全く毛色の違うPINKCREAM69というバンドで、ポップな色彩が魅力だったアンディが加入して、ファンは大きな不安をもって船出を見つめていたと思う。
当然、アンディ加入後のHELLOWEENは、その「HELLOWEENらしさとアンディのメロディセンスの融和」がキーポイント。
結果、それを見事に成立させてくれた。
カイ信者だったワタシも「これはこれでイイ!」と思えた。(ま、ワタシがPINKCREAM69も好きだった、ってのもあるけどね)
そして、その段階を越えて「アンディのHELLOWEEN」としての存在が確立できたところで、ようやくその足枷が外れて自由にアルバムを作ってみた・・・そんな印象です。
タイトルの通り、全体を覆うダークな印象。
正統派メタルファンが嫌悪する「モダン」という言葉。
賛否両論のアルバムだと思います。
(いつも書くけど、「賛否両論」ってときは概して「否」が多いときの表現だよね)
確かに、モダンでフックのない曲も多い。
アルバム全体の印象も暗い。
だけど、キラーチューンの破壊力という点では、アンディ加入後のアルバムの中でも珠玉だと思うのだ。
だから個人的にはそれほど否定的な印象はないんだな。
[All Over The Nations]でのHELLOWEEN節満載の典型的「ジャーマンメタル」。そしてこの飛翔感。この曲をアンディが歌って違和感がないってのは大きいと思うんだ。
ヘヴィながらもキャッチーな[Mr.Torutre]は、アンディ加入後のHELLOWEENの一つの新しい「王道」とも取れる曲だ。
[Salvation]もヴァイキーらしさ満点、スピーディーなリフにゆったりとしたアンディの声が心地よく、イントロのリフだけで「よしよし、その筋の曲だな。ちゃんとちゃんとだな。」と直感できる名曲。
そしてなんといっても得意の大曲[The Dark Ride]。アルバムのダークな印象と、得意のドラマティックな世界観が一体になったハイライト。
・・・と、HELLOWEENの歴史に残る名曲群を収録していながら、駄曲との差が激しい印象が強いこのアルバム。
個人的には「75点~85点の曲が満載の、トータル80点のアルバム」よりは「トータル70点だけど、90点以上の曲が数曲ある」というアルバムのほうが印象に残ったりする。
だから、「THE DARK RIDEの前後のアルバムってなんだっけ・・・」と思うほど、この時期はこのアルバムの印象が強い。
古くからのHELLOWEENファンは、カイのリフじゃないHELLOWEEN、キスケのハイトーンが聞けないHELLOWEENを追いかける気にならない人もいるかもしれない。
そんな人には、敢えてこのアルバムから入るってのも手だと思うんだ。
アンディ加入直後のアルバムは良くも悪くもアンディの魅力が詰まってるからそのギャップに苦しむかもしれないけど、このアルバムは新生HELLOWEENの新しい魅力が見えると思うから。
Helloween - Mr. Torture
Helloween - Salvation
Helloween - The dark ride
2010年01月22日
偉大なるパクリッシュ
昨年度末に飛び込んできた、この界隈のファンにとっての注目の一枚。
良くも悪くも、その路線に徹底的にズームしてきてくれた彼らですが、今回は試行錯誤の痕跡が見え隠れ。
HEAVENLY [CARPE DIEM]

・・・すんごいジャケで来ました。前作も違う意味でスゴいものだったけど。
フランス出身。
パクリかトリビュートかオマージュかリスペクトか・・・という微妙な音楽性も、突き抜けてしまえば個性になるのさ!
こういう音が大好きだからいいのさ!
好きな人たちだけ、ついてきてくれればいいのさ!
・・・といった声が聞こえそうな彼らのサウンドですが、なんだかんだで5枚目です。
GAMMA RAY に代表されるメロディックパワーメタル勢の美味しいところだけドリップして、さらに濃くしたかのような音楽性は時に「パクリッシュ・メタル」などと揶揄され、賛否両論かなとは思います。
同じ界隈のファンでも「あぁ、カイ・ハンセン好きなんだね、キミたち。オレも大好きだぜブラザー!」と微笑むことができるか、「オリジナリティの欠如!二番煎じ!」と声高に叫ぶか、それによって楽しみ方も変わるでしょうね。
そんな彼らですが、前作までも一歩一歩、しかし自分たちの道を踏み外すことなく進化を重ねていました。
が。
今回はさらにベクトルを広げたように感じます。
全体的に感じるスペーシーな高揚感はSTRATOVARIUSっぽかったり。
ドラマティックな大曲[FAREWELL]はGAMMA RAYの名曲[THE SILENCE]っぽいし。。
K-1 WORLD MAXでお馴染みの、これまたGAMMA RAYの[INDUCTION]に酷似した曲もあったり。
終盤のミステリアスなムードがKAMELOTっぽかったり。
ヴォーカルの歌いまわしが、あきらかにマイケル・キスクを思わせたり。
「○○っぽい」の乱舞のように聞こえますが(実際そうですが)、それを楽しむこととHEAVENLYを楽しむことは同義。
5枚目まで追いかけてきたファンなら気にしないどころか、むしろ期待してるくらいだと思うから、いいのだ。
そんな中、前述したようなスペーシーなムードや、シンフォニックなアレンジなど、今回は今までの作品と比べてもスケールアップした感があります。
偉大なるマンネリズムの中にもフレッシュな新風が吹いたような。
爆裂疾走は控えめ(といっても、それなりに・・・)。
ですが、HEAVENLYらしいキラキラとした美旋律は随所に散りばめられていて、頬が緩むことは間違いなし。
正直、一聴したときはDARK MOORの新作を聞いた時のような「あぁ、そっちへ行くのか・・・」という落胆があったのですが・・・
それは彼らの疾走感を期待したからだと思うのですが・・・
聴けば聴くほど、ミディアムで彼らのサウンドの中庸を行くような楽曲の魅力が分かるようになってくると、充分に「らしさ」を保ったままだな・・・と感じます。
新しい方向性を模索しつつも踏みとどまった・・・という印象。
そういう中で考えると、次作で自分たちのフィールドを見失うことなく開き直って勝負するのか。
それとも新たな可能性と新たな個性を見出そうとして勝負に出るのか。
大きなターニングポイントになりそうな気がします。
・・・ワタシとしては、奇をてらうことなく徹底的に王道ド真ん中を邁進してほしいのですが。
でも、クラシックベースのメタルが好きなワタシにとっては、「第九」をモチーフにした[ODE TO JOY]のような路線なら歓迎です。
Heavenly - Ashen Paradise
Heavenly - Lost in your Eyes
良くも悪くも、その路線に徹底的にズームしてきてくれた彼らですが、今回は試行錯誤の痕跡が見え隠れ。
HEAVENLY [CARPE DIEM]

・・・すんごいジャケで来ました。前作も違う意味でスゴいものだったけど。
フランス出身。
パクリかトリビュートかオマージュかリスペクトか・・・という微妙な音楽性も、突き抜けてしまえば個性になるのさ!
こういう音が大好きだからいいのさ!
好きな人たちだけ、ついてきてくれればいいのさ!
・・・といった声が聞こえそうな彼らのサウンドですが、なんだかんだで5枚目です。
GAMMA RAY に代表されるメロディックパワーメタル勢の美味しいところだけドリップして、さらに濃くしたかのような音楽性は時に「パクリッシュ・メタル」などと揶揄され、賛否両論かなとは思います。
同じ界隈のファンでも「あぁ、カイ・ハンセン好きなんだね、キミたち。オレも大好きだぜブラザー!」と微笑むことができるか、「オリジナリティの欠如!二番煎じ!」と声高に叫ぶか、それによって楽しみ方も変わるでしょうね。
そんな彼らですが、前作までも一歩一歩、しかし自分たちの道を踏み外すことなく進化を重ねていました。
が。
今回はさらにベクトルを広げたように感じます。
全体的に感じるスペーシーな高揚感はSTRATOVARIUSっぽかったり。
ドラマティックな大曲[FAREWELL]はGAMMA RAYの名曲[THE SILENCE]っぽいし。。
K-1 WORLD MAXでお馴染みの、これまたGAMMA RAYの[INDUCTION]に酷似した曲もあったり。
終盤のミステリアスなムードがKAMELOTっぽかったり。
ヴォーカルの歌いまわしが、あきらかにマイケル・キスクを思わせたり。
「○○っぽい」の乱舞のように聞こえますが(実際そうですが)、それを楽しむこととHEAVENLYを楽しむことは同義。
5枚目まで追いかけてきたファンなら気にしないどころか、むしろ期待してるくらいだと思うから、いいのだ。
そんな中、前述したようなスペーシーなムードや、シンフォニックなアレンジなど、今回は今までの作品と比べてもスケールアップした感があります。
偉大なるマンネリズムの中にもフレッシュな新風が吹いたような。
爆裂疾走は控えめ(といっても、それなりに・・・)。
ですが、HEAVENLYらしいキラキラとした美旋律は随所に散りばめられていて、頬が緩むことは間違いなし。
正直、一聴したときはDARK MOORの新作を聞いた時のような「あぁ、そっちへ行くのか・・・」という落胆があったのですが・・・
それは彼らの疾走感を期待したからだと思うのですが・・・
聴けば聴くほど、ミディアムで彼らのサウンドの中庸を行くような楽曲の魅力が分かるようになってくると、充分に「らしさ」を保ったままだな・・・と感じます。
新しい方向性を模索しつつも踏みとどまった・・・という印象。
そういう中で考えると、次作で自分たちのフィールドを見失うことなく開き直って勝負するのか。
それとも新たな可能性と新たな個性を見出そうとして勝負に出るのか。
大きなターニングポイントになりそうな気がします。
・・・ワタシとしては、奇をてらうことなく徹底的に王道ド真ん中を邁進してほしいのですが。
でも、クラシックベースのメタルが好きなワタシにとっては、「第九」をモチーフにした[ODE TO JOY]のような路線なら歓迎です。
Heavenly - Ashen Paradise
Heavenly - Lost in your Eyes
2009年11月27日
サイゴノトリデ
先日のフレンチメタルの繋がりですが、そういえばこのバンドもフランスだった。
HEAVENLY [DUST TO DUST]

この前の作品[SIGN OF THE WINNER] で、ネタか?パクりか?開き直りか?といった具合にメロディックスピードメタルを具現化し、コノ手が好きなファンなら
「いや、もうね、笑うしかないっしょ。いろんな意味で。」
と凄まじい印象を植えつけただけに、その続編のこのアルバムは賛否分かれたようです。
結論から言うと、自分はカナリ好きですね。
コンセプトアルバムっぽくなったとか、ちょっとプログレ気味とかいう情報もありましたが、ま、前作のテンションが異常だったわけで。
地に足をつけて演奏も締まった感がありますし、曲もパワフルで輪郭がハッキリした気がします。
メロディもHEAVENLY節全開。
フラフラとしたビミョーな高音ヴォーカルも、このバンドの個性だと思えば気になりません。
HEAVENLYの魅力は、そのクサすぎるメロディに尽きるわけですが、個人的には
・何の音か分からないけど、疾走前の「ドゴーン!!」っていう効果音
・疾走中にバックを彩る鐘の音
コレですね。HEAVENLYだなーと思うのは。
GAMMA RAY が最近やけに地味だなーと感じる方には、うってつけ。
かくいうワタシもカイ・ハンセンおよびGAMMA RAYを愛していることは今さら言うまでもないのだが、ここ数作のアルバムの内容を比較するとHEAVENLYの方が「GAMMA RAYっぽくて美味しい」という本末転倒な印象すらあるのだ。
しかもそれに違和感を覚えないところが、我ながら「いいのか?これで?」と自問自答なのだ。
近々、久々のアルバムをリリースするようです。
DARK MOORも新境地を開拓し、SONATA ARCTICAも違うステージへ向かい、GAMMA RAYもやや落ち着いてしまっている今。
純粋培養メロディックスピードメタル最後の砦と言っても過言ではないHEAVENLY。
笑われてもいい。
パクリと言われてもいい。
その信念を持って進んでほしい。
期待は高まるのだ。
Heavenly - Evil
(パクリって言わないでね。HEAVENLYらしさを継承しつつ新境地を見せた大曲ですよ)
HEAVENLY [DUST TO DUST]

この前の作品[SIGN OF THE WINNER] で、ネタか?パクりか?開き直りか?といった具合にメロディックスピードメタルを具現化し、コノ手が好きなファンなら
「いや、もうね、笑うしかないっしょ。いろんな意味で。」
と凄まじい印象を植えつけただけに、その続編のこのアルバムは賛否分かれたようです。
結論から言うと、自分はカナリ好きですね。
コンセプトアルバムっぽくなったとか、ちょっとプログレ気味とかいう情報もありましたが、ま、前作のテンションが異常だったわけで。
地に足をつけて演奏も締まった感がありますし、曲もパワフルで輪郭がハッキリした気がします。
メロディもHEAVENLY節全開。
フラフラとしたビミョーな高音ヴォーカルも、このバンドの個性だと思えば気になりません。
HEAVENLYの魅力は、そのクサすぎるメロディに尽きるわけですが、個人的には
・何の音か分からないけど、疾走前の「ドゴーン!!」っていう効果音
・疾走中にバックを彩る鐘の音
コレですね。HEAVENLYだなーと思うのは。
GAMMA RAY が最近やけに地味だなーと感じる方には、うってつけ。
かくいうワタシもカイ・ハンセンおよびGAMMA RAYを愛していることは今さら言うまでもないのだが、ここ数作のアルバムの内容を比較するとHEAVENLYの方が「GAMMA RAYっぽくて美味しい」という本末転倒な印象すらあるのだ。
しかもそれに違和感を覚えないところが、我ながら「いいのか?これで?」と自問自答なのだ。
近々、久々のアルバムをリリースするようです。
DARK MOORも新境地を開拓し、SONATA ARCTICAも違うステージへ向かい、GAMMA RAYもやや落ち着いてしまっている今。
純粋培養メロディックスピードメタル最後の砦と言っても過言ではないHEAVENLY。
笑われてもいい。
パクリと言われてもいい。
その信念を持って進んでほしい。
期待は高まるのだ。
Heavenly - Evil
(パクリって言わないでね。HEAVENLYらしさを継承しつつ新境地を見せた大曲ですよ)
2009年11月04日
鍵、指輪、ハロウィン
あんまりニッポンジンとは関係なさそうなのに「はろうぃん!はろうぃん!」と、なんだか違和感のある喧騒の中、ハロウィンも終わり・・・。
「ハロウィン」というキーワードで、このバンドを取り上げる安直さもどうかと思いますが、ま、いいでしょう。分かりやすいし。
昨年もこのバンドのこと書いたから恒例行事にしちゃおっかなー。
楽だし。
ってことで(?)、まだ書いてないアルバムから、コレをチョイス。
Helloween [Master Of The Rings]

物語は「鍵」 (Keeper of the Seven Keys) から「指輪」へ。
過去の名作と韻を踏んだタイトルにはハッキリとした新生HELLOWEENの意志が見えてきます。
カイ・ハンセンの脱退から数年。
今度はマイケル・キスクとインゴ・シュヴィヒテンバーグが脱退。
そして、新たに加入したのがPinkCream 69のアンディ・デリスである。
当時のPinkCream69を知っていた人なら「あの声が!HELLOWEENに!!ムリムリ!!」という不安。
さらにPinkCream69のファンなら「アンディを抜いていくなよ~!どーすんだよ~!」という不安。
そりゃーもー、全てが不安だらけさ!
崩壊まっしぐら!
・・・だと思ってた。
まぁ、マイケル・キスクの後釜じゃ誰だってキツいわなぁ。
HELLOWEENもPINKCREAM69も好きだったワタシにとって、どうやって贔屓目に見ても双方にとってメリットが無いように思っていた。
が、その不安はいい意味で裏切られた。
元々の不安はHELLOWEENの音楽性にアンディがフィットするのかという一点が重要だった。
この時点でワタシの中でのアンディは「HELLOWEENに雇われたアンディ・デリス」的な位置づけだったように思う。
が、アンディのメロディセンスはHELLOWEENの音楽性をさりげなく包容し、ワタシの中では「コレは・・・アンディ with HELLOWEEN だな。」といった具合にアンディ・デリス中心のバンドに変わったかのような錯覚を覚えた。
元々、HELLOWEENのヴァイキー、PC69のアンディともにメロディメーカーとしての才は突出していた。
が、とても融合できるようなイメージではなかった。
それが意外な化学反応を見せた。
初期HELLOWEENこそがHELLOWEEN!というオールドファンにとっては耐え難いアルバムかもしれない。
かくいうワタシもHELLOWEENでHeavyMetalに目覚め、最も尊敬するアーティストは「カイ・ハンセン!」って言っちゃうヒトだから、思い入れは別格だ。
だけど。
ワタシは「死に体だったHELLOWEENが新たな一歩を踏み出した!」とプラスに捉えることができました。
ま、元々PinkCream69の音楽性が好きだったからってのも大きな要因だけどね。
ヴァイキーの手による[Sole Survivor][Where The Rain Grows]といった名曲も、HELLOWEENであることを主張しながらも「新しい血」の参入によって今までとは全く異なる息吹を感じます。
そして、まさに「アンディ節」といった趣の[Perfect Gentleman][Why?]もPinkCream69のファンにはウレシイ。
このあたりが違和感なく交錯しているところが素晴らしい。
既にカイ時代/キスケ時代が「昔話」であるかのようにアンディの叙情性が溶け込んだHELLOWEEN。
アンディが抜け一時迷走したものの、その叙情性を失ったことをプラスに作用させて欧州正統派路線へシフトしたPinkCream69。
さらにはHELLOWEENが「横」方向へ裾野を広げているのに対し、ひたすら自分の音楽性を「縦」方向へ突き進むカイのGAMMA RAY。
今になってみれば「これはこれで必然だったのか」と思えるのだ。
・・・ただ唯一、マイケル・キスクが表舞台から退いていることだけは残念だけど。
Helloween - Where The Rain Grows
Helloween - Perfect Gentleman
「ハロウィン」というキーワードで、このバンドを取り上げる安直さもどうかと思いますが、ま、いいでしょう。分かりやすいし。
昨年もこのバンドのこと書いたから恒例行事にしちゃおっかなー。
楽だし。
ってことで(?)、まだ書いてないアルバムから、コレをチョイス。
Helloween [Master Of The Rings]

物語は「鍵」 (Keeper of the Seven Keys) から「指輪」へ。
過去の名作と韻を踏んだタイトルにはハッキリとした新生HELLOWEENの意志が見えてきます。
カイ・ハンセンの脱退から数年。
今度はマイケル・キスクとインゴ・シュヴィヒテンバーグが脱退。
そして、新たに加入したのがPinkCream 69のアンディ・デリスである。
当時のPinkCream69を知っていた人なら「あの声が!HELLOWEENに!!ムリムリ!!」という不安。
さらにPinkCream69のファンなら「アンディを抜いていくなよ~!どーすんだよ~!」という不安。
そりゃーもー、全てが不安だらけさ!
崩壊まっしぐら!
・・・だと思ってた。
まぁ、マイケル・キスクの後釜じゃ誰だってキツいわなぁ。
HELLOWEENもPINKCREAM69も好きだったワタシにとって、どうやって贔屓目に見ても双方にとってメリットが無いように思っていた。
が、その不安はいい意味で裏切られた。
元々の不安はHELLOWEENの音楽性にアンディがフィットするのかという一点が重要だった。
この時点でワタシの中でのアンディは「HELLOWEENに雇われたアンディ・デリス」的な位置づけだったように思う。
が、アンディのメロディセンスはHELLOWEENの音楽性をさりげなく包容し、ワタシの中では「コレは・・・アンディ with HELLOWEEN だな。」といった具合にアンディ・デリス中心のバンドに変わったかのような錯覚を覚えた。
元々、HELLOWEENのヴァイキー、PC69のアンディともにメロディメーカーとしての才は突出していた。
が、とても融合できるようなイメージではなかった。
それが意外な化学反応を見せた。
初期HELLOWEENこそがHELLOWEEN!というオールドファンにとっては耐え難いアルバムかもしれない。
かくいうワタシもHELLOWEENでHeavyMetalに目覚め、最も尊敬するアーティストは「カイ・ハンセン!」って言っちゃうヒトだから、思い入れは別格だ。
だけど。
ワタシは「死に体だったHELLOWEENが新たな一歩を踏み出した!」とプラスに捉えることができました。
ま、元々PinkCream69の音楽性が好きだったからってのも大きな要因だけどね。
ヴァイキーの手による[Sole Survivor][Where The Rain Grows]といった名曲も、HELLOWEENであることを主張しながらも「新しい血」の参入によって今までとは全く異なる息吹を感じます。
そして、まさに「アンディ節」といった趣の[Perfect Gentleman][Why?]もPinkCream69のファンにはウレシイ。
このあたりが違和感なく交錯しているところが素晴らしい。
既にカイ時代/キスケ時代が「昔話」であるかのようにアンディの叙情性が溶け込んだHELLOWEEN。
アンディが抜け一時迷走したものの、その叙情性を失ったことをプラスに作用させて欧州正統派路線へシフトしたPinkCream69。
さらにはHELLOWEENが「横」方向へ裾野を広げているのに対し、ひたすら自分の音楽性を「縦」方向へ突き進むカイのGAMMA RAY。
今になってみれば「これはこれで必然だったのか」と思えるのだ。
・・・ただ唯一、マイケル・キスクが表舞台から退いていることだけは残念だけど。
Helloween - Where The Rain Grows
Helloween - Perfect Gentleman
2008年12月11日
終焉のとき
「これで最後」
そう余命宣告されて向き合うアルバムは普段とは違う想いが交錯する。
自分が愛したバンドなら、なおさらだ。
あのアルバム。あの曲。
それぞれの想いを脳裏に描きながら、ラストアルバムと向き合う。
HAREM SCAREM [HOPE]

その美しくメランコリックなメロディと華麗なコーラス。
日本のメロディアスハードロックファンのココロを鷲掴みにしてきた彼らの軌跡も幕を閉じる。
当然、ファンとしては感傷的になる。
が・・・。
全体的には、そんなセンチメンタルなムードは薄い。
前作 [Human Nature] で「復活!」という印象を刻んだ反動が来たかのようだ。
位置づけとしては、名作 [Mood Swings]と迷作 [Voice of Reason]の中間といったところでしょうか。
ラストだから、彼らのファンだから、ハッキリ言いますとですね。
なんだか中途半端です。
すんごく歯痒い気分です。
「え、このアルバムがHAREM SCAREMの歴史の終止符なの?」と。
最初に書いた通り、ラストアルバムということで「あの時代」を思い描きながら聞くから尚更なのでしょう。
しかし冷静に考えれば彼ら自身が[Voice of Reason]を傑作として肯定している以上当然の流れであり、彼らなりに懐古的に振り返ってくれたのかもしれません。
そうは言いながらも、実質のラストソングとなる[Nothing Without You]では彼らの十八番である美しく儚げなアンサンブルを紡いでくれます。
波瀾万丈、紆余曲折、暗中模索。
ホントにいろいろ試行錯誤していた印象が強いけど、その素晴らしい曲が色褪せることはありません。
素晴らしい音楽を提供してきてくれた彼らに感謝。
そして彼らも、最後まで見届けてくれた日本のファンに感謝してくれている・・といいなぁ。
[Nothing Without You]
http://jp.youtube.com/watch?v=ExetMDG6tRk
そう余命宣告されて向き合うアルバムは普段とは違う想いが交錯する。
自分が愛したバンドなら、なおさらだ。
あのアルバム。あの曲。
それぞれの想いを脳裏に描きながら、ラストアルバムと向き合う。
HAREM SCAREM [HOPE]

その美しくメランコリックなメロディと華麗なコーラス。
日本のメロディアスハードロックファンのココロを鷲掴みにしてきた彼らの軌跡も幕を閉じる。
当然、ファンとしては感傷的になる。
が・・・。
全体的には、そんなセンチメンタルなムードは薄い。
前作 [Human Nature] で「復活!」という印象を刻んだ反動が来たかのようだ。
位置づけとしては、名作 [Mood Swings]と迷作 [Voice of Reason]の中間といったところでしょうか。
ラストだから、彼らのファンだから、ハッキリ言いますとですね。
なんだか中途半端です。
すんごく歯痒い気分です。
「え、このアルバムがHAREM SCAREMの歴史の終止符なの?」と。
最初に書いた通り、ラストアルバムということで「あの時代」を思い描きながら聞くから尚更なのでしょう。
しかし冷静に考えれば彼ら自身が[Voice of Reason]を傑作として肯定している以上当然の流れであり、彼らなりに懐古的に振り返ってくれたのかもしれません。
そうは言いながらも、実質のラストソングとなる[Nothing Without You]では彼らの十八番である美しく儚げなアンサンブルを紡いでくれます。
波瀾万丈、紆余曲折、暗中模索。
ホントにいろいろ試行錯誤していた印象が強いけど、その素晴らしい曲が色褪せることはありません。
素晴らしい音楽を提供してきてくれた彼らに感謝。
そして彼らも、最後まで見届けてくれた日本のファンに感謝してくれている・・といいなぁ。
[Nothing Without You]
http://jp.youtube.com/watch?v=ExetMDG6tRk
2008年10月24日
あの涙から一年
昨年の秋に20代前半で亡くなったイトコのKちゃんの一周忌に行ってきた。
もう一年かぁ。
東京出張中のホテルで聞いた訃報だったなぁ。
お別れ会での胸を引き裂かんばかりの悲しさは、今でも時々脳裏をよぎる。
なんだかまだ現実じゃないような。
でも、その日のことを思い出せば鮮烈すぎる記憶として蘇ってくる。
一周忌というよりは、Kちゃんを偲ぶ会のような形式だった。
仲のよかったイトコ一同で集まり、笑いの絶えない会だった。
お別れ会のような涙は一切無かったけど、喜んでいてくれるんじゃないかと思いたい。
自分は「星になった」とか「空からいつも見ててくれる」なんて感傷的なことを考えるタイプじゃない。
けど、フトンから窓の夜空を見上げたときに、なんだか「Kちゃん、元気にしてっかなぁ・・見守ってくれよなぁ。」なんてココロで呟いたりしてしまうから不思議だ。
人生、何が起きるかわかんない。
ムスメが小憎らしいことを言おうが、ボウズがイヤイヤしていようが、奥様が不機嫌だろうが、とりあえず今、この瞬間を過ごせてることに感謝しないといけないなぁと感じるのでした。
♪
Now it's your turn to break free
When you want it all you've got to see
Now it's your turn to break free
When you want the life, you've got to see what it means
・・・LYRICS FROM [Your Turn] By HELLOWEEN [Pink Bubbles Go Ape] Album
:
:
:
:
:

思い出にふけったついでに、書いちゃいましょう。
発売延期、音楽性変化、様々な物議を醸したHELLOWEENのアルバム。
カイ・ハンセンが抜けたということも重要なターニングポイント。
批判的な意見が多いこのアルバムですが、ワタシは好きです。
[Kids of the Century][Someone's Crying][The Chance]といった佳曲も揃ってます。
なにより、上記の[Your Turn]が泣ける。
カイのこと、インゴのこと、そしてこの後のマイケル・キスク自身のこと。
バンドが混沌と混迷の時期を迎えていたからこそ生まれた名曲。
ことあるごとに ♪ Now it's your turn to break free というフレーズはワタシの脳裏をよぎるのです。
もう一年かぁ。
東京出張中のホテルで聞いた訃報だったなぁ。
お別れ会での胸を引き裂かんばかりの悲しさは、今でも時々脳裏をよぎる。
なんだかまだ現実じゃないような。
でも、その日のことを思い出せば鮮烈すぎる記憶として蘇ってくる。
一周忌というよりは、Kちゃんを偲ぶ会のような形式だった。
仲のよかったイトコ一同で集まり、笑いの絶えない会だった。
お別れ会のような涙は一切無かったけど、喜んでいてくれるんじゃないかと思いたい。
自分は「星になった」とか「空からいつも見ててくれる」なんて感傷的なことを考えるタイプじゃない。
けど、フトンから窓の夜空を見上げたときに、なんだか「Kちゃん、元気にしてっかなぁ・・見守ってくれよなぁ。」なんてココロで呟いたりしてしまうから不思議だ。
人生、何が起きるかわかんない。
ムスメが小憎らしいことを言おうが、ボウズがイヤイヤしていようが、奥様が不機嫌だろうが、とりあえず今、この瞬間を過ごせてることに感謝しないといけないなぁと感じるのでした。
♪
Now it's your turn to break free
When you want it all you've got to see
Now it's your turn to break free
When you want the life, you've got to see what it means
・・・LYRICS FROM [Your Turn] By HELLOWEEN [Pink Bubbles Go Ape] Album
:
:
:
:
:

思い出にふけったついでに、書いちゃいましょう。
発売延期、音楽性変化、様々な物議を醸したHELLOWEENのアルバム。
カイ・ハンセンが抜けたということも重要なターニングポイント。
批判的な意見が多いこのアルバムですが、ワタシは好きです。
[Kids of the Century][Someone's Crying][The Chance]といった佳曲も揃ってます。
なにより、上記の[Your Turn]が泣ける。
カイのこと、インゴのこと、そしてこの後のマイケル・キスク自身のこと。
バンドが混沌と混迷の時期を迎えていたからこそ生まれた名曲。
ことあるごとに ♪ Now it's your turn to break free というフレーズはワタシの脳裏をよぎるのです。
2008年06月27日
カラオケに戸惑う
カラオケがキライだ。
いや、元々歌うのはキライじゃない。その「場」が苦手とでもいいましょうか・・・
仕事関係、近隣、知人などなどでのカラオケに行くとですね。
J-POPにほとんど興味がないワタシは、まずヒトが歌ってる曲が分からない。
まったく盛り上がることができず、冷やかな目線が降り注ぎます。
で、歌う曲がない。
J-POPは分からないし。
メタルじゃ引かれるし。(気にしないけどね。)
アニソンじゃ「アキバ系」って言われるし。(ま、いいんだけどね。)
けど、カラオケにどんな曲があるかを見るのがスキだ。
で、それを歌ったらキモチイイだろなと思いを馳せるのがスキだ。
でも、一人でカラオケなんていかないから、ほぼ実現しないけど。
数年前なら
「おぉぉ!METALLICAのBatteryが!」
「ぬぉぉ!IRON MAIDENのProwlerが!」
といった大御所があっただけで驚愕だった。
ちょっと前ならHELLOWEEN/FAIR WARNING/RIOT/PRETTY MAIDS/RAGE/FIREHOUSE/KAMELOT ・・・その他モロモロ。
凄まじいラインナップが並び始めた。
で、最近はさらにマニアックな曲が増えつつある。
彼らの曲が今更追加されるってことはニーズがあるってことだ。
それがウレシイ。
HEAVENS GATE [Gate of Heaven] From... [LIVIN' IN HYSTERIA]

ジャーマンメタル全盛期に現れ、このアルバムで一気にブレイク。(したはず。)
BURRN!の表紙を飾り、今でも笑いの種・・いや、伝説に。(なっているはず。)
いわゆるHELLOWEEN直系のジャーマンメタルとは一線を画した音楽性は、JUDAS PRIESTやIRON MAIDENあたりの純潔HEAVY METALからの流れでしょう。
実際、後のアルバムではJUDAS PRIESTの[THE SENTINEL]をカバーし、結構ハマってた…というか、そのカッコよさで他のオリジナル楽曲の弱さが際立つという不幸もありましたが…。
このアルバムはですね、素晴らしいです。
明朗快活なメロディ。
緩急をつけた構成。
ジャーマン的な高揚感と伝統的HeavMetalのサウンドの融合。
ちょっと不安定ながらも伸びのいいヴォーカル。
特にラストを飾る[Gate of Heaven]は、彼らのアンセムというだけでなく、この時代のメタル・アンセム、いや、ジャーマンメタルという歴史の中に刻まれたメタル・アンセムと言っても過言ではないでしょう。
(いや、ちょっと過言でした・・・)
元々、そういった要素を持ってはいましたが突然変異的に開花した印象です。
開花したけど・・
次のアルバムがビミョーで。
ライブも、「そりゃねーべ」的で。
せっかくの[Gate of Heavn]や[Livin' in Hysteria]もフェイク&観客任せで。
そこから竜頭蛇尾的に失速していったのでした。
今でも好きだけどね。
いや、元々歌うのはキライじゃない。その「場」が苦手とでもいいましょうか・・・
仕事関係、近隣、知人などなどでのカラオケに行くとですね。
J-POPにほとんど興味がないワタシは、まずヒトが歌ってる曲が分からない。
まったく盛り上がることができず、冷やかな目線が降り注ぎます。
で、歌う曲がない。
J-POPは分からないし。
メタルじゃ引かれるし。(気にしないけどね。)
アニソンじゃ「アキバ系」って言われるし。(ま、いいんだけどね。)
けど、カラオケにどんな曲があるかを見るのがスキだ。
で、それを歌ったらキモチイイだろなと思いを馳せるのがスキだ。
でも、一人でカラオケなんていかないから、ほぼ実現しないけど。
数年前なら
「おぉぉ!METALLICAのBatteryが!」
「ぬぉぉ!IRON MAIDENのProwlerが!」
といった大御所があっただけで驚愕だった。
ちょっと前ならHELLOWEEN/FAIR WARNING/RIOT/PRETTY MAIDS/RAGE/FIREHOUSE/KAMELOT ・・・その他モロモロ。
凄まじいラインナップが並び始めた。
で、最近はさらにマニアックな曲が増えつつある。
彼らの曲が今更追加されるってことはニーズがあるってことだ。
それがウレシイ。
HEAVENS GATE [Gate of Heaven] From... [LIVIN' IN HYSTERIA]

ジャーマンメタル全盛期に現れ、このアルバムで一気にブレイク。(したはず。)
BURRN!の表紙を飾り、今でも笑いの種・・いや、伝説に。(なっているはず。)
いわゆるHELLOWEEN直系のジャーマンメタルとは一線を画した音楽性は、JUDAS PRIESTやIRON MAIDENあたりの純潔HEAVY METALからの流れでしょう。
実際、後のアルバムではJUDAS PRIESTの[THE SENTINEL]をカバーし、結構ハマってた…というか、そのカッコよさで他のオリジナル楽曲の弱さが際立つという不幸もありましたが…。
このアルバムはですね、素晴らしいです。
明朗快活なメロディ。
緩急をつけた構成。
ジャーマン的な高揚感と伝統的HeavMetalのサウンドの融合。
ちょっと不安定ながらも伸びのいいヴォーカル。
特にラストを飾る[Gate of Heaven]は、彼らのアンセムというだけでなく、この時代のメタル・アンセム、いや、ジャーマンメタルという歴史の中に刻まれたメタル・アンセムと言っても過言ではないでしょう。
(いや、ちょっと過言でした・・・)
元々、そういった要素を持ってはいましたが突然変異的に開花した印象です。
開花したけど・・
次のアルバムがビミョーで。
ライブも、「そりゃねーべ」的で。
せっかくの[Gate of Heavn]や[Livin' in Hysteria]もフェイク&観客任せで。
そこから竜頭蛇尾的に失速していったのでした。
今でも好きだけどね。
2008年04月09日
こんなもんだろ
「ま、こんなもんだろ」そんな声が聞こえてきそうです。
ここでいう「こんなもんだろ」は、妥協の「こんなもんでいいかな」ではありません。
「俺たちがその気になれば、このくらいのアルバムは普通だな。」という「余裕」。
HELLOWEEN [GAMBLING WITH THE DEVIL]

思えば前作[KEEPER OF THE SEVEN KEYS -THE LEGACY-] は唐突だった。
なぜ今更?
アンディ・デリスで、そのストーリーを蘇らせる必要があるのか?
数々の葛藤の中でリリースされたそのアルバムは、スケールの大きな曲、シリアスなムード…
過去の憧憬も思い浮かべつつも、この時代の姿を映し出していました。
そして、今回。
その反動からか、コンパクトかつバラエティに富んだアルバムになりました。
[BETTER THAN RAW]あたりに近い感じかな。
ただ、全体的にリラックスムードと言いますか…。
「全力投球、渾身の一撃」というよりは「風格と余裕」を感じます。
曲単位でも「アンディ節」「ヴァイキー節」はやや控えめ。
直感的に「うん!これだよ!やっぱ!」という瞬間風速の強い曲が乏しい気がします。
そんな中でも[Final Fortune]のような名曲が当然のように存在するところがさすがです。
過去との決別とも思える前作。
現在を自然体で表現した今作。
きっと次は…この手の音楽のパイオニアとしての意地と底力が見られそうな予感がします。
ここでいう「こんなもんだろ」は、妥協の「こんなもんでいいかな」ではありません。
「俺たちがその気になれば、このくらいのアルバムは普通だな。」という「余裕」。
HELLOWEEN [GAMBLING WITH THE DEVIL]

思えば前作[KEEPER OF THE SEVEN KEYS -THE LEGACY-] は唐突だった。
なぜ今更?
アンディ・デリスで、そのストーリーを蘇らせる必要があるのか?
数々の葛藤の中でリリースされたそのアルバムは、スケールの大きな曲、シリアスなムード…
過去の憧憬も思い浮かべつつも、この時代の姿を映し出していました。
そして、今回。
その反動からか、コンパクトかつバラエティに富んだアルバムになりました。
[BETTER THAN RAW]あたりに近い感じかな。
ただ、全体的にリラックスムードと言いますか…。
「全力投球、渾身の一撃」というよりは「風格と余裕」を感じます。
曲単位でも「アンディ節」「ヴァイキー節」はやや控えめ。
直感的に「うん!これだよ!やっぱ!」という瞬間風速の強い曲が乏しい気がします。
そんな中でも[Final Fortune]のような名曲が当然のように存在するところがさすがです。
過去との決別とも思える前作。
現在を自然体で表現した今作。
きっと次は…この手の音楽のパイオニアとしての意地と底力が見られそうな予感がします。
2008年01月28日
両雄並び立つ
HELLOWEENとGAMMA RAY。
袂を分けて何年経ったんだったっけ。
HELLOWEENは自分がHeavyMetalに足を踏み入れるキッカケであり、
GAMMA RAYのカイ・ハンセンは、HELLOWEEN=カイ・ハンセンだと思っていた自分にとってはとても思い入れが深い。
決して交わることのないと思っていた彼らが、日本で、同時に、しかも同じ舞台に立つ。
2月のカップリングツアー。
どうしても参戦したかったが、今回は見送らざるを得ない。
ハァ、行きたかった。
老舗のブランドを守りつつ新たなチャレンジで「横」へ拡がりを見せるHELLOWEEN。
かたやカイのスタイルを突き詰めて「縦」への探求を見せるGAMMA RAY。
今となって交わる必然性があるかどうかは別にして、ファンにとっては夢の舞台でしょう。
アンディ加入後のライブで「聞くも苦痛、歌うも苦痛」の[EAGLE FLY FREE]を聴いてから、
「アンディ加入後のHELLOWEENは別モノ」と思っている自分は、現在のHELLOWEENに昔の曲を期待していない。
アンディ加入後のHELLOWEENの楽曲だけで充分に勝負できるし。
でも、今回はカイが歌ってくれるのであれば、やはり昔の曲が盛り上がるだろな。
HELLOWEEN [Walls of Jericho]

[Walls of Jericho ~ Ride the Sky]
今となってはGAMMA RAYのライブ定番曲ですね。
守護神伝シリーズ以降のドコドコバスドラに緩やかなメロが乗る、典型的サウンドに至る前の名曲です。
攻撃的で荒々しいリフ。
直線的なスピード感にカイの金属的でヒステリックなヴォーカル。
この初期の名曲がカイとヴァイキーのツインリードで蘇ったら感涙だな。モエモエだな。
…って、GAMMA RAYのライブ定番曲って言ったばっかじゃん。
そうすると[FUTURE WORLD]あたりのポップな曲でシメるのかな。
袂を分けて何年経ったんだったっけ。
HELLOWEENは自分がHeavyMetalに足を踏み入れるキッカケであり、
GAMMA RAYのカイ・ハンセンは、HELLOWEEN=カイ・ハンセンだと思っていた自分にとってはとても思い入れが深い。
決して交わることのないと思っていた彼らが、日本で、同時に、しかも同じ舞台に立つ。
2月のカップリングツアー。
どうしても参戦したかったが、今回は見送らざるを得ない。
ハァ、行きたかった。
老舗のブランドを守りつつ新たなチャレンジで「横」へ拡がりを見せるHELLOWEEN。
かたやカイのスタイルを突き詰めて「縦」への探求を見せるGAMMA RAY。
今となって交わる必然性があるかどうかは別にして、ファンにとっては夢の舞台でしょう。
アンディ加入後のライブで「聞くも苦痛、歌うも苦痛」の[EAGLE FLY FREE]を聴いてから、
「アンディ加入後のHELLOWEENは別モノ」と思っている自分は、現在のHELLOWEENに昔の曲を期待していない。
アンディ加入後のHELLOWEENの楽曲だけで充分に勝負できるし。
でも、今回はカイが歌ってくれるのであれば、やはり昔の曲が盛り上がるだろな。
HELLOWEEN [Walls of Jericho]

[Walls of Jericho ~ Ride the Sky]
今となってはGAMMA RAYのライブ定番曲ですね。
守護神伝シリーズ以降のドコドコバスドラに緩やかなメロが乗る、典型的サウンドに至る前の名曲です。
攻撃的で荒々しいリフ。
直線的なスピード感にカイの金属的でヒステリックなヴォーカル。
この初期の名曲がカイとヴァイキーのツインリードで蘇ったら感涙だな。モエモエだな。
…って、GAMMA RAYのライブ定番曲って言ったばっかじゃん。
そうすると[FUTURE WORLD]あたりのポップな曲でシメるのかな。
2007年10月31日
ハロウィンの衝撃
今日はハロウィンですか。
ついさっきソレを知って、今、取り急ぎ書き込んでいるわけですよ。
ハロウィンやらクリスマスやら盆やら正月やらバレンタインやら。
ニッポン人は忙しいですねぇ。
ハロウィンというイベント自体は全く自分に関係ありません。
が、コッチのハロウィンは非常に大きな意味があります。
学生だった自分は、メタルといえば X だった。
洋楽はFM STATIONやMTVでチャートをチェックするフツーの洋楽ファンだった。
友人に借りた、この一枚のCDが人生を変えた。大げさじゃなく。
奥様との出会い、このアルバムとの出会いが人生の二大分岐点だな。
HELLOWEEN / KEEPER OF THE SEVEN KEYS -PART 2-

エックス=メタル だった自分にとって、それは衝撃的だった。
パワフルかつ安定感抜群、どこまでも伸びるキスクのヴォーカル。
珠玉のメロディを奏でるツインギター、ヴァイキー&カイ。
そして憂いを帯びつつも圧倒的攻撃力で煽り続けるメロディライン。
バンドのメンバーのスキル高さ。
楽曲のレベルの高さ。
アルバム全体を支配する緊張感。
すべてにおいて「次元が違う」「これがホンモノだったのか。」と感じました。
おそらく自分の人生の中で最もリピートされたアルバムでしょう。
そこから、自分のHeavy Metal Life が始まったのでした。
エックスがHELLOWEENをパクって(…というとマズいか。オイシイところを頂いて)いた…ということが理解できたのはそれから数年後でした。
ま、エックスはジャパニーズポップスとパワーメタルをうまく混ぜ合わせたなぁと思うし、今でもそれなりに好きだけどね。
ついさっきソレを知って、今、取り急ぎ書き込んでいるわけですよ。
ハロウィンやらクリスマスやら盆やら正月やらバレンタインやら。
ニッポン人は忙しいですねぇ。
ハロウィンというイベント自体は全く自分に関係ありません。
が、コッチのハロウィンは非常に大きな意味があります。
学生だった自分は、メタルといえば X だった。
洋楽はFM STATIONやMTVでチャートをチェックするフツーの洋楽ファンだった。
友人に借りた、この一枚のCDが人生を変えた。大げさじゃなく。
奥様との出会い、このアルバムとの出会いが人生の二大分岐点だな。
HELLOWEEN / KEEPER OF THE SEVEN KEYS -PART 2-

エックス=メタル だった自分にとって、それは衝撃的だった。
パワフルかつ安定感抜群、どこまでも伸びるキスクのヴォーカル。
珠玉のメロディを奏でるツインギター、ヴァイキー&カイ。
そして憂いを帯びつつも圧倒的攻撃力で煽り続けるメロディライン。
バンドのメンバーのスキル高さ。
楽曲のレベルの高さ。
アルバム全体を支配する緊張感。
すべてにおいて「次元が違う」「これがホンモノだったのか。」と感じました。
おそらく自分の人生の中で最もリピートされたアルバムでしょう。
そこから、自分のHeavy Metal Life が始まったのでした。
エックスがHELLOWEENをパクって(…というとマズいか。オイシイところを頂いて)いた…ということが理解できたのはそれから数年後でした。
ま、エックスはジャパニーズポップスとパワーメタルをうまく混ぜ合わせたなぁと思うし、今でもそれなりに好きだけどね。
2007年08月20日
必ず訪れる「その時」
長年音楽を聴いていれば、愛するバンドの「解散」という場面に必ず遭遇する。
まただ。
良質な音楽を提供してくれるバンドが消えてしまうのは切ない。
HAREM SCAREM [MOOD SWINGS]

HAREM SCAREM が頭に浮かぶとき。彼らのメロディが頭をかすめる時。
同時に浮かぶ光景があります。
「夕暮れの遊園地、誰も乗っていないメリーゴーランド」
どうしてか分からないけど。
彼らのメロウな音楽からのインスピレーションでしょうか。
アルバムごとに微妙に異なった個性を見せてくれる彼らですが、代表作といえばコレでしょう。
なんっつったって [Change Comes Around] という名曲を収録していますし。
HAREM SCAREM の一番の武器であり魅力であるのが「ハーモニー」。
アカペラっぽい曲では、その魅力を存分に堪能できます。
ポップな曲からダークな曲、美しいバラードからハードな曲まで。
カラフルでバラエティに富んだ楽曲が溢れています。
共通しているのは、明るくなりきれない物憂げなメロディ。
彼らはバンドを最も愛してくれた日本でその歴史にピリオドを打つようです。
秋の日本ツアー。
残念ながら名古屋での予定はない。
今までに「好きなバンド」「それなりに気になるバンド」一通りのライブは見てきた。
…つもりだった。
けど彼らのライブは行ってなかったことに気付いた。
そのときには既に遅かった…。
まただ。
良質な音楽を提供してくれるバンドが消えてしまうのは切ない。
HAREM SCAREM [MOOD SWINGS]

HAREM SCAREM が頭に浮かぶとき。彼らのメロディが頭をかすめる時。
同時に浮かぶ光景があります。
「夕暮れの遊園地、誰も乗っていないメリーゴーランド」
どうしてか分からないけど。
彼らのメロウな音楽からのインスピレーションでしょうか。
アルバムごとに微妙に異なった個性を見せてくれる彼らですが、代表作といえばコレでしょう。
なんっつったって [Change Comes Around] という名曲を収録していますし。
HAREM SCAREM の一番の武器であり魅力であるのが「ハーモニー」。
アカペラっぽい曲では、その魅力を存分に堪能できます。
ポップな曲からダークな曲、美しいバラードからハードな曲まで。
カラフルでバラエティに富んだ楽曲が溢れています。
共通しているのは、明るくなりきれない物憂げなメロディ。
彼らはバンドを最も愛してくれた日本でその歴史にピリオドを打つようです。
秋の日本ツアー。
残念ながら名古屋での予定はない。
今までに「好きなバンド」「それなりに気になるバンド」一通りのライブは見てきた。
…つもりだった。
けど彼らのライブは行ってなかったことに気付いた。
そのときには既に遅かった…。
2007年02月01日
変革の時
世間では「好景気」と言われておりますが、この地方のサラリーマンの方々は如何でしょうか。
私は「景気に乗って左ウチワ」のようなわけにはいかず、いろいろ模索中でございます。
「今こそ改革の時!」
「俺たちで革命を!」
と、狼煙をあげるものの、なかなか実態が伴わないのが現状です…。
革命…Revolution
かれこれ10年以上前になりますが、ジャーマンメタルの大御所 HELLOWEEN のLIVEにて。
確か、PINK BUBBLES GO APE のツアーだったかな。
マイケル・キスクがMCで「○△×□?*…… NEW SONG! 」(ニューソングしか聞き取れない)
「おお、新曲か!」
で、始まった曲が「Revolution Now」。
……ウソ、コレ、ホント、ちょっと、コレはないやろ?この曲が次のアルバムに?
で、その後発売されたアルバムが「問題作」と言われている [CHAMELEON]でした。

HELLOWEEN の中でも異彩を放つこのアルバム、いつもの緊張感がなく、なんだかユルい印象です。
意図的に過去を振りほどこうとしているような感もあります。
ポップ、穏やかというと聞こえはいいけど、やっぱ受け入れがたいなぁ。
(First Time とかは今でも好きな曲ですが。)
そういえば、そのLIVE では定番の名曲 [How Many Tears]も演奏されることなく
「本日の公演は終了しました」
:
「おい!How Many Tears は!」との怒声、罵声が飛び交っていました。(自分も含めて)
このとき「HELLOWEENも変わっていくなぁ。」と思い、実際にその後にマイケル・キスクが脱退したのでした。
まさに変革の時。
最終的にはアンディ・デリスを迎えて落ち着いた HELLOWEEN の「革命・改革」はショックが大きかったものの、今となっては「それがあったから今があるなぁ。」と思えるのでした。
私は「景気に乗って左ウチワ」のようなわけにはいかず、いろいろ模索中でございます。
「今こそ改革の時!」
「俺たちで革命を!」
と、狼煙をあげるものの、なかなか実態が伴わないのが現状です…。
革命…Revolution
かれこれ10年以上前になりますが、ジャーマンメタルの大御所 HELLOWEEN のLIVEにて。
確か、PINK BUBBLES GO APE のツアーだったかな。
マイケル・キスクがMCで「○△×□?*…… NEW SONG! 」(ニューソングしか聞き取れない)
「おお、新曲か!」
で、始まった曲が「Revolution Now」。
……ウソ、コレ、ホント、ちょっと、コレはないやろ?この曲が次のアルバムに?
で、その後発売されたアルバムが「問題作」と言われている [CHAMELEON]でした。

HELLOWEEN の中でも異彩を放つこのアルバム、いつもの緊張感がなく、なんだかユルい印象です。
意図的に過去を振りほどこうとしているような感もあります。
ポップ、穏やかというと聞こえはいいけど、やっぱ受け入れがたいなぁ。
(First Time とかは今でも好きな曲ですが。)
そういえば、そのLIVE では定番の名曲 [How Many Tears]も演奏されることなく
「本日の公演は終了しました」
:
「おい!How Many Tears は!」との怒声、罵声が飛び交っていました。(自分も含めて)
このとき「HELLOWEENも変わっていくなぁ。」と思い、実際にその後にマイケル・キスクが脱退したのでした。
まさに変革の時。
最終的にはアンディ・デリスを迎えて落ち着いた HELLOWEEN の「革命・改革」はショックが大きかったものの、今となっては「それがあったから今があるなぁ。」と思えるのでした。