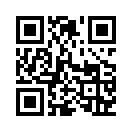2013年05月07日
30年の轍
偉大なバンドだ。
そして、メタルだのハードロックだのという垣根を越えて、一般的な音楽ファンと話題を共有できる希有なバンドだ。
ワタシも大好きだ。
大好きなんだが・・以前抱いてた想いとは多少変わってきた気がしなくもない。
BON JOVI / WHAT ABOUT NOW

歴史が長すぎて何枚目かなんて意識してもないので例によってwikiで確認。
1984年デビューから数えて約30年。
この作品が12枚目・・ん?もっと出してたような気がしなくもないな。
単なる「洋楽好き」だったワタシが「ハードロック」というジャンルに興味を持つキッカケになってくれた、重要なバンドであり大好きであり続けているバンドだ。
さて、このアルバム。
結論から言ってしまえば、今回も間違いなくBonJovi印のアルバムです。
安心のクオリティ、安心のメロディ。
ここ数作のアルバムが好きな人なら文句ナシでしょう。
が、これだけ長い歴史を刻んできたバンドだから、「この時期のアルバムはいいんだけど、最近は・・ねぇ」って人も多いと思う。
wikiを見てたら、ちょうど3作づつで「節目」的なものがあるような気がしてきたので、ちょっと紐解いてみる。
個人的な想いだから、「それ、ちゃうやろ!」「ケッ。わかってねーな。」と思ってもスルーでお願いしますね。
① Bon Jovi(1st) ~ Slippery When Wet(3rd)
ロックスターとして花開く時期。なんだかアイドル的な扱いもありつつ、曲の華やかさも際立つ。
② New Jersey(4th) ~ These Days(6th)
彼ら(特にリッチー)のバックグラウンドを如実に全面に押し出し、初期のメロディにブルージーな空気のブレンドが絶妙。
名実ともに「世界のBonJovi」に。
③ Crush(7th) ~ Have A Nice Day(9th)
ややジョンのカラーを押し出し、さらにスケールアップ。オトナの魅力とBonJoviのメロディが絶妙なバランスの円熟期。
④ Lost Highway(10th)~What About Now(12th)
穏やかで優しいメロディが印象的。スタイリシュなメロディに織りまぜられたリッチーのギターに懐かしさを覚えたり。
乱暴な分け方で申し訳ないと思いつつ、こんな印象だ。
①の時期が一番好きな人にとっては、②~③あたりで華やかさが薄れてしまったと感じるかもしれない。
②の時期が好きな人は、③以降は魅力が半減したと思ってるかもしれない。
③以降が好きな人は、①はチープで②は地味すぎるかもしれない。そして最近のアルバムには充実感を感じていることだと思います。
ちなみにワタシがBonJoviに出会ったのは①の後半、そして一番大好きなのは②の時代だ。
③の時代も、それなりに好きだ。
そして④の時代、つまり[Lost Highway]以降は、新作を聞くたびに「おー、今回も間違いないな」と思いつつ、リピート数が減ってきている。
印象に残る曲も減ってきている。
ある意味、「惰性」で聞き続けていると言われても否定できない。
その惰性の中でも、今までの名作の残像が色濃く残っているから、「惰性」と同じくらいの「期待」があるから聞き続けているのだと思う。
そして、いつも期待通りのアルバムをリリースしてくれるのだ。
今回のアルバムも非の打ち所がないのだ。
ないのだが、特筆すべき点もないのだ。
ゼイタクな話だが、「期待通り」だけど「期待以上」じゃないのだ。
高いクオリティでありながら、曲の起伏、刺激、胸を締めつけるようなメロディ、といったワタシが求めるものは薄い。
年輪を重ねた大人のサウンドは万人受けする大衆性を見せつつ、一歩間違うと単なるBGMで終わってしまう可能性も。
ザックリ言ってしまうと、①~②の時代が好きな人にはオススメできません。
たぶん「退屈」というのが第一印象になっていまうことでしょう。
③の時代が好きな人なら、10th/11thよりは③に近い気がするので、「最近パッとしないな」と思っていても聞いてみてほしいところ。
最近の④が好きなら、間違いなく買いでしょうね。
なんだかんだ言っても、今後もBonJoviを追いかけていくことでしょう。
さすがに、もう以前のサウンドを期待しているわけじゃない。
当時生み出してくれた名作たちは、そのまま色あせず残っていくわけだし、今さら「NewJerseyⅡ」なんてのを出されてもドン引きだし。
いろいろとイチャモンをつけつつも、結局BonJoviが好きなのだ。
落ち着いちゃったBonJoviも、それはそれで魅力的なのだ。
最初にBonJoviに出会った10代の頃、そして現在。彼らのサウンドの変移と自分の立場の変移をダブらせて楽しんでいるところもあるのかもしれませんね。
Bon Jovi - What About Now
そして、メタルだのハードロックだのという垣根を越えて、一般的な音楽ファンと話題を共有できる希有なバンドだ。
ワタシも大好きだ。
大好きなんだが・・以前抱いてた想いとは多少変わってきた気がしなくもない。
BON JOVI / WHAT ABOUT NOW

歴史が長すぎて何枚目かなんて意識してもないので例によってwikiで確認。
1984年デビューから数えて約30年。
この作品が12枚目・・ん?もっと出してたような気がしなくもないな。
単なる「洋楽好き」だったワタシが「ハードロック」というジャンルに興味を持つキッカケになってくれた、重要なバンドであり大好きであり続けているバンドだ。
さて、このアルバム。
結論から言ってしまえば、今回も間違いなくBonJovi印のアルバムです。
安心のクオリティ、安心のメロディ。
ここ数作のアルバムが好きな人なら文句ナシでしょう。
が、これだけ長い歴史を刻んできたバンドだから、「この時期のアルバムはいいんだけど、最近は・・ねぇ」って人も多いと思う。
wikiを見てたら、ちょうど3作づつで「節目」的なものがあるような気がしてきたので、ちょっと紐解いてみる。
個人的な想いだから、「それ、ちゃうやろ!」「ケッ。わかってねーな。」と思ってもスルーでお願いしますね。
① Bon Jovi(1st) ~ Slippery When Wet(3rd)
ロックスターとして花開く時期。なんだかアイドル的な扱いもありつつ、曲の華やかさも際立つ。
② New Jersey(4th) ~ These Days(6th)
彼ら(特にリッチー)のバックグラウンドを如実に全面に押し出し、初期のメロディにブルージーな空気のブレンドが絶妙。
名実ともに「世界のBonJovi」に。
③ Crush(7th) ~ Have A Nice Day(9th)
ややジョンのカラーを押し出し、さらにスケールアップ。オトナの魅力とBonJoviのメロディが絶妙なバランスの円熟期。
④ Lost Highway(10th)~What About Now(12th)
穏やかで優しいメロディが印象的。スタイリシュなメロディに織りまぜられたリッチーのギターに懐かしさを覚えたり。
乱暴な分け方で申し訳ないと思いつつ、こんな印象だ。
①の時期が一番好きな人にとっては、②~③あたりで華やかさが薄れてしまったと感じるかもしれない。
②の時期が好きな人は、③以降は魅力が半減したと思ってるかもしれない。
③以降が好きな人は、①はチープで②は地味すぎるかもしれない。そして最近のアルバムには充実感を感じていることだと思います。
ちなみにワタシがBonJoviに出会ったのは①の後半、そして一番大好きなのは②の時代だ。
③の時代も、それなりに好きだ。
そして④の時代、つまり[Lost Highway]以降は、新作を聞くたびに「おー、今回も間違いないな」と思いつつ、リピート数が減ってきている。
印象に残る曲も減ってきている。
ある意味、「惰性」で聞き続けていると言われても否定できない。
その惰性の中でも、今までの名作の残像が色濃く残っているから、「惰性」と同じくらいの「期待」があるから聞き続けているのだと思う。
そして、いつも期待通りのアルバムをリリースしてくれるのだ。
今回のアルバムも非の打ち所がないのだ。
ないのだが、特筆すべき点もないのだ。
ゼイタクな話だが、「期待通り」だけど「期待以上」じゃないのだ。
高いクオリティでありながら、曲の起伏、刺激、胸を締めつけるようなメロディ、といったワタシが求めるものは薄い。
年輪を重ねた大人のサウンドは万人受けする大衆性を見せつつ、一歩間違うと単なるBGMで終わってしまう可能性も。
ザックリ言ってしまうと、①~②の時代が好きな人にはオススメできません。
たぶん「退屈」というのが第一印象になっていまうことでしょう。
③の時代が好きな人なら、10th/11thよりは③に近い気がするので、「最近パッとしないな」と思っていても聞いてみてほしいところ。
最近の④が好きなら、間違いなく買いでしょうね。
なんだかんだ言っても、今後もBonJoviを追いかけていくことでしょう。
さすがに、もう以前のサウンドを期待しているわけじゃない。
当時生み出してくれた名作たちは、そのまま色あせず残っていくわけだし、今さら「NewJerseyⅡ」なんてのを出されてもドン引きだし。
いろいろとイチャモンをつけつつも、結局BonJoviが好きなのだ。
落ち着いちゃったBonJoviも、それはそれで魅力的なのだ。
最初にBonJoviに出会った10代の頃、そして現在。彼らのサウンドの変移と自分の立場の変移をダブらせて楽しんでいるところもあるのかもしれませんね。
Bon Jovi - What About Now
Posted by テン at 07:17│Comments(0)
│B